@Koukakurou スープカレーは↓のリンクで、 地域で食べ物、日常生活の風習は様々なんです。私たちの頃の札幌の学校は冬は二週間に一度は山に朝から行くスキー授業がありました。体育の授業6時間を1日にまとめてバス遠足でした!
rankingshare.jp/rank/blvhdhotka
@robipion 返す返すも学びの本質が分かっていないのです。一斉に均質に学ぶことは学びではなくて強制・矯正飼育なのです。1日に100項目覚える子どもがいる中で3項目の覚えが目標の子どもがいても差支えないのが学び舎です。学ぶ悦び歓びを共有していれば構わないのです。→
@robipion
身体の特性から寝転んで勉強する子、車椅子で勉強する子、点字、補聴器、携帯端末、百科事典・ネットを駆使する子、ノート鉛筆の子、ホワイトボードの子、各自の学習が1人の教師の存在で成立つのが教室です。私はそれが教育の姿だと思います。私はそんな学びの姿が好きです。
【降】? 【絳(あか・コウ)】の関連は私の独断理解かも知れないが… 【夂】に足、下方向、遅延、後発の意味が示されているとの知識の伝え方を怠っているのが漢字ドリル教育だと考えている。
小学校低学年学習漢字
【終、冬、夏、各】
に 「夂」は含まれている。
どの様に教え学ぶのだろうか?
@robipion 私の数学の授業中は様々な視点からの別解答を試みさせていた。チャート式解法の丸写し解法指導は教え込みで発想の自由の妨げだとの考えからの授業だった。勿論、チャート式解法も1つの解法として尊重はするが視点を変えれば実に様々な解法が有る得るのが数学との視点の授業だった
私はそれの40年先駆けをしていたのですが…指導法が固定化してtossみたいに絶対化してしまいます。彼処に行けば太鼓判の評判は実は堕落に繋がります。怖い罠です。教育は常に新たな出会いなのに… RT @robipion 発達支援の塾が流行っている理由が、見えてきたような気がする。
@robipion 評判を聴き付けて来た保護者は実に付き合いづらいし、ブランド好きの安心感・固定観念が抜けないのです。そんな保護者の子も肝心の自分の学びが何処か他所事なのです。母親の安心感の為の学びとは付き合いたくない私は今は我が子の学びに付き合う日常が楽しい訳です。
保護者(殆んど母親)と話していて違和感を感じた事がある。学校に何かを期待し過ぎて居る!ということだ。
「何々できるようにして欲しい。」
「何々の面を伸ばして欲しい」
尤もな事のように思わ
れるが、これが一番困る。→
blogs.yahoo.co.jp/yosh0316/46319…
私が指導をしていた時、一番苦手だったのは保護者面談だった。
私は何よりも土台造りを重んじる教師である。
勉強が出来る子より,寧ろ好きな子になって欲しいと思っている。 世間では、勉強は難しくて、辛いものだとの思い込みがある。しかし、やり方によっては面白くて楽しいものである。→
→好きになれば皆その域に達するものだ。土台造りとは子供達と一緒にその域まで時間を掛けて、手間隙掛けて行く行程である。好きになると、いつの間にか出来るようになっているものだ。成績が伸びているのだ。私は、「出来るようにした」わけでは無いのである。→
→「出来るようにはできません。」「伸ばせません」が私の本意の答えである。「伸びている」「出来ている」が一番嬉しい子供達の成長の姿だと思う。
→教師として子供に「何々して上げる」「してやる」「してあげた」と言うのは2流、3流、未熟。思い上がりだと思っている。土台、環境造りをただ楽しく子供達と一緒にするそんな教師が理想だ。肩の力みが抜けている人が望ましい先生だと思っている。










 YOSH @yosh0316
YOSH @yosh0316



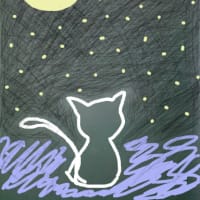
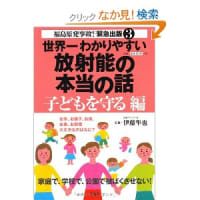
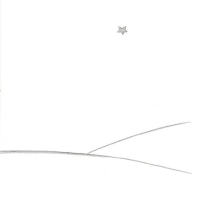
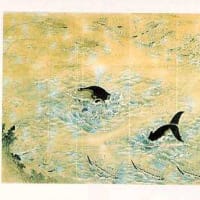

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます