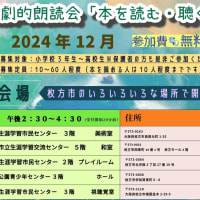またミキシングとも言えるなあ、と思っています。どんなものをどのように混ぜ込むか。そこに演出意図があります。
具体例を出せば、最近パブリックドメインになっているある戯曲をテキストレジしました。私は基本的にセリフの改変を良しとしないので、削っていく作業になります。それは12場ありましたが、メインの3場面(4,9,10場)と前後として2場と11場を短く挟み込みました。出立と別れの場面です。そしてここからさらに刈り込むわけですが、シンプルに登場人物を減らします。今回は思い切りよく主人公をカットしました・・・。まあそこにはお客さんが主人公を演じる(つまり劇中を旅していただく)という思考(嗜好?)があります。そして、メインの3場面も大きく前半と後半に分けて、さらにその半分の中でも序破急もしくは起承転結が出来るようにします。混ぜ込んだものとしては、時計の音ですね。最後のシーンで用いられるのですが、全場面その音で始まるようにしたのと、思い切って文学的表現満載のト書きを作者が読む、というシーンを入れ込みました。
もう一つの例は、他の人が書かれたある処女戯曲を上演台本にする過程です。みんなの要望を取り入れつつ書かれたこともあり、冗長な部分や、多少(効果としては)重複しているシーンがありました。そのため、結構大胆に組み替えました。これは裁判ものだったのですが、陪審員の話し合いを後半に集中させるために、前半に証人3人が出てくる裁判シーンを集め、後半部分も全部が全部ぐいぐいいくとしんどいので、ダレ場(押井守さんの言葉をお借りしています)を入れ込みながら、本音が漏れ出ていくシーンが入るような構成にしました。この作業をするときは、上記の例のように細かいシーンに分けて、最近好んで使うハリウッド型(もしくはディズニー)のドラマツルギー(という言葉を用いていいのか不勉強ですが)を使用してそれにのっとって作りました.
本当に紙に書いて、並べ替えていくのです。
これ、すごいもので、一旦書いてしまうと頭の中でちゃんと並べ替えられるようになるのが不思議で、寝ながら仕事できるなーっていう感じです。
最近の「演出の目」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事