
斎藤清/木版「目」1975年
今朝の福島民友新聞に木版画家・故斎藤清氏について室井東志生氏が
コメントをしていた。(以下、敬意をもって敬称略)
絵画をジャンル別に分けるべきかどうかは分からないが、筋の違う人が
評論をするということについて、いささか疑問を持ったので書いてみた。
どういうことかというと、同じ芸術でも例えて言うなら、演歌歌手が民謡
歌手についてどうこう評論できるかどうかに似ているかもしれない。
オペラ歌手とミュージカル俳優、似ているようだが、本当は違うハズだ。
室井東志生は日本画家だ。しかも、日展という画壇に属している。
この画壇という組織はけっこう複雑でやっかいである。
表向きは公募という形で広く一般から作品を募っているけれど、本当は
中心の聖域にはちっとやそっとでは入り込めない。何故なら、厳格な師弟
制度の上に成り立っており、いわゆる目上の先生からの推薦がなければ
ランキングは決して上がることはない。(このランク付けは日本固有の
もので、世界にそういう芸術のものさしや、評価を載せている年鑑など
は存在しない)聞くところによると、自らの先生のために相当な寄進を
しないとダメだという。自分の絵を売って先生に貢ぐのだ。そうすること
で次の展覧会には、○○君の作品が××賞にどうか・・・となる。
審査員になっても力関係が存在し、派閥に属さないと組織の上部に上がる
ことはできない。日本画界というものは特殊な構造になっていて、実力
(画力?)があったとしてもなかなか頭角を現すのに不適格な組織になっ
ているのだ。実力は当然のことだが、政治力も必要な世界なのだそうだ。
さて、そういう中心にいる日本画家が、斎藤清の芸術性についてそれら
しいコメントをしていることに疑問をもつ。ただ、斎藤清の木版画の晩年
の作品については、この日本画家がコメントすることは可能かも知れない。
斎藤清の会津の冬シリーズのように、ごく一般的な美しさを表現した画面
は、この日本画家が描いている舞妓や動物などの雅な感覚にも通ずるとこ
ろがあるとは思う。
しかし、斎藤清が画人として評価されている部分については、そういう
美しさという部分ではないのだ。斎藤清の初期作品に見られるような、
写実を単純化すること、画面構成を意図的に強調したりするなどの表現が
独自性があって苦労の末に自らの内側から搾り出されたものなのである。
そういう仕事に対して、美しさだけを追い求める仕事をする人が言える
ことがあるのかということだ。
昨日、県立美術館の常設展示室で初期の斎藤清の木版画を見てきた。
大画面の女性の頭部を大胆に描いた作品(1950年頃)は、創作版画
の道筋をつけたといわれている。つまり、それまでの見た目のありの
ままの姿を画面に写し取る写生ではなく、表現の仕方を変えて画面から
見る人が受ける感じ方についても、作家が意図的に仕組みを加えている
作風なのである。技術的にもいろいろと伝統の技法を織り交ぜながら
遊びがあって楽しい、そういう作品なのである。
そもそも、そういうことを考えながら作られた絵について、同じ絵描き
だから、同じ地方の出身だからということで話をされたのかもしれない。
芸術といわれるものはものさしがひとつでないので評論は難しい。
共感を得るということが評論ではないと思う。少なくとも、命がけで
絵を描いている人がいることは確かで、必死になって独自性を追求して
いる。画壇の内側に居て、上を見ながら絵を描いている人と、自分の
仕事に満足できなくて、気が狂わんばかりの状態でもがいているそういう
絵描きに会ったことがある。人間的に斎藤清は好きになれないが、初期
の仕事は筆舌に尽くしがたいものがあったと思うし、大好きな作品が
多い。
福島民友新聞の記事を載せた方が、このあたりまで考えていたかどうか
聞いてみたいようにも思う。
今朝の福島民友新聞に木版画家・故斎藤清氏について室井東志生氏が
コメントをしていた。(以下、敬意をもって敬称略)
絵画をジャンル別に分けるべきかどうかは分からないが、筋の違う人が
評論をするということについて、いささか疑問を持ったので書いてみた。
どういうことかというと、同じ芸術でも例えて言うなら、演歌歌手が民謡
歌手についてどうこう評論できるかどうかに似ているかもしれない。
オペラ歌手とミュージカル俳優、似ているようだが、本当は違うハズだ。
室井東志生は日本画家だ。しかも、日展という画壇に属している。
この画壇という組織はけっこう複雑でやっかいである。
表向きは公募という形で広く一般から作品を募っているけれど、本当は
中心の聖域にはちっとやそっとでは入り込めない。何故なら、厳格な師弟
制度の上に成り立っており、いわゆる目上の先生からの推薦がなければ
ランキングは決して上がることはない。(このランク付けは日本固有の
もので、世界にそういう芸術のものさしや、評価を載せている年鑑など
は存在しない)聞くところによると、自らの先生のために相当な寄進を
しないとダメだという。自分の絵を売って先生に貢ぐのだ。そうすること
で次の展覧会には、○○君の作品が××賞にどうか・・・となる。
審査員になっても力関係が存在し、派閥に属さないと組織の上部に上がる
ことはできない。日本画界というものは特殊な構造になっていて、実力
(画力?)があったとしてもなかなか頭角を現すのに不適格な組織になっ
ているのだ。実力は当然のことだが、政治力も必要な世界なのだそうだ。
さて、そういう中心にいる日本画家が、斎藤清の芸術性についてそれら
しいコメントをしていることに疑問をもつ。ただ、斎藤清の木版画の晩年
の作品については、この日本画家がコメントすることは可能かも知れない。
斎藤清の会津の冬シリーズのように、ごく一般的な美しさを表現した画面
は、この日本画家が描いている舞妓や動物などの雅な感覚にも通ずるとこ
ろがあるとは思う。
しかし、斎藤清が画人として評価されている部分については、そういう
美しさという部分ではないのだ。斎藤清の初期作品に見られるような、
写実を単純化すること、画面構成を意図的に強調したりするなどの表現が
独自性があって苦労の末に自らの内側から搾り出されたものなのである。
そういう仕事に対して、美しさだけを追い求める仕事をする人が言える
ことがあるのかということだ。
昨日、県立美術館の常設展示室で初期の斎藤清の木版画を見てきた。
大画面の女性の頭部を大胆に描いた作品(1950年頃)は、創作版画
の道筋をつけたといわれている。つまり、それまでの見た目のありの
ままの姿を画面に写し取る写生ではなく、表現の仕方を変えて画面から
見る人が受ける感じ方についても、作家が意図的に仕組みを加えている
作風なのである。技術的にもいろいろと伝統の技法を織り交ぜながら
遊びがあって楽しい、そういう作品なのである。
そもそも、そういうことを考えながら作られた絵について、同じ絵描き
だから、同じ地方の出身だからということで話をされたのかもしれない。
芸術といわれるものはものさしがひとつでないので評論は難しい。
共感を得るということが評論ではないと思う。少なくとも、命がけで
絵を描いている人がいることは確かで、必死になって独自性を追求して
いる。画壇の内側に居て、上を見ながら絵を描いている人と、自分の
仕事に満足できなくて、気が狂わんばかりの状態でもがいているそういう
絵描きに会ったことがある。人間的に斎藤清は好きになれないが、初期
の仕事は筆舌に尽くしがたいものがあったと思うし、大好きな作品が
多い。
福島民友新聞の記事を載せた方が、このあたりまで考えていたかどうか
聞いてみたいようにも思う。











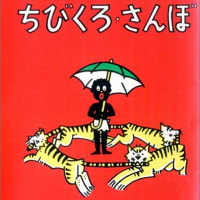








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます