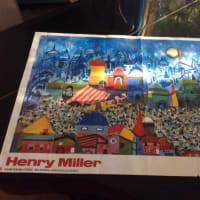入学から1年間が過ぎました・・・・
お陰様で、順調にスタートし、これを守った一年間でした。31、2人と少ない人数の学級規模にも恵まれました。チャイム着席、授業集中から始めました。暑い夏も、がんばりました。(来年はクーラー)
今でも、朝学習は「シーン」と取り組んでいます。授業も静かです。「2年生になってもこの調子でいこう。」と思います。上向きのスパイラルに加速をつけ「中だるみ」の時期を乗り越えていきましょう。
保護者のみなさん引きつづき、応援お願い致します。
以下、はじめの方針をふりかえってみます。
1,学年の教育目標は
|
3年間で 「基礎基本から自主自立へ」「自ら考え判断し行動できる生徒」「自分で進路を決定できる生徒」の育成をめざして、各学年の発達段階に応じて指導する。 |
→ 一定の到達を指導できたと考えます。「基礎基本」を重視し「自主自立」へ向けての布石がうてました。最後の移動教室で大きな成果が見られました。
2,具体的な指導内容と留意点
|
(1)基礎学力の充実と学習の習慣化を図り、教え合い、主体的に学習する生徒を育てる。 (2)人への思いやりの心を持ち、進んで協力し行動できる生徒を育てる。 (3)集団の一員としての自覚をもち、規律ある行動、団結する活動ができる生徒を育てる。 |
・学年教員は生徒一人一人と向き合いよく理解し、個性を生かしつつ協力共同して指導にあたる。
・保護者との連携を今まで以上に強くする。地域の理解を得て支援していただけるよう努力する。
→ 学級指導、委員会活動、行事などを通して一定の自主性、自律性を養うことができました。自治と自立へ向け指導を継続します。知的探求心や学習習慣は引き続き課題です。
学年教員は、力を合わせてがんばりました。何よりも保護者の協力が力となりました。
3.指導の重点
(1)学習指導・・・確かで豊かな基礎学力の向上
・学問の楽しさをたっぷりと ・わかる授業の工夫 ・反復練習
・教え合い学習・授業規律はきびしく ・本をたくさん読む ・家庭学習
→ チャイム着席・授業規律を重視し成果がありました。「学習表」の取り組み、放課後学習会、質問教室、教え合い学習で学習面での成果が見えてきました。
(2)生活指導・・・居場所のある落ち着いた学校生活
・指導が入るような生徒との関係づくり ・快適な生活のためのルールある学年づくり ・勇気づける共感的な対応と、ダメなことへの毅然とした対応の統一的指導
→ 学年教員・保護者・生徒の努力でよい状況に到達できました。「ルール」を守る意識を養いました。教員を信頼し、指導が入るようになりました。
問題行動に対しては、引き続き指導をします。
(3)進路指導・・・将来の希望や働くことについて学ぶ。
・保護者から学ぶ ・将来の夢や希望
・「身近な働く人に聞く」・「自分を知る」
→「働く人に聞く」は全員発表して、意識を高めました。常に親子のコミュニケーションをとる取り組みをしました。ご協力ありがとうございました。
(4)総合、学活など教科外活動
6月 校外学習 (班活動)
→各行事で「一致団結」をスローガンに取り組み成功しました。
・立川調べ・・・自分の町を知りません。発見!
→テーマ決定と発表のまとめ方を丁寧に指導しました。
・主張作文・・・7月から9月。市の主催。表現する力を。
→全員発表しました。
・定期考査・・・年間4回、計画表づくり、教え合い学習
→「計画を立て実行する」指導を重視しました。「自習力」が
課題です。
・三者面談・・・7月、12月。有意義な時間になるような事前の取り組み
→事前によく自分を見つめる取り組みに力を入れました。
保護者へも事前アンケートをお願いしました。たいへん役立ちました。
・学級活動・・・学級の問題の討議、学級レクレーション
→もう少し時間をとったほうが良かったと思いました。
・保健・給食・・健康・安全と栄養・マナーの知識と意識の向上
→日常的に指導し続けました。たいへんです。
・部活動・・・・より活発に激励
→やめないように声をかけ続けました。続かない子も多く、家庭で話し合いをお願いします。
(5)道徳の時間
教員が輪番で指導。生き方について、一生徒としてのマナーやモラルについて考える。
→各教員の個性ある授業が行なわれ、生徒も生き方を考える良い機会となりました。
(6)家庭・地域との連携
・何よりも日常的なつながり ・保護者会、懇談会、三者面談 ・学年PTA
→保護者会や行事への参加率は高く、熱心なご家庭が多く心強いです。2年生はいろいろと大変で大切な時期です。より積極的な協力をお願い致します。