
悩みがあります。
まぁただの気にしすぎでしょうが。
というのも、
このブログを読んでくれているいぼがえる氏が、
最近、
音沙汰がないのです。
と言ってもここ数日のことなので、
何をそんなに気にしているんだとか、
余計なお世話とか、
そう言われればそれまでですが、
やっぱりちょっと気になるのです。
超飽きっぽい私が、
ここまでネペンテス栽培記を続けてこれたのも、
間違いなくいぼがえる氏のおかげなので、
気にするなと言われても、
このままブログを続けていくのは難しい状態です。
私にムカついたとか、
失礼にあたることを書いてしまったとか、
思想が合わないとか、
そういう理由で離れていかれてしまったのなら、
その方がまだいい。
何も問題が起きてないのなら、
それでいいのですが、
やはり何かあったのかと気になってしまうのです。
ネットの世界なので、
お互いの素性も不明ですし、
何もどうすることもできないのですが、
いまできることは、
いぼがえる氏がいつでも帰ってこれるように、
ネペンテス栽培記を続けていくしかありません。
で、
せっかく続けていくのですから、
やはり高い目標を設定した方がいいかと思いまして。
高い目標となるとやはり、
「日本中にネペンテスを普及する」
現状ではこれ以外にないでしょう。
普及していく上でネックなのが、
1、知名度
2、栽培難易度
3、値段
だと思うんですよね。
ぶっちゃけ100円ショップに並べるくらいに大量生産に成功すれば、
もっと広まると思うんですよね。
で、
この上記1、2、3、の問題点をどう解決していくか、
これを今後テーマとして織り込んでネペンテス栽培記を続けていく、
とまぁ、
こういうことなわけですよ。
で、
今日はですね、
兼ねてから実験中だったネペンテスのまとめをしようかと。
まず表題の恐竜の卵なのですが、
話すと長くなりますので、
簡単にまとめますと、
~ 恐竜の卵のこれまでの流れ ~
ネペンテスをネットでゲット!
名前がネペンテス (バイキング×ラフレシアナ・ダーク)×ビカルカラタ・レッド!
おぼえられねーよ!
見た目が丸くて柄があるから恐竜の卵でいいや!
あっという間に枯れちった!
ちくしょー買いなおしだ!
同じ品種でも見た目が固体ごとに違うって聞いてねーよ!
四つも買ったけどどれも初代恐竜の卵に似てねーよ!
見た目違うけど同じようなのがこんなにある!
じゃあせっかくだから実験に使うか!
とまぁ、
こんな流れなわけですよ。
話しを進めまして、
ネペンテスの簡単栽培に向け、
さっそく一つの鉢に3つ並べて植えつけてみたわけですよ。
今年(2014年)7月31日の植え付け当時の写真

初めて用土として生ミズゴケを導入し、
どう扱えばいいのか、
練習も兼ねてのことでした。
生きた用土というのは始めてで、
その可能性の大きさに興奮したのをおぼえています。
これが約一ヵ月後の8月24日の状態

微妙に成長している。
ネペンテスじゃなくて生ミズゴケがだけど。

ネペンテスの成長自体は緩慢で、
特に生ミズゴケが効いているという感じはありませんでした。
ただ、
この実験のおかげで、
私の栽培技術が飛躍的に進歩しました。
簡単栽培の道が開けたと言っても過言ではありません。
百聞は一見にしかず。
さらに一ヶ月たった9月21日現在の様子を見てみましょう。
これが現在の状態。

どうよこれ

みずみずし過ぎでしょこれ。
成長し過ぎてネペンテス呑み込んじゃってるからねこれ。

まだ実験段階ですが、
生ミズゴケを使いこなし始めてると見ていいのではないでしょうか。
環境も整ってきましたので、
ネペンテスも順調に袋をつけ始めています。
これが一番新しい袋。

ど派手な柄のネペンテスが多い中、
これはこれで風情があっていいのかもしれません。
なんとなく、
ネペンテス栽培の初心を思い出させてくれます。
ビカルカラタの血が入ってるので、
おさえるとこはおさえたキレイなデザイン。
まだ小苗ですが、
発展途上の牙らしきものが、
愛着をわかせてくれます。

うん、
いいかもしれません。
実験とは言え、
大事に育てていきます。
本当に基本的なネペンテスという感じ。

この恐竜の卵には本当に感謝しています。
栽培していく上で、
色々なことがわかりましたからね。
もうちょっと観察を続けたら、
新たな栽培用の鉢の作成に着手した意と思います。
ただの入れ物だった、
ネペンテス用の鉢、
プロトタイプ。
それを進化させたプロトタイプ2。
さらに見た目を重視した育てる鉢、
プロトタイプ3。
今度は新たに、
室内専用の鉢として、
プロトタイプ4を考案しています。
室内栽培の欠点は、
日照不足。
解消するためには、
窓際に置くという選択肢になるはず。
ここにネペンテス普及の鍵が隠されていると思うわけですよ。
現在は冬季に備えて室内栽培に移行したため、
実験にはもってこいの状態です。
恐竜の卵たちには、
もうひと踏ん張りしてもらうことになりますが、
その功績はとてつもなく大きいと思っています。
ではでは、
また次回をお楽しみに。
いぼがえる氏以外、
誰も見てない可能性もありますが。
まぁただの気にしすぎでしょうが。
というのも、
このブログを読んでくれているいぼがえる氏が、
最近、
音沙汰がないのです。
と言ってもここ数日のことなので、
何をそんなに気にしているんだとか、
余計なお世話とか、
そう言われればそれまでですが、
やっぱりちょっと気になるのです。
超飽きっぽい私が、
ここまでネペンテス栽培記を続けてこれたのも、
間違いなくいぼがえる氏のおかげなので、
気にするなと言われても、
このままブログを続けていくのは難しい状態です。
私にムカついたとか、
失礼にあたることを書いてしまったとか、
思想が合わないとか、
そういう理由で離れていかれてしまったのなら、
その方がまだいい。
何も問題が起きてないのなら、
それでいいのですが、
やはり何かあったのかと気になってしまうのです。
ネットの世界なので、
お互いの素性も不明ですし、
何もどうすることもできないのですが、
いまできることは、
いぼがえる氏がいつでも帰ってこれるように、
ネペンテス栽培記を続けていくしかありません。
で、
せっかく続けていくのですから、
やはり高い目標を設定した方がいいかと思いまして。
高い目標となるとやはり、
「日本中にネペンテスを普及する」
現状ではこれ以外にないでしょう。
普及していく上でネックなのが、
1、知名度
2、栽培難易度
3、値段
だと思うんですよね。
ぶっちゃけ100円ショップに並べるくらいに大量生産に成功すれば、
もっと広まると思うんですよね。
で、
この上記1、2、3、の問題点をどう解決していくか、
これを今後テーマとして織り込んでネペンテス栽培記を続けていく、
とまぁ、
こういうことなわけですよ。
で、
今日はですね、
兼ねてから実験中だったネペンテスのまとめをしようかと。
まず表題の恐竜の卵なのですが、
話すと長くなりますので、
簡単にまとめますと、
~ 恐竜の卵のこれまでの流れ ~
ネペンテスをネットでゲット!
名前がネペンテス (バイキング×ラフレシアナ・ダーク)×ビカルカラタ・レッド!
おぼえられねーよ!
見た目が丸くて柄があるから恐竜の卵でいいや!
あっという間に枯れちった!
ちくしょー買いなおしだ!
同じ品種でも見た目が固体ごとに違うって聞いてねーよ!
四つも買ったけどどれも初代恐竜の卵に似てねーよ!
見た目違うけど同じようなのがこんなにある!
じゃあせっかくだから実験に使うか!
とまぁ、
こんな流れなわけですよ。
話しを進めまして、
ネペンテスの簡単栽培に向け、
さっそく一つの鉢に3つ並べて植えつけてみたわけですよ。
今年(2014年)7月31日の植え付け当時の写真

初めて用土として生ミズゴケを導入し、
どう扱えばいいのか、
練習も兼ねてのことでした。
生きた用土というのは始めてで、
その可能性の大きさに興奮したのをおぼえています。
これが約一ヵ月後の8月24日の状態

微妙に成長している。
ネペンテスじゃなくて生ミズゴケがだけど。

ネペンテスの成長自体は緩慢で、
特に生ミズゴケが効いているという感じはありませんでした。
ただ、
この実験のおかげで、
私の栽培技術が飛躍的に進歩しました。
簡単栽培の道が開けたと言っても過言ではありません。
百聞は一見にしかず。
さらに一ヶ月たった9月21日現在の様子を見てみましょう。
これが現在の状態。

どうよこれ

みずみずし過ぎでしょこれ。
成長し過ぎてネペンテス呑み込んじゃってるからねこれ。

まだ実験段階ですが、
生ミズゴケを使いこなし始めてると見ていいのではないでしょうか。
環境も整ってきましたので、
ネペンテスも順調に袋をつけ始めています。
これが一番新しい袋。

ど派手な柄のネペンテスが多い中、
これはこれで風情があっていいのかもしれません。
なんとなく、
ネペンテス栽培の初心を思い出させてくれます。
ビカルカラタの血が入ってるので、
おさえるとこはおさえたキレイなデザイン。
まだ小苗ですが、
発展途上の牙らしきものが、
愛着をわかせてくれます。

うん、
いいかもしれません。
実験とは言え、
大事に育てていきます。
本当に基本的なネペンテスという感じ。

この恐竜の卵には本当に感謝しています。
栽培していく上で、
色々なことがわかりましたからね。
もうちょっと観察を続けたら、
新たな栽培用の鉢の作成に着手した意と思います。
ただの入れ物だった、
ネペンテス用の鉢、
プロトタイプ。
それを進化させたプロトタイプ2。
さらに見た目を重視した育てる鉢、
プロトタイプ3。
今度は新たに、
室内専用の鉢として、
プロトタイプ4を考案しています。
室内栽培の欠点は、
日照不足。
解消するためには、
窓際に置くという選択肢になるはず。
ここにネペンテス普及の鍵が隠されていると思うわけですよ。
現在は冬季に備えて室内栽培に移行したため、
実験にはもってこいの状態です。
恐竜の卵たちには、
もうひと踏ん張りしてもらうことになりますが、
その功績はとてつもなく大きいと思っています。
ではでは、
また次回をお楽しみに。
いぼがえる氏以外、
誰も見てない可能性もありますが。
















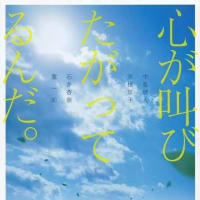






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます