
というわけで、
さっそく挿し木にチャレンジしてみました。
今回の記事から、
記録も兼ねて詳細に書いていこうと思います。
今回選択した品種はこちら。
1 マキシマ×ビーチ・ハイランド・ストライプ
2 プロスペリティ×アンプラリア・トリカラー
3 (バイキング×ラフレシアナ)×(ラフレシアナ×メリリアナ)
4 バイキング×フーケリアナ斑点
以上の四種です。
未経験のものを、
いきなり多数で行うリスクは当然ありますが、
もし単体で失敗した場合、
品種による難易度の差なのか、
挿し木方法によるものなのか、
管理の問題なのか、
検証が曖昧になってしまうため、
敢えて挿し木候補を増やしました。
多数同時は、
リスクに見合うだけのリターンはあると確信しています。
参考までに、
二種しかありませんが、
過去に撮った写真がこちら。
(バイキング×ラフレシアナ)×(ラフレシアナ×メリリアナ)

バイキング×フーケリアナ斑点 (※同交配の種ですが、画像とは別固体)

奇しくも根が発達しやすい種が選抜されたのは、
とても幸運なことかもしれません。
もしくは、
その根の発達自体に秘密があり、
選ばれるべくして選ばれたのか、
とても興味深いところです。
選択理由は以下
1 脇芽が出ている
2 徒長気味である
3 袋をつける様子が無い
の三つです。
成長がぐずついてる植物の、
いわゆる挿し木更新的な意味合いもありますが、
ネペンテスの場合、
徒長して袋がつかないのは、
逆に成長が順調である、
というのが私の考えです。
なので、
根から潤沢であった水分供給を断ち、
光合成に必要な葉を切ってやれば、
慌てて袋を生成するのでは、
と睨んだのです。
もしこの理論が多少なりとも正しければ、
挿し木の成功後、
ネペンテスは直ちに袋の生成を開始するはず。
ただ、
袋を作るには、
かなりのエネルギーを消費するのは想像に難くないわけで、
そうなると、
少しでもエネルギーが余ってそうな固体、
つまり上記の条件に合致したものが良いと判断したわけです。
(バイキング×ラフレシアナ)×(ラフレシアナ×メリリアナ)なんかは、
私の栽培下で生き残ってくれたお気に入り品種であり、
失敗はできない状況です。
ものぐさな私ですが、
ネペンテスの植替えだけは慎重に行います。
具体的に言えば事前準備です。
今まで行ってきた、
他の観葉植物の挿し木を参考に、
以下のものを準備しました。

植替え作業ケース
芽切りばさみ
切り口に塗る被覆塗布剤
植えつけ用のペットボトルを加工した枠(見づらいですが作業ケース内にあるやつ)
乾燥ミズゴケを水につけたもの
秘密兵器の生ミズゴケ
以上です。
芽切りばさみは剪定ばさみと違って、
より正確に狙った場所を切れますのでチョイスしました。
被覆塗布剤は殺菌作用があり、
切り口からの枯れこみを防ぐ
という用途が主ですが、
私は切り口からの余計な水分蒸発防止で塗ります。
根が弱い植物には今のところ抜群の効果を発揮しています。
塗らなくてもほとんどの植物は大丈夫ですが、
今回は念を入れて使用します。
ちなみに水分蒸発防止目的なら、
ボンドでも接着剤でもシールでも、
水に溶けずにはがれ落ちないやつならなんでも大丈夫です。
参考までに。
市販品の中には、
発根促進剤なる便利な薬剤もあるようですが、
今回は使用しません。
成長に必要な栄養素であったり、
ホルモン促進の効果があるのかもしれませんが、
ネペンテスはちょっと奇異な植物体であるため、
余計なことをして成長のバランスを崩したくなかったのです。
すいません、
かっこつけちゃいました。
持ってないってのが一番の理由です。
切り戻し前の状態のネペンテス達

袋が残ってる種もありますが、
袋つきだった方が成功しやすいのかどうかの検証のため、
もったいないですが
後学のため例外的に挿し木選抜に組み込みました。
さて、
どこから切るかが今回の最大の争点ですが、
一週間前から全ネペンテスを入念にリサーチした結果、
ネペンテスの脇芽は例外なく葉の根元、
もしくは少し上から発生しています。
つまりここを余分に残した状態でカットする、
というのがベストな選択ではないでしょうか。

ちなみに、
今回は脇芽を残し、
徒長した部分をカットする、
という内容の挿し木を行います。
念のため。
といわけで、
切ってみました。

残された本体に、
すぐに塗布剤をぬり、
水分蒸発をシャットアウト。
どの程度の長さを残し、
どの部分から挿し木が成功しやすいのか、
記録を取るためにいくつかに分断してみました。

過剰な水分放出防止のため、
葉もほとんどカットします。
この要領で、
どんどん切っていきます。

水に数十分~数時間つけるべきかどうか、
非常に迷うところですが、
これまでの経験上、
私はまったく時間をかけません。
即座に植付け開始します。
水につけてもつけなくても、
他の観葉植物の挿し木成功率は変わらなかったからです。
ただ、
多肉やサボテン、
強健な樹木類以外の、
植替えまでの待機中は乾燥厳禁のため、
キレイな水の張った入れ物を用意しておくのが無難です。
様々なパターンで切り分けました。

案の定、
予想はしていましたが、
どれがどれだか全然わかりません

葉っぱも切り落としてしまったため、
もう何がなにやら。
袋が出来るまでのお楽しみになってしまいました、
本来ならばここで植込み開始といきたいとこですが、
予想以上にネペンテスの幹は貧弱で、
ミズゴケの中ではうまく立ちません。
それどころか、
幹とミズゴケの間に隙間が出来てしまい、
これでは切り口が乾燥してしまいます。
そのため、
急遽ビニール紐でミズゴケを巻きつけ、
その後に植込むことにしました。
簡単栽培が目標なはずなのに、
思ったより手間がかかります。
これでよし。

ミズゴケは房状になっているため、
簡単にまとめて縛れます。
5分もかかりません。
発根が確認できたらビニール紐は切り取ることにします。
仕上げの植込み方法ですが、
前回ご紹介した室内の大型ネペンテス栽培場である、
第3スペースの栽培ケースに直に植込むことにしました。

ケース内は水遣りで余った水が常にたまっており、
乾燥の危険がないと判断したためです。
他の用度から流れ出た老廃物が溜まっている状態なので、
腐敗などの衛生面ではどうかという意見もあるでしょうが、
ネペンテスの用土は基本的に酸性のため、
目に見えて腐ることはほとんどありません。
むしろ鉢から流れ出た水が、
カルキの抜けた適温の酸性に保たれているので、
ネペンテスの幼苗の育成には好都合です。
こんな感じになりました。

観賞用自作鉢、
プロトタイプ3のノウハウを生かしてあるので、
ただの枠にミズゴケを置いてあるだけです。
底はなく、
水のたまったケースに直置きです。

グループ分けの概要は、
根元に近い部分、
中間部分、
頂点芽がある先端部分、
の三つです。
根元に近い部分と中間部分は、
見分けがつかなくなってしまったため、
事前に記録用に撮った写真で見比べながら分別しました。
いやー、
スマホとブログの組み合わせって本当に便利ですね。
記録用に、
投稿してない画像中心の下書き記事があるのですが、
困ったらこれを見れば、
過去どんな状態だったか瞬時に分かるわけですからね。
まぁ、
幹しか映ってないから種類わからなかったけど

一応、
本命は頂点芽を中心とした挿し木部分です。
やはり、
まだ木質化してないため、
成長に対して柔軟性があり、
成長点なので当然、
栄養が特に集中しやすいこと。
それに加えさらに、
すでに芽があるというアドバンテージは、
相当に大きいと考えています。
対して幹部分は、
固くなった部位で、
発根と発芽の大仕事を同時に行わなければならないため、
途中で力尽きる可能性大と思った方がいいでしょう。
発根の様子も表面ではわかりづらいため、
今後の経過による状態変化の観察は至難と見ています。
成功した場合は、
ブログを応援してくださるいぼがえる氏に、
どれか好きなものをプレゼントしようと予定しているため、
なんとしても発根まではこぎつけたいところです。
いらないって言われたらそれまでですが。
ここまでが、
今日から始める挿し木増殖計画の経過報告 その1
となります。
他の植物の挿し木経過で予想すると、
早くて二週間、
遅くて一ヶ月半ということになりそうです。
逆に、
それ以上経過して動きが無い場合、
植物体に余力が残されている可能性は低く、
植込み方法から見て腐敗は免れないため、
失敗ということになります。
以上を考慮して、
経過報告スパンは一週間くらいが妥当と言ったところでしょうか。
他の予定の時間も押してますので、
今日はこの辺で。
ではでは、
次回をお楽しみに。
さっそく挿し木にチャレンジしてみました。
今回の記事から、
記録も兼ねて詳細に書いていこうと思います。
今回選択した品種はこちら。
1 マキシマ×ビーチ・ハイランド・ストライプ
2 プロスペリティ×アンプラリア・トリカラー
3 (バイキング×ラフレシアナ)×(ラフレシアナ×メリリアナ)
4 バイキング×フーケリアナ斑点
以上の四種です。
未経験のものを、
いきなり多数で行うリスクは当然ありますが、
もし単体で失敗した場合、
品種による難易度の差なのか、
挿し木方法によるものなのか、
管理の問題なのか、
検証が曖昧になってしまうため、
敢えて挿し木候補を増やしました。
多数同時は、
リスクに見合うだけのリターンはあると確信しています。
参考までに、
二種しかありませんが、
過去に撮った写真がこちら。
(バイキング×ラフレシアナ)×(ラフレシアナ×メリリアナ)

バイキング×フーケリアナ斑点 (※同交配の種ですが、画像とは別固体)

奇しくも根が発達しやすい種が選抜されたのは、
とても幸運なことかもしれません。
もしくは、
その根の発達自体に秘密があり、
選ばれるべくして選ばれたのか、
とても興味深いところです。
選択理由は以下
1 脇芽が出ている
2 徒長気味である
3 袋をつける様子が無い
の三つです。
成長がぐずついてる植物の、
いわゆる挿し木更新的な意味合いもありますが、
ネペンテスの場合、
徒長して袋がつかないのは、
逆に成長が順調である、
というのが私の考えです。
なので、
根から潤沢であった水分供給を断ち、
光合成に必要な葉を切ってやれば、
慌てて袋を生成するのでは、
と睨んだのです。
もしこの理論が多少なりとも正しければ、
挿し木の成功後、
ネペンテスは直ちに袋の生成を開始するはず。
ただ、
袋を作るには、
かなりのエネルギーを消費するのは想像に難くないわけで、
そうなると、
少しでもエネルギーが余ってそうな固体、
つまり上記の条件に合致したものが良いと判断したわけです。
(バイキング×ラフレシアナ)×(ラフレシアナ×メリリアナ)なんかは、
私の栽培下で生き残ってくれたお気に入り品種であり、
失敗はできない状況です。
ものぐさな私ですが、
ネペンテスの植替えだけは慎重に行います。
具体的に言えば事前準備です。
今まで行ってきた、
他の観葉植物の挿し木を参考に、
以下のものを準備しました。

植替え作業ケース
芽切りばさみ
切り口に塗る被覆塗布剤
植えつけ用のペットボトルを加工した枠(見づらいですが作業ケース内にあるやつ)
乾燥ミズゴケを水につけたもの
秘密兵器の生ミズゴケ
以上です。
芽切りばさみは剪定ばさみと違って、
より正確に狙った場所を切れますのでチョイスしました。
被覆塗布剤は殺菌作用があり、
切り口からの枯れこみを防ぐ
という用途が主ですが、
私は切り口からの余計な水分蒸発防止で塗ります。
根が弱い植物には今のところ抜群の効果を発揮しています。
塗らなくてもほとんどの植物は大丈夫ですが、
今回は念を入れて使用します。
ちなみに水分蒸発防止目的なら、
ボンドでも接着剤でもシールでも、
水に溶けずにはがれ落ちないやつならなんでも大丈夫です。
参考までに。
市販品の中には、
発根促進剤なる便利な薬剤もあるようですが、
今回は使用しません。
成長に必要な栄養素であったり、
ホルモン促進の効果があるのかもしれませんが、
ネペンテスはちょっと奇異な植物体であるため、
余計なことをして成長のバランスを崩したくなかったのです。
すいません、
かっこつけちゃいました。
持ってないってのが一番の理由です。
切り戻し前の状態のネペンテス達

袋が残ってる種もありますが、
袋つきだった方が成功しやすいのかどうかの検証のため、
もったいないですが
後学のため例外的に挿し木選抜に組み込みました。
さて、
どこから切るかが今回の最大の争点ですが、
一週間前から全ネペンテスを入念にリサーチした結果、
ネペンテスの脇芽は例外なく葉の根元、
もしくは少し上から発生しています。
つまりここを余分に残した状態でカットする、
というのがベストな選択ではないでしょうか。

ちなみに、
今回は脇芽を残し、
徒長した部分をカットする、
という内容の挿し木を行います。
念のため。
といわけで、
切ってみました。

残された本体に、
すぐに塗布剤をぬり、
水分蒸発をシャットアウト。
どの程度の長さを残し、
どの部分から挿し木が成功しやすいのか、
記録を取るためにいくつかに分断してみました。

過剰な水分放出防止のため、
葉もほとんどカットします。
この要領で、
どんどん切っていきます。

水に数十分~数時間つけるべきかどうか、
非常に迷うところですが、
これまでの経験上、
私はまったく時間をかけません。
即座に植付け開始します。
水につけてもつけなくても、
他の観葉植物の挿し木成功率は変わらなかったからです。
ただ、
多肉やサボテン、
強健な樹木類以外の、
植替えまでの待機中は乾燥厳禁のため、
キレイな水の張った入れ物を用意しておくのが無難です。
様々なパターンで切り分けました。

案の定、
予想はしていましたが、
どれがどれだか全然わかりません

葉っぱも切り落としてしまったため、
もう何がなにやら。
袋が出来るまでのお楽しみになってしまいました、
本来ならばここで植込み開始といきたいとこですが、
予想以上にネペンテスの幹は貧弱で、
ミズゴケの中ではうまく立ちません。
それどころか、
幹とミズゴケの間に隙間が出来てしまい、
これでは切り口が乾燥してしまいます。
そのため、
急遽ビニール紐でミズゴケを巻きつけ、
その後に植込むことにしました。
簡単栽培が目標なはずなのに、
思ったより手間がかかります。
これでよし。

ミズゴケは房状になっているため、
簡単にまとめて縛れます。
5分もかかりません。
発根が確認できたらビニール紐は切り取ることにします。
仕上げの植込み方法ですが、
前回ご紹介した室内の大型ネペンテス栽培場である、
第3スペースの栽培ケースに直に植込むことにしました。

ケース内は水遣りで余った水が常にたまっており、
乾燥の危険がないと判断したためです。
他の用度から流れ出た老廃物が溜まっている状態なので、
腐敗などの衛生面ではどうかという意見もあるでしょうが、
ネペンテスの用土は基本的に酸性のため、
目に見えて腐ることはほとんどありません。
むしろ鉢から流れ出た水が、
カルキの抜けた適温の酸性に保たれているので、
ネペンテスの幼苗の育成には好都合です。
こんな感じになりました。

観賞用自作鉢、
プロトタイプ3のノウハウを生かしてあるので、
ただの枠にミズゴケを置いてあるだけです。
底はなく、
水のたまったケースに直置きです。

グループ分けの概要は、
根元に近い部分、
中間部分、
頂点芽がある先端部分、
の三つです。
根元に近い部分と中間部分は、
見分けがつかなくなってしまったため、
事前に記録用に撮った写真で見比べながら分別しました。
いやー、
スマホとブログの組み合わせって本当に便利ですね。
記録用に、
投稿してない画像中心の下書き記事があるのですが、
困ったらこれを見れば、
過去どんな状態だったか瞬時に分かるわけですからね。
まぁ、
幹しか映ってないから種類わからなかったけど

一応、
本命は頂点芽を中心とした挿し木部分です。
やはり、
まだ木質化してないため、
成長に対して柔軟性があり、
成長点なので当然、
栄養が特に集中しやすいこと。
それに加えさらに、
すでに芽があるというアドバンテージは、
相当に大きいと考えています。
対して幹部分は、
固くなった部位で、
発根と発芽の大仕事を同時に行わなければならないため、
途中で力尽きる可能性大と思った方がいいでしょう。
発根の様子も表面ではわかりづらいため、
今後の経過による状態変化の観察は至難と見ています。
成功した場合は、
ブログを応援してくださるいぼがえる氏に、
どれか好きなものをプレゼントしようと予定しているため、
なんとしても発根まではこぎつけたいところです。
いらないって言われたらそれまでですが。
ここまでが、
今日から始める挿し木増殖計画の経過報告 その1
となります。
他の植物の挿し木経過で予想すると、
早くて二週間、
遅くて一ヶ月半ということになりそうです。
逆に、
それ以上経過して動きが無い場合、
植物体に余力が残されている可能性は低く、
植込み方法から見て腐敗は免れないため、
失敗ということになります。
以上を考慮して、
経過報告スパンは一週間くらいが妥当と言ったところでしょうか。
他の予定の時間も押してますので、
今日はこの辺で。
ではでは、
次回をお楽しみに。
















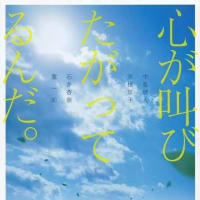






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます