はい、
というわけで、
今日からお送りするネペンテス情報局、
その記念すべき初日から、
大スクープが飛び出しましたので、
さっそくご報告を。
その前に、
ネペンテス情報局の概要ですが、
三つの部門から成り立っています。
まず今回のようにブログ投稿する、
ネペンテス情報発信部です。
活動内容は、
この通り、
様々な発見や記録をネットにアップしていくのが中心です。
研究の結果報告が重要な仕事となっております。
その他のカテゴリーに画像や情報を提供するのも任務の一つです。
そのうち、
撮影班が独立したり、
分譲部門を立ち上げたりする可能性がありますが、
それはまだ先の話し。
もう一つは、
ネペンテス通常管理部門です。
栽培場のネペンテス達を大切に管理する、
それ以上でもそれ以下でもない、
もしかしたら一番大事かもしれない部門です。
基本的にありのままの情報元となるため、
袋がついたとか、
成長が著しいとか、
そんな感じの部門です。
そして最後、
満を持して設立した、
ネペンテス研究開発部。
その名の通り、
実験や研究を通して、
様々な角度からネペンテスの秘密に迫る、
ネペンテス栽培記の肝となるメイン機関です。
これまで、
自作鉢の開発や、
挿し木増殖、
生ミズゴケの培養など、
数々の実績を残しており、
実力は十分といった感じです。
現在、
通常管理部門と共同で、
大型プロジェクトが進行中のようなので、
まだシークレットの段階ですが、
発表を楽しみに待ちたいと思います。
以上の構成からなるネペンテス情報局、
ようやく話が戻りまして、
今日はなんと、
研究開発部から重大ニュースが飛び込んできたので、
さっそく発表したいと思います。
題して、
ついに解き明かされる、
ネペンテス袋生成の知られざるトリガー発動条件
です。
やりました。
ついにやりましたよ。
苦節一年、
ようやく、
安定した袋の生成方法を発見したかもしれません。
以前のネペンテス栽培記にて、
袋がつかない要因として、
以下の五つに絞ったと言う話がありました。
1 光の量
2 温度
3 湿度
4 風
5 土
ブログ上ではその日だけで、
その後その話しは打ち切りのようになっていましたが、
実は研究開発部の方で、
以前とその後もずっと検証を続けておりまして。
で、
それぞれの条件の元、
密閉してみたり、
風を当ててみたり、
植替えしてみたり、
暖かくしてみたりと、
一つずつ試してみたのですが、
ついに、
断トツで効果が期待できる要素を発見いたしました!
それがこちら!
ズバリ、
日照時間
これです!
我々は、
大切なことを忘れていたのです。
そう、
ネペンテスは工芸品ではなく、
植物であるということを。
まずは研究成果をご覧ください。
※ クラッチとは
ネペンテスが袋生成に入る初期段階のことを、
普及委員会では勝手にそう呼んでいます。
袋の元が生成に入る予兆を見せることを、
クラッチが入ると表現しています。
実験NO1
まったく袋をつける様子のなかったネペンテスが、
いきなりクラッチ状態。

実験NO2
半年間、
うんともすんとも言わなかったネペンテスが、
NO1と合わせてまさかのダブルクラッチ。

実験NO3
新しい葉が出来上がる前に、
驚きの先行クラッチ。

実験NO4
購入以来、
一度も袋を生成せず、
すっかりあきらめていたネペンテスに、
待望のクラッチが入る。

実験NO5
一年間、
なにをしても袋をつけなかったネペンテスが、
嬉しすぎる白きクラッチ入力。

どうですかこれ。
一個や二個だったら、
偶然というかたまたまかもしれませんが、
全部ですよこれ。
しかも、
袋をつけないで有名な、
普及委員会でも有数の猛者を集めた結果ですよこれ。
しかもしかも、
複数個を実験にセットする前に試した初期ロットなんか、
10日間でこの状態ですからね。

現在、
さらなる成果を求めてデータを収集中です。
結果がまとまれば、
今後の普及委員会の活動に大きく貢献してくれることは、
もはや疑いようもありません。
続報を期待してお待ちください。
以上、
ネペンテス情報局でした。
というわけで、
今日からお送りするネペンテス情報局、
その記念すべき初日から、
大スクープが飛び出しましたので、
さっそくご報告を。
その前に、
ネペンテス情報局の概要ですが、
三つの部門から成り立っています。
まず今回のようにブログ投稿する、
ネペンテス情報発信部です。
活動内容は、
この通り、
様々な発見や記録をネットにアップしていくのが中心です。
研究の結果報告が重要な仕事となっております。
その他のカテゴリーに画像や情報を提供するのも任務の一つです。
そのうち、
撮影班が独立したり、
分譲部門を立ち上げたりする可能性がありますが、
それはまだ先の話し。
もう一つは、
ネペンテス通常管理部門です。
栽培場のネペンテス達を大切に管理する、
それ以上でもそれ以下でもない、
もしかしたら一番大事かもしれない部門です。
基本的にありのままの情報元となるため、
袋がついたとか、
成長が著しいとか、
そんな感じの部門です。
そして最後、
満を持して設立した、
ネペンテス研究開発部。
その名の通り、
実験や研究を通して、
様々な角度からネペンテスの秘密に迫る、
ネペンテス栽培記の肝となるメイン機関です。
これまで、
自作鉢の開発や、
挿し木増殖、
生ミズゴケの培養など、
数々の実績を残しており、
実力は十分といった感じです。
現在、
通常管理部門と共同で、
大型プロジェクトが進行中のようなので、
まだシークレットの段階ですが、
発表を楽しみに待ちたいと思います。
以上の構成からなるネペンテス情報局、
ようやく話が戻りまして、
今日はなんと、
研究開発部から重大ニュースが飛び込んできたので、
さっそく発表したいと思います。
題して、
ついに解き明かされる、
ネペンテス袋生成の知られざるトリガー発動条件
です。
やりました。
ついにやりましたよ。
苦節一年、
ようやく、
安定した袋の生成方法を発見したかもしれません。
以前のネペンテス栽培記にて、
袋がつかない要因として、
以下の五つに絞ったと言う話がありました。
1 光の量
2 温度
3 湿度
4 風
5 土
ブログ上ではその日だけで、
その後その話しは打ち切りのようになっていましたが、
実は研究開発部の方で、
以前とその後もずっと検証を続けておりまして。
で、
それぞれの条件の元、
密閉してみたり、
風を当ててみたり、
植替えしてみたり、
暖かくしてみたりと、
一つずつ試してみたのですが、
ついに、
断トツで効果が期待できる要素を発見いたしました!
それがこちら!
ズバリ、
日照時間
これです!
我々は、
大切なことを忘れていたのです。
そう、
ネペンテスは工芸品ではなく、
植物であるということを。
まずは研究成果をご覧ください。
※ クラッチとは
ネペンテスが袋生成に入る初期段階のことを、
普及委員会では勝手にそう呼んでいます。
袋の元が生成に入る予兆を見せることを、
クラッチが入ると表現しています。
実験NO1
まったく袋をつける様子のなかったネペンテスが、
いきなりクラッチ状態。

実験NO2
半年間、
うんともすんとも言わなかったネペンテスが、
NO1と合わせてまさかのダブルクラッチ。

実験NO3
新しい葉が出来上がる前に、
驚きの先行クラッチ。

実験NO4
購入以来、
一度も袋を生成せず、
すっかりあきらめていたネペンテスに、
待望のクラッチが入る。

実験NO5
一年間、
なにをしても袋をつけなかったネペンテスが、
嬉しすぎる白きクラッチ入力。

どうですかこれ。
一個や二個だったら、
偶然というかたまたまかもしれませんが、
全部ですよこれ。
しかも、
袋をつけないで有名な、
普及委員会でも有数の猛者を集めた結果ですよこれ。
しかもしかも、
複数個を実験にセットする前に試した初期ロットなんか、
10日間でこの状態ですからね。

現在、
さらなる成果を求めてデータを収集中です。
結果がまとまれば、
今後の普及委員会の活動に大きく貢献してくれることは、
もはや疑いようもありません。
続報を期待してお待ちください。
以上、
ネペンテス情報局でした。
















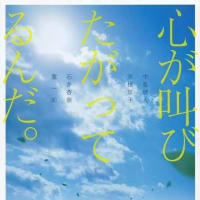






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます