
ネペンテス マキシマ・ダーク×(ノーシアナ×ビーチ)
ですが、
今までで一番大きな葉をつけそうです。

めちゃ期待しています。
葉が出来る前のデザインは、
一番かっこいいかもしれません。

ネペンテス マキシマ・ダーク×(ノーシアナ×ビーチ)は、
大きすぎる袋対策のためか、
葉の先端ではなく、
途中から袋の蔓を伸ばします。
なので、
ちょっと独特のシルエットになるんですね。

この部分です。

で、
本日の表題なのですが、
ネペンテスの栽培を本格的に始めて早1年。
そこそこ、
ネペンテスのことが理解でき始めてると勘違いしていると、
すぐに問題が出てくるんですよね。
それがこれ、
袋がつかない問題

当初から懸案事項だったので、
何を今さらな感じですが、
これは本当に困っています。
ひどいのになると、
購入してから一年近くたつのに、
一個も袋をつけたことのないものまでありますからね。
ただの葉っぱですよほんと。
もちろん、
ただ袋がつかないなと、
漠然と眺めていたわけではありません。
一応、
原因は以下の五つに絞りました。
1 光の量
2 温度
3 湿度
4 風
5 土
この五つの条件が揃うと、
袋が出来やすくなると判断しました。
まず1の光の量ですが、
これには2つの要素がありまして、
それは光の強さと時間の関係です。
袋をまったくつけないネペンテスがいる一方で、
ポコポコとつけるものも存在します。
ポコポコつける方はスイッチがあるようで、
強い光にさらすとつけやすくなる、
という事実に気づきました。
で、
さらに光を当て続けると、
安定して袋を作り続けることがわかったのです。
で、
ここからがおもしろいところなのですが、
じゃあ全部強い光に当てればいいじゃんってことで、
他も試してみたのですが、
葉っぱばかり立派になったり、
逆に葉が萎縮したりと、
うまくいきませんでした。
ここで考えたのですが、
ネペンテスそれぞれに、
最適な光量があるではないか、
ということです。
仮にデスクライト下の光の強さをAとします。
で、
普及委員会ではライトを何本か使っていますので、
光が重なり合う地点をAAとしましょう。
これを1日8時間照射し続けるとします。
そうすると、
AA×8という、
ちょっと乱暴な式で表記できるわけですね。
つまり、
Aの部分をそれぞれのネペンテスに合わせて調節し、
8を10、12と増やしていけば、
どんどん袋ができていくのではないかと思ったわけです。
でも、
ことはそんなに簡単に運びません。
ずっと袋をつけない種もいるわけですからね。
そこで次に目をつけたのが、
温度。
そう、
寒いと成長しないってのは、
植物に限らず、
昆虫などの生き物の間でも常識。
活動が鈍るわけですからね。
じゃあ室内の温度を高くしてみようと思ったわけです。
電気代もかかりますから、
とりあえず20℃としておきましょう。
そうすると、
20×(AA×8)
という考え方になるわけですね。
お、
これはよさそうと思ったのですが、
これもあまりうまくいきません。
相変らず袋をつける組と、
つけない組は分かれたままです。
次に目をつけたのが、
湿度でした。
ここで、
袋ができるパターンとできないパターンを見てみましょう。
まずできる場合ですが、
ほとんどが葉の先端が下向きになります。
こんな感じです。

こういう感じで全体的に上向き、、
立ち上がる感じになるとかなり厳しくなります。

で、
そこから蔓を伸ばし、
袋をつけるのですが、
ここも鬼門なわけです。
なぜかというと、
蔓を伸ばしたとき、
袋の先端が、
正しい方向で上を向かなければならないからです。
わたしはこれをクラッチと呼んでいます。
これは理想的なクラッチ状態。

クラッチが上手くいけばほぼ着袋する。

逆にクラッチ状態にならないと、
まず袋がつきません。
これは蔓が延びても、
クラッチが入らずに袋をつけないパターン。

で、
このクラッチ形成の過程に、
湿度が関係しているのではないか、
そう考えるようになったのです。
まずクラッチですが、
って、
眠さが限界です。
また次の機会に書きます。
ではでは、
次回もお楽しみに。
ですが、
今までで一番大きな葉をつけそうです。

めちゃ期待しています。
葉が出来る前のデザインは、
一番かっこいいかもしれません。

ネペンテス マキシマ・ダーク×(ノーシアナ×ビーチ)は、
大きすぎる袋対策のためか、
葉の先端ではなく、
途中から袋の蔓を伸ばします。
なので、
ちょっと独特のシルエットになるんですね。

この部分です。

で、
本日の表題なのですが、
ネペンテスの栽培を本格的に始めて早1年。
そこそこ、
ネペンテスのことが理解でき始めてると勘違いしていると、
すぐに問題が出てくるんですよね。
それがこれ、
袋がつかない問題

当初から懸案事項だったので、
何を今さらな感じですが、
これは本当に困っています。
ひどいのになると、
購入してから一年近くたつのに、
一個も袋をつけたことのないものまでありますからね。
ただの葉っぱですよほんと。
もちろん、
ただ袋がつかないなと、
漠然と眺めていたわけではありません。
一応、
原因は以下の五つに絞りました。
1 光の量
2 温度
3 湿度
4 風
5 土
この五つの条件が揃うと、
袋が出来やすくなると判断しました。
まず1の光の量ですが、
これには2つの要素がありまして、
それは光の強さと時間の関係です。
袋をまったくつけないネペンテスがいる一方で、
ポコポコとつけるものも存在します。
ポコポコつける方はスイッチがあるようで、
強い光にさらすとつけやすくなる、
という事実に気づきました。
で、
さらに光を当て続けると、
安定して袋を作り続けることがわかったのです。
で、
ここからがおもしろいところなのですが、
じゃあ全部強い光に当てればいいじゃんってことで、
他も試してみたのですが、
葉っぱばかり立派になったり、
逆に葉が萎縮したりと、
うまくいきませんでした。
ここで考えたのですが、
ネペンテスそれぞれに、
最適な光量があるではないか、
ということです。
仮にデスクライト下の光の強さをAとします。
で、
普及委員会ではライトを何本か使っていますので、
光が重なり合う地点をAAとしましょう。
これを1日8時間照射し続けるとします。
そうすると、
AA×8という、
ちょっと乱暴な式で表記できるわけですね。
つまり、
Aの部分をそれぞれのネペンテスに合わせて調節し、
8を10、12と増やしていけば、
どんどん袋ができていくのではないかと思ったわけです。
でも、
ことはそんなに簡単に運びません。
ずっと袋をつけない種もいるわけですからね。
そこで次に目をつけたのが、
温度。
そう、
寒いと成長しないってのは、
植物に限らず、
昆虫などの生き物の間でも常識。
活動が鈍るわけですからね。
じゃあ室内の温度を高くしてみようと思ったわけです。
電気代もかかりますから、
とりあえず20℃としておきましょう。
そうすると、
20×(AA×8)
という考え方になるわけですね。
お、
これはよさそうと思ったのですが、
これもあまりうまくいきません。
相変らず袋をつける組と、
つけない組は分かれたままです。
次に目をつけたのが、
湿度でした。
ここで、
袋ができるパターンとできないパターンを見てみましょう。
まずできる場合ですが、
ほとんどが葉の先端が下向きになります。
こんな感じです。

こういう感じで全体的に上向き、、
立ち上がる感じになるとかなり厳しくなります。

で、
そこから蔓を伸ばし、
袋をつけるのですが、
ここも鬼門なわけです。
なぜかというと、
蔓を伸ばしたとき、
袋の先端が、
正しい方向で上を向かなければならないからです。
わたしはこれをクラッチと呼んでいます。
これは理想的なクラッチ状態。

クラッチが上手くいけばほぼ着袋する。

逆にクラッチ状態にならないと、
まず袋がつきません。
これは蔓が延びても、
クラッチが入らずに袋をつけないパターン。

で、
このクラッチ形成の過程に、
湿度が関係しているのではないか、
そう考えるようになったのです。
まずクラッチですが、
って、
眠さが限界です。
また次の機会に書きます。
ではでは、
次回もお楽しみに。
















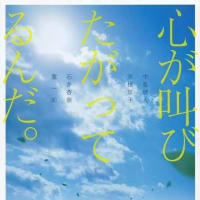






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます