今日は、
挿し木苗の整理をしていましたので、
作業ついでに写真を撮りました。
まぁ今さらも今さらなんですが、
ブログに掲載することを前提に画像を撮るなら、
ある程度テーマを決めて撮っておかないと、
書くときに画像に合わせて書かないといけないので、
肝心なことが書けなくなるというね。
でもまぁ、
実際の作業中は、
時間や両手がふさがっているなど、
撮れと言われても撮れない、
めんどくさがりな自分との戦いなので、
決めていたシーンを撮るかと言われると、
そうでもない今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
こんばんは、
流行の最先端である、
こどおじ代表の悠です。
いやほんと、
いい言葉ができましたね。
現状がまさにそんな感じで、
これ以上ない適格な表現、
いまの私にピッタリですよ。
ん?
なんすか?

で、
掘り下げてもしょうがないことなので、
話しを戻しまして、
挿し木をしていたので、
それについて書こうと思っていたのですが、
なんと、
またしても新規の方からコメントを頂いてしまいまして。
いやこのブログ、
地味に凄いなと思うのが、
けっこう前の記事にもコメントを頂くんですよ。
いや他のところも普通そうだよ、
と言われてしまうかもしれませんが、
いま頂けるということは、
いまも続けているからということが大きいわけで。
凄くないこれ。
第一回の栽培記がいつですか。
えーと、
調べるのがめんどくさいので、
まぁ5年くらい前?
もっとか。
いやそんなに前でもなかったか。
まぁそこは別にいいとして、
って、
こと書いているうちに、
眠くなってやめて、
けっきょく肝心のことを書いてないから、
ご質問を頂くわけで。
なので、
今日は本題から入りますよ!
冒頭部分は、
昨日から挿し木について書いてた部分だから、
実際はここからが今日書いてますから、
今日は本題から入りますよ!
で、
ユグドラシルについては、
頂いたコメントの返信でも書いたのですが、
絶対的な根拠があるとか、
何か実際に証明されていることがあるとか、
確かな情報を元にしているとか、
そういった一般的なものではなく、
私の経験をベースにした、
あくまで実践的な研究途中のものなので、
情報の公開を出し渋ってるとか、
決してそういう大層な代物ではないんですね。
こんなことしてみたら、
こんなことになりました、
とそういう感じのノリに近いので、
ぜひこうやって育てましょうとか、
この栽培方法がおすすめですとか、
そう言えるようなものでもないので、
よく出てくる割には、
内容が曖昧で中身がさっぱり、
と感じられるのは、
まったくもってその通りだと思います。
なので、
私が独自の栽培理論や、
ユグドラシルやユグドラソイルについて説明すると、
相手の方はまったく悪気なく、
間違ってますよとか、
他の栽培されてる方はこう言ってるのに、
おかしくないですか、
というご指摘を頂くことが多少あるのですが、
まぁそれに関して、
私としては、
気分を害したからとか、
レスバトルとか、
そういうつもりは一切なく、
ただ本心として、
確かなソースがあるのであれば、
私ではなく、
ぜひそちらを参考にされた方がいいですよと、
そう返さざるをえなくなってしまうわけです。
逃げたと思われても、
その通りだから、
これはまったくしょうがない。
自分で自分のやってることを、
きちんと説明できないわけですから、
理論も情報も確かな元、
年数も実績もある方に師事した方が、
栽培の腕は間違いなく上がりますからね。
そういう予防線を張りまくった上で、
ユグドラシルシステムについて書いていきましょう。
ただですね、
また逃げるわけではないですが、
ペットボトルに土を入れて、
ただ水で満たしてるだけなので、
内容どうこうよりも、
ユグドラシルを使う理由と、
その結果について書いた方がわかりやすいと思いますので、
ご満足頂ける内容にならないことは重々承知ですが、
そこをご了承頂けるのであれば、
ぜひ参考にして頂きたいと思います。
で、
まず現在ですが、
私の栽培場では、
90%がユグドラソイルで栽培しております。
画像は昨年配合したもので、
毎年内容を変えていますので、
これは6代目くらいになるのかな。

あ、
画像は今まで掲載したものの使い回しです、
すみません。
で、
これが今年配合した、
最新のユグドラソイル。
入れ物変えたので、
黒っぽく見えますが、
実際に黒い用土を混ぜたので、
実物もけっこう黒くなっております。

ユグドラソイルを使用していない、
残りの10%は、
幼苗をミズゴケに植えて密閉栽培にしていたり、
購入後間もないので、
そのままにしていたりなので、
実質私が野外で育てているネペンテスは、
100%ユグドラソイルを使用していることになります。
で、
購入後間もないネペンテスは、
袋から出さずに、
ずっとそのままにして放置しています。

長いのだと、
2年くらいこのままですね。
中には枯れるのもちらほら出てきますが、
このサイズだと、
袋から出して育てても、
成功率は変わらないというのが私の経験則なので、
下手にいじったり、
管理場所の制限がかかるよりは、
温度と光が確保できる場所であればどこでもいいので、
一定のサイズになるまでは、
基本このままです。

で、
いきなり今回の結論になって申し訳ないのですが、
これがユグドラシルです。
私はネペンテスの入っているビニールをほぼ密閉した状態にして、
植えられてる黒いビニールポットがうまるくらい水を入れますので、
画像では見づらいと思いますが、
中の黒いビニールポットはほとんど水没しております。
さらに言えば、
このまま半年くらい、
水やりも何もせず、
ひたすら完全放置です。
で、
ユグドラシルシステムは、
この黒いビニールポットから、
2リットルの注ぎ口を切ったペットボトルに変え、
用土をユグドラソイルにして植え込むだけですから、
このビニールのネペンテスとの違いと言えば、
外部の空気に完全にさらされている、
ということくらいでしょうか。
なんでこの放置栽培に辿り着いたかと言うと、
ネペンテスは、
ある一定のサイズにならないと、
大きくなりづらい性質によるんですね。
ホームセンターで売られている、
小さいサイズのネペンテスでも、
あれでもけっこう育った方なんですよ。
種から育てるとなると、
実際は、
一年でちょっとしか大きくならない、
米粒サイズからスタートしてますからね。
この小さいサイズを、
どうしたら短時間で大きくできるか、
最初は試行錯誤していたんですが、
ヒョロヒョロに伸びたり、
変な形に育って枯れたりするネペンテスを見て、
小さいうちは、
成長じゃなくて、
力を溜め込む時期なんじゃないかと考えをシフトし、
変に力を使い過ぎないよう、
外部とほぼ遮断した、
箱入りで育てることにしたわけです。
なぜこの状態で長期間大丈夫なのか、
私も理由がよくわかりませんが、
小さいうちのネペンテスは、
代謝が極端に遅く、
光と温度と一定量の空気しか必要としない、
いわゆるコケに近い生態なんじゃないかなと思います。
実際に、
ビニールの中は、
超高湿度、
昼夜の低酸素と高濃度酸素を繰り返しますので、
ネペンテスと同じ環境で芽生えたコケや、
半水草のようなものしか育ちません。
栄養も、
光合成などで、
自力で作り出せるもの以外、
かなり厳しい環境だと思います。
なので、
病原菌や害虫の侵入も少ないせいか、
ネペンテスが枯れるとカビが生える以外は、
目立った変化はないですね。
ただこれの欠点としては、
根の生育が悪いということです。
中干しとか、
田んぼの水抜きとか、
聞いたことはあるでしょうか。
これは様々な利点があるのですが、
わかりやすいところで言えば、
水を求めて根を伸ばす性質を利用して、
健康な成長を促す、
というものがあります。
さらに、
秋に大きな稲穂が実っても、
根が張ってないと、
自重でバッタリ倒れてしまいますからね。
芝生もそうですね、
ちょっと乾かしてやらないと、
しっかりと根付きません。
ネペンテスの場合、
常に根が水の中にあったため、
乾燥を経験しておらず、
また、
土中の栄養の乏しい状態だったので、
とくに伸ばす必要はなく、
まぁだいたい土から抜くと、
え、
これだけ、
って状態になるのがほとんどだと思います。
そこで、
成長段階に達したネペンテスの新たな受け皿として、
ユグドラシルシステムの出番なわけです。
ユグドラシルに移行したばかりのネペンテスは、
根の発育が十分ではありません。
なので、
これまで通り用土は水没と、
まぁそういう状況になるわけですね。

さらに根には、
先ほどの稲穂の例のように、
地上部の植物体を支えるという、
重要な役目がありますが、
ネペンテスの根には、
もともとそういう機能は発達しておらず、
また、
用土自体も水に浸かってるので、
非常に不安定であるため、
固定するバンドと支えの棒は、
ユグドラシルシステムではセットアイテム、
ということになります。

で、
じゃあユグドラソイルとはなんなのか、
ということですが、
これは上記の流れの通り、
密閉状態から出されたネペンテスの根を守り、
密閉状態と同等の高い環境維持性能を持つ、
最強の守護用土、
ということになるわけですね。
この性能を追い求めて、
何度も配合を変えて作り直しているわけです。
ただ、
これまでの記事内には、
ネペンテスの根を守る以外に、
根の成長を促すために、
根を下に誘導するための用土も混ぜたということも、
記述したと思います。
これこそが、
ユグドラシルがハイブリッド栽培であり、
私がユグドラソイルを、
最強の培養用土と豪語した理由です。
ユグドラシル自体は、
私にとって、
非常に都合の良いシステムでした。
水やりに悩まなくていいし、
雑草が生えて用土を荒らす心配もなし、
水分のある場所が好きな病害虫が、
用土に潜り込む心配もなく、
ボウフラなどは、
水をやると溢れて勝手に流れていきますので、
とにかく管理が楽です。
野外でのコツは、
用土の水温が上昇しないよう、
直射日光に当てない、
イオン交換と光合成を促すため、
風通しのいい場所で管理する、
くらいでしょうか。
これはユグドラシルに限らず、
ネペンテス栽培で非常に大事なことなので、
よくおぼえておきましょう。
さて、
そんなユグドラシルシステムですが、
夏場の成長シーズンでは、
万能とも思える成績を叩き出してくれますが、
気温が低くなる時期になると、
状況は一変します。
ここで重要になるのが、
乱暴ではありますが、
根の長さと量が、
そのまま植物の生命力数値になる、
と、
いまこのブログの中だけで仮定してください。
そうなると、
根がほとんど伸びていないネペンテスが、
環境の変化という事態にさらされると、
いったいどうなってしまうか。
これは、
単に気温の低下ではなく、
日照時間の減少や、
低湿度の無風状態の室内に移動した、
という変化です。
これまで成長に良い条件だけ享受していたネペンテスにとって、
いきなり家畜が野生動物の王国に放り出されたようなものでしょう。
ここ、
ここが、
私が、
ユグドラシルは、
水耕と土耕のハイブリッド栽培ですと、
何度も説明していた理由です。
そうなんです、
夏場はとにかく葉と袋を増やし、
秋になるころには、
ユグドラシルからすべて水を抜いて、
根に土中の水分を求めさせて伸ばすという、
大事な作業をしなければならないのです。

密閉栽培から解放され、
成長期に入ったネペンテスは、
快適な温度と新鮮な空気、
適度な日光の中、
潤沢な水分のもと、
バンバン葉を出して、
ノンストレスによる素晴らしい袋を作り出します。
ただこの状態のままにしてしまうと、
根はほとんど伸びません。
つまり、
成長しているのに、
生命力数値は幼苗のままなので、
大きいのにあっさり枯れるという、
ネペンテスって難しいという錯覚ができてしまいます。
じゃあ日ごろから乾燥状態で栽培すれば、
となるでしょうが、
ちょっと長くなるのでここは割愛します。
まぁ要は、
乾燥栽培は、
用土のチョイスと環境のマッチングが、
ちょっと難しいんですよ。
用土は乾燥気味だけど、
じゃあ空中湿度はとか、
そうなると、
保水性の高い用土なのか、
通気性のいい用土なのか、
とか、
これについてはまた別の栽培の話しになってしまいますので、
すみませんがカットで。
あと、
もう寝る時間みたいな。
で、
最後にご質問者様の2つ目のご質問。
腰水栽培ですが、
そう、
それこそが、
ハイブリッド栽培の要、
そして根を下に誘導するために、
ユグドラシルを砂利ではなく、
団粒構造にした理由、
そしてそして、
ネペンテスの成長を根にシフトするため、
肥料栽培にこだわった、
究極のユグドラシルシステムへとつながっていくわけです。
そして、
マジで寝る時間です。
ではでは、
また次回、
お会いしましょう。
挿し木苗の整理をしていましたので、
作業ついでに写真を撮りました。
まぁ今さらも今さらなんですが、
ブログに掲載することを前提に画像を撮るなら、
ある程度テーマを決めて撮っておかないと、
書くときに画像に合わせて書かないといけないので、
肝心なことが書けなくなるというね。
でもまぁ、
実際の作業中は、
時間や両手がふさがっているなど、
撮れと言われても撮れない、
めんどくさがりな自分との戦いなので、
決めていたシーンを撮るかと言われると、
そうでもない今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
こんばんは、
流行の最先端である、
こどおじ代表の悠です。
いやほんと、
いい言葉ができましたね。
現状がまさにそんな感じで、
これ以上ない適格な表現、
いまの私にピッタリですよ。
ん?
なんすか?

で、
掘り下げてもしょうがないことなので、
話しを戻しまして、
挿し木をしていたので、
それについて書こうと思っていたのですが、
なんと、
またしても新規の方からコメントを頂いてしまいまして。
いやこのブログ、
地味に凄いなと思うのが、
けっこう前の記事にもコメントを頂くんですよ。
いや他のところも普通そうだよ、
と言われてしまうかもしれませんが、
いま頂けるということは、
いまも続けているからということが大きいわけで。
凄くないこれ。
第一回の栽培記がいつですか。
えーと、
調べるのがめんどくさいので、
まぁ5年くらい前?
もっとか。
いやそんなに前でもなかったか。
まぁそこは別にいいとして、
って、
こと書いているうちに、
眠くなってやめて、
けっきょく肝心のことを書いてないから、
ご質問を頂くわけで。
なので、
今日は本題から入りますよ!
冒頭部分は、
昨日から挿し木について書いてた部分だから、
実際はここからが今日書いてますから、
今日は本題から入りますよ!
で、
ユグドラシルについては、
頂いたコメントの返信でも書いたのですが、
絶対的な根拠があるとか、
何か実際に証明されていることがあるとか、
確かな情報を元にしているとか、
そういった一般的なものではなく、
私の経験をベースにした、
あくまで実践的な研究途中のものなので、
情報の公開を出し渋ってるとか、
決してそういう大層な代物ではないんですね。
こんなことしてみたら、
こんなことになりました、
とそういう感じのノリに近いので、
ぜひこうやって育てましょうとか、
この栽培方法がおすすめですとか、
そう言えるようなものでもないので、
よく出てくる割には、
内容が曖昧で中身がさっぱり、
と感じられるのは、
まったくもってその通りだと思います。
なので、
私が独自の栽培理論や、
ユグドラシルやユグドラソイルについて説明すると、
相手の方はまったく悪気なく、
間違ってますよとか、
他の栽培されてる方はこう言ってるのに、
おかしくないですか、
というご指摘を頂くことが多少あるのですが、
まぁそれに関して、
私としては、
気分を害したからとか、
レスバトルとか、
そういうつもりは一切なく、
ただ本心として、
確かなソースがあるのであれば、
私ではなく、
ぜひそちらを参考にされた方がいいですよと、
そう返さざるをえなくなってしまうわけです。
逃げたと思われても、
その通りだから、
これはまったくしょうがない。
自分で自分のやってることを、
きちんと説明できないわけですから、
理論も情報も確かな元、
年数も実績もある方に師事した方が、
栽培の腕は間違いなく上がりますからね。
ユグドラシルシステムについて書いていきましょう。
ただですね、
また逃げるわけではないですが、
ペットボトルに土を入れて、
ただ水で満たしてるだけなので、
内容どうこうよりも、
ユグドラシルを使う理由と、
その結果について書いた方がわかりやすいと思いますので、
ご満足頂ける内容にならないことは重々承知ですが、
そこをご了承頂けるのであれば、
ぜひ参考にして頂きたいと思います。
で、
まず現在ですが、
私の栽培場では、
90%がユグドラソイルで栽培しております。
画像は昨年配合したもので、
毎年内容を変えていますので、
これは6代目くらいになるのかな。

あ、
画像は今まで掲載したものの使い回しです、
すみません。
で、
これが今年配合した、
最新のユグドラソイル。
入れ物変えたので、
黒っぽく見えますが、
実際に黒い用土を混ぜたので、
実物もけっこう黒くなっております。

ユグドラソイルを使用していない、
残りの10%は、
幼苗をミズゴケに植えて密閉栽培にしていたり、
購入後間もないので、
そのままにしていたりなので、
実質私が野外で育てているネペンテスは、
100%ユグドラソイルを使用していることになります。
で、
購入後間もないネペンテスは、
袋から出さずに、
ずっとそのままにして放置しています。

長いのだと、
2年くらいこのままですね。
中には枯れるのもちらほら出てきますが、
このサイズだと、
袋から出して育てても、
成功率は変わらないというのが私の経験則なので、
下手にいじったり、
管理場所の制限がかかるよりは、
温度と光が確保できる場所であればどこでもいいので、
一定のサイズになるまでは、
基本このままです。

で、
いきなり今回の結論になって申し訳ないのですが、
これがユグドラシルです。
私はネペンテスの入っているビニールをほぼ密閉した状態にして、
植えられてる黒いビニールポットがうまるくらい水を入れますので、
画像では見づらいと思いますが、
中の黒いビニールポットはほとんど水没しております。
さらに言えば、
このまま半年くらい、
水やりも何もせず、
ひたすら完全放置です。
で、
ユグドラシルシステムは、
この黒いビニールポットから、
2リットルの注ぎ口を切ったペットボトルに変え、
用土をユグドラソイルにして植え込むだけですから、
このビニールのネペンテスとの違いと言えば、
外部の空気に完全にさらされている、
ということくらいでしょうか。
なんでこの放置栽培に辿り着いたかと言うと、
ネペンテスは、
ある一定のサイズにならないと、
大きくなりづらい性質によるんですね。
ホームセンターで売られている、
小さいサイズのネペンテスでも、
あれでもけっこう育った方なんですよ。
種から育てるとなると、
実際は、
一年でちょっとしか大きくならない、
米粒サイズからスタートしてますからね。
この小さいサイズを、
どうしたら短時間で大きくできるか、
最初は試行錯誤していたんですが、
ヒョロヒョロに伸びたり、
変な形に育って枯れたりするネペンテスを見て、
小さいうちは、
成長じゃなくて、
力を溜め込む時期なんじゃないかと考えをシフトし、
変に力を使い過ぎないよう、
外部とほぼ遮断した、
箱入りで育てることにしたわけです。
なぜこの状態で長期間大丈夫なのか、
私も理由がよくわかりませんが、
小さいうちのネペンテスは、
代謝が極端に遅く、
光と温度と一定量の空気しか必要としない、
いわゆるコケに近い生態なんじゃないかなと思います。
実際に、
ビニールの中は、
超高湿度、
昼夜の低酸素と高濃度酸素を繰り返しますので、
ネペンテスと同じ環境で芽生えたコケや、
半水草のようなものしか育ちません。
栄養も、
光合成などで、
自力で作り出せるもの以外、
かなり厳しい環境だと思います。
なので、
病原菌や害虫の侵入も少ないせいか、
ネペンテスが枯れるとカビが生える以外は、
目立った変化はないですね。
ただこれの欠点としては、
根の生育が悪いということです。
中干しとか、
田んぼの水抜きとか、
聞いたことはあるでしょうか。
これは様々な利点があるのですが、
わかりやすいところで言えば、
水を求めて根を伸ばす性質を利用して、
健康な成長を促す、
というものがあります。
さらに、
秋に大きな稲穂が実っても、
根が張ってないと、
自重でバッタリ倒れてしまいますからね。
芝生もそうですね、
ちょっと乾かしてやらないと、
しっかりと根付きません。
ネペンテスの場合、
常に根が水の中にあったため、
乾燥を経験しておらず、
また、
土中の栄養の乏しい状態だったので、
とくに伸ばす必要はなく、
まぁだいたい土から抜くと、
え、
これだけ、
って状態になるのがほとんどだと思います。
そこで、
成長段階に達したネペンテスの新たな受け皿として、
ユグドラシルシステムの出番なわけです。
ユグドラシルに移行したばかりのネペンテスは、
根の発育が十分ではありません。
なので、
これまで通り用土は水没と、
まぁそういう状況になるわけですね。

さらに根には、
先ほどの稲穂の例のように、
地上部の植物体を支えるという、
重要な役目がありますが、
ネペンテスの根には、
もともとそういう機能は発達しておらず、
また、
用土自体も水に浸かってるので、
非常に不安定であるため、
固定するバンドと支えの棒は、
ユグドラシルシステムではセットアイテム、
ということになります。

で、
じゃあユグドラソイルとはなんなのか、
ということですが、
これは上記の流れの通り、
密閉状態から出されたネペンテスの根を守り、
密閉状態と同等の高い環境維持性能を持つ、
最強の守護用土、
ということになるわけですね。
この性能を追い求めて、
何度も配合を変えて作り直しているわけです。
ただ、
これまでの記事内には、
ネペンテスの根を守る以外に、
根の成長を促すために、
根を下に誘導するための用土も混ぜたということも、
記述したと思います。
これこそが、
ユグドラシルがハイブリッド栽培であり、
私がユグドラソイルを、
最強の培養用土と豪語した理由です。
ユグドラシル自体は、
私にとって、
非常に都合の良いシステムでした。
水やりに悩まなくていいし、
雑草が生えて用土を荒らす心配もなし、
水分のある場所が好きな病害虫が、
用土に潜り込む心配もなく、
ボウフラなどは、
水をやると溢れて勝手に流れていきますので、
とにかく管理が楽です。
野外でのコツは、
用土の水温が上昇しないよう、
直射日光に当てない、
イオン交換と光合成を促すため、
風通しのいい場所で管理する、
くらいでしょうか。
これはユグドラシルに限らず、
ネペンテス栽培で非常に大事なことなので、
よくおぼえておきましょう。
さて、
そんなユグドラシルシステムですが、
夏場の成長シーズンでは、
万能とも思える成績を叩き出してくれますが、
気温が低くなる時期になると、
状況は一変します。
ここで重要になるのが、
乱暴ではありますが、
根の長さと量が、
そのまま植物の生命力数値になる、
と、
いまこのブログの中だけで仮定してください。
そうなると、
根がほとんど伸びていないネペンテスが、
環境の変化という事態にさらされると、
いったいどうなってしまうか。
これは、
単に気温の低下ではなく、
日照時間の減少や、
低湿度の無風状態の室内に移動した、
という変化です。
これまで成長に良い条件だけ享受していたネペンテスにとって、
いきなり家畜が野生動物の王国に放り出されたようなものでしょう。
ここ、
ここが、
私が、
ユグドラシルは、
水耕と土耕のハイブリッド栽培ですと、
何度も説明していた理由です。
そうなんです、
夏場はとにかく葉と袋を増やし、
秋になるころには、
ユグドラシルからすべて水を抜いて、
根に土中の水分を求めさせて伸ばすという、
大事な作業をしなければならないのです。

密閉栽培から解放され、
成長期に入ったネペンテスは、
快適な温度と新鮮な空気、
適度な日光の中、
潤沢な水分のもと、
バンバン葉を出して、
ノンストレスによる素晴らしい袋を作り出します。
ただこの状態のままにしてしまうと、
根はほとんど伸びません。
つまり、
成長しているのに、
生命力数値は幼苗のままなので、
大きいのにあっさり枯れるという、
ネペンテスって難しいという錯覚ができてしまいます。
じゃあ日ごろから乾燥状態で栽培すれば、
となるでしょうが、
ちょっと長くなるのでここは割愛します。
まぁ要は、
乾燥栽培は、
用土のチョイスと環境のマッチングが、
ちょっと難しいんですよ。
用土は乾燥気味だけど、
じゃあ空中湿度はとか、
そうなると、
保水性の高い用土なのか、
通気性のいい用土なのか、
とか、
これについてはまた別の栽培の話しになってしまいますので、
すみませんがカットで。
あと、
もう寝る時間みたいな。
で、
最後にご質問者様の2つ目のご質問。
腰水栽培ですが、
そう、
それこそが、
ハイブリッド栽培の要、
そして根を下に誘導するために、
ユグドラシルを砂利ではなく、
団粒構造にした理由、
そしてそして、
ネペンテスの成長を根にシフトするため、
肥料栽培にこだわった、
究極のユグドラシルシステムへとつながっていくわけです。
そして、
マジで寝る時間です。
ではでは、
また次回、
お会いしましょう。
















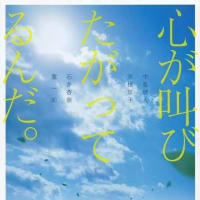






ユグドラシルシステム全く想像の斜め上を行くシステムでした。
真似しようと思っていましたが、いきなり鉢をひたひたにするのはなれていない株にはよろしくないと思うので鹿沼土ベースの用土で普通のよくある腰水をしようと思います。
しかし、考え方はとても面白く納得のいく参考になるものでした。機会があれば、新しく買ってきた小さめの株は完全密閉を試してみたいです。
参考になったかわかりませんが、
そういう栽培方法もあるんだな程度にでも記憶して頂けたら、
書いた甲斐があります笑
用土の異常さえ注意しておけば、
鹿沼土ベースの腰水栽培でまったく問題ないと思うので、
大事に育ててあげてください(^^)/
大きな株は、
元の環境で成長していた時間が長いので、
環境変化の対応に以外に鈍く、
小さい株よりも逆に注意してあげないと、
気づいたら手遅れの場合もままありますので、
頂点芽や葉、
幹に変化が出てないか、
よく注意して観察する必要があります。
特に葉の萎れや展開不良、
頂点芽の生長停止は、
すでにレッドラインを突破してる可能性がありますので、
日ごろの観察でいかにはやく察知できるかが重要です。
完全密封はコツがありますので、
最初はちょっとだけ空気穴を設けてあげた方が、
失敗は少ないです(^_^;)