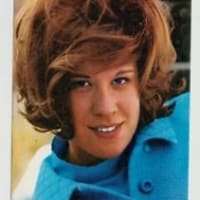(フランソワ・ラブレーの肖像)
学生時代、西欧のルネッサンス期ユマニスト・・・モンテーニュ、ラブレー、エラスムス・・・などの著作を読もうと努力したことがありました。結局の所は十分に読みこなすところまでは行かず、表面をつるりと撫でただけ・・・に終わりましたが、ヨーロッパや中東世界の不寛容・・・もっと言えば一神教を始めとする宗教的な一途さに基づく不寛容についてはずいぶん印象的ではありました。
明治以降ごく最近も、ヨーロッパが軍事的・宗教的に世界を圧倒したことに起因した「文化的な不寛容性」は随所で見ることが出来たと思います。日本に対してヨーロッパ人、更にアメリカの「白人」が自らの価値観や論理を振りかざすのは、食文化などを始め、結構経験したところではないでしょうか?
今回のロシアによるウクライナへの軍事侵略もこうした自己中心的な不寛容な論理の延長上にある行為でしょう。領土の問題、人種の問題・・・19世紀以来、欧米帝国主義諸国によって引き起こされ、20世紀を「戦争の世紀」としてしまったのは、ひとえに欧米人の思い上がった国家観の帰結・・・根本的な不寛容性によるものだと言っても良いのではないでしょうか。
・・・情けないことに、明治期以降、それまでの理知的でグローバルな世界観を駆逐し、吉田松陰に代表されるような皇国史観・帝国主義に支配され、不寛容な欧米のつまらない追従者になってしまった日本もまた、戦後70年経って未だに古い国家観から抜け出せないでいますが・・・
21世絹相応しい世界の仕組みは、まだ兆しが見えないばかりか、偏狭な国粋主義的な主張や強欲な国家、強欲な資本家、強欲な「国民」がますます力を大きくしている様な気がします。19世紀的な国民国家や帝国主義、20世紀後半の民族自決・・・これらを乗り越えて溶かしていくような「寛容性」の論理は見いだせないものでしょうか?