
ここの神社の前は、車で幾度も通っていながら一度も参拝していなかったので歯科治療で韮崎に出向いたおり診療予約時間まで時間があったので参拝して参りました。
八幡宮ですので、なんて事は無い神社と高を括っていたのですが、意外や意外!中々見どころが多い神社でした。

隋神門 駅前へと続く道路に面して参道石段があります。


神像二体

文化年間に再建


狛犬一対 昭和10年製

手水舎 なかなか見事な造形です。

拝殿 昭和12年再建

拝殿~本殿
祭祀:大鷦鷯命(おおささぎのみこと)(第十六代 仁徳天皇)
由緒:
古記録(棟札)によると885~889年(仁和年間)の創建と伝えられます。もとは七里岩の上に鎮座されていましたが、1583年(天正11)に暴風雨による山崩れがあり社殿が倒壊したため、翌々年、現在地に再建されました。この時代は武田家滅亡により国内は混乱しており、徳川家康により社頭の安堵はなされましたが、再建は遅れたといわれています。また、1193年(建久4)、イチキシマヒメノミコト、タギツヒメノミコト、タゴリヒメノミコトの三女神を鎌倉より当社に勧請しました。現在この三女神は、毎年酷い洪水に悩まされていた村民が安全を祈るために、下宿舟山の丘に姫宮神社として祀られるようになりました。
(引用:若宮八幡宮公式ページより)
※大鷦鷯命(386~429)は、15代応神天皇(誉田別尊、ほむたわけのみこと363~403)の第4皇子
八幡神社なので、祭神はてっきり応神天皇と思っていたらまさかの“大鷦鷯命”つまり仁徳天皇をお祀りしている神社でした。(ちなみに“サザキ”とは鳥のミソサザイの事です。大鷦鷯命の出生時に産屋に飛び込んできたと言う故事に因みます。)
由緒にある旧社地は七里岩の上にあって、山崩れで社殿が崩壊しこちらに遷宮されたこと。以前までは、宗像三女伸を祀り現在の姫宮神社に遷座したと言う事実も興味深いです。
韮崎はかつて河原部村(かわらべむら)といい、甲州街道の宿場駅で、富士川からの舟運による海産物の取引中継の町としてにぎわっていました。
将軍家御用達の宇治茶を送る御茶壺道中、徳川一橋家の御陣屋もおかれ、参勤交代による諸大名の通行など、この地方の政治、経済、文化の中心地だったそうです。
そんな背景からここ若宮八幡宮は、河原部村の氏神、通称「かわらべさん」として親しまれてきました。(若宮八幡宮HPより)
それでは、境内を散策して参ります。

神楽殿 例大祭7月30日・31日

正一位稲荷大明神・天神宮

末社金刀比羅神社

石祠群
境内に興味深い石灯篭一対がありました。


柱の部分に彫刻が施されています。


昇竜と降竜の彫像でした。石灯篭では珍しいのではないかと思います。

丸石道祖神

金精様もいらっしゃいました。
実は、ここを一躍有名にしたある騒動がありました。
例のコロナ騒動です。
2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した北里大学の大村 智特別栄誉教授 がここ韮崎市ご出身で、彼の発見した寄生虫が原因で失明などが引き起こされる感染症の特効薬「イベルメクチン」がコロナにも効くと言う噂が一時期流れました。

もともとここで授与されていた学業成就をはじめ、仕事、健康の御守 「イベルメクチン御守」(イベルメクチンの構造式の模様 柄)を授与しに来られる参拝客が押しよせ一時期けっこうな騒動だったらしいです。(出典:にらレバ)

駐車場脇にあった巨石 特に謂れなどはありませんが七里岩から崩落したものでしょうか?
【マップ】




















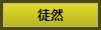



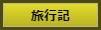
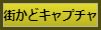

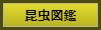


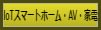

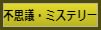
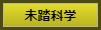
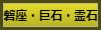


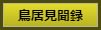
昨年この時期に駒ヶ根に来ていた時にruriboさんの記事を読んで「筥石社」に行きました。もともと懸造が好きでしたので巨石にも興味がわくようになりました。これからも楽しく拝見させていただきます。
鳥居の前は、生活道路、背後には中央線の路線があるので電車の音が響き、あまり良い環境に立地に建っているとは思えませんが地元民には昔から親しまられていると言った雰囲気の神社です。
今は伊那へ行かれているんですね。
見どころが多い地域でもありますので、またご報告楽しみにしております。