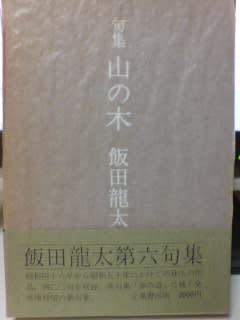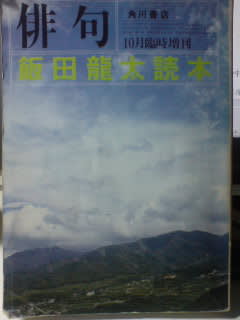1月テーマ句会のお勉強
句会が終わり連衆の選評を読むたびに、あそこをこうすれば、
ここはこうだった、そう思うのは私だけではないでしょう。
俳句を30年もやっていて、普通はどこぞの主要同人になって
いてもおかしくないはず。もちろん句歴だけではなく才能が
有ったらの話。恥ずかしながら私の拙句を俎上にあげて、
今回の句会に投句するまでの話。推敲の話など、書いてみます。
何かの参考になれば・・・・・
雪掻きて掻きても夢の雪の丈
評価は別として、まず「雪の丈」を詠みたかった。そして降り積もる
イメージとして同じ言葉のリフレインを考えた。それが「掻く」と「雪」
の二度使いになった。この句は私の実体験ではなく「夢」であり、
そんな体験への憧れを詠んでみた。ある人は言葉遊びと言うかも
しれないが、俳句をつきつめて行く過程では必要なこと。
新春のかなめにややの眠りかな
多くの支持を頂いた句。テーマである「慶事の挨拶句」のつもり
だったが補足の「使いまわしの出来る挨拶句」ではなかった。
唯一投句後も気にしていた季語の「新春」は見事に師匠に、
見破られた。しかし「にいはる」と読んで頂いて感謝です。
この場合の季語は「初春」にすれば「やや」が初孫、初子の感じが
したのかもしれない。季語の音、訓表記でギクシャクする場合も
ありえる。
仮縫いのピンはもも色春隣
この句も多くの指示を頂き有難うございました。
師匠ご指摘の通り、「ピンは」ではなく「ピンの」だったと
思います。「は」では春隣という季語への導きのようですね。
仮縫いのピンのもも色に触発されて春を感じた。とするのが
俳句=詩なんでしょう。
もう一つの目的はころころが作者である事がばれない句を
詠もうとしましたが、うまくいきましたでしょうか?
ゲレンデに遠き日向のありにけり
自分では自信句だった。「遠き日向」へ行き着くまでに
時間もかかった。読み返すと少し古臭い気もするが、
発見という俳句の要素はあると思う。
深夜バス雪をかむって今着けリ
連衆のご意見の中にも「今」が気になる。「着きにけり」で良い
のではと有ったが、勿論最初は「着きにけり」だった。
眼前の景(時間)を活かすためにそうしたが失敗だったかも
しれない。
しばらくは焚火にあそぶ遊山かな
投句まで一番時間のかかった句です。
しばらくは焚火にあたる遊山かな
しばらくは焚火にあそぶ旅路かな
しばらくは焚火とあそぶ遊山かな
しばらくは焚火とあそぶひとり旅
あそぶと遊山のならびにもかなり悩んだが、今だに納得に
至らない。どうぞご意見を聞かせてください。