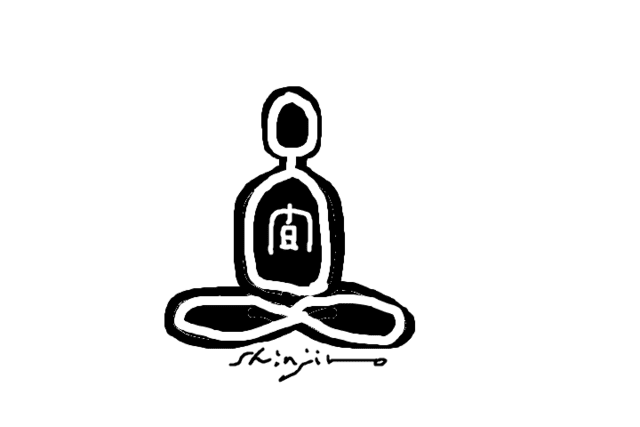配信動画Newspick で、久々に松岡正剛氏の笑顔を拝顔した。彼は、昨日1月25日で80歳を迎え、傘寿(さんじゅ)となる。祝!
80歳となっても『知の巨人』ぶりは相変わらずで、若干痩せたぶん、渋さに磨きがかかった男前ぶり・・・。
松岡正剛と鈴木大拙の本を読むと、必ずインスパイアする馬骨であるが、
還暦スキャンしてみると、意外に松岡正剛との出会いが鈴木大拙よりもだいぶ前であった。
私が23歳の時、芦屋芸術学院という所に写真科助手として勤務したが、学院の図書室に『遊』という奇妙奇天烈な雑誌があって魅せられたが
それが、松岡正剛が主催する工作舎の刊行雑誌であったから、その意味では禅修行のずっと以前に彼との因縁があったといえる。
ただその時は、『遊』という雑誌を夢中になって観ただけで、編集者『松岡正剛』については、名前すらも知らなかったが・・・。
その後、彼の著書に親しむものの、鈴木大拙の著書と同じで、何が書いてあるのか『良くわからん』状態が長きに渡って続いたが
定年退職記念帰国旅行で『千本鳥居』をくぐり、『考えるな、漢字ろ!』に開眼してからは、彼の『編集工学』が手に取るように解った。(気がする)
というか、私の潜在意識の中で、彼の『編集工学』思想の影響を受けていたのかもしれない・・・。
彼の『日本の方法』の思想のなかで、しきりに『面影』という言葉を用いているが・・・それって
禅のいう『無』に向っての瞑想の中で、脳神経のシナプスが自ずと核心にむけて編集する・・・ことでは? と、私は思い始めている。
私の『人"間"工学』という命題は、松岡正剛氏の『編集工学』影響下のモジリであることに"間"違いないが、その"間"にこそ
『日本の方法』が、秘められていることも間違いない。