第058回国会 科学技術振興対策特別委員会 第6号
昭和四十三年三月二十一日(木曜日)
URL:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0560/05803210560006c.html
三宅正一先生先生も
「これは重大な問題だから、ぜひとも試験をやるべきだ」と発言したわけですが、
肝心の松下敬一博士は
特に国でやらなくても、そんなのは実験で何度も確かめているほど確実性がある。
と自信たっぷりの回答でした。
しかし、国でやらないと意味がないんです。
斉藤委員が再三再度くどく要求する意味は、
「もしも、この新理論が実験で確認された場合、医学の土台からひっくり返るほど重大な理論になる。だから、今後の病気治療や国民の将来にまで渡る健康を左右することになる・・」
だから、「個人でいくら検証しても、いつまでも理論の繰り返しで終わる」
絶対に「国家で、おおやけにやるべきことなのだ。」
と主張したのでしょう。
本当に国を想い、国民の健康と生命を守る意志があるならば、
こんな簡単な基礎実験をやれないわけがない!!
しかし、厚生省と医学界は「おおやけの実験を拒否した」
だからこそ、
今現在でも「千島、松下理論はインチキ論」だとか「トンデモ論」だとか誹謗中傷されているわけです。
その理由は、「国家がその白黒をつけてやると決議した」のに、「無視、うやむやにしてしまった」からに他なりません。
つまり、権力が強いもの勝ちになっている医療産業界(あえて産業と入れました)には、勢力のない弱小団体くらいがいくら正論を唱えても、痛くもかゆくもないのです。
権力は政治を動かし、厚生省まで動かしてしまうからです。
そして、新聞テレビなどマスコミまでそれになびくほど金力も使えるから、国民には真の情報はいつまで経っても伝えられないのです。
だからこそ、松下千島理論は世の中に浮かび上がってこられない、来られなかった訳です。
あのとき、40年前に何度も特別委員会を開いておきながら、何もしなかった厚生省と医師会の幹部(そこに出席された人名まで出ている)がたは、存命していない方が多いかも知れませんが、
いやしくも国の最高機関でおこなわれ、国会議員を交えて厚生省幹部とガン研究権威ある医師達が集まり、
それはいったい何の意味があったんだ!
たとえ、40年経とうが50年経とうが、いったん決議された内容は行うべきなのだ。
国でやるからこそ意義があるんです。
巷でいくら議論を交わしたって、権力がある方が勝つに決まっています。
真実が決めるのではない、数が決める世界だから、そういう世界はどこにでもあります
そういう意味で、今回の国会証言シリーズはもう終わりがないかもです。
それほど重要なのですよ。
わかるかなああ~~
ーーーーーーーー以下引用ーーーーーーーーーーーーーー
前略
それから、ついでにここで私、はっきり申し上げておきたいと思いますことは、ただいま塚本先生が血液の問題についていろいろ意見をお述べになっていらっしゃいました。
これは全くそのとおりであります。
現代医学のピークに立っておられる先生でありますから、既成概念の頂点に立っていらっしゃる方でありますから、既成概念を否定するということは、とりもなおさず、
御自分の存在を否定するということにもつながるわけでありまして、
それはとうてい私はできないことだと思います。
しかし、たとえば、いま塚本先生がおっしゃられた考え方の中に、赤血球が成熟その極限に到達した細胞である、これは現在の血液学の定説でありますが、この考え方が私はそもそも間違いである。
私の考え方では、食べものが材料になって腸でつくられた細胞でありますから、きわめて原始的な細胞であります。
しかるがゆえに赤血球の中には何十種類もの酵素があり、しかも、エネルギーがプールされている。
最近これはわかった事柄であります。いままでは極端に成熟をした、老いぼれの、死の一歩手前の細胞であるという考え方で赤血球を見ていたわけでありますが、その考え方にそもそも大きな間違いがあると思います。
最近の生化学の進歩は、赤血球の中の無数の酵素が含まれている、あるいは、エネルギーがちゃんとプールされていて、死ぬまぎわの細胞がなぜそういうものを持っているのか、いまの医学的な常識では説明がつかないという段階であります。
そういうことから考えましても、もう根本的にやはり考え方の土台が違っているというような気がいたします。
それからガン細胞の分裂についてであります。
いま塚本先生がおっしゃいましたように、ガン細胞というものは、体細胞が突然変異を起こして異常な細胞になって、その細胞が無限に分裂増殖をする細胞であるというふうに説明をされました。
これは現在のガンに関する定義であります。世界の学者が、ガンとはそういう病気であるというふうに信じております。
そういう意味ではもちろん間違いのない考え方でありますが、しかし私の立場から申し上げますと、そういうことももちろん承知の上で、からだの中にあるガン組織というものは、私は分裂増殖をしておらないというふうに見ております。
しかし、実際にガン細胞の分裂がきれいに映画の中にとらえられたりしております。
東京シネマでつくられましたガン細胞に関する映画などを見ますと、ガン細胞の分裂というものは実にみごとにとらえられております。
が、それはそういう特殊なガン細胞が示す行動であって、
すべてのガンがそういうふうに体内で分裂増殖をしているのではないと思います。
もしガン細胞がほんとうに分裂増殖をしているのであれば、
たとえば、現在がんセンターで入院あるいは手術をされたガンの患者さんのその組織の一片を持ってきて、
そして顕微鏡の下でガン細胞の分裂というものは観察されてしかるべきであります。
しかし、そういう観察がなされたという報告は、私は一例も聞いておりません。
実際に手術をして、ガンの組織というものは幾らでも、いつでも、随意にわれわれは取り出すことができるわけでありますから、
そういうガン細胞が分裂増殖をしているかどうかということは
確かめようと思えばいつでも確かめられるはずであります。
そういう実際のガンの組織というものを取り出して、そして、顕微鏡の下でそれを観察した学者というものは、私はいないと思います。
実際には、われわれのからだの中では、定説はガン細胞の分裂ということであります
けれども、赤血球がガン細胞に変わっていることは、ほぼ間違いのない事実だと私は確信いたします。
実際に、最近フランスでも、ガン研究の権威であるアルぺルン教授が、ガン細胞というものが分裂しているかどうかということについては、これは詳しく触れておりませんけれども、小さなガンの種になる細胞が寄り集まって、そうして一個の典型的なガン細胞に発展をしていくのだという説を唱えまして、そういう報道がヨーロッパではなされております。
そういうことを見ましても、分裂増殖だけではなさそうである。
分裂増殖一辺倒ではいけないのではないか。
たとえば、現在のガンの治療薬にいたしましても、ガン細胞は分裂増殖をするから、その分裂を抑制するような化学物質であればガンはなおるであろうというふうに、
きわめて単純に、機械的に考えてその開発が進められているわけでありますが、
こういう考え方のもとでは、
私は幾ら研究費をつぎ込んでもしかるべき抗ガン剤というものはできないというふうに見ております。
また、いままで長年私はそういう考え方を講演会で述べたり、あるいは私の著書の中ではっきりと明記いたしております。
ガン細胞が赤血球からできるということにつきましては、私が八年前に書きました「血球の起原」という本の中でそれをはっきり述べております。
たとえば、吉田肉腫の場合でありますが、あの吉田肉腫の細胞というものは、実際にはほとんど分裂増殖をしておりません。
種を動物の腹腔の中に植えつけますと、まず必ず腹膜に出血性の炎症が起こってまいります。そして、腹腔の中にまず血液が浸出する、赤血球が腹水の中にたくさんまざり始めるということを前提にして、初めてガン細胞はふえるのであります。
吉田肉腫の細胞というものは増殖していっております。
その過程を、私は八年前に書いた私の本の中ではっきり指摘いたしております。
吉田肉腫の増殖というものも、私は、腹膜の炎症が起こらなければ、腹膜の炎症を起こさないように処置してこの吉田肉腫の種を植えつけたのでは、絶対にこの肉腫細胞は増殖をしないであろうというふうに想像いたしております。
炎症というものが背景にあって、血液が腹水の中に出てくるということが前提条件である、そうしなければガン細胞はできない、その赤血球がお互いに融合し合いまして、そうして一つのガン細胞に発展をしていくということであります。
また、実際にこの吉田肉腫の細胞を観察してみますと、形がまちまちであります。
もし一定の分裂方式で細胞が増殖していくのであれば、ほとんどきまった形の細胞ができなければならないのに、増殖している細胞は全く千差万別であるということも、でき方が単に分裂増殖ではないということを物語っているように思われます。
それから、話はだいぶ前にさかのぼりますが、さっき斎藤議員が申しておられました
無菌的な血液を培養して、
そうして点状の小さなバクテリアが発生をし、
これが球菌になり、桿菌に発展をしていくことが
実際にあるのかどうか、
これは国の機関でひとつはっきりさせろということを申しておられましたが、
この問題につきましては、
私自身すでに、SICの牛山氏とは全然別個に実験を行なっております。
私はSICの問題とは一切無関係に、
血液というものは無菌的な条件のもとで、
試験管の中で放置しておけば、一体最後にはどういうふうに変わってしまうものであろうか
というようなことを追求する目的で、
大学時代に大ぜいの研究員を使いまして、こまかく探索をいたしました。
その結果は、この八年前に書きました「血球の起原」という本の一〇〇ページ、それから今度出しました「血液とガン」という本の一五ぺ-ジに、
その写真も掲載をいたしまして、その結論を披瀝いたしておりますが、
これは無菌的な血液であっても、
血漿の中に、これは実は赤血球の中にそういう点状のバクテリア様のものが発生をいたしまして、
これがだんだん発育をいたしまして、
そうして球菌になり、
かつ、桿菌にまで発展をする
という事実を私は認めております。
この問題は、国家の機関で追求せよということでありますけれども、私はその必要はほとんどないのではないかというような、むしろ逆の考え方をしております。
といいますのは、
はっきりとそういうふうになるのでありまして、
牛山氏が無菌的に血液を培養して、ああいう桿菌様のものが得られたというその事実に対しましては、
私は絶対に間違いがなかったというふうに判定できると思います。
ただ、
そういう桿菌様のものを材料にしてつくられた
SICという化学物質がガンにきくかどうかということは、
私は臨床医でありませんので、
これは全くわかりません。
そういうことをこの際つけ加えておきたいと思います。
-----------------------以上引用終わり--------------------------------
国の機関でやるほどのものでのないと言われた新理論の松下博士は、「そんなのは当たり前に見ることが出来る」という自信が言わしたものでしょうから、
専門家であれば「誰でも確認出来る」という意味なのでしょう。
そうなると、
誰でもそれをやろうと思えばいつでもできるほど確実性が、再現性があるという事です。
じゃあ、国がやらないなら個々の医師達がやればいいじゃないか?
普通の考えならそうなります。
しかし、普通の世界じゃなかったようです。
もっとも、それが確認されても、黙殺しちゃうでしょうから。
やっぱり、国家がその権威を利用して公開実験で確認すべきだったのです。
昭和四十三年三月二十一日(木曜日)
URL:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0560/05803210560006c.html
三宅正一先生先生も
「これは重大な問題だから、ぜひとも試験をやるべきだ」と発言したわけですが、
肝心の松下敬一博士は
特に国でやらなくても、そんなのは実験で何度も確かめているほど確実性がある。
と自信たっぷりの回答でした。
しかし、国でやらないと意味がないんです。
斉藤委員が再三再度くどく要求する意味は、
「もしも、この新理論が実験で確認された場合、医学の土台からひっくり返るほど重大な理論になる。だから、今後の病気治療や国民の将来にまで渡る健康を左右することになる・・」
だから、「個人でいくら検証しても、いつまでも理論の繰り返しで終わる」
絶対に「国家で、おおやけにやるべきことなのだ。」
と主張したのでしょう。
本当に国を想い、国民の健康と生命を守る意志があるならば、
こんな簡単な基礎実験をやれないわけがない!!
しかし、厚生省と医学界は「おおやけの実験を拒否した」
だからこそ、
今現在でも「千島、松下理論はインチキ論」だとか「トンデモ論」だとか誹謗中傷されているわけです。
その理由は、「国家がその白黒をつけてやると決議した」のに、「無視、うやむやにしてしまった」からに他なりません。
つまり、権力が強いもの勝ちになっている医療産業界(あえて産業と入れました)には、勢力のない弱小団体くらいがいくら正論を唱えても、痛くもかゆくもないのです。
権力は政治を動かし、厚生省まで動かしてしまうからです。
そして、新聞テレビなどマスコミまでそれになびくほど金力も使えるから、国民には真の情報はいつまで経っても伝えられないのです。
だからこそ、松下千島理論は世の中に浮かび上がってこられない、来られなかった訳です。
あのとき、40年前に何度も特別委員会を開いておきながら、何もしなかった厚生省と医師会の幹部(そこに出席された人名まで出ている)がたは、存命していない方が多いかも知れませんが、
いやしくも国の最高機関でおこなわれ、国会議員を交えて厚生省幹部とガン研究権威ある医師達が集まり、
それはいったい何の意味があったんだ!
たとえ、40年経とうが50年経とうが、いったん決議された内容は行うべきなのだ。
国でやるからこそ意義があるんです。
巷でいくら議論を交わしたって、権力がある方が勝つに決まっています。
真実が決めるのではない、数が決める世界だから、そういう世界はどこにでもあります
そういう意味で、今回の国会証言シリーズはもう終わりがないかもです。
それほど重要なのですよ。
わかるかなああ~~
ーーーーーーーー以下引用ーーーーーーーーーーーーーー
前略
それから、ついでにここで私、はっきり申し上げておきたいと思いますことは、ただいま塚本先生が血液の問題についていろいろ意見をお述べになっていらっしゃいました。
これは全くそのとおりであります。
現代医学のピークに立っておられる先生でありますから、既成概念の頂点に立っていらっしゃる方でありますから、既成概念を否定するということは、とりもなおさず、
御自分の存在を否定するということにもつながるわけでありまして、
それはとうてい私はできないことだと思います。
しかし、たとえば、いま塚本先生がおっしゃられた考え方の中に、赤血球が成熟その極限に到達した細胞である、これは現在の血液学の定説でありますが、この考え方が私はそもそも間違いである。
私の考え方では、食べものが材料になって腸でつくられた細胞でありますから、きわめて原始的な細胞であります。
しかるがゆえに赤血球の中には何十種類もの酵素があり、しかも、エネルギーがプールされている。
最近これはわかった事柄であります。いままでは極端に成熟をした、老いぼれの、死の一歩手前の細胞であるという考え方で赤血球を見ていたわけでありますが、その考え方にそもそも大きな間違いがあると思います。
最近の生化学の進歩は、赤血球の中の無数の酵素が含まれている、あるいは、エネルギーがちゃんとプールされていて、死ぬまぎわの細胞がなぜそういうものを持っているのか、いまの医学的な常識では説明がつかないという段階であります。
そういうことから考えましても、もう根本的にやはり考え方の土台が違っているというような気がいたします。
それからガン細胞の分裂についてであります。
いま塚本先生がおっしゃいましたように、ガン細胞というものは、体細胞が突然変異を起こして異常な細胞になって、その細胞が無限に分裂増殖をする細胞であるというふうに説明をされました。
これは現在のガンに関する定義であります。世界の学者が、ガンとはそういう病気であるというふうに信じております。
そういう意味ではもちろん間違いのない考え方でありますが、しかし私の立場から申し上げますと、そういうことももちろん承知の上で、からだの中にあるガン組織というものは、私は分裂増殖をしておらないというふうに見ております。
しかし、実際にガン細胞の分裂がきれいに映画の中にとらえられたりしております。
東京シネマでつくられましたガン細胞に関する映画などを見ますと、ガン細胞の分裂というものは実にみごとにとらえられております。
が、それはそういう特殊なガン細胞が示す行動であって、
すべてのガンがそういうふうに体内で分裂増殖をしているのではないと思います。
もしガン細胞がほんとうに分裂増殖をしているのであれば、
たとえば、現在がんセンターで入院あるいは手術をされたガンの患者さんのその組織の一片を持ってきて、
そして顕微鏡の下でガン細胞の分裂というものは観察されてしかるべきであります。
しかし、そういう観察がなされたという報告は、私は一例も聞いておりません。
実際に手術をして、ガンの組織というものは幾らでも、いつでも、随意にわれわれは取り出すことができるわけでありますから、
そういうガン細胞が分裂増殖をしているかどうかということは
確かめようと思えばいつでも確かめられるはずであります。
そういう実際のガンの組織というものを取り出して、そして、顕微鏡の下でそれを観察した学者というものは、私はいないと思います。
実際には、われわれのからだの中では、定説はガン細胞の分裂ということであります
けれども、赤血球がガン細胞に変わっていることは、ほぼ間違いのない事実だと私は確信いたします。
実際に、最近フランスでも、ガン研究の権威であるアルぺルン教授が、ガン細胞というものが分裂しているかどうかということについては、これは詳しく触れておりませんけれども、小さなガンの種になる細胞が寄り集まって、そうして一個の典型的なガン細胞に発展をしていくのだという説を唱えまして、そういう報道がヨーロッパではなされております。
そういうことを見ましても、分裂増殖だけではなさそうである。
分裂増殖一辺倒ではいけないのではないか。
たとえば、現在のガンの治療薬にいたしましても、ガン細胞は分裂増殖をするから、その分裂を抑制するような化学物質であればガンはなおるであろうというふうに、
きわめて単純に、機械的に考えてその開発が進められているわけでありますが、
こういう考え方のもとでは、
私は幾ら研究費をつぎ込んでもしかるべき抗ガン剤というものはできないというふうに見ております。
また、いままで長年私はそういう考え方を講演会で述べたり、あるいは私の著書の中ではっきりと明記いたしております。
ガン細胞が赤血球からできるということにつきましては、私が八年前に書きました「血球の起原」という本の中でそれをはっきり述べております。
たとえば、吉田肉腫の場合でありますが、あの吉田肉腫の細胞というものは、実際にはほとんど分裂増殖をしておりません。
種を動物の腹腔の中に植えつけますと、まず必ず腹膜に出血性の炎症が起こってまいります。そして、腹腔の中にまず血液が浸出する、赤血球が腹水の中にたくさんまざり始めるということを前提にして、初めてガン細胞はふえるのであります。
吉田肉腫の細胞というものは増殖していっております。
その過程を、私は八年前に書いた私の本の中ではっきり指摘いたしております。
吉田肉腫の増殖というものも、私は、腹膜の炎症が起こらなければ、腹膜の炎症を起こさないように処置してこの吉田肉腫の種を植えつけたのでは、絶対にこの肉腫細胞は増殖をしないであろうというふうに想像いたしております。
炎症というものが背景にあって、血液が腹水の中に出てくるということが前提条件である、そうしなければガン細胞はできない、その赤血球がお互いに融合し合いまして、そうして一つのガン細胞に発展をしていくということであります。
また、実際にこの吉田肉腫の細胞を観察してみますと、形がまちまちであります。
もし一定の分裂方式で細胞が増殖していくのであれば、ほとんどきまった形の細胞ができなければならないのに、増殖している細胞は全く千差万別であるということも、でき方が単に分裂増殖ではないということを物語っているように思われます。
それから、話はだいぶ前にさかのぼりますが、さっき斎藤議員が申しておられました
無菌的な血液を培養して、
そうして点状の小さなバクテリアが発生をし、
これが球菌になり、桿菌に発展をしていくことが
実際にあるのかどうか、
これは国の機関でひとつはっきりさせろということを申しておられましたが、
この問題につきましては、
私自身すでに、SICの牛山氏とは全然別個に実験を行なっております。
私はSICの問題とは一切無関係に、
血液というものは無菌的な条件のもとで、
試験管の中で放置しておけば、一体最後にはどういうふうに変わってしまうものであろうか
というようなことを追求する目的で、
大学時代に大ぜいの研究員を使いまして、こまかく探索をいたしました。
その結果は、この八年前に書きました「血球の起原」という本の一〇〇ページ、それから今度出しました「血液とガン」という本の一五ぺ-ジに、
その写真も掲載をいたしまして、その結論を披瀝いたしておりますが、
これは無菌的な血液であっても、
血漿の中に、これは実は赤血球の中にそういう点状のバクテリア様のものが発生をいたしまして、
これがだんだん発育をいたしまして、
そうして球菌になり、
かつ、桿菌にまで発展をする
という事実を私は認めております。
この問題は、国家の機関で追求せよということでありますけれども、私はその必要はほとんどないのではないかというような、むしろ逆の考え方をしております。
といいますのは、
はっきりとそういうふうになるのでありまして、
牛山氏が無菌的に血液を培養して、ああいう桿菌様のものが得られたというその事実に対しましては、
私は絶対に間違いがなかったというふうに判定できると思います。
ただ、
そういう桿菌様のものを材料にしてつくられた
SICという化学物質がガンにきくかどうかということは、
私は臨床医でありませんので、
これは全くわかりません。
そういうことをこの際つけ加えておきたいと思います。
-----------------------以上引用終わり--------------------------------
国の機関でやるほどのものでのないと言われた新理論の松下博士は、「そんなのは当たり前に見ることが出来る」という自信が言わしたものでしょうから、
専門家であれば「誰でも確認出来る」という意味なのでしょう。
そうなると、
誰でもそれをやろうと思えばいつでもできるほど確実性が、再現性があるという事です。
じゃあ、国がやらないなら個々の医師達がやればいいじゃないか?
普通の考えならそうなります。
しかし、普通の世界じゃなかったようです。
もっとも、それが確認されても、黙殺しちゃうでしょうから。
やっぱり、国家がその権威を利用して公開実験で確認すべきだったのです。












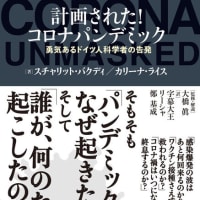
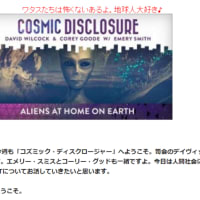
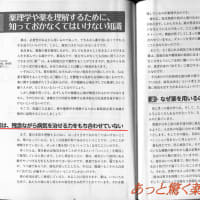
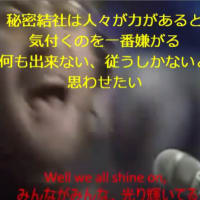
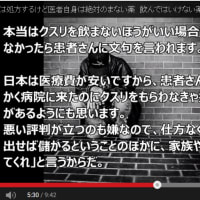

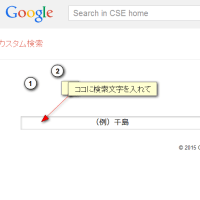
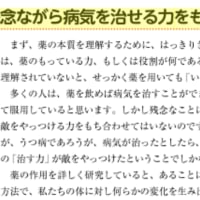







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます