一流と言われる医学者まで洗脳されている・・・としたら・・・
一般人など
part5 大いなる洗脳 (世界医薬産業の犯罪)音声読み上げmp3です。
元記事はウェブ魚拓
PART5 大いなる洗脳権力への道 ロックフェラーのマスコミ支配●社会的イメージ●インテリの買収ロックフェラーⅠ世の伝記作家
以下転載ーーーーーーーーーーーー
PART5 大いなる洗脳
↑
権力への道 ロックフェラーのマスコミ支配
彼のキャリアを公平な目で検討すれば、必ずや、彼が人間の持つもっとも醜悪な情熱-すなわち金銭に対するあくなき欲の犠牲者であったという結論に達するだろう……。
この金の亡者が、密かに忍耐強く、ひたすらに、いかにして富を増やそうかと画策を巡らせている図それは決して快いものではない……。
彼は残酷と背徳をもって、商業を平和的なりわいから戦いへと変化させた。市場競争を品位ある競い合いから凶暴な殺し合いへと変化させた。そして彼は自らの組織を慈善団体と呼び、教会出席と慈善行為を己れの正しさの証明とする。しかし我々のような単純な人間の目には、彼のこの二面性はどうしてもうまく噛み合わない。これは信仰という仮面をかぶった悪行である。その名を偽善という。
これは一九〇五年当時、広く読まれていた『マックルアー』という雑誌に、アイダ・ターベルが連載した「スタンダード石油の歴史」に出てくるジョン・D・ロックフェラーⅠ世の描写である。
この当時、ロックフェラーの評判はまだ最低というところまでは落ちていなかった。ロバート・ラフォレット上院議員が彼のことを「我々の時代の最悪の犯罪人」と呼んだのはこの後だし、新聞が彼を「世界でもっとも嫌われている人」と評し、漫画で、片手で金の詰まった袋を盗みながらもう一方の手で子供に一〇セントを恵んでいる偽善者に描いたのも、これより後のことである。
ところがずっと時代が下って第二次大戦後になると、アメリカ国内でも外国でも、ロックフェラーⅠ世の名誉を傷つけるような記事を見つけるのは非常に難しくなってしまった。さらに、父親の足跡を忠実に辿ったジュニアー、そしてその四人の息子たちについての非難もまったく聞こえてこない。それどころか、今日、さまざまな百科事典をくると、ロックフェラー家への賞賛しか見当たらないだろう。こんな具合である。
ジョン・D・ロックフェラーⅠ世は、一九一一年にはビジネス活動から引退し、余生は社会への寄付に没頭して過した。彼の莫大な財産によって設立された、数々の慈善団体は、受託人がそれを管理し、運営に当たる職員たちは国民への奉仕の機会を模索し続けた。寄付総額は六億ドルに上るとされている(ロックフェラー所有になる『ブリタニカ大百科事典』国際版、一九七二年)。
また彼の独り息子、ロックフェラー・ジュニアー(一八七四~一九六〇年)についても同じ事典にこうある。
彼はロックフェラー家のビジネス、慈善、市民団体において、父親の手足となって働いた。その生涯は慈善、市民活動に献げられたと言って過言ではない――一九 七年から五五年末までの寄付総額は四億ドルに上る。
もちろんここでは、ロックフェラー家のこれほどの財力を築き上げた冷酷なビジネスのやり方については一言も触れていない。モルガンやメロンと手を組んでアメリカを第一次大戦に巻き込み、五万人のアメリカ人兵士をヨーロッパで死なせた政治的陰謀についてもまったく触れていない。
では、二〇世紀初頭の、前掲の『マックルアー』の連載記事に見られるようなロックフェラー父子への声高な非難が登場した時代と、非難の声が徐々にマスコミの表面から消え、ついには、ロックフェラー家とその慈善行為への全面的な賞賛ばかりになってしまった現代との問に、いったい何がおこったのだろうか。
ブリタニカによればⅠ世が「ビジネス活動から引退」したとされる一九一一年というのは、彼が違法経営によって有罪判決を受け、スタンダード石油トラストを解散するよう裁判所に命じられた年なのである。当時スタンダード石油トラストは四〇の会社を包括しており、そのうち一四はロックフェラーの一〇〇パーセント所有だった。
ところが皮肉なことに、ロックフェラー帝国をさらに強力にしたのが、この強制解散だったのである。おそらく、これはロックフェラー自身さえ予想しえなかったことだろう。解散以前のトラストは誰の目にもはっきりと見える格好の標的だった。
しかし解散後、地下にもぐってそのカは見えない場所で安全に守られるようになった。見えない暴君を撃つことはできない。ロックフェラーは裁判所に命じられた通りにトラストを解体した――ふりをした。トラストを多数の別会社に分割し、それらの会社を、自分の息子をも含めた傀儡を通して支配し続けたのである。
二〇世紀というコミュニケーションの時代を支配する鍵は「世論」だということに、ロックフェラーが気づいたのは一九一三~四年におこったある事件がきっかけだった。それまでは彼は世論というものを馬鹿にしていた。
当時はまだラジオ、テレビ以前の時代で、新聞がマスコミの中心だったが、その新聞が彼への敵意をあらわにし始めた時でさえそうだった。そして現在では当たり前のようになっている世論の形成ということなどまったく考えず、せいぜい参考にして利用する程度だった。
ある事件とは、「ラドロウ殺戮」と呼ばれている事件である。この時、世論の風当たりがあまりにも激しくなり、さしもの厚顔のロックフェラーⅠ世も、何とか手を打たねばという気をおこした。
そして、この時の世論操作が思いのほかうまくゆき、これを機にロックフェラーはアメリカの一財閥から世界のそれへと変身することになったのである。
↑
●社会的イメージ
鉱山労働者組合、というのは後に有名な労働運動家ジョン・L・ルイスを生んだ組合であるが、この組合がロックフェラー所有の会社のひとつ、コロラド燃料・鉄鋼山会社の鉱山労働者の給料アップと生活条件向上を要求してきた。
ヨーロッパの貧しい国々からの移民がほとんどを占める鉱山労働者は、途方もない家賃を払って会社支給のあばら屋に住み、それでなくとも低い賃金は、これまた途方もない値段で品物を売る会社の売店でしか通用しない金券で支払われ、彼らが行く教会の牧師は会社雇いで、子弟は会社運営の学校で教育を受けていた。
また会社の図書館には、熱狂的クリスチャンであるロックフェラーが「破壊的」とみなす種類の本、たとえばダーウィンの『種の起源』などは置かれていなかった。さらに労働者たちが組合に入るのを防ぐために、警備員やスパイをおき、そのためには年間二万ドル以上を費やしていた。これが当時のコロラド燃料・鉄鋼山会社の状況だった。
この会社の公式の責任者だったロックフェラー・ジュニアーと、財団の理事でシニアーの腹心、バプテスト派の牧師フレデリック・T・ゲイツの二人は、組合と交渉することさえ拒んだ。そしてストライキに参加した労働者たちを社宅から立ち退かせ、ボールドウィン・フェルツ探偵社を通して何千人ものスト破りを雇い入れた。さらに、アモンズ・コロラド州知事に説いて州兵を動員させた。
ラドロウ鉱山は戦闘状態に陥った。州兵が、さらには社宅立ち退き以後テントを張ってキャンプしていた労働者やその家族が情容赦なく殺された。恐れをなしたアモンズ知事がウィルソン大統領に連邦軍の出動を要請し、ようやく騒ぎが収まった。
現在ほど強いロックフェラー色はなかったとは言え、すでに決して反ロックフェラーでもなかった『ニューヨーク・タイムズ』がこの事件を一九一四年四月二十一日、次のように報じている。
今日、コロラド州ラドロウ地区で、ストライキ中の炭鉱労働者とコロラド州兵による戦闘が一四時間にわたって繰り広げられ、ギリシャ系のストライキ指導者ルイス・ティカスが殺され、ラドロウのテント村には火が放たれた。
翌日の『ニューヨーク・タイムズ』の記事はさらに続ける。
コロラド州ラドロウ地区のロックフェラー所有のコロラド燃料・鉄鋼山会社でおこった州兵とストライキ中の炭鉱労働者間の一四時間にわたる戦闘の結果は、死者四五人(うち三二人は婦人と子供)、行方不明二〇人、負傷者二〇人余と判明した。ラドロウキャンプは焼け焦げた残骸に覆われ、労働闘争の歴史に類を見ない恐怖に満ちた事件を物語っている。労働者たちが州兵のライフル射撃から身を守るために掘った穴の中で、婦人や子供たちが捕らえられたネズミのように炎に煽られて死んだ。今日午後、掘りおこされた穴のひとつには、一〇人の子供、二人の婦人の死体があった。
ロックフェラーへの世論の風当たりが急に強くなった。そこで彼は、米国随一と言われた腕ききの新聞記者アイヴィ・リーを雇い入れることにした。リーに与えられた課題は、この暴君の社会的イメージを塗り直すという難しいものだった。
設立されたばかりのロックフェラー財団に用途未定のお金が一億ドルばかり転がっているのを知ったリーは、そのうちのほんの一〇〇万ドルほどを著名な大学、病院、教会、慈善団体などに寄付することを思いついた。この提案はただちに受け入れられた、もちろん一〇〇万ドルは喜んで受け取られた。そしてこのニュースは世界中の新聞を賑わした。新聞社にとって、二〇〇万ドル」は内容のいかんにかかわらず常に大きなニュースなのである。
これが今日まで延々と続くマスコミへの巧妙なニュース売り込みの始まりだった。華々しい新聞報道にのって、ロックフェラー家から流れ出す多額の寄付金の輝きに目をくらまされて、気まぐれな大衆は外国人移民の殺戮事件のことなどすぐに忘れてしまった-少なくとも大目に見る気になった。
その後、ロックフェラーは新聞記者だけではなく、新聞社そのものを買収、資金援助、そして創業した。一九二三年にヘンリー・ルースが創刊した『タイム』は間もなく経営困難に陥り、J・P・モルガンに買い取られたがモルガンの死とともに彼の金融帝国も崩壊した。その時、ロックフェラーは時を移さず、この見返りの多そうな雑誌をその姉妹誌『フォーチュン』『ライフ』とともに買い取った。
そしてこの三誌のためにロックフェラーセンターの中に豪華な一四階建ての社屋、「タイム&ライフ・ビル」まで建てた。ロックフェラーはその上『タイム』のライバルである『ニューズ・ウィーク』の共同所有者でもあった。『ニューズ・ウィーク』はルーズベルトのニューディール時代のはじめ、ロックフェラー、ヴィンセント・アスター、ハリマン一族の共同出資で創刊されたが、表面に出ていたのは、フランクリン・D・ルーズベルト大統領のブレーン・トラストの長、レイモンド・モレイ教授だった。
いかにロックフェラーとは言え、その財力にはやはり限度があった。そこでリーは、もう少し日常的レベルで大衆の目にこの帝王の気前の良さ、親切さを印象づける名案を思いついた。道ばたで彼のもとに近づいて来る子供たちにピカピカの一〇セント銅貨を恵んでやるという案である。一人としてお金を貰えない子供がでてはいけない。そこで彼のボディガードたちは銅貨を入れた袋を持ってついて歩くようになったのである。
↑
●インテリの買収
生来の皮肉屋であったロックフェラーでさえも、いわゆる「インテリ」がいかに簡単に買収されてしまうかという点では、いささかの驚きを禁じ得なかったようである。実際のところ、インテリという人種はロックフェラーにとって最高利回りの投資の対象となった。
アメリカの内外に「教育資金」を設立し、これにふんだんにお金を出すことにより、ロックフェラーは政府や政治家のみならず、知識階級、科学者たちをも支配できるようになったのである。
↑
権力への道 ロックフェラーのマスコミ支配
彼のキャリアを公平な目で検討すれば、必ずや、彼が人間の持つもっとも醜悪な情熱-すなわち金銭に対するあくなき欲の犠牲者であったという結論に達するだろう……。
この金の亡者が、密かに忍耐強く、ひたすらに、いかにして富を増やそうかと画策を巡らせている図それは決して快いものではない……。
彼は残酷と背徳をもって、商業を平和的なりわいから戦いへと変化させた。市場競争を品位ある競い合いから凶暴な殺し合いへと変化させた。そして彼は自らの組織を慈善団体と呼び、教会出席と慈善行為を己れの正しさの証明とする。しかし我々のような単純な人間の目には、彼のこの二面性はどうしてもうまく噛み合わない。これは信仰という仮面をかぶった悪行である。その名を偽善という。
これは一九〇五年当時、広く読まれていた『マックルアー』という雑誌に、アイダ・ターベルが連載した「スタンダード石油の歴史」に出てくるジョン・D・ロックフェラーⅠ世の描写である。
この当時、ロックフェラーの評判はまだ最低というところまでは落ちていなかった。ロバート・ラフォレット上院議員が彼のことを「我々の時代の最悪の犯罪人」と呼んだのはこの後だし、新聞が彼を「世界でもっとも嫌われている人」と評し、漫画で、片手で金の詰まった袋を盗みながらもう一方の手で子供に一〇セントを恵んでいる偽善者に描いたのも、これより後のことである。
ところがずっと時代が下って第二次大戦後になると、アメリカ国内でも外国でも、ロックフェラーⅠ世の名誉を傷つけるような記事を見つけるのは非常に難しくなってしまった。さらに、父親の足跡を忠実に辿ったジュニアー、そしてその四人の息子たちについての非難もまったく聞こえてこない。それどころか、今日、さまざまな百科事典をくると、ロックフェラー家への賞賛しか見当たらないだろう。こんな具合である。
ジョン・D・ロックフェラーⅠ世は、一九一一年にはビジネス活動から引退し、余生は社会への寄付に没頭して過した。彼の莫大な財産によって設立された、数々の慈善団体は、受託人がそれを管理し、運営に当たる職員たちは国民への奉仕の機会を模索し続けた。寄付総額は六億ドルに上るとされている(ロックフェラー所有になる『ブリタニカ大百科事典』国際版、一九七二年)。
また彼の独り息子、ロックフェラー・ジュニアー(一八七四~一九六〇年)についても同じ事典にこうある。
彼はロックフェラー家のビジネス、慈善、市民団体において、父親の手足となって働いた。その生涯は慈善、市民活動に献げられたと言って過言ではない――一九 七年から五五年末までの寄付総額は四億ドルに上る。
もちろんここでは、ロックフェラー家のこれほどの財力を築き上げた冷酷なビジネスのやり方については一言も触れていない。モルガンやメロンと手を組んでアメリカを第一次大戦に巻き込み、五万人のアメリカ人兵士をヨーロッパで死なせた政治的陰謀についてもまったく触れていない。
では、二〇世紀初頭の、前掲の『マックルアー』の連載記事に見られるようなロックフェラー父子への声高な非難が登場した時代と、非難の声が徐々にマスコミの表面から消え、ついには、ロックフェラー家とその慈善行為への全面的な賞賛ばかりになってしまった現代との問に、いったい何がおこったのだろうか。
ブリタニカによればⅠ世が「ビジネス活動から引退」したとされる一九一一年というのは、彼が違法経営によって有罪判決を受け、スタンダード石油トラストを解散するよう裁判所に命じられた年なのである。当時スタンダード石油トラストは四〇の会社を包括しており、そのうち一四はロックフェラーの一〇〇パーセント所有だった。
ところが皮肉なことに、ロックフェラー帝国をさらに強力にしたのが、この強制解散だったのである。おそらく、これはロックフェラー自身さえ予想しえなかったことだろう。解散以前のトラストは誰の目にもはっきりと見える格好の標的だった。
しかし解散後、地下にもぐってそのカは見えない場所で安全に守られるようになった。見えない暴君を撃つことはできない。ロックフェラーは裁判所に命じられた通りにトラストを解体した――ふりをした。トラストを多数の別会社に分割し、それらの会社を、自分の息子をも含めた傀儡を通して支配し続けたのである。
二〇世紀というコミュニケーションの時代を支配する鍵は「世論」だということに、ロックフェラーが気づいたのは一九一三~四年におこったある事件がきっかけだった。それまでは彼は世論というものを馬鹿にしていた。
当時はまだラジオ、テレビ以前の時代で、新聞がマスコミの中心だったが、その新聞が彼への敵意をあらわにし始めた時でさえそうだった。そして現在では当たり前のようになっている世論の形成ということなどまったく考えず、せいぜい参考にして利用する程度だった。
ある事件とは、「ラドロウ殺戮」と呼ばれている事件である。この時、世論の風当たりがあまりにも激しくなり、さしもの厚顔のロックフェラーⅠ世も、何とか手を打たねばという気をおこした。
そして、この時の世論操作が思いのほかうまくゆき、これを機にロックフェラーはアメリカの一財閥から世界のそれへと変身することになったのである。
↑
●社会的イメージ
鉱山労働者組合、というのは後に有名な労働運動家ジョン・L・ルイスを生んだ組合であるが、この組合がロックフェラー所有の会社のひとつ、コロラド燃料・鉄鋼山会社の鉱山労働者の給料アップと生活条件向上を要求してきた。
ヨーロッパの貧しい国々からの移民がほとんどを占める鉱山労働者は、途方もない家賃を払って会社支給のあばら屋に住み、それでなくとも低い賃金は、これまた途方もない値段で品物を売る会社の売店でしか通用しない金券で支払われ、彼らが行く教会の牧師は会社雇いで、子弟は会社運営の学校で教育を受けていた。
また会社の図書館には、熱狂的クリスチャンであるロックフェラーが「破壊的」とみなす種類の本、たとえばダーウィンの『種の起源』などは置かれていなかった。さらに労働者たちが組合に入るのを防ぐために、警備員やスパイをおき、そのためには年間二万ドル以上を費やしていた。これが当時のコロラド燃料・鉄鋼山会社の状況だった。
この会社の公式の責任者だったロックフェラー・ジュニアーと、財団の理事でシニアーの腹心、バプテスト派の牧師フレデリック・T・ゲイツの二人は、組合と交渉することさえ拒んだ。そしてストライキに参加した労働者たちを社宅から立ち退かせ、ボールドウィン・フェルツ探偵社を通して何千人ものスト破りを雇い入れた。さらに、アモンズ・コロラド州知事に説いて州兵を動員させた。
ラドロウ鉱山は戦闘状態に陥った。州兵が、さらには社宅立ち退き以後テントを張ってキャンプしていた労働者やその家族が情容赦なく殺された。恐れをなしたアモンズ知事がウィルソン大統領に連邦軍の出動を要請し、ようやく騒ぎが収まった。
現在ほど強いロックフェラー色はなかったとは言え、すでに決して反ロックフェラーでもなかった『ニューヨーク・タイムズ』がこの事件を一九一四年四月二十一日、次のように報じている。
今日、コロラド州ラドロウ地区で、ストライキ中の炭鉱労働者とコロラド州兵による戦闘が一四時間にわたって繰り広げられ、ギリシャ系のストライキ指導者ルイス・ティカスが殺され、ラドロウのテント村には火が放たれた。
翌日の『ニューヨーク・タイムズ』の記事はさらに続ける。
コロラド州ラドロウ地区のロックフェラー所有のコロラド燃料・鉄鋼山会社でおこった州兵とストライキ中の炭鉱労働者間の一四時間にわたる戦闘の結果は、死者四五人(うち三二人は婦人と子供)、行方不明二〇人、負傷者二〇人余と判明した。ラドロウキャンプは焼け焦げた残骸に覆われ、労働闘争の歴史に類を見ない恐怖に満ちた事件を物語っている。労働者たちが州兵のライフル射撃から身を守るために掘った穴の中で、婦人や子供たちが捕らえられたネズミのように炎に煽られて死んだ。今日午後、掘りおこされた穴のひとつには、一〇人の子供、二人の婦人の死体があった。
ロックフェラーへの世論の風当たりが急に強くなった。そこで彼は、米国随一と言われた腕ききの新聞記者アイヴィ・リーを雇い入れることにした。リーに与えられた課題は、この暴君の社会的イメージを塗り直すという難しいものだった。
設立されたばかりのロックフェラー財団に用途未定のお金が一億ドルばかり転がっているのを知ったリーは、そのうちのほんの一〇〇万ドルほどを著名な大学、病院、教会、慈善団体などに寄付することを思いついた。この提案はただちに受け入れられた、もちろん一〇〇万ドルは喜んで受け取られた。そしてこのニュースは世界中の新聞を賑わした。新聞社にとって、二〇〇万ドル」は内容のいかんにかかわらず常に大きなニュースなのである。
これが今日まで延々と続くマスコミへの巧妙なニュース売り込みの始まりだった。華々しい新聞報道にのって、ロックフェラー家から流れ出す多額の寄付金の輝きに目をくらまされて、気まぐれな大衆は外国人移民の殺戮事件のことなどすぐに忘れてしまった-少なくとも大目に見る気になった。
その後、ロックフェラーは新聞記者だけではなく、新聞社そのものを買収、資金援助、そして創業した。一九二三年にヘンリー・ルースが創刊した『タイム』は間もなく経営困難に陥り、J・P・モルガンに買い取られたがモルガンの死とともに彼の金融帝国も崩壊した。その時、ロックフェラーは時を移さず、この見返りの多そうな雑誌をその姉妹誌『フォーチュン』『ライフ』とともに買い取った。
そしてこの三誌のためにロックフェラーセンターの中に豪華な一四階建ての社屋、「タイム&ライフ・ビル」まで建てた。ロックフェラーはその上『タイム』のライバルである『ニューズ・ウィーク』の共同所有者でもあった。『ニューズ・ウィーク』はルーズベルトのニューディール時代のはじめ、ロックフェラー、ヴィンセント・アスター、ハリマン一族の共同出資で創刊されたが、表面に出ていたのは、フランクリン・D・ルーズベルト大統領のブレーン・トラストの長、レイモンド・モレイ教授だった。
いかにロックフェラーとは言え、その財力にはやはり限度があった。そこでリーは、もう少し日常的レベルで大衆の目にこの帝王の気前の良さ、親切さを印象づける名案を思いついた。道ばたで彼のもとに近づいて来る子供たちにピカピカの一〇セント銅貨を恵んでやるという案である。一人としてお金を貰えない子供がでてはいけない。そこで彼のボディガードたちは銅貨を入れた袋を持ってついて歩くようになったのである。
↑
●インテリの買収
生来の皮肉屋であったロックフェラーでさえも、いわゆる「インテリ」がいかに簡単に買収されてしまうかという点では、いささかの驚きを禁じ得なかったようである。実際のところ、インテリという人種はロックフェラーにとって最高利回りの投資の対象となった。
アメリカの内外に「教育資金」を設立し、これにふんだんにお金を出すことにより、ロックフェラーは政府や政治家のみならず、知識階級、科学者たちをも支配できるようになったのである。
彼の支配下に入った知識階級の筆頭に挙げられるのが医学界、すなわち現代の新しい宗教の司祭たる医者の集団である。
賞金と栄誉の両方が揃ったピューリッツア賞、ノーベル賞などは、ロックフェラー支配体制にあからさまに敵対する人物には、これまで一度も与えられたためしがない。
ロックフェラー王朝の創始者によって考え出されたこの支配体制は今日も続いており、王位継承者たちによりさらに強化されている。
枯れることのない基金の生み出す収入の一部を毎年投げ与えることによって、ひょっとすると次は自分が貰えるかもしれないと期待しながらしっぽを振っている飼い犬すなわち大学長、大学教授、科学者、研究者、編集者、ジャーナリストといったインテリを自分のまわりにいつまでも侍らせておけるわけである。そして御馳走を期待して待っている人々は、それを与える主人を非難するような発言はしないものなのである。
たとえばピューリッツア賞受賞者であり、ロックフェラー医学研究所教授である細菌学者のルネ・デュボス教授である。彼は動物実験に対しては繰り返し懐疑的見解を発表してはいるが、常に奥歯にもののはさまったような言い方しかしない。ロックフェラーの資金に依存し、動物実験が盛んなロックフェラー研究所で仕事をしている彼としては仕方のないところなのだろう。
一九七八年、ヘンリー・キッシンジャーが国務長官在任当時、ネルソン・ロックフェラーから用途不明の五万ドルの「ギフト」を受け取ったという事実を公に認めざるを得なくなった。この件は、内部ではすでに皆が知っていたこと――すなわち政治動物園の中でうごめいている他の動物たち同様に、キッシンジャーさえも、ロックフェラー工場の製品にすぎないということーを、はじめて公衆の前にさらけ出したのだった。
またヘンリー・ルースは『タイム』のれっきとした創始者、編集長でありながら、経済的にはロックフェラー家からの広告収入に全面的に頼らざるを得なかった。彼の広告主に対するへつらいぶりは有名だった。
ジョン・D・ロックフェラー・ジュニアーは前述のラドロウ殺戮には大きな責任がある上、父親の問題の多い汚ないビジネスのほとんどに協力してきた。それにもかかわらず、一九五六年ヘンリー・ルースはジュニアーを『タイム』の表紙に取り上げ、「The Good Man」というタイトルで特別記事を組んだ。次のような誇張が随所に見られる。
ジョン・D・ロックフェラー・ジュニアーの生涯は、建設的社会事業への献身の一生だった。
この献身のゆえに、彼は戦争に大勝利をおさめた将軍や外交で国に尽した政治家と並ぶ、アメリカの真の英雄に列せられるのである。
『タイム』はその後もずっとロックフェラー家からの広告収入に依存しており、ジュニアーとルースが共に世を去った後も、編集部にはその基調を変える自由が与えられなかったものらしい。一九七九年、ジュニアーの息子、ネルソン・A・ロックフェラーの死に際して、次のような死亡記事を載せている(彼はベトナム戦争をはじめとする各地での戦争に関し、最右翼のタカ派であり、アッティカ刑務所での捕虜大量虐殺の責任者だった。他にもスキャンダルは多い)。
彼は祖国を向上させ、高揚させ、祖国に奉仕するという使命感にかられていた。
↑
ロックフェラーⅠ世の伝記作家
ロックフェラーⅠ世に戻ろう。アイヴィ・リーの世論操作は大成功を収めていた。傍らでジュニアーは父親の伝記の執筆を誰に依頼するかで悩んでいた。「権威ある」作品に仕上がらなくてはならないし、さきにアイダ・ターベルやジョン・T・ブリンのスキャンダル本でかぶせられた汚名をすすぐようなものでもなくてはならない。
しかし、伝記制作の最初の関門はシニアー自身の非協力的態度だった。これは老人にありがちの過度とも言える秘密主義が原因だった。リーがニューヨークの『ワールド』紙のリポーターで同時にすばらしいゴルファーでもあったウィリアム・O・イングリスを伝記作家として推薦し、やっとこの第一の関門を通り抜けた。事実、イングリスはよき作家であるよりはよきゴルファーであろうとしていた様子がうかがえる。彼はシニアーとともにロックフェラー私有のポカンティコの一八ホールのコースを無限と思われるほどの回数まわり、そのたびに老人は思い出を少しずつ語った。二人の交友は一九一五年から二五年まで続き、イングリスはようやく伝記の草稿を仕上げた。
当然のことながら、シニアーもジュニアーもその草稿の良し悪しを判断できる立場にはなかった。
そこで財団の中の「鑑識眼のある」専門家の判断に委ねることになった。
五セントで葉巻の買えた時代に、イングリスに支払われた年俸八〇〇〇ドルというのは、かなりの額の報酬だったと言、尺よう。この高給が彼の批判精神を鈍らせてしまったらしい。財団のブレーンは、彼の伝記はあまりにへつらいが過ぎ、とても世問に公表できない、との合意に達した。イングリスはロックフェラー宮廷内での寵を失い職を追われた。そこで、リーは今度はドイツからエミール・ルードヴィヒを招請することにした。ルードヴィヒはベストセラー伝記作家で、その頃ちょうど、彼の記念碑的作品とも言えるナポレオン伝を書き上げたばかりだった。
もちろん、ルードヴィヒの他にもロックフェラーの伝記執筆依頼を断った人物がいたかもしれない。
けれども記録に残っているのは彼一人である。彼はアメリカ行の渡航費を支払うというリーの申し出は受け入れた。しかしアメリカでロックフェラーに直接会い、どのような伝記を期待されているのかを聞かされると、すっかりこの仕事に興味を失ってしまった。
そしてそのままドイツに戻った。アイヴィ・リーの伝記作家捜しは振り出しに戻った。
その頃、ウィンストン・チャーチルが自分の父祖、マールボロ侯爵の伝記を書き、文筆家としての名声を博していた。リーはイギリスに渡り、チャーチルに、どのくらい支払えばロックフェラーの伝記作家となる屈辱に甘んじてくれるか、と恐る恐る尋ねた。チャーチルは前金で五万ポンドニ五万ドル、しかも大恐慌の時代のことである――を要求した。
その報告を受けたロックフェラーは、自分が二五万ドルに値するほどには後世の人々の評判を気にしてはいないと感じ、NOの返事を出した。そして一九三〇年、ジョン・D・ロックフェラーI世は世を去った。息子はまだ、ロックフェラー王朝創始者の伝記作家にふさわしい人物を見つけていなかった。
しかしアメリカ国内でも名誉とお金を求める物書きには不足していなかった。ロックフェラー財団ブレーンの白羽の矢は、コロンビア大学(ロックフェラーがスポンサー)教授で、著書のクリーブランド大統領伝がピューリッツア賞(同じくロックフェラー後援)を受賞したばかりのアラン・ネヴィンズに立った。
ネヴィンズには、ルードヴィヒやチャーチルの華麗さはなかった。しかしロックフェラー体制内の囲われ者であるだけに信頼はおけた。実際、彼の書き上げた伝記のタイトルを見ただけで、彼がロックフェラー家の求めていたものが何であったかを、十分了解していたことが分かるだろう
『ジョン・D・ロックフェラー、アメリカの英雄時代を生きた男』。この伝記には、ロックフェラー批判が適所に適量ばら撤かれており、そのため辟易するような追従的部分をも何とか受け入れられるものにしている。しかし追従も相当なもので、「ロックフェラーは一瞬たりとも個人の商業上の利益追求と慈善活動とを混同するようなことはなかった」と書き、さらに、リシュリュー(フランス、ルイ一三世の宰相)、ビスマルク(ドイツ、鉄血宰相)、セシル・ローズ(南ア政治家、ローデシアは彼の名に因む)に比べても、少しも遜色がない、と恥ずかしげもなく述べている。
***
やがて、あちこちの出版社から、洪水のようにロックフェラーの伝記や一族の歴史を綴った書物が出版され始めるに及んで、隠そうにも隠しおおせぬほころびも見え出した。もちろんそれを見る眼を持った人々にのみ、見え出したという意味である。時が経つにつれ、故人の好ましからざる性癖であるとか若い頃の違法行為などを公にすることも許されるようになった。もっとも、まだ生存中の一族の輝かしいイメージを傷つけたり、財閥の経済的地位を脅かすような発言は許されるべくもなかったが。
例のアイダ・ターベルの文章も再登場したし、フェルディナンド・ランドバーグ教授の『金持ちと超金持ち』(一九六八年)、ピーター・コリエ、ディヴィッド・ホロヴィッツ共著の『ロックフェラー家』(一九七六年)など、相当批判的な内容のものも次々と出版された。ランドバーグはコロンビア大学に学んだ後、これもまた、ロックフェラー傘下のニューヨーク大学に移った歴史学者であるが、ロックフェラービジネスの過去の不正のあれこれを堂々と公開した。
またコリエとホロヴィッツもあちこちに発表した「容赦のない暴露記事」で、ロックフェラーの慈善活動の大半が、実は節税対策であり、寄付したよりもはるかに多額の見返りのあった利己的なものだったという事実を証拠だてることさえできたのである。しかしこれらの「容赦のない暴露記事」のどれからも見逃されているひとつの重要なビジネス分野がある。そのひとつとは何か?
彼らは、ロックフェラーが関心を寄せていた工業、商業分野を、たったひとつを除き、すべて言及している――石油、石炭、天然ガス、電気、鉄道、自動車、鉄鋼、ゴム、不動産、美術、出版、ラジオ、TV。
しかし、激しいロックフェラー攻撃の本においてさえ、常に忘れられているもっとも利潤の大きい分野、すなわちⅠ世の父親「ビルおやじ」が、まむし油とびん詰め石油を癌の特効薬と偽って、片田舎を売り歩いていた頃からずっと、ロックフェラー帝国の中心に位置してきた商売――薬である。
ではなぜ、薬への言及がないのか。ロックフェラーと二〇〇もの製薬会社との関わりに言及すれば、アメリカの「一般教育財団」と、その後、世界各地に設立された同種の慈善団体の設立の真の理由を暴露することになるからである。すなわち、ロックフェラー家は、他でもない一族の利益と権力の増大を図るもっとも有効な手段として「教育財団」という名の慈善団体を設立したのである。
そしてこの教育財団を通して何も知らない大衆に薬の大量使用を崇拝する「新しい宗教」を押しつけたのである。
もし、ホロヴィッツらの本に、ロックフェラーと製薬業界との関わりが述べられていたとすれば、おそらく無事出版されることなどなかっただろう。また、たとえ出版されたとしても、すぐ絶版になっていただろう。
ロックフェラー王朝の創始者によって考え出されたこの支配体制は今日も続いており、王位継承者たちによりさらに強化されている。
枯れることのない基金の生み出す収入の一部を毎年投げ与えることによって、ひょっとすると次は自分が貰えるかもしれないと期待しながらしっぽを振っている飼い犬すなわち大学長、大学教授、科学者、研究者、編集者、ジャーナリストといったインテリを自分のまわりにいつまでも侍らせておけるわけである。そして御馳走を期待して待っている人々は、それを与える主人を非難するような発言はしないものなのである。
たとえばピューリッツア賞受賞者であり、ロックフェラー医学研究所教授である細菌学者のルネ・デュボス教授である。彼は動物実験に対しては繰り返し懐疑的見解を発表してはいるが、常に奥歯にもののはさまったような言い方しかしない。ロックフェラーの資金に依存し、動物実験が盛んなロックフェラー研究所で仕事をしている彼としては仕方のないところなのだろう。
一九七八年、ヘンリー・キッシンジャーが国務長官在任当時、ネルソン・ロックフェラーから用途不明の五万ドルの「ギフト」を受け取ったという事実を公に認めざるを得なくなった。この件は、内部ではすでに皆が知っていたこと――すなわち政治動物園の中でうごめいている他の動物たち同様に、キッシンジャーさえも、ロックフェラー工場の製品にすぎないということーを、はじめて公衆の前にさらけ出したのだった。
またヘンリー・ルースは『タイム』のれっきとした創始者、編集長でありながら、経済的にはロックフェラー家からの広告収入に全面的に頼らざるを得なかった。彼の広告主に対するへつらいぶりは有名だった。
ジョン・D・ロックフェラー・ジュニアーは前述のラドロウ殺戮には大きな責任がある上、父親の問題の多い汚ないビジネスのほとんどに協力してきた。それにもかかわらず、一九五六年ヘンリー・ルースはジュニアーを『タイム』の表紙に取り上げ、「The Good Man」というタイトルで特別記事を組んだ。次のような誇張が随所に見られる。
ジョン・D・ロックフェラー・ジュニアーの生涯は、建設的社会事業への献身の一生だった。
この献身のゆえに、彼は戦争に大勝利をおさめた将軍や外交で国に尽した政治家と並ぶ、アメリカの真の英雄に列せられるのである。
『タイム』はその後もずっとロックフェラー家からの広告収入に依存しており、ジュニアーとルースが共に世を去った後も、編集部にはその基調を変える自由が与えられなかったものらしい。一九七九年、ジュニアーの息子、ネルソン・A・ロックフェラーの死に際して、次のような死亡記事を載せている(彼はベトナム戦争をはじめとする各地での戦争に関し、最右翼のタカ派であり、アッティカ刑務所での捕虜大量虐殺の責任者だった。他にもスキャンダルは多い)。
彼は祖国を向上させ、高揚させ、祖国に奉仕するという使命感にかられていた。
↑
ロックフェラーⅠ世の伝記作家
ロックフェラーⅠ世に戻ろう。アイヴィ・リーの世論操作は大成功を収めていた。傍らでジュニアーは父親の伝記の執筆を誰に依頼するかで悩んでいた。「権威ある」作品に仕上がらなくてはならないし、さきにアイダ・ターベルやジョン・T・ブリンのスキャンダル本でかぶせられた汚名をすすぐようなものでもなくてはならない。
しかし、伝記制作の最初の関門はシニアー自身の非協力的態度だった。これは老人にありがちの過度とも言える秘密主義が原因だった。リーがニューヨークの『ワールド』紙のリポーターで同時にすばらしいゴルファーでもあったウィリアム・O・イングリスを伝記作家として推薦し、やっとこの第一の関門を通り抜けた。事実、イングリスはよき作家であるよりはよきゴルファーであろうとしていた様子がうかがえる。彼はシニアーとともにロックフェラー私有のポカンティコの一八ホールのコースを無限と思われるほどの回数まわり、そのたびに老人は思い出を少しずつ語った。二人の交友は一九一五年から二五年まで続き、イングリスはようやく伝記の草稿を仕上げた。
当然のことながら、シニアーもジュニアーもその草稿の良し悪しを判断できる立場にはなかった。
そこで財団の中の「鑑識眼のある」専門家の判断に委ねることになった。
五セントで葉巻の買えた時代に、イングリスに支払われた年俸八〇〇〇ドルというのは、かなりの額の報酬だったと言、尺よう。この高給が彼の批判精神を鈍らせてしまったらしい。財団のブレーンは、彼の伝記はあまりにへつらいが過ぎ、とても世問に公表できない、との合意に達した。イングリスはロックフェラー宮廷内での寵を失い職を追われた。そこで、リーは今度はドイツからエミール・ルードヴィヒを招請することにした。ルードヴィヒはベストセラー伝記作家で、その頃ちょうど、彼の記念碑的作品とも言えるナポレオン伝を書き上げたばかりだった。
もちろん、ルードヴィヒの他にもロックフェラーの伝記執筆依頼を断った人物がいたかもしれない。
けれども記録に残っているのは彼一人である。彼はアメリカ行の渡航費を支払うというリーの申し出は受け入れた。しかしアメリカでロックフェラーに直接会い、どのような伝記を期待されているのかを聞かされると、すっかりこの仕事に興味を失ってしまった。
そしてそのままドイツに戻った。アイヴィ・リーの伝記作家捜しは振り出しに戻った。
その頃、ウィンストン・チャーチルが自分の父祖、マールボロ侯爵の伝記を書き、文筆家としての名声を博していた。リーはイギリスに渡り、チャーチルに、どのくらい支払えばロックフェラーの伝記作家となる屈辱に甘んじてくれるか、と恐る恐る尋ねた。チャーチルは前金で五万ポンドニ五万ドル、しかも大恐慌の時代のことである――を要求した。
その報告を受けたロックフェラーは、自分が二五万ドルに値するほどには後世の人々の評判を気にしてはいないと感じ、NOの返事を出した。そして一九三〇年、ジョン・D・ロックフェラーI世は世を去った。息子はまだ、ロックフェラー王朝創始者の伝記作家にふさわしい人物を見つけていなかった。
しかしアメリカ国内でも名誉とお金を求める物書きには不足していなかった。ロックフェラー財団ブレーンの白羽の矢は、コロンビア大学(ロックフェラーがスポンサー)教授で、著書のクリーブランド大統領伝がピューリッツア賞(同じくロックフェラー後援)を受賞したばかりのアラン・ネヴィンズに立った。
ネヴィンズには、ルードヴィヒやチャーチルの華麗さはなかった。しかしロックフェラー体制内の囲われ者であるだけに信頼はおけた。実際、彼の書き上げた伝記のタイトルを見ただけで、彼がロックフェラー家の求めていたものが何であったかを、十分了解していたことが分かるだろう
『ジョン・D・ロックフェラー、アメリカの英雄時代を生きた男』。この伝記には、ロックフェラー批判が適所に適量ばら撤かれており、そのため辟易するような追従的部分をも何とか受け入れられるものにしている。しかし追従も相当なもので、「ロックフェラーは一瞬たりとも個人の商業上の利益追求と慈善活動とを混同するようなことはなかった」と書き、さらに、リシュリュー(フランス、ルイ一三世の宰相)、ビスマルク(ドイツ、鉄血宰相)、セシル・ローズ(南ア政治家、ローデシアは彼の名に因む)に比べても、少しも遜色がない、と恥ずかしげもなく述べている。
***
やがて、あちこちの出版社から、洪水のようにロックフェラーの伝記や一族の歴史を綴った書物が出版され始めるに及んで、隠そうにも隠しおおせぬほころびも見え出した。もちろんそれを見る眼を持った人々にのみ、見え出したという意味である。時が経つにつれ、故人の好ましからざる性癖であるとか若い頃の違法行為などを公にすることも許されるようになった。もっとも、まだ生存中の一族の輝かしいイメージを傷つけたり、財閥の経済的地位を脅かすような発言は許されるべくもなかったが。
例のアイダ・ターベルの文章も再登場したし、フェルディナンド・ランドバーグ教授の『金持ちと超金持ち』(一九六八年)、ピーター・コリエ、ディヴィッド・ホロヴィッツ共著の『ロックフェラー家』(一九七六年)など、相当批判的な内容のものも次々と出版された。ランドバーグはコロンビア大学に学んだ後、これもまた、ロックフェラー傘下のニューヨーク大学に移った歴史学者であるが、ロックフェラービジネスの過去の不正のあれこれを堂々と公開した。
またコリエとホロヴィッツもあちこちに発表した「容赦のない暴露記事」で、ロックフェラーの慈善活動の大半が、実は節税対策であり、寄付したよりもはるかに多額の見返りのあった利己的なものだったという事実を証拠だてることさえできたのである。しかしこれらの「容赦のない暴露記事」のどれからも見逃されているひとつの重要なビジネス分野がある。そのひとつとは何か?
彼らは、ロックフェラーが関心を寄せていた工業、商業分野を、たったひとつを除き、すべて言及している――石油、石炭、天然ガス、電気、鉄道、自動車、鉄鋼、ゴム、不動産、美術、出版、ラジオ、TV。
しかし、激しいロックフェラー攻撃の本においてさえ、常に忘れられているもっとも利潤の大きい分野、すなわちⅠ世の父親「ビルおやじ」が、まむし油とびん詰め石油を癌の特効薬と偽って、片田舎を売り歩いていた頃からずっと、ロックフェラー帝国の中心に位置してきた商売――薬である。
ではなぜ、薬への言及がないのか。ロックフェラーと二〇〇もの製薬会社との関わりに言及すれば、アメリカの「一般教育財団」と、その後、世界各地に設立された同種の慈善団体の設立の真の理由を暴露することになるからである。すなわち、ロックフェラー家は、他でもない一族の利益と権力の増大を図るもっとも有効な手段として「教育財団」という名の慈善団体を設立したのである。
そしてこの教育財団を通して何も知らない大衆に薬の大量使用を崇拝する「新しい宗教」を押しつけたのである。
もし、ホロヴィッツらの本に、ロックフェラーと製薬業界との関わりが述べられていたとすれば、おそらく無事出版されることなどなかっただろう。また、たとえ出版されたとしても、すぐ絶版になっていただろう。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
かくして・・・
隣の家のおじいちゃんも、あの大病院の医学博士も・・・同じ穴のムジナ(笑い
映画すらいぶより
スライヴ 医療
スライブ金融










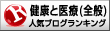



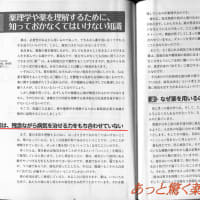

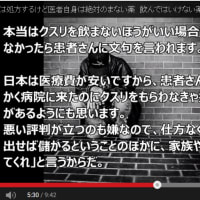


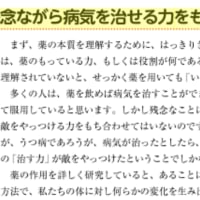







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます