現代医学の科学的根拠は動物実験から成り立っているという・・
が、この愛無き地獄絵のような動物実験から何が産み出されるというのだろうか?
動物虐待の意味だけではない、無用な非科学的根拠となり得る、「動物と人間の違い」が実際の医療に負の遺産を残してきたのだ・・・・
その一例として、レイプ・ラップという実験がある。
さて何のことだろうか? 転載記事の次にレイプ・ラップの記事を転載(なんだ、転載バッカし)
元記事
世界医薬産業の犯罪
一部転載ーーーーーーー
●レイプ・ラック
一般にどこの国でも、報道機関は動物実験の実態を公表するについては非常に消極的だと言えよう。しかし、カナダの『トロント・サン』のように、何度も繰り返し強硬な姿勢でこの問題に挑んでいる新聞もあるにはある。同紙の「実験室における科学という名のサディズム」というピーター・ウォージングトンの記事は、次のような書き出しで始まる。
カナダやアメリカにおける最重要機密事項は、諜報活動でも公定歩合でもプールでの首相のプライバシーでもない。さまざまな大学、研究所、実験施設における動物実験で何が行なわれているか、なのである。
続いてウォージングトンは実験室内で繰り広げられている残虐行為の実例を示す。回転ドラムの中で死ぬまで振り回されるイヌ、未精製の石油を食べさせられる北極グマ、「レイプ・ラック」にくくりつけられて妊娠させられる雌ザル――このサルはやがて自分の赤ん坊を虐待するようになる。
すなわち、床に赤ん坊の顔を叩きつけたり、体を引き裂いたり、歯で頭を噛み砕いたりするのである。何のためにこのような実験をするのかと言えば、虐待された人間の子供が成長すれば、やがて自分自身の子供を虐待するということを証明するためという。
サディストたちはこの手の実験を飽きもせず繰り返す。人間の苦痛を防止するためにというもっともらしい口実に隠れて、実は空前の規模で、新手の拷問が動物たちに与えられているのである。明らかに精神的に狂ったサディストどもの手によって。しかも明らかに文明社会の立法者としてはふさわしくない立法者どもの庇護のもとで。
***
ケンブリッジの研究員、コリン・ブレイクモアが同僚と行なった実験については『罪なきものの虐殺』でも紹介したが、彼らはまず、アルバートという名のネコの片目を一〇二度回転させ、ヴィクトリアという別のネコの片目を七七度回転させた。手術は二匹が生後一二日目に行なわれ、手術後は一日一八時間明かりをつけた部屋に入れられていた。九カ月が経過した後、二匹には一〇カ月間の行動実験が行なわれた。その結果、二匹は回転された目だけを使っていても障害物を避けるこ
とができた、という(『実験脳研究』Vol.125,一二九七六年)。
***
ここで『アニマルズ・ディフェンダー』(動物擁護者)八〇年十二月号に載った動物実験の宣伝を少しばかり拾ってみることにしよう。
まず『イギリス実験病理学誌』(六一巻、一九八〇年、pp.61-68)に、マンチェスター大学外傷科のH・B・ストーナー、A・ハント、J・ハドフィールドおよびH・W・マ~シャルが次のように書いた。「人によっては納得しかねるような奇妙な実験が、そこかしこで行なわれているのも事実だろう。しかし、大部分の実験はほとんど苦痛のないものである」。
『ネイチャー』二八五号(一九八〇年、pp.225-227)には、シアトルのワシントン大学心理学部霊長類研究センターのH・M・H・ウー、W・G・ホームズ、S・R・メディナ、およびG・P・サケットがこう書いた。「忘れてならないのは、動物たち自身も実験の恩恵を受けているという点である」。
前述の『イギリス実験病理学誌』(六〇巻、一九七九年、p.589)にはグラスゴー西部病院病理生化学部D・F・J・ローム、G・ジェデオン、J・ブルーム、およびA・フレックがこう書いた。
「動物実験を行なう有資格者は動物を愛している。同時に、それらの人々は現状では何をすれば一番よいのかを的確に判断したのである」。
一九八〇年、イギリスの動物実験反対団体、動物解放戦線が、ケンブリッジ郊外にある実験研究農場に踏み込んだことがある。当時その農場では、ヤギの乳房を首に移植するという実験が行なわれていた。警察はカメラマンを逮捕し、カメラとフィルムを押収した。とにかくまず第一に保護されるべきは実験者であり、すべての証拠は国家機密法の名のもとに差し押さえられねばならないというわけだろう。この法によれば、政府は動物実験研究室内の写真をとる人物は誰でも告訴することができるのである。『ザ・ガーディアン』(八〇年七月一日付)はこの乱入事件を次のように報じた。
バブラハム・ホール研究農場を運営する農業研究委員会は、この乱入事件を非難する次のようなステートメントを発表した。「バブラハムの実験動物たちは、日頃、平穏な雰囲気の中で、気心の知れた世話係による静かで優しい取り扱いに慣れている。それゆえに、動物たちは今回のような、窓ガラスや柵の破壊、カメラのフラッシュなどに、ひどい苦痛を覚えたはずである」。
このようなイギリス流の偽善に比べると、アメリカの動物実験者たちのあけっぴろげの率直さは、むしろ斬新にさえ響くだろう。たとえば、『ザ・ナショナル』〔一九五四年六月号)に載ったシカゴ大学のジョージ・ウェィカリン教授の言葉、「この件に関しては『人道的』という語とはいっさい関わりを持たせたくない」。『ピッツバーグ・プレス』(一九七四年十月二十七日)のインタビユーでのウィスコンシン霊長類センター所長バリー・F・ハーロウ博士の言葉、「私は動物は好きではない。ネコもイヌも嫌いだ。サルなどどうして好きになれよう」。このハーロウ博士というのは、
「愛」についての研究というもっともらしい口実をもうけて、生まれたばかりのチンパンジーの赤ん坊たちを母親から引き離し、最長の場合は八年間も、一匹ずつを完全な隔離状態で暗闇の中に置き、その成長過程を観察した人物である。
***
一九五〇年、ボストン生まれのヘンリー・フォスターという獣医が、チャールズ・リバー繁殖研究所という名の実験動物供給会社を設立した。この会社は実験用ビーグル犬の繁殖で大儲けし、七七年には一五〇〇万ドルもの利益を上げる優良企業へと成長した。八〇年四月二十八日号の『タイム』は、ユーモアさえ交え、次のようにチャールズ・リバー社について書いている。
一九七九年度の同社の売り上げは三〇〇〇万ドル、純益は三〇〇万ドルに上った。本年度は同社から一八〇〇万匹を越える動物たちが世界中に送り出される予定である。これらのお育ちの良い動物たちは、科学の名のもとに、サッカリンをむさぼり食い、酒に溺れ、紫煙をくゆらせ、放蕩に身をもち崩すことになっている。
動物実験の量、質では世界のトップをひた走るアメリカが、長寿ランキングでは世界の一七位にしか顔を出さないのはどうしたことなのだろう。しかもアメリカでは末期患者を一秒でも長く生かすべく必死の延命努力が行なわれている――事実、多くのアメリカ人にとって人生の最後の数年間は集中治療室内での苦痛の引き延ばし期間にすぎない――にもかかわらず、こうなのである。
大雑把な数字を示すと、アメリカでの心臓麻痺による死者は、一九四九年の四〇万人から七三年は二倍の八〇万人に、癌死の割合は一〇万人につき六八人から一七〇人へと急増、さらに一九〇〇年には糖尿病による死者は一〇万人につき一二・二人だったが、四分の三世紀の進歩の後、一八・五人(五ニパーセント増)に増えている。この間に何百万とも知れぬイヌたちが糖尿病のための実験と称して膵臓切除の苦しみをなめさせられてきたのである。何と素晴らしい成果ではないか!
過去一〇〇〇年にわたる動物実験は、人間の病気のために、ただのひとつの治療法さえも生み出さなかった。しかし、無数の新種の病気を作り出してきたのである。
***
動物実験者は実験が単に研究者個人の野心や好奇心を満たすためのものではなく、人類の幸福にとって不可欠なものであると主張する。しかし実験の実態が公表さえされないという事実が、この主張の立証を困難にしているように思われる。
今日の豊かな社会で、高騰する燃料費が支払えないため、寒さに凍えて死ぬお年寄りが何千人といる。その傍らで、癌撲滅キャンペーンでは、昨年、七五〇万ポンドが集まり、研究費としてあちこちの研究団体に寄付した。医学という名の祭壇に捧げものをすることによって、悪魔の目を避けることができると信じている迷信深い大衆の貢ぎ物を当然のように受け取っている団体が
いくつもあるのだ――痙性麻痺協会は三〇〇万ポンドを研究助成に使った。この協会はガイズ病院の研究プログラムに二〇〇万ポンドの助成金を出したことがあるのだが、そのお金がどんなことに使われたか知っているのだろうか。かつてこの病院で働いていた青年研究者の母親の証言を聞いてみよう。
この青年が、ロンドン大学内のある建物の最上階から動物のなき声が聞こえてくるのに気づいて上がっていった。そこではさまざまな動物が、たとえば、筋ジストロフィーの実験のために手術をされた後ろ足をひきずるなどして、苦痛にのたうち回っている光景を目にした。
この時、この青年は動物実験への嫌悪感から、科学者としての自らのキャリアを捨てたのだという(動物の権利擁護協会の機関紙『クラリオン』一九八〇年二月号、ロンドン)。
***
これまで三五年聞、エストロゲン錠剤の定期的服用は女性の乳癌予防に効果があると言われていた。しかし、この主張に真っ向から対立する新しい研究が報告された。――そのリポートによれば、エストロゲンはかえって癌を発生させる可能性があるという――アメリカだけでも、五〇〇万人から六〇〇万人の中年女性が医者にエストロゲンを処方されていると言われる(『インターナショナル・ヘラルド・トリビューン』一九七六年八月十七日)。
***
――アメリカでの、ここ数年来の保健行政のあり方には懸念すべき点が多々ある。これは単に、例の豚インフルエンザについてだけ言っているのではない。豚インフルエンザプログラムが始まった年の九月、食品医薬品局(FDA)特別委員会の作成した報告書によれば、普通の感冒を治すあるいは予防する薬は存在しないにもかかわらず、製薬会社は三万五〇〇〇種類もの感冒薬を市販しており、消費者は年間三億五〇〇〇万ドルを、それらの薬のために支払っているとの指摘があった……。
――保健行政の優先順位を決めるのは企業の営利主義である。豚インフルエンザの時も、主だった製薬会社は、いずれ持ち上がるかもしれない損害賠償の申し立てから、納税者のコスト負担で会社の損失が守られるという保証がとれるまで、ワクチン製造を見合わせていた(つまり会社側はワクチンの副作用を十分予測していたということである。現実にワクチンは多数の死者と麻痺患者を出し、その結果、企業ではなく政府が訴えられた――著者)。
我が国の経済においては、保健行政は私企業の利潤追求の手段になっている。最近の調査によると、全国の病院の九〇万床のうち二五パーセントが空いているというが、それにもかかわらず、病院の拡張は続けられているのである(『ザ・プログレッシヴ』一九七七年一月の中の記事「我が国の病める保健行政」より)。
***
現在、世界中で年間四億人が飢えのため死んでゆくという。その一方で、医者たちは片や健康な
胎児を堕胎して金持ちになり、片や試験官ベビーのための費用をかき集めているというこの現実。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
上記の中でレイプ・ラップという聞き慣れない言葉があったので検索してみた。
文字や言葉だけでは伝わらないものがあるが、ここには写真があったので直ぐ分かった。
目からの情報は直ぐ届く(時には錯覚も起こしやすいが)
一部転載ーーーーーーーURL:http://open.mixi.jp/user/2473503/diary/1937893934
心理学者のハリー・ハーローはこんな実験を行った。
生まれたてのアカゲザルを母親から引き離し、2体の「代理母」と過ごさせる。
代理母のうち、一体は針金製。
胸には哺乳瓶が取り付けられ、ミルクが出る様になっている。
もう一体の代理母はタオル製。
タオル母には哺乳瓶は付いていないが、ふかふかと柔らかい。
すると何が起こったか?
仔ザルはミルクをくれる針金母ではなく、ずっとタオル製の母親にしがみついていたのである。
ミルクを飲む時だけ針金母のところに行き、すぐに走ってタオル母に戻るのだ。
彼は「接触」が重要な変数であることを見出した。
仔ザルには接触が必要なのだ。
ふかふかとして暖かい存在を抱きしめ、抱きしめられることが。
そしてそれは給餌よりも大切なことであるらしい。
我々がハグなどのスキンシップを好むのも、根源的にはこれと同じ理由であると思われる。
孤独に震え、温もりを求める仔ザルは、私やあなたの心の中にもいるのだ。【註1】
この実験から教訓を引き出すなら、「子育ての際にはできるだけ赤ちゃんを抱きしめてあげましょう」ということだと現代に生きる我々なら誰もが思うだろう。
だがハーローの結論は別の方角を向いていた。
彼は「母親による授乳はあまり重要ではない」と考え、女性が積極的に社会進出することを薦めた(当時はフェミニズム台頭の時代だった)。
しかし後に「代理母に育てられた仔ザルは攻撃的で暴力的で反社会的に育つ」ことが判明。
そこでハーローは、代理母が自動的に揺れる仕掛けを組み込んだ。
仔ザルをあやし、遊ばせる様に。
事態はやや改善されたが完全ではなかった。
ハーローは実験を続け、「一日に30分、本物の母ザルと一緒にさせる」ことで仔ザルは正常に育つことを発見した。
接触・動き・遊び。
愛にはこの3つの変数が関係しており、この3つを与えてやれば、霊長類の欲求は満たせるのだ、と彼のチームは主張した。
こうして彼は自分の結論を守ることができた。
30分のケアなら女性の負担になることもない、と。【註2】
…それから数十年、現在では孤独なサルの物語はどう扱われているのだろうか?
アメリカのコメディードラマ『ビッグバンセオリー』にその片鱗を見ることが出来る。
主人公の一人、レナードは合理的すぎる冷淡な母親に育てられ、そのことについて複雑な感情を抱える青年だ。
彼は小学生の時にハグ・マシーンを製作した、と語る。
いつでも自分を抱きしめてくれる機械を。
その話を聞いたヒロイン、ペニーは「そんな悲しい話、初めて聞いた…」と絶句する。
だがレナードは続けてこう言う。
「一番悲しかったのは、パパも使っていたことだ」
…機械化されたハグはギャグのネタになるほど文化に根を下ろしたらしい。
ハーローの一連の実験はかなり有名だが、実際に使われた代理母の画像は不思議と目にしない。
「針金でできている」とか文章ではよく見るのだが、一体どんなデザインだったのか?
以前は探すのも一苦労だったが、ネットの発達した現代ではぐぐればすぐに見つかる。
えっ、こんなんなの!?



…だが「こんなん」であっても、仔ザルは明らかにタオル母に愛着を示した。
「空腹時にはミルクを、そうでない時は居心地の良い場所を求めているだけ」では決してない。
タオル母のデザインを少し変えただけで怒る。
仔ザルに向かって棘を突き出したり、冷水を浴びせる悪魔的なタオル母も作られたが、仔ザルはどれほど虐待されようともタオル母から離れようとはしなかったという。
ハーローの一連の実験はその残酷性を非難され、動物権利運動のきっかけとなった。
ハーローは挑発的な物言いをする人間で、動物嫌いだったらしい。
彼は実験に使うサルを少しも愛していないと公言した。
実験のせいで正常に育たなかった雌ザルは正しい交尾姿勢を取らなかったので、ハーローは実験用の仔ザルを得るために雌ザルを拘束具に固定し、雄ザルをけしかけて妊娠させた。
彼はこの器具を「レイプラック」と呼んだという。
TITLE:
DATE:2017年2月27日(月)
URL:http://open.mixi.jp/user/2473503/diary/1937893934
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
これを見ると医学研究者って(特に動物実験者たち)なにか変だよね。
ボクも変だけど・・
あちらはしかめっ面をして、さも科学者に見えるけど、実際は・・・・・へんしつ者じゃないか!!
ボクもよくしかめっ面をすることがあるけど(酒が無い!とか金が無い!とか、女がいない!とか・・・でんでん(云々)・・・
だが、白衣を着ていれば尊敬されるだろうか? (無いだろう無~~~)
上の猿の実験など可愛いものでしょう・・
もっと本格的な実験?はこちらでどうぞ。
一部転載ーーー
“罪なきものの虐殺”
この本ほど動物実験の真実を克明に記している本はありませんが、この本は弾圧を受け、
書店から回収されたことさえあります。
リューシュ氏は、本書から得た情報を広めてほしいと願っています。
私は彼の意思を汲んで、当サイトに多くの引用を掲載しました。
残念ながら、出版者に問い合わせたところ、現在日本でこの本は絶版中であり、
再販の時期も決定されていません。しかし、図書館に置いてある可能性が高いです。
当サイト掲載の文章は一部に過ぎないため、ぜひこの本を読んで頂きたいと思います。
著者 ハンス・リューシュ
訳者 荒木敏彦・戸田清
発行所 株式会社新泉社
下記サイトでは、この本からの抜粋を、動物実験の写真とともに紹介しています。
動物実験の無益性 どんな動物実験が行われているのか?
動物実験についての証言集 ‐1‐ 動物実験についての証言集 ‐2‐
動物実験の残虐性 ‐1‐ 動物実験の残虐性 ‐2‐
動物実験によってもたらされる悲劇 ‐1‐ 動物実験によってもたらされる悲劇 ‐2-
無駄な実験に使われる動物たち ‐1‐ 無駄な実験に使われる動物たち ‐2‐
化粧品のための動物実験 金欲の犠牲となる動物たち
動物実験写真集 ‐1‐ 動物実験写真集 ‐2‐
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
本当にきちがいかきょう人と言ってもよいくらい医学上の動物実験は見るに堪えないものです。
(もっとも肉を食べる手前、他人に殺させた肉を美味しいねえ♪と言って食べるボクも同質なのかな?)
いやいやいやいやいやいや
人類のため」と言って動物実験から人間の治療に応用できるという「錯覚」こそ問題なのです。
そもそも、最初から「愛無き」動物実験から産まれた「科学」が疑似科学だということなのです。
そこに気づくまで「動物実験 → 人体実験」という構図は続くでしょう。
もっとも、医学者達だけをわるもの扱いは出来ませんね。患者という「わたし」が要求しているんですから。
ボク達が居て、キミたち(動物実験者)が居る












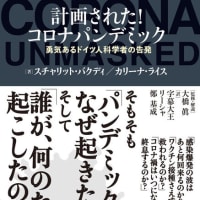
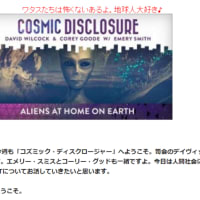
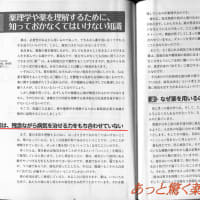
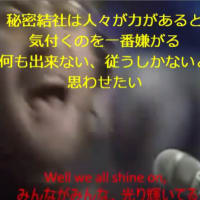
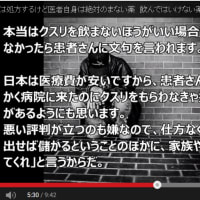

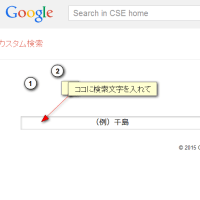
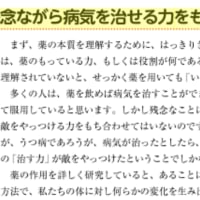







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます