<title>本日の会議に付した案件</title><style type="text/css" media="screen"></style>
○上村説明員 いまお話しのように、年々ガン死亡率というのは高くなっておりますが、それはその研究が実態に合わないからといいますよりも、むしろ先ほどお話しになりましたように、早期診断によってガンとして診断されることが確実になってまいったということが考えられますというのが一つと、もう一つは、寿命が延びてまいりまして、ガンにかかる年齢の階層というものがふえてまいったことも一つの原因じゃなかろうかというふうに考えます。
○齋藤(憲)委員 実は、私、きょう対ガン問題に関してここで質問をしたい、こういう考え方を持ちましたのは、この間新聞に、富国生命が小児ガンに対して毎年一億円ずつ十年間寄付をするという記事が出たのです。これを読みますと、ガンによって小さな子供が毎年生命を奪われる数というものは千五百人にのぼっておるという。
これが小さな子供としての生命を奪われる病気においては最高の率を示しておるのだという記事であります。それを読みますと、ただいま御説明がありましたように、
寿命が延びたからガンの率が高くなったということには、これは当てはまらぬ。
小児ガンなんだ。
小児ガンがだんだん年々死亡率が高くなって、ついに子供の死亡率の最高を示す病気だということなんです。
いまのお話とはこれは合わないのですね。
ですから、私はもちろんそういう生命が延長されて、そこにガン患者もたくさん出るかもしれないし、あるいは早期発見によってガンの確率が高まるということもあるかもしらぬけれども、
小さな子供の死亡率がガンによって年々高められておるということからいうと、
結局、ガンというものは、幾ら金をつぎ込んで研究をやってみても
、はっきりしたガンに対する根本的な病理学的な結論というものは見出し得ないのだ
というふうに考えるのですが、どうですか。
がんセンターの塚本病院長、そういう点どういうふうにお考えになりますか。
○塚本説明員
私がこれから申し述べることが斎藤先生の御期待に沿うかどうか別問題でございますが、ただいまの、小児のガンがふえているというので、寿命が延長したということと話が別じゃないかというお考え、一応ごもっとものように思えるのでございますが、ガンの占める中では、先ほど申し上げましたように十四歳くらいまでを含めましても千四百とか千五百とかいう実数が出ております。したがいまして、全体からいうと、そのふえ方のプロポーションというものはそう大きくはないと思います。ただ、小児のガンがなぜふえてきているかという問題になりますと、非常にむずかしいいろいろな問題もございますし、この小児のガンと称するものの大部分が白血病であるということ、それからまた、そのほかには、先天的なかなりの異常によって生後にガン化したものがかなり含まれている。そういう二つのことを考えますと、ほかのガンでも近来非常にふえているものがあったり、この説明はまちまちでありますし、非常にむずかしい問題で、なかなか軽率に予断は許されませんけれども、ある学者は、小児のガンがふえてきているのは、かなり妊娠中に放射線を使うというような問題もふえてきておるであろうし、放射線との関係を否定することはできないという考えの人もありますが、実際の研究に基づいてそういうはっきりした数字がまだ出ておりません。
それからもう一つは、白血病の発生というものは食物、ことに栄養価の高い食べものと関係があるということを言う学者もございます。そういうことを見ますと、われわれが子供のときに食べていたものから見ますと、いまの子供ははるかにいい栄養をとっておりますし、たん白質もふえております。ネズミの実験で恐縮ですが、同じネズミに白血病をつくります実験で、いい食餌をとらせるとパーセンテージがふえてくるなどということから、そういうことを言っておる学者もありますが、これも私はその真偽のほどはよくわかりません。
大体そういうことが、小児のガンがふえているということに関して私の知っておることであります。
○齋藤(憲)委員
まあ世間では、ガンはタブーだ、あまりガンということを口にすると、それは人格を疑われるぞというまでガンというものは非常にむずかしい問題だと私は思います。ああすればガンがなおるとか、これがガンの原因だとかということは、今日の医学の進歩においても、その原因を追求してもなかなか追求し切れない大きなむずかしい問題だと思うのです。
〔委員長退席、内海(清)委員長代理着席〕
私、きょう特にこの委員会で、
本来ならば関係各大臣御出席のもとにこの問題をひとつ考えていただきたいと
思ったのでありますが、そういうふうにもまいりませんでしたが、
出席の厚生省及び科学技術庁に一つ問題を提起して御回答を得たいと思いますことは、
昭和三十七年の四月二十五日に科学技術振興対策特別委員会で、ガンの問題に対するディスカッションをやったわけであります。
それに出席をせられましたのは、なくなられました田崎勇三博士、それから東京医科歯科大学の太田邦夫博士、それからSICの牛山医学博士、東京慈恵会医科大学付属東京病院の荻原医学博士、こういう方が参考人になって、
そしてここで終日ガンのディスカッションをやったわけであります。
それは牛山博士のSICというものは鼻くそだ、こう田崎勇三博士が言ったということが週刊雑誌に出たわけです。
それをこの委員会で取り上げまして、いろいろ論議を重ねたのでありますが、そのときに私は、これを読みますと、もう六、七年前のこの記事でございますが、こういうことを言っている。
自分はこの委員会において、牛山博士のつくられたSICという注射薬がガンに効果があるとかないとかということを取り上げて問題にするのではない。
牛山博士と田崎勇三博士のSICに対する考え方の食い違いをただすのだ。
というのは、
この牛山博士がSICの製造方法に対しまして、
ガン患者の静脈血を無菌的に取って、その血漿を分離してこれを無菌五プロのポリタミンの中に培養していくんだ。
そうすると、そこに点の細菌があらわれる。
それが十日ほどたつと球菌に成長していく。
さらに温度を適正にし、数日これを培養していくと桿菌になる。
その桿菌をタンク培養して、その代謝産物を精製して、そうしてこれを注射薬にする。
SICというものはこういうものなんです。
ところが田崎博士は、そんなばかなことはない。カエルの子はカエルで、ヘビの子はヘビだ。
点菌が球菌になって、球菌が桿菌になって、そうして、代謝産物を注射薬にするというとガンにきくなんということはもってもないことであるということなんですね。
私がこの委員会のときに執拗に当局に要求をいたしましたのは、
どっちが正しいか実験をするということが必要じゃないか。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
最後のこの要求に対して厚生省当局はどう反応したか。
文字制限があるのでつづく。
追記。
癌検診で早期発見早期治療は既に
役に立っていなかった 。つまり、癌死亡率に役立たなかったということは以前の記事で岡田医学博士の本で紹介したかも知れません。
何十年もたってから、この時代に医学がさかんに勧め始めた早期発見早期治療が破綻したという事です。
しかし、未だにそれをやめない、やっている・・・ということは・・・
ここでの公開実験に対する態度と同じなんです。
呪縛。












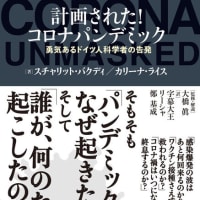
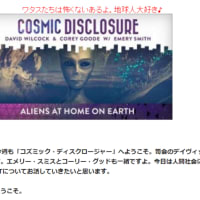
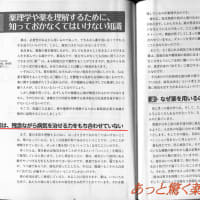
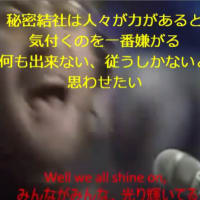
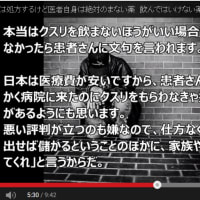

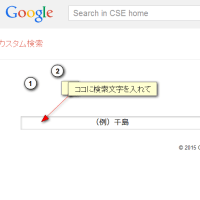
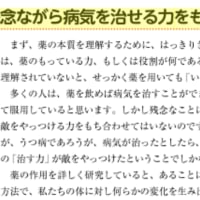







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます