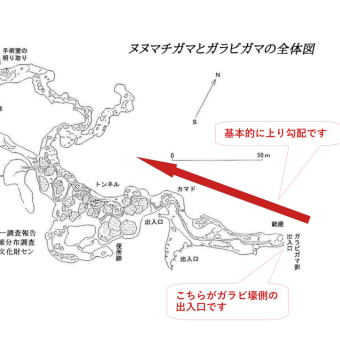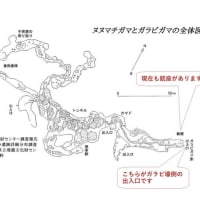海上挺身第三戦隊
渡嘉敷島集団自決の実像解明において、現地住民の行動は無論のこと、現地に駐屯した軍の存在も、絶対に無視できないものだということに異論がないと思います。
ではそもそも、渡嘉敷島に配備された海上挺身第三戦隊と海上挺身基地第三大隊とは何なのかということを、ここではできるだけわかりやすく説明したいと思います。
海上挺身戦隊についてですが、トラック用エンジンを流用したベニヤ製の、現代でいうところのモーターボートのような高速艇が主な兵器です。正式名称は「四式肉薄攻撃艇」といい、別名㋹(マルレ)とも呼ばれていました。基本的には一人用ですが、指揮官用では二人乗りとなり、後部には250㎏の爆雷(爆弾)が一個装備されていました。
具体的な攻撃方法は敵の艦船へと突進していき、衝突する直前になって反転Uターンします。そのUターンで生じた遠心力によって爆雷を投下して、そのまま退避するというものです。ちなみに爆雷は5秒後に爆発するといった時限式でした。
海軍にもマルレと同じような「震洋」という名称の高速艇がありました。しかし海軍の震洋は特攻といった、体当たり自爆を前提としているのに対し、マルレは体当たり自爆をしない運用方法となっていました。「四式肉薄攻撃艇」の「肉薄」というのは、必ずしも自爆を前提としないという意味にもなっています。
しかしながら、敵の艦船にギリギリまで接近することと、爆雷が5秒後に爆発することといった攻撃の性質上、限りなく体当たりに等しいものとなります。実際の部隊、海上挺身第三戦隊も例にもれず、訓練としては体当たり自爆を想定していたようです。
次に基本的な戦隊の編成ですが、戦隊長以下104名となり、マルレは100隻保有していました。
戦隊内の具体的な内訳は、戦隊長以下11名の戦隊本部、中隊長以下31名の3個中隊となり、その中隊も中隊長以下4名の中隊本部と各9名からなる3個群となっています。実際の作戦行動になった場合、マルレ9隻が最小グループということになります。
海上挺身戦隊の特徴として、現地の最高司令官が直轄して運用することになっていることがあげられます。
これを渡嘉敷島の海上挺身第三戦隊に当てはめると、現地の最高司令官は沖縄本島に布陣する第三十二軍の牛島満中将ですから、その牛島中将が命令しない限り、出撃することは許されませんでした。
もう一つの特徴として、徹底的な秘匿がなされたということです。
これは渡嘉敷島に限らず、慶良間諸島全体に配備された全ての海上挺身戦隊に当てはまるのですが、攻撃の性質上、できるだけギリギリまで隠しておかないと、任務完遂の見込みがなくなるということになるからです。
なぜそうなるかといえば、慶良間諸島に配備された海上挺身戦隊は、将来沖縄本島へ上陸してくるであろう、米軍の艦船群を攻撃することが主目的であるからです。
慶良間諸島に海上挺身戦隊が配備される前から、すでに沖縄本島の第三十二軍は、米軍がどこに上陸してくるかを予想していました。場所の選定は複数あり、そのうちの一つが的中しています。つまり、実際に上陸作戦が行われた読谷村の渡久地海岸と北谷海岸一帯です。
渡久地海岸と北谷海岸の海域に米軍の艦船が集結した場合、慶良間諸島の位置は米軍艦船群の背後ということになります。米軍の攻撃対象が本島の陸地でありますから、目の届きにくい背中を攻撃するといったようなものですので、そういった意味では比較的防備が薄くなります。その隙を狙って突進していくということでした。
ただし、マルレ自体の設置された武器は爆雷のみですから、防御するという観点からすれば非常に貧弱です。仮にたった一隻で攻撃したとしても、あるいは少数のマルレを逐次投入していった場合でも、失敗することは誰から見ても明らかなのです。
従って、作戦行動が見えにくい夜間のうちに、慶良間諸島全体のマルレが一斉に出発し、一斉に攻撃を仕掛けるというのが当初の計画でした。そういったわけですから、慶良間諸島にマルレの基地があること自体を隠しておきたかったのです。
米軍は沖縄本島から先に上陸して、慶良間諸島のような島嶼部は二次的に後から攻撃される、というような第三十二軍の予想に反して、慶良間諸島のほうが先に攻撃、上陸してきたという事実になりましたから、海上挺身戦隊は全ての部隊が作戦を遂行することができませんでした。
こういった事実が集団自決になってしまった遠因でもありますが、ここでは割愛します。
海上挺身基地第三大隊については次回以降に続きます。
参考文献
特攻隊慰霊顕彰会編『特別攻撃隊』(特攻隊慰霊顕彰会 1990年)
八原博通『沖縄決戦』(読売新聞社 1972年)
防衛庁防衛研究所戦史室『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』(朝雲新聞社 1968年)