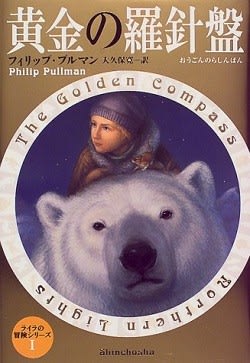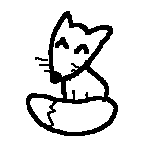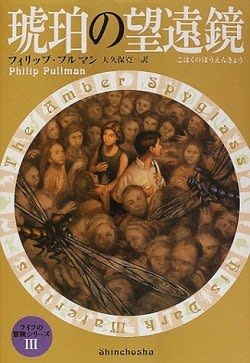「ハリー・ポッターと賢者の石」と「黄金の羅針盤」どっちが面白い?
今や押しも押されぬベストセラー「ハリー・ポッターシリーズ」。邦訳では「賢者の石」「秘密の部屋」の二作が書店店頭に平積みされている。英語圏ではすでに四作まで出版され、いずれもベストセラーとなっているらしい。構想では七作のシリーズとなるとか。後ほど紙数も増え、長編シリーズの面目躍如というところだろうか。著者のJ・K・ローリングスは本の著者紹介によれば「シングルマザーで、幼い子供を抱え、生活保護を受けながら」この物語を書き上げたとのことである。
正直に言えば、この本を書店で見たとき、買ってみようと言う気にならなかった。まず、装丁が今ひとつである。そして何より、本文中、強調のため活字がボールドになっていたり、級数が大きくされている。原典に忠実とはいえ、学習参考書でもあるまいに。きっとさほどのことはないと、読まず嫌いになったのだけど、借りて読むなら損はないかと、姉の購入するのをまっていた。読んでみたら面白い。挿絵も少なく、そこそこ長い物語を子ども達が嬉々として読んでいるという話に感心もし納得もする。(が、日本でもそうかわからない)
主人公は魔法使いである。と同時に普通の小学生(十一才)で、勉強は好きではない。生い立ちを知らぬまま、普通の人間として意地悪な伯父伯母のもと、さんざんな扱いを受けながらもけなげに育ってきた。ある日、突然魔術学校の入校案内が届く。それは、伯父伯母の妨害に会いながらも、尋常ならぬ方法で届けられる。そして、自分が、魔法使いなら誰一人知らぬ者の無いヒーローであることを知り、ホグワーツ魔法学校での生活が始まる。
何より面白かったのは、推理仕立てになっているところだろうか。ただの子供向けの童話ではなく、きちんと構成された筋立てと、意外な仕掛けが次へ次へと読み進めさせる。学校での人間関係、いじめやライバル、そして友情。それをただ教訓的に、あるいは面白おかしく書くのではなく、小説の様に仕立てている。子どもに媚びていないところが良いのかもしれない。さらに、あらかじめシリーズ化をも意識してか、次の物語への布石も随所に散りばめてある。
心ならずもヒーローとなるポッター少年。その仇敵の存在。なぜ彼は赤ん坊の時、最大の敵を滅ぼし、生き延びたのか。これはシリーズを通しての謎として封印され、その仇敵との最後の決着のときに明かされることになるのだろうか。一作を読み終えると、次にと、読者に飢えをあたえのどの渇きを覚えさせる、作者の非凡なる所を感じさせるものがある。
一方、「黄金の羅針盤」「神秘の短剣」と二作品が訳されているライラシリーズは子供向けとはいえない。ファンタジーだが、夢は無い。(ファンタジーだから何らかの「夢」を持っていなければいけないということは無い)著者のフィリップ・ブルマンは大学では英文学を教えるかたわら小説、芝居の脚本、絵本などを発表。ビクトリア時代を背景とした小説を書いている。この作品は発表されるや話題となり、多くの賞を受けたとある。だが、今世紀最後の大ファンタジーと書けば大げさな気がする。腰巻にいわく「『指輪物語』『ナルニア国物語』『はてしない物語』に熱中したすべての人に―」とあるが、それらとは明らかに毛色が違う。面白いが「大」とつくほどの哲学がなさそうな気がするのだ。
シリーズ三作目を読んでみないと断定は難しいところがある。大人と子ども、無辜なるものの持つエネルギーは、人類を救う力を秘めている、とか、解き明かされたとき見えてくる主張があるのかも知れない。シリーズというより、完結する一話の上、中、下巻といったほうが良いように、そ れぞれはクライマックスを迎えて終わっている。面白くないわけではない。が、子どもに読み聞かせるかといえば、他に読む本が多くあるし、奨めるべき本が数多あるだろう。
大人が面白い読み物を求めるとき、この物語には今までに無い新鮮味があり、筋立ての妙がある。熊人間(ただの喋る白熊?)が出てくるし、魔女も、魔法もある。ファンタジーなのだが、その枠を越えているようでもある。
こうした物語に通底する要素として、主人公が特別な印を持っているか、特別なものの所持者として選ばれた者であるということが挙げられると思うが、ポッターには印が、ライラには所持者としての特殊な能力が与えられており、伝統に適っている。しかし、両者とも今までの類型のファンタジーとは一線を画しているように思える。(ファンタジーという概念自体が難しく、非現実的な要素を含むものの総体をそう呼ぶとしての話である。)
ポッターのシリーズは、開明された現代では衰退の一途を辿る「魔法世界」を、現代のロンドン、イギリスにみごとに再構成して描き出している。魔法を信じないマグル、それこそが笑われてしかるべき。マグル代表のダーズリー氏の滑稽さは、空想の世界に時間を取られることを惜しみ、現実に汲々とする現代人のそれということか。魔法があるということは、学校の授業がつまらないということと同じぐらい確かなものだと読者に思わせる、作者の力量がある。童話にありがちな「この物語では魔法があたりまえということにしてありますからそのようにお願いします」という注書きが必要とされない。もともと子ども向きなのだから、どんな不思議なこともご承知置きくださいといった、作者の手抜きが無い。子ども向きということを、格を下げることと解釈して手抜きをした本は、子どもからも見下される。子どもなりに辻褄や合理性を気にかけ、説明を求めながら物語を聞き、読んでいるもののようだ。
ライラシリーズは、SF小説のようでもある。平行世界に住む少年と少女の出会い。その重なる世界を支配する現象を解き明かすための冒険。異世界の交点となる世界の存在は、ナルニア国物語の「魔術師のおい」を連想させる部分もあるが、切り離されることができないダイモン、エーテルを思わせるダストなどファンタジーの面目躍如たる道具立てに溢れていながら「希望」がない。道が険しく、どれほど過程が苦しくとも、探求の最後に「安住」を期待させるものが多い中で、この物語にはそれがない。主人公は、二人とも不幸な家庭を背負い、追い立てられるように、使命としての旅に出る。その旅はオズの魔法使いのようなものではなくて、ストリートチルドレンを想起させるような過酷さがある。読んでいるうちは面白く、部分部分は感心し良くできているが、全体としては心に残らない。三作目がすべてを決めるのだろうが、今のところの評価は微妙なところがある。それを狙って書いているだろう作者の試みがいままでにない感じをあたえるのだろうか。
誉めているのだかけなしているのだかわからない。感想文だか書評だかもわからない、という体たらくは御免被るとして、どっちが面白いだろうか。どっちも面白いと行って逃げるのも一考だが、どっちもつまらないということはない。双方、趣を異にしているから、読み手が変われば判断も異なる。子どもを基準にすれば、ライラシリーズは読みがたいだろう。しかし、了解ごとのうえに虚構を楽しむならライラシリーズの方に分がある。
どちらが面白いと問いかけながら、答えはあなたが出してくださいと言って終わっては無責任のきわみ。あえて、私にはどちらが面白いかと問われれば、ライラシリーズが面白い。(装丁と強調文字がハンディにもなっているけれど)どちらを先に読むべきかと聞かれれば、ハリー・ポッターだねと答えるだろう。その辺りのニュアンスは読んでもらえばわかっていただけると思う。

「ハリー・ポッターと賢者の石」、J・K・ローリング著、松岡祐子訳、静山社、1999年

「ハリー・ポッターと秘密の部屋」、J・K・ローリング著、松岡祐子訳、静山社、2000年
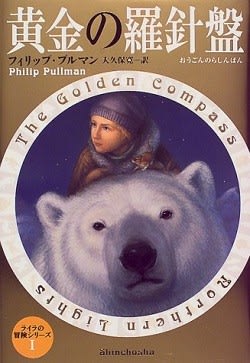
「黄金の羅針盤」フィリップ・ブルマン著、大久保寛訳、新潮社、1999年

「神秘の短剣」フィリップ・ブルマン著、大久保寛訳、新潮社、2000年発行
*これはライラ・シリーズの3「琥珀の望遠鏡」が出る前に書いたもの
シリーズとしての完成度はポッターシリーズの方が高いことを付記します
 狐が泣かせる
狐が泣かせる

 狐が泣かせる
狐が泣かせる










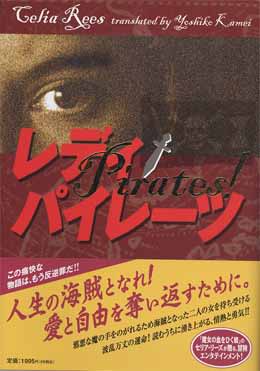

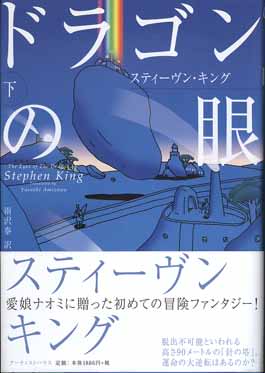


 そこそこ面白いのだが、次の本の方が面白かったので・・相対的に一歩下がる
そこそこ面白いのだが、次の本の方が面白かったので・・相対的に一歩下がる