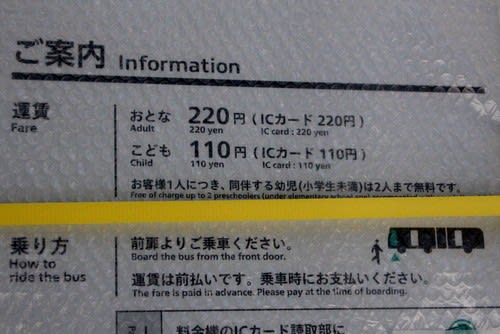2023年1月31日。羽田空港第3ターミナルに直結する「羽田エアポートガーデン」がグランドオープンしました。
同時に併設されているバスターミナルも開業し、バスの発着がスタート。外観などは
以前の記事で紹介したので、今回は内部と発着するバスの様子を紹介します。

「羽田エアポートガーデン」のメインフロアは2階。
この階で第3ターミナルと直結しています。バスターミナルは1階に位置するため、バス利用者はフロアを一つ降りる必要があります。

1階にもいくつもの店舗がありますが、まずはバスターミナル「A」の紹介から。
フロア図です。10の乗降場を持ち、1~7番が屋内、8~10番が屋外になります。

バスターミナル屋内部です。
7つののりばがあり、奥行きが長いのが特徴。

インフォメーションカウンター。

自動券売機。
青色が京浜急行バス、オレンジ色がリムジンバスのもの。
今回の開業時点では、どちらも「羽田エアポートガーデン」バスターミナルには乗り入れていません。そのためか、共に券売機の電源は落とされていました。

発券窓口。
こちらも準備中のようです。開業時点では発券窓口の機能はありません。
頭上には、方面別で分けられた5連の出発案内表示器が並びます。左から「中四国方面」「東海・関西方面」「関東方面」「甲信越・北陸方面」「東北方面」の順です。

「関東方面」の出発案内表示。
まだ乗り入れ路線が少ないので、空欄が目立ちます。

各のりばの様子。
頭上と壁面に出発案内表示器を設置。

吊り下げタイプの案内表示器。

壁面タイプは、空席情報も表示されます。

テーブル付きのソファー。
残念ながら、充電設備はないようですが、座り心地はGood。

中央から1番のりば方向を見渡しました。

さて、バスターミナル最初の出発便は、ジャムジャムエクスプレスが運行する「シュプールライナー」白馬・栂池行きです。

6番のりばで発車を待つ「シュプールライナー」。

「シュプールライナー」は、三菱ふそう、ローザでの運行でした。

そして、のりばを発車。
「羽田エアポートガーデン」バスターミナルの歴史が始まりました。

「羽田エアポートガーデン」には、2つのバスターミナルが存在します。
これまで紹介したターミナル「A」の他、建物反対側には団体向け「B」があります。

ターミナル「B」の乗降場は、11~15番の5つ。

乗降場は屋外ですが、しっかりと屋根があり、雨天時でも濡れる心配はありません。

再び、ターミナル「A」に戻りました。
9時20分発は、はとバスが運行する東京駅丸の内南口行き。
ただし、この便は「はとバスコース利用者専用」です。航空機利用者や「羽田エアポートガーデン」のホテルに宿泊した利用者等を想定した送迎用途のようです。

6番のりばで発車を待つ、はとバス。
「東京名所散歩」と表示があることから、東京駅到着後は、そのまま定期観光バスとなる模様です。
発車時刻が近づくと自動放送が流れました。
「最終のご案内です。6番のりばから、はとバス東京駅八重洲南口行きが・・・」的なニュアンスの案内がターミナル内に響きました。

「羽田エアポートガーデン」の1階フロアと2階フロアは吹き抜けになっています。

ここには、イベントホールもあります。

フロアには、美味しそうな店舗がたくさん並んでいました。

11時を過ぎ、静岡から、しずてつジャストラインの「静岡羽田空港線」が到着。
この路線は、しずてつジャストラインとWILLER EXPRESSの共同運行ですが、しずてつ便が先に運行を開始しました。

「羽田エアポートガーデン」の行先表示。
新静岡では静岡放送SBSが取材に入ったようで、「静岡羽田空港線」の運行開始がニュース番組で報道されました。

静岡市と羽田空港を結ぶ高速バスとして期待が高まります。

最後に、バスターミナル「A」では、コンビニ形式の売店が営業をしています。
取り扱い品目は、お土産、食料品、文房具など、多岐にわたりました。

店内には「COSTA」のコーヒーメーカーが設置され、本格的なコーヒーを楽しむ事が出来ます。バス車内に持ち込んでもいいかもしれません。

今はまだ、バスの発着が少ないのが実状ですが、日本が観光国として発展するにあたり、国際空港と各地とを結ぶ「かけ橋」の整備は必須で、このバスターミナルはその役割を担うこととなります。いつの日か、ここがバスや観光客で賑わう日が来ることを切に願います。
<撮影2023年1月>