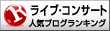2020年12月20日(自動車)
二十三番札所
平寺観音
御本尊:馬頭観世音菩薩
別当寺:曹洞宗 鳳凰山 光臺寺
御詠歌:名も知るる 行くはたいらの 道すがら いさめる駒の 足なみの音


地蔵堂

とても立派な山門

ご法事が行われているようです。

供養塔もお堂の中にあります


手水舎

御本堂
永禄4年(1561)創建。光台寺は豪農の佐藤輿惣左衛門が造った
前身は伏黒平寺。
江戸中期には本堂、開山堂、経蔵など建てられたが明治三十一年(1898)大火で殆どを消失
こうしてお参りしていると、火事で燃えてしまったお寺や観音堂がいかに多いかがわかります
木造だし、お線香やお焚き上げなど火を用いての供養が多いからでしょうか
お線香から立ち上がる煙があの世とこの世をつなぐ橋渡しになるとのことです
また、「倶舎論」(くしゃろん)経典には「死後の人間が食べるは匂いだけで、善行を行った死者は良い香りを食べる」とあることから、白檀などの香木を材料にしているんだと思います
まあ庶民の家の火災も多かったでしょうから特別寺院が多く燃えたのではなく民家からの類焼もあったでしょう
昔は宗派の利権争いで僧兵もいたし、政治とも絡み合って焼き討ちされたことが多かったのかもですね
信長の時代など延暦寺や本能寺なんかはまさしくそれですね
現在の立派な本堂は大正12年(1923)やはり豪農の富田家の篤い(あつい)支援により再建されました
格子天井の花絵、外陣欄間の彫刻など豪華な造りで、保管されている「絹本著色仏涅槃図」(伊達市指定文化財)も富田家の寄進によるものです
涅槃図と言うのはお釈迦様が入滅(亡くなられた)の時の情景を描いた図で絹地に描かれているものだそうです

馬頭観音は、よく峠、それも旧道などの厳しい坂道のところでよく見かけます
馬返し、とも言われるほどきつい坂道登りを重い荷物を背負った馬が登れずに死んでしまうことがあって
そこへ馬を埋めて、馬頭観音像を建てて供養したのかもしれませんね
間違えてるかもですが、自分的には旅の観音様として身近に感じています

これは福井の中山寺のものですが、忿怒の相が凄いですね。
怒れば怒る程人々を救う力が大きいそうです。馬は大食いであるので、人々の煩悩や苦悩も食べつくしてしまうとも言われます。
旅の道具としての馬、ですが、農耕馬も多くいたので馬のお墓としてあちこちに石仏が建てられているのだと思います。斧や刀、などを持って怒ってる姿は、かっこいいですね、などと言っては罰が当たりますかね