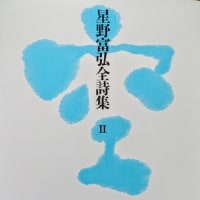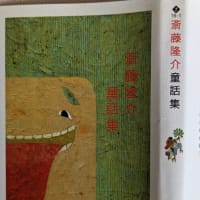高濱虚子(たかはま・きょし)の一句
高濱虚子の俳句に
金亀子擲つ闇の深さかな(こがねむし なげうつやみの ふかさかな)
というのがある。好きな俳句のひとつである。
握った掌からそっと放られたコガネムシ。外は闇。放られた瞬間、ちいさな虫のちいさな甲がかすかに輝(て)った。目に映ったその輝きの先に、思いのほかの闇の深さがあった。
「擲(なげう)つ」という言葉は強い。野球の球を投げるほどの強さである。スピードもある。コガネムシは、彗星(すいせい)のごとく夜の深さに沈んでいったか。
外の暗さは、その照りによっていっそう増した。刹那(せつな)の光。そのあとにしんとした闇。奥深い闇。
この句から私は、「闇は、闇だけで深さを増すだろうか」と考えた。闇は、コガネムシという一点の光を受けとめた。そして呑みこもうとした。その一瞬、初めて奥行きを露わにしたのではないか、と。
闇に闇を塗りこめたような真っ暗闇、それを見たことがある。
手に触れたらべっとりと染まってしまうような、そんな濃さ。闇という生き物に全身を包囲された感じ。それも血の気の無い冷たい生き物に。恐怖さえ感じた闇。それはほんとうに濃いものだった。
だが、濃さと深さとはちょっと違う。
闇の濃さには奥行きがなかったような気がする。もしもわずかな光があったら、闇に深さが生まれ、奥行きが現れたのではないか。変な言い方だが、静かななかにも何となく温もりのある闇であったのではないか。
虚子の俳句を読み、まぶたに残るのは闇だけではない。
小さなちいさなあの黄金虫(こがねむし)。恐怖に脚をばたつかせたか、あるいは縮まってしまったか、それは分からないが、重さをもち命の温もりをもった、かそけき光、それも同時に映るのだ。
●ご訪問ありがとうございます。
この句を初めて知ったときから、暗闇を見ると思い出すようになりました。そして、光と闇、闇と光について、密な関係のあることに関心を深めてきました。
一つの俳句のもつ力の大きさを感じます。