uTerm-S を 作るにあたって、まずは
主要な部品の入手を試みます。 もっとも無くてはならない部品は「頭脳」とも云える CPUで、STM32シリーズの STM32F030 という型番の部品です。 もし、これが手に入らなければ この基板と買った意味がなくなります。 代替えがきかないからです。
最近は便利な世の中になったもので、わざわざ東京の秋葉原に行かなくても、ネット販売で これら特殊な部品すらも手に入れることができます。 良く使う「電子部品」通販サイトとしては、
① 秋月電子通商 ・・・安くて良いが、無い部品も多い
② RSコンポーネンツ ・・・少し高いが、すぐに来る
③ 千石通商 (せんごくネット通販)
④ Digi-Key (デジ キー) ・・・ プロ向け(大抵の部品が揃う)
⑤ Mouser(マウザー)
⑥ marutsu (マルツオンライン)
⑦ KYOHRITSU(共立エレショップ)
⑧ チップワンストップ
⑨ aitendo(アイテンド)
⑩ スイッチ サイエンス
⑪ MiSUMi (ミスミ)
⑫ KURA Yahoo!
こんな所でしょうか? 有名どころだけでも こんなにあります。
そして、ちょっと毛色が違いますが
・ASKUL(アスクル) や
・カウネット
・モノタロウ
といった所でもちょっとした電子機器が手に入りますし
(これらサイトは 注文すると すぐに送られてくる)
そして、意外ですが 侮れないのが
● ヤフオク だったり、
● Amazon だったりします。
アマゾンの通販で普通に 電子部品の型番を検索すると、かなりの確率でヒットし、購入できます。
さらに、最近の流行りの中国の通販サイト
● TEMU電子部品通販 (テムー)
でも電子部品がとんでもなく安く売られていて(安かろう、悪かろう)の傾向があって、かなり賭けに近いのですが 安価に買うことができます。
各サイトで 値段を見比べながら、
まずは STM32のCPUと、74HCT00 という標準ロジックICを
(1) アールエス・コンポーネンツ から購入してみます。↓
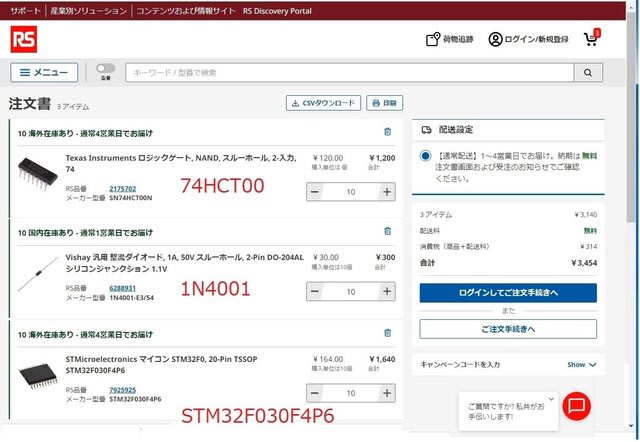
このSTM32が入手できそうなので、ほっと胸を撫で下ろす思いです。
ただし・・・ 購入最小単位が 10個・・・ よって1つしか使わなくても10個まとめて買わないといけない。 誰か共同購入してくれる人いないかな?

(2)次に、マルツ・オンラインで、VGAコネクタを見つけたので
これも先行購入しておきます。
これだって、もし入手でき無いと大変な事になります。

その他、秋月電子で扱っていない部品も何点かいっしょに購入。
(3)そして、真っ先に部品実装しなければならない「電源周り」の部品
から揃えていきます。
そのために今回 初めて利用してみたのが アマゾン です。
三端子レギュレータという分類の部品の型番を アマゾンで検索したら、簡単にヒットしました。↓
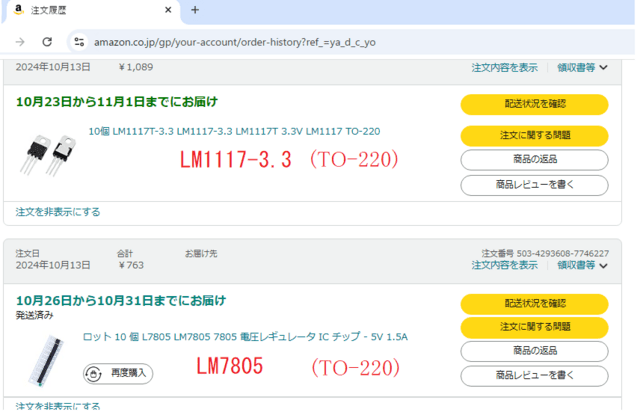
パッケージのサイズ (ここでは TO-220)を間違えないように、これも先行手配します。 これらが届いてから 後、 足りない部品を 秋月 で揃えようと思っています。
ここまで使った部品代=8900円/10台分
今回はここまで。
。












 サンプル・プログラムの入ったCDも付いて1000円。
サンプル・プログラムの入ったCDも付いて1000円。



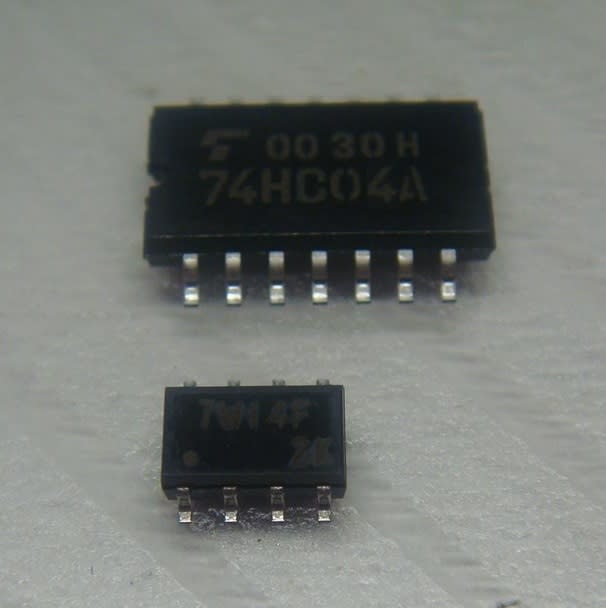
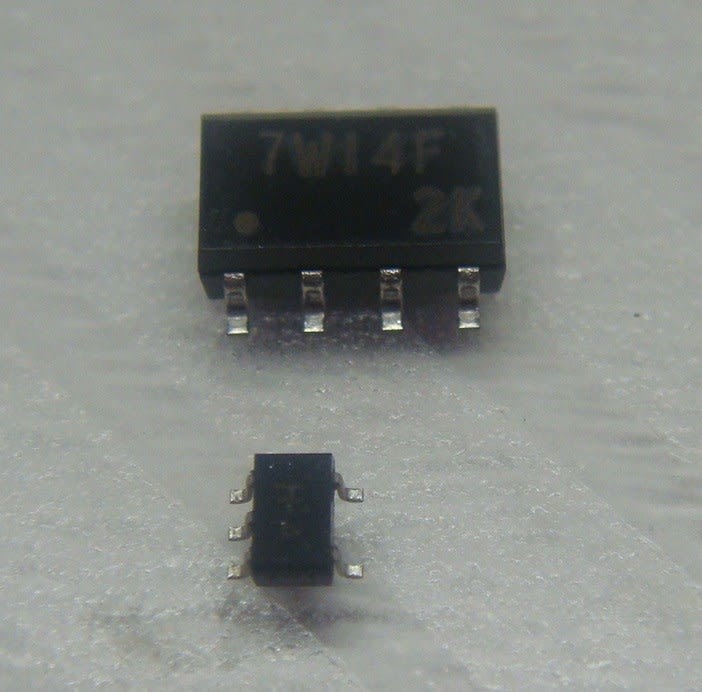
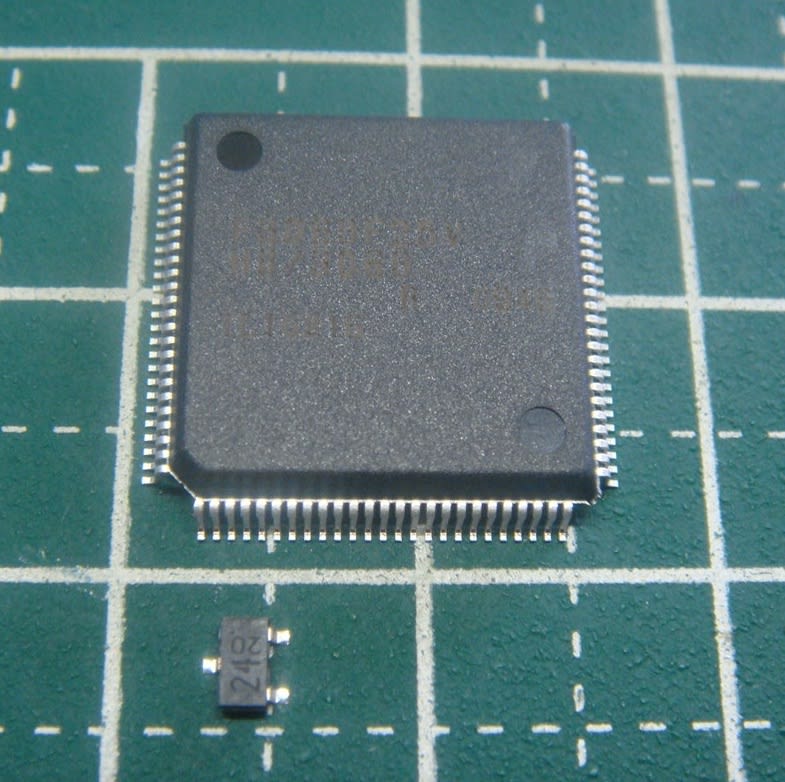
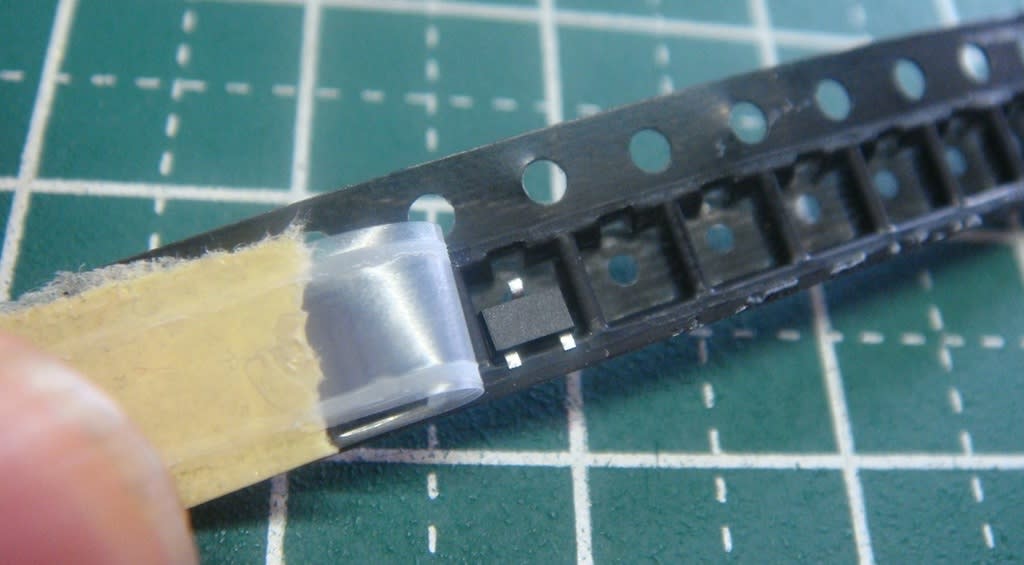



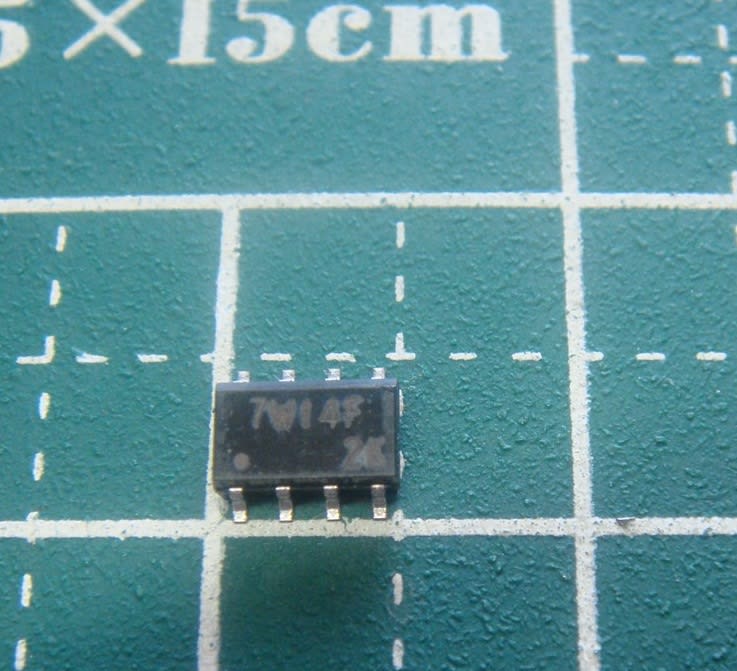
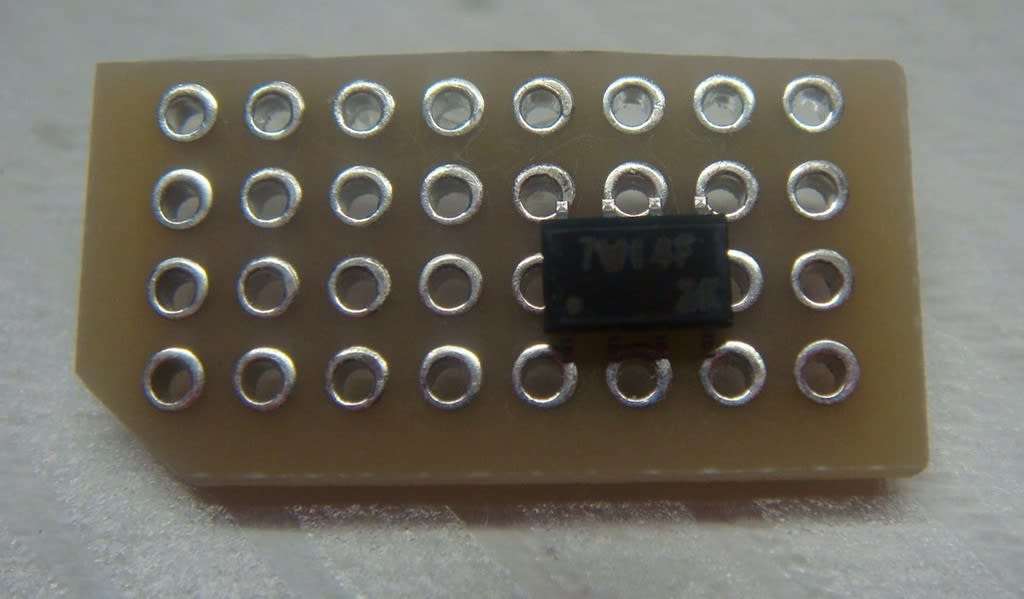




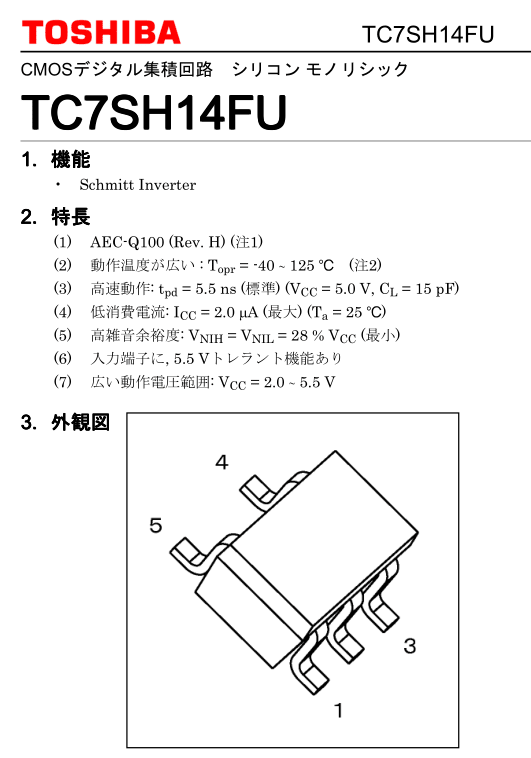
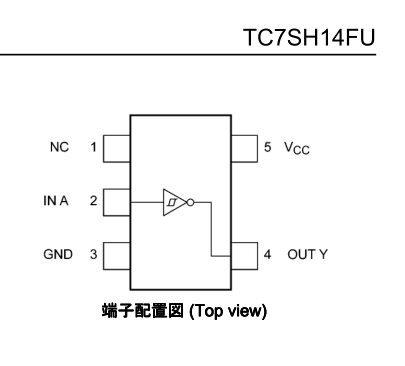
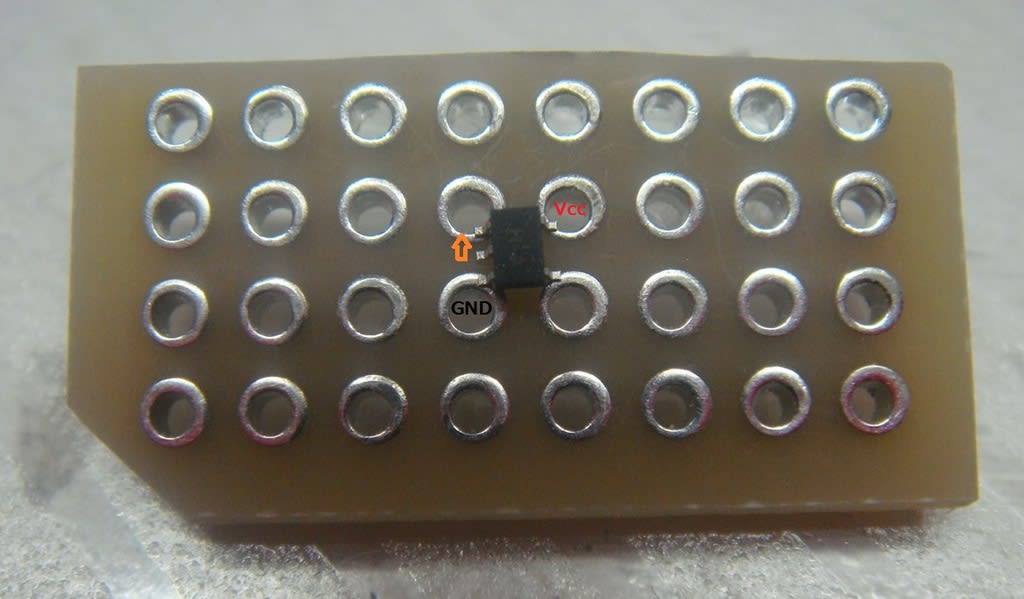
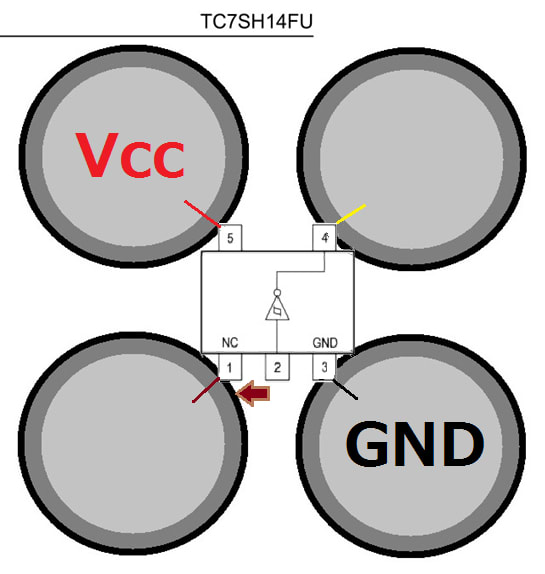
 (大きさ比較)
(大きさ比較)