学生生活
「関西学院での学生生活の4年間は、私にとっては病気療養の続きの時代で、すきな剣道がやれなかったのは今考えても残念だと思っている。当時関西学院はすぐ隣に、神戸高商(今の神戸大学)というスポーツにおけるラィバルを持っていた。当時の神戸高商は歴史も古く、スポーツでも日本有数の名門校だった。
専門部が出来てから、関西学院のスポーツは専門学校としても急速に力を加え、私の入学した頃はすでに日本的な存在となっていて、神戸高商のスポーツと対立していた。それが全学生の愛校心を沸き立たせ、学生を団結させた。これはスポーツだけではなく、関西学院の学生生活全般の刺激となった。
そして関西学院の学生は、独自の関西学院精神を持っていなければならないと常に強調された。私の興味も関西学院の精神である人間形成の問題に主として集中されるようになった。関西学院では専門部も毎日礼拝の時間があり、20分ぐらいの話をきくことは私にいろいろな意味で刺激となった。英文学者であった佐藤清先生は、「およそ人間として尊いのは、真理を愛する学者、善を行なう善人、美を追求する芸術家、この三種類の人間である。これ以外の人間は人間というには余りに遠い」と力強く語られた。後に神戸一中の校長となられた池田多助先生は、スポーツ・勉学・宗教にわたって学生生活の理想をさし示されたし、河上丈太郎先生はまだ若く、雄弁をもって学生に感化を与えられた。
人生において最も尊いものは何か、という問題は常に我々に投げかけられた課題だった。そういう日々の刺激があって、私の関西学院4年の学生生活は、人生の問題を深く考えることに中心をおいた生活となり、本も主としてそのようなものを読んだ。
倉田百三氏の『出家とその弟子』や、『愛と認識の出発』が出たのはその頃で、当時のベストセラーだった。下宿の部屋で、強い感激をもってこれらの本を読みふけったことを思い出す。倉田氏の本から西田幾多郎氏の『善の研究』に導かれた。
「下宿の部屋に、私はミレーの「晩鐘」の複製の額をかけていた。これは当時私のすきな絵で、長年私の生活の友となった。その絵のムードが私はすきだった。この絵に表現されているものは神と愛と勤労だった。忠実な勤労、男女の協力と愛、そして神に対する敬虔な祈り、その絵の描き出しているものが私の深いあこがれとなっていた。
賀川豊彦氏の『死線を越えて』や西田天香氏の『餓悔の生活』が出て、ずいぶん売れたのもその頃だった。武者小路実篤氏の文学に親しみ、『新しい村』の運動に興味を持ったのも、トルストイにひかれ、聖フランシスの伝記などを愛読したのもこの時代である。
漱石のもので一番すきだったのは『こころ』だった。主人公である「先生」を自殺からのがれさせる道はどこに開かれているのだろうか、という問題を解くことは私にとって大きな課題だった。 」
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より
「関西学院での学生生活の4年間は、私にとっては病気療養の続きの時代で、すきな剣道がやれなかったのは今考えても残念だと思っている。当時関西学院はすぐ隣に、神戸高商(今の神戸大学)というスポーツにおけるラィバルを持っていた。当時の神戸高商は歴史も古く、スポーツでも日本有数の名門校だった。
専門部が出来てから、関西学院のスポーツは専門学校としても急速に力を加え、私の入学した頃はすでに日本的な存在となっていて、神戸高商のスポーツと対立していた。それが全学生の愛校心を沸き立たせ、学生を団結させた。これはスポーツだけではなく、関西学院の学生生活全般の刺激となった。
そして関西学院の学生は、独自の関西学院精神を持っていなければならないと常に強調された。私の興味も関西学院の精神である人間形成の問題に主として集中されるようになった。関西学院では専門部も毎日礼拝の時間があり、20分ぐらいの話をきくことは私にいろいろな意味で刺激となった。英文学者であった佐藤清先生は、「およそ人間として尊いのは、真理を愛する学者、善を行なう善人、美を追求する芸術家、この三種類の人間である。これ以外の人間は人間というには余りに遠い」と力強く語られた。後に神戸一中の校長となられた池田多助先生は、スポーツ・勉学・宗教にわたって学生生活の理想をさし示されたし、河上丈太郎先生はまだ若く、雄弁をもって学生に感化を与えられた。
人生において最も尊いものは何か、という問題は常に我々に投げかけられた課題だった。そういう日々の刺激があって、私の関西学院4年の学生生活は、人生の問題を深く考えることに中心をおいた生活となり、本も主としてそのようなものを読んだ。
倉田百三氏の『出家とその弟子』や、『愛と認識の出発』が出たのはその頃で、当時のベストセラーだった。下宿の部屋で、強い感激をもってこれらの本を読みふけったことを思い出す。倉田氏の本から西田幾多郎氏の『善の研究』に導かれた。
「下宿の部屋に、私はミレーの「晩鐘」の複製の額をかけていた。これは当時私のすきな絵で、長年私の生活の友となった。その絵のムードが私はすきだった。この絵に表現されているものは神と愛と勤労だった。忠実な勤労、男女の協力と愛、そして神に対する敬虔な祈り、その絵の描き出しているものが私の深いあこがれとなっていた。
賀川豊彦氏の『死線を越えて』や西田天香氏の『餓悔の生活』が出て、ずいぶん売れたのもその頃だった。武者小路実篤氏の文学に親しみ、『新しい村』の運動に興味を持ったのも、トルストイにひかれ、聖フランシスの伝記などを愛読したのもこの時代である。
漱石のもので一番すきだったのは『こころ』だった。主人公である「先生」を自殺からのがれさせる道はどこに開かれているのだろうか、という問題を解くことは私にとって大きな課題だった。 」
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より










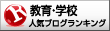










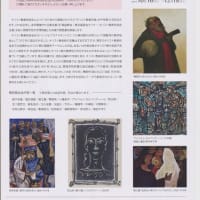






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます