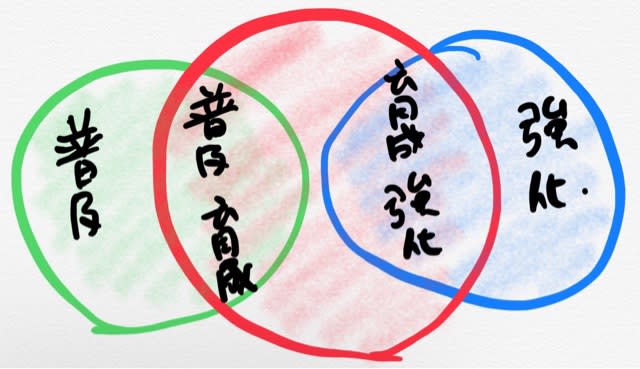週1回、学童クラブで児童厚生員をしています。
仕事内容は
下校した子ども達を保護者が迎えに来るまで安全に預かる事。
迎えに来る間は
おやつを食べたりトランプなどで遊んだり…
そして天気が良ければ公園へ遊びに出ます。

今日は、雨も降らなかったので公園で
子ども達とサッカーをして遊びました。
そうしたら地域の子ども達がやって来ました。
私がサッカーのコーチをしている事は
全然知らない子ども達も一緒にサッカーをプレー。
「おじさん。オレ達、サッカーチームに入っているから上手いぜ。」
と自信満々で言う子ども達。
一緒にプレーしながら
「そうなんだ。凄いねぇ〜」
「おぉ!すごくドリブルが上手い!」
と子ども達を褒めていました。
そうしているうちに
味方からセンターリングっぽいパスが
少しズレてゴール前へ入ってきたので
ボールに合わせて入ってちょこんとシュート…
「ゴール!」
とみんなで喜んでいる時に
サッカーチームに入っている子ども達から
「おじさん、走って良い位置に行ったね!上手い!」
って褒められました。
とても嬉しいかったです!
やっぱり褒められるって良いですね!
仕事内容は
下校した子ども達を保護者が迎えに来るまで安全に預かる事。
迎えに来る間は
おやつを食べたりトランプなどで遊んだり…
そして天気が良ければ公園へ遊びに出ます。

今日は、雨も降らなかったので公園で
子ども達とサッカーをして遊びました。
そうしたら地域の子ども達がやって来ました。
私がサッカーのコーチをしている事は
全然知らない子ども達も一緒にサッカーをプレー。
「おじさん。オレ達、サッカーチームに入っているから上手いぜ。」
と自信満々で言う子ども達。
一緒にプレーしながら
「そうなんだ。凄いねぇ〜」
「おぉ!すごくドリブルが上手い!」
と子ども達を褒めていました。
そうしているうちに
味方からセンターリングっぽいパスが
少しズレてゴール前へ入ってきたので
ボールに合わせて入ってちょこんとシュート…
「ゴール!」
とみんなで喜んでいる時に
サッカーチームに入っている子ども達から
「おじさん、走って良い位置に行ったね!上手い!」
って褒められました。
とても嬉しいかったです!
やっぱり褒められるって良いですね!