
毛鉤論というものがある。
いや、別に論理に名前がついてるわけぢゃないんですがね。
釣のスタイルから来るものだと思います。
毛鉤は絶対に浮かせるか、沈み込む波に揉みこまれて自然に沈むのは仕方が無いとする釣り方。
も一つは、
毛鉤といえども、餌に見立てて、水中深く沈めて流れの底から中くらいの深さを探る釣り方。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前者は毛鉤釣の面白さを水面を割って出てくる渓流魚を釣ることにあるとする主張であり
後者は何処にいる魚であれ、兎に角、釣ることに重きを置く考え方であります。
必然的に毛鉤には水面に浮く毛鉤と水面下に沈む毛鉤の2種類に分かれる。
こういう分類もあるわけですが、また別の切り口で分類されることもある。
それは、フライ・フィッシングとテンカラ釣の釣り方の違いからくる分類ですね。
おおまかに言えば、例外もありますが・・・
◎ フライ・フィッシングは西洋での一般的な釣り方で、大きな河川や湖を釣り場とする。
道糸は太くて長いため竿にはリールを付けて、糸巻きにしている。
釣り場の環境に応じて道糸をリールから繰り出して長くしたり、巻き取って短くもできる。
但し、毛鉤に動きを加えること(誘いとも言います)は殆ど不可能な釣り方である。
◎ テンカラ釣は日本古来の釣り方で、比較的川幅の狭い河川を対象にする。
延べ竿を軽くして、ラインも短く、普通はリールなどは付けないので
仕掛けの長さは固定長である。
最近この釣法の一番の特徴は毛鉤へのアクション(誘い)なのでは?と思うようになっている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こういう釣り方の違いから来る毛鉤の違いがあります。
これは大変大きな差であり、何故?と今まで思ってました。
● フライ・フィッシングに於ける毛鉤はリアル・フライとでも言いましょうか?
現実の水棲昆虫(川虫)にモロに似た毛鉤を目指します。
季節により、時合いにより、川虫の様態(さなぎ、幼虫、成虫)に合わせた毛ばりを作るのです。
初めてフライを見る方には
まぁ~こんなのまでいるのか?見たいな驚きがあるはずです。
● テンカラに使う毛鉤はといいますと・・・これはファンシー・フライと呼ばれるようですが
実に抽象的な形をした毛鉤でして、極端に言えば
針に糸を下巻きして、その上から鳥の羽をくるくるっと巻いて下糸と同じもので巻き止めただけ。
1個毛鉤を巻くのに5分も掛からないでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もし、テンカラもフライ・フィッシングも同じ様に釣れるのなら
なぜ、毛鉤としての違いがこれほど大きいのでしょうか?
普通の釣り人の場合、フライ・フィッシングならテンカラに比べて遥かに遠方まで
毛鉤を飛ばすことが出来ます。
理由は道糸の目方が大きいのと道糸の長さが長いからです。
遥かに遠いところまで毛鉤を飛ばしてポイントに入れるのですから、これは難しい。
しかもポイントへ投じられた毛鉤は水流に乗って自然に流れ下るのに任せるしかない。
数メートルに亘って毛鉤が流れる。
その間に渓流魚が毛鉤をくわえる。
合わせる。
この間、毛鉤は贋物と見破られてはならない!!
方やテンカラでは数メートル先の上流へ打ち込んだ毛鉤を1メートル程度しか流さない。
僅か2秒程度しか流さない。
その間だけ渓流魚をダマせば良い。
となれば・・・いい加減な毛鉤でも
毛鉤にアクションを加え、誘いを掛けて
あたかも水生昆虫がもがいているような風情をかもし出せば良い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このような違いが毛鉤の在り様を変えているのだと思わざるを得なくなりました。
方や、ジオラマのように精細な昆虫のモデルで魚を長時間騙す。
方や、な~んだか虫みたいな毛で、動きを見せ付けて短時間、魚を騙す。
オイラの勝手な毛鉤論議にお時間を頂き、誠に恐縮でございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さ~て。
毛鉤釣にしてもお魚を騙す方法もた~くさんある訳です。
それ以外の釣り方にしてもいっぱいあり、
どれがエライ、どれがアホだなんてことはある筈も無いですよね。
但し、渓流から魚が居なくなってしまうような釣をするのはアホだと思いますね。
自分達で自分達の首を絞めるようなもんですし
自然に対しても優しくないですから。
オイラにはそんな釣はやりたくても下手だから出来ません。
近頃は一谷一尾だなんてシャレたことを言ってるオイラです。













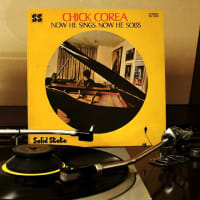







オイラゎ、なぁ~んも考えずに、ただただ足を運んで釣りを…してるって感じ
爺さんの、物事に打ち込む熱意に脱帽です。
こんどテンカラ教えてね…
天才的な釣師の方々はな~んも考えんで、た~くさん釣るんですよね。
熱意といえば、お師匠様のもんぢゃぁござんせんか?
明日はよさそうだけんども、どっかいくんですかい?
憧れにしてますからね
爺様をね(笑)
明日ですか、久々のまとまった雨で、多分に濁り入って芥が流れて…
どぉ~だろぉ~かね??
松尾を頭に浮かべてたんだがね。
なんせ、こちらゎ、アマゾン川か、ガンジス川か…濁りと濁流です(苦笑)
日曜が良いかな???
宵から一杯引っかけに行くことにしましょうかね。
ふふふ。
山本素石著「渓流物語」(朔風社)の
「越前のテンカラ師」というエッセイを思い出しました。
昭和30年代に石徹白川で出合った、目がほとんど見えない老テンカラ師の話で
その翁は著者がたった今釣り上ってきたコースを釣って下ると言う。
どんな釣りをするのか見たかったのでついて行ったら、とても目が不自由だとは思えないようにポンポンと釣ったとのこと。
越前各地の山村には、昔から竹の延べ竿に馬の尾の毛を何本かをより合わせ
テーパーにした糸を使うテンカラ釣りが伝わっていると書いています。
すでにお読みになっておられるかも知れませんが
まだのようでしたら一読をお勧めします。
釣り上がって来たところを釣り下がると言われたのでは参りますね。
素石さんのエッセイも脚色されていると思われますが。
目が悪いと言う釣り人を知ってますが、めちゃくちゃ上手い渓流釣をします。
おそらく長年同じ渓をこなしてきていて、魚の出るポイントを熟知しているのでしょうね。
勿論、キャストも正確でしょうから、毛鉤の飛んだ位置も手に取るように判ってる。
アワセは決めた時間毛鉤を流して取っているのではないでしょうか?
それと誘いによって手に来る衝撃で合わせているのでは?
オイラ、なかなかそんなレベルには程遠く、もがく姿はヒラタカゲロウみたいです。
素石さんも、テンカラをよくしたようです。機会があれば読んで見たいものです。
情報をありがとうございました。