朝日記150812 青木昌彦経済入門~制度論の地平と拡大ときょうの絵
 (わたくしの朝散歩)
(わたくしの朝散歩)
おはようございます。
きのうは、街の図書館に取り寄せを依頼していた本が
用意できたという連絡があり、受け取りにいきました。(新たに購入してくれたようです)
家内が、午後の暑さしのぎにファミレスという誘いに乗ったのでした。
ワンコインでハンバーグランチをたのみ、あとはフリードリンクで 図書館から借りたばかりの本を読みこもうという魂胆でした。この季節は、おばさんたちや、幼児の騒ぎ声も少なく、ちょっと時間をずらせば図書館の閲覧室より快適ですね。
*青木昌彦 経済入門~制度論の地平と拡大 ちくま新書 2014 ISBN978-4-480-06753-1因みにこの本の章立ては以下です。
第1章 経済学をどう読むか
第2章 制度分析の考え方
第3章 制度分析の応用
第4章 制度分析の広がる地平
知識の土地勘として、この本で一番ありがたかったのは第2章での制度分析つまりInstitutionの考え方の状況でした。
認知哲学は、現代分子生物学や脳科学の進展で人文社会学へのパラダイム転換があったようですが、それもすでに1990年代で 私への啓蒙は大分遅い到着といえます。
彼の鍵ワードを荒井流に翻訳して、あげますと以下です;
実施(implementation)と機能(function)の概念的な区分
Institutionをになう主体(agency)と価値観(文化)
Institutionの枠組みとして 機能~構造~文化~制約
ゲーム理論(動的シミュレーション実験)
Institutionの問題領域(ドメイン)(ここに哲学の問題が入ってきます。
*青木さんは、社会科学での状況としてつぎの流派を挙げています;
法実証主義、メカニカルデザイン、サール(二分法(価値と合理的選択)、ビンモア、盛山和夫。
*荒井としては、サール(Searle)の思考構造に目がくぎ付けなりました。(これは青木さんのこの本にはありませんが、彼は意識しているようでした)
機能(function)を 認識論的判断と存在論的実体とのマトリクスで 考えています。
(判断)
認識論的主観 認識論的客観
(実体)
存在論的主観 (意味論的機能) (技術的機能)
存在論的客観 (心理的機能) (生物学的機能)
(これは、Carten Hermann- PillathというひとがSearleの発想を使ってマトリクスにしたものです。このひとの論文はInstitutionの概念のなかにエントロピー概念で解釈を統一しようとした野心的なものです)
カントは経験を尊重して、存在論を排除して、如何に知るかの認識哲学を展開していますので、一見おどろきでもありました。しかし、判断力批判で人間の行動(技術)の機能については形式的提示に止まっています。 現象概念を提示している延長として 当然 実体に即した思考があって当然で
あると理解します。 つまり、認識論哲学と現象哲学が組になっているところがなるほどとおもいました。
これでシステム論での目的論構造を考えてみるのが8月の遊びごとです。 (松島瑞巌寺ほど)
(松島瑞巌寺ほど)
さて、どうしてこんなことを考えることになってしまったかを頭のなかでたどってみます;
たまたま、先回の研究会で「Institution」と「Agence」の概念を スタンフォード哲学ネットで紹介したこと。
なぜこの語に意識が及んだのかは、文化背景の異なる集団の価値の多元主義についてですが、その問題の動機は、イルカ漁のイルカの水族館使用の禁止など「共約不可能性」の問題構造でありました。その問題のさらに動機は、目的性(客観性)の設定上限のようなものをどう考えるという素朴なものです。さらにその出発は、カントの「判断力批判」で、人間理性と自由意志というところからでした。
結局その過程で、問題を解決するための現実は「制度」となりますが、この語のもとになっている「Institution」という概念が思考パラダイムの転換となりうるように気が付きました。ここで、ある先輩筋からのアドバイスがあり、先般亡くなられた青木昌彦さんの経済学を知ったことになります。
で、青木さんのこの世界での功績を確認する結果となったことによります。
これだけ、材料があると暑さしのぎにはなります。
雑駁な語りでおそれいります。












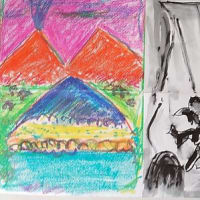













青木昌彦とJ.R.Searle です。
私がこの二人に敬意を表する理由は以下のURLを見ていただいたほうが早いと思いますので此処で一々ご説明するのは控えさせていただきます。
青木昌彦:https://www.facebook.com/masuteru.sekiguchi/posts/886654068081474?pnref=story
J.R.Searle :http://byoshonikki.blogspot.jp/2015/02/blog-post_28.html
青木昌彦さんとSearleさんは、この夏の私の焦点でした。 いろいろ教えてください。私はラッキーですね。
2012年に総合知学会(小松昭英会長)という小さな学会で「システム思考による目的論理と社会倫理」というテーマで、研究発表をしています。カントの判断力批判からはいり、多元主義、共約不可能性、科学的目的性(客観性)、などスタンフォード大学の哲学ミュージアムをたどっているうちに 上の二賢人の存在の大きさに偶然たどりついたところです。また書きます。
ありがとうございました。