日本原子力研究開発機構の高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市白木)が14年5か月ぶりに運転再開してから6日で1か月。
この間、試験運転はおおむね順調に進んでいるものの、軽微なレベルのトラブルは続発。中でも各種の警報装置は頻繁に作動しており、機構は緊急性や重要度がかなり低い警報は鳴らないようにするなど、警報の運用体制を見直している。
もんじゅは現在、0%に近い低出力で原子炉の状態を調べる「炉心確認試験」を実施中。5日は原子炉内を循環する冷却材のナトリウムの温度を約190度から約300度へと上げて、原子炉への影響を調べた。
機構によると、警報の作動件数は運転再開の5月6日から6月2日までで560件以上。作業に伴ってあらかじめ作動がわかっていたり、天候のわずかな変化でも鳴ったりするなど、大半は緊急性がなかった。
中でも、核燃料一時貯蔵施設内を満たす窒素ガスの圧力監視装置は、施設外の大気圧との圧力差が大きくなると警報が鳴り、5月23日には低気圧の影響で222回も作動。中央制御室に詰める運転員は、警報が鳴るたびに確認作業を行うため、警報が頻発すると負担が増す。この日の場合、原子炉の起動操作を、午前中から午後6時頃まで延ばさざるを得なかった。
圧力監視装置は、施設内への空気流入を防ぐために、窒素ガスの圧力を大気圧より高く保つのが目的。ただし、同施設には警報機能を持つ酸素濃度計も取り付けられており、酸素の検知で空気流入を監視できることから、機構は圧力の警報を「不要」と判断し、5月28日から使用を停止している。
もんじゅ運営管理室の瀬戸口啓一室長は「運転停止中は、運転員も単に『よく鳴る警報』という程度の認識だった。だが、警報は本来、異常を知らせるものであり、運転状態となったもんじゅでは、安全上不可欠な警報と必ずしもそうでないもの、あるいは無駄だったものを識別していかなければならない」と話す。
研究開発段階の原発であるもんじゅには、試験目的や運転状態の多重監視のために、一般の軽水炉原発と比べて格段に多くの警報装置が取り付けられている。
再開初日から連続誤作動した原子炉内の放射性物質検出器の感度は、軽水炉に設置されているものよりも数万倍も高い。だが、もんじゅ用の特注品で、使うこと自体が研究開発の一環という面もあるだけに、誤作動の原因究明にも時間がかかっている。
福井大国際原子力工学研究所の竹田敏一所長(原子炉工学)は「高速増殖炉を安全に運転する上でどのような警報が必要なのかを調べるのも、もんじゅの重要な役割だ」と指摘する。
業界の話題、問題、掘り出し物、ちょっとしたニュース配信中。
この間、試験運転はおおむね順調に進んでいるものの、軽微なレベルのトラブルは続発。中でも各種の警報装置は頻繁に作動しており、機構は緊急性や重要度がかなり低い警報は鳴らないようにするなど、警報の運用体制を見直している。
もんじゅは現在、0%に近い低出力で原子炉の状態を調べる「炉心確認試験」を実施中。5日は原子炉内を循環する冷却材のナトリウムの温度を約190度から約300度へと上げて、原子炉への影響を調べた。
機構によると、警報の作動件数は運転再開の5月6日から6月2日までで560件以上。作業に伴ってあらかじめ作動がわかっていたり、天候のわずかな変化でも鳴ったりするなど、大半は緊急性がなかった。
中でも、核燃料一時貯蔵施設内を満たす窒素ガスの圧力監視装置は、施設外の大気圧との圧力差が大きくなると警報が鳴り、5月23日には低気圧の影響で222回も作動。中央制御室に詰める運転員は、警報が鳴るたびに確認作業を行うため、警報が頻発すると負担が増す。この日の場合、原子炉の起動操作を、午前中から午後6時頃まで延ばさざるを得なかった。
圧力監視装置は、施設内への空気流入を防ぐために、窒素ガスの圧力を大気圧より高く保つのが目的。ただし、同施設には警報機能を持つ酸素濃度計も取り付けられており、酸素の検知で空気流入を監視できることから、機構は圧力の警報を「不要」と判断し、5月28日から使用を停止している。
もんじゅ運営管理室の瀬戸口啓一室長は「運転停止中は、運転員も単に『よく鳴る警報』という程度の認識だった。だが、警報は本来、異常を知らせるものであり、運転状態となったもんじゅでは、安全上不可欠な警報と必ずしもそうでないもの、あるいは無駄だったものを識別していかなければならない」と話す。
研究開発段階の原発であるもんじゅには、試験目的や運転状態の多重監視のために、一般の軽水炉原発と比べて格段に多くの警報装置が取り付けられている。
再開初日から連続誤作動した原子炉内の放射性物質検出器の感度は、軽水炉に設置されているものよりも数万倍も高い。だが、もんじゅ用の特注品で、使うこと自体が研究開発の一環という面もあるだけに、誤作動の原因究明にも時間がかかっている。
福井大国際原子力工学研究所の竹田敏一所長(原子炉工学)は「高速増殖炉を安全に運転する上でどのような警報が必要なのかを調べるのも、もんじゅの重要な役割だ」と指摘する。
業界の話題、問題、掘り出し物、ちょっとしたニュース配信中。













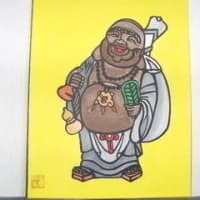








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます