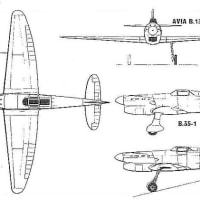ある本で、アメリカの雑誌The Unied States Newsの1941年10月31日号に、「日本への爆撃経路-各戦略地点から日本までの飛行時間」と題する見開きの説明図があると読んだ。そこで、国会図書館で雑誌の所在を調べてもらった。なかなか見つからず、何か所かの大学の図書館にあると分かった。更に調べると、その後雑誌のタイトルにworld reportsというのが加わっているのだが、関西館にあることが分かった。二人掛りで30分はかかり、こちらは諦めかけていたが、さすがのプロである。
東京館に送ってもらうと到着日から休刊日を除いた、3日間だけ閲覧できるが、送ることはできても、コピー不可の場合があるが、到着日までに電話連絡がなければ、着いていると言った。指定された初日に行ったら紙が古びていて、BC複写という方法しかないと指定されていたが、仕方ない。アメリカの雑誌でも、当時の紙質はさほどよくないのである。スペースの都合で洋雑誌は関西館に置いてあるというのだから、関西館などできなければいつでも閲覧できるのに、と勝手なことを考えたが仕方ない。
前置きが長くなったが、前記の箇所を探していると、意外な収穫があった。週刊誌が3か月分の合本にしてあったので、何冊分も見ることができたのである。まず広告が戦時色いっぱいなのである。コピーしてきたものだけでも、ユナイテッドエアクラフト社のB-24の写真入りの広告、ベンディックスアビエーション社の爆撃機、軍艦、大砲などのいろんな兵器の写真入りの広告、などがある。
これらは兵器製造会社だからまだしも、煙草のキャメルの広告には陸軍、海軍、など4人の制服の軍人が煙草を持って「キャメル大好き」と言って、にこにこしているのである。今の日本の常識では、昭和16年の12月の真珠湾攻撃の直前までの時点では、米国民が厭戦気分に浸っていたということになっている。それが事実なら、こんな軍事一色の広告など忌避されているであろう。それが、武器の広告ばかりではなく、非軍事商品の広告までに、兵隊さんが登場するのである。この常識は全くの間違いに違いないのである。ちなみに、この週刊誌は、経済問題も取り扱っており、表紙の説明によれば、国の問題に関する興味深いニュースを扱う、と書いてあるから今の日本で言いえば、「軍事研究」のような軍事専門誌ではないのである。
この週刊誌を探した本命の記事には、日本を中心とした世界地図があって、シンガポール、キャビテ(フィリピン)、香港、重慶、グァム、ウラジオストック、ダッチハーバーの7箇所からの東京までの爆撃機の飛行時間が書かれている。図の説明の記事は、いきなり「日本は現在では主要7か所からの爆撃圏内にはいっている」というぶっそうな書き出しである。
そして、戦時には、これらの米国、ロシア、支那からの準備ができていると続く。各基地から東京までの飛行距離まで書かれており、最も近いのはウラジオストックの440マイルという近さである。
10月24日の記事も面白い。タイトルからして、AMMERICA READY TO MEET THREAT OF TWO-OCEANWAR、すなわち、アメリカは両洋の戦争の脅威に対して準備ができている、という刺激的なものである。TWO-OCEANとは大西洋と太平洋のことだから、いつでも対日独両方の戦争をやってやれるぜ、というのである。
中身はドイツ潜水艦がアメリカ船を攻撃したら、いつでも潜水艦を攻撃してやる、とか日本がアメリカ船の航行を妨害したら、日本はリスクを覚悟せよ、という。ドイツや日本が対英ソへの武器供与のレンドリースの船と護衛駆逐艦の邪魔をしたら攻撃するぞ、というのである。既に中立を犯しておいて、その邪魔をするな、という傍若無人ぶりである。ちなみに日本の邪魔というのは、ウラジオストック経由の軍需物資輸送のことだそうである。
アメリカは資源なども日々増強しているのに、ドイツはどんどん不足していくともいう。駆逐艦キアニーが独潜水艦に攻撃され犠牲者が出たという。その時までに米商船と軍艦の護衛をしていて、ルーズベルト大統領は、独潜水艦を発見し次第、攻撃すると警告している、というのである。
最後の方では日本もイタリアも戦争に疲れており、日本の国民は8年間もの戦争で疲れており、工業も資源も尽きつつある、というようなことを言う。1941年の時点で8年というのは、満州事変では短く、支那事変では長すぎるが、いずれにしても日本が支那との戦争でかなり消耗している、と判断しているのは間違いない。結局のところ日本は継戦能力が尽きているから、簡単に勝てると見ていたのである。
結びで、米英の戦略は海軍戦略で、それは消耗戦であるという。だからこの戦争は我慢比べであり、その結果はひとえにヒトラーが勝利の為に何をなすかにかかっている、というのだ。This war,at present,などと平気で書くのだから、記事を書いた米人記者にとっては、英ソが戦っている対独戦は既に米国の戦争なのであろう。