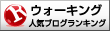平成27年4月25日(土)
名鉄主催 2015年春 東海の自然歩け歩け大会
「降り注ぐ紫のカーテン 尾張津島藤まつり①」の続きです。

川沿いの道を反れて、住宅街の細い道を歩いて行きます。
この辺りから「上街道」になります。
江戸時代に尾張藩が中山道と名古屋城下を結ぶために作った街道です。
約1キロほど続きます。

津田正生の六合庵跡
津田正生(つだ まさなり)
1776-1852 江戸時代後期の地誌家。
安永5年4月生まれ。生家は尾張(おわり)(愛知県)の造り酒屋。恩田仲任,鈴木朖(あきら)にまなぶ。
31歳のとき「尾張地名考」の執筆にとりかかり,文化13年完成させた。嘉永(かえい)5年10月21日死去。77歳。
通称は神助。号は六合庵。著作はほかに「眼前教近道」など。

ハナミズキが満開です。

スタッフによる交通誘導。
ご苦労様です。

兼平堤
佐織町から市内へ入る道として天王川の左岸の堤(旧上街道)が利用されていた。
応永十年(1403)津島牛頭天王の鐘を造ったところから、この堤を「鐘平堤」と呼ぶようになった。
堤の近くには古い家並も多く、江戸時代には巡見使(幕府の見まわり役人)が通ったので「巡見街道」ともいわれた。
このあたりは肥料・材木などの問屋、日用品などを作るかじ屋が多く、二本マストの荷船で品物が運ばれていた。
宝暦九年(1759)橋詰町と向島(天王島)に掛けられていた大橋が取り払われ、天明五年(1785)に仕切り堤が築かれたので後になって上流は蓮田や水田に利用された。

確かにこの辺りは古い感じの建物が多かったですね。

何やらフワフワとしたものが生えていました。

(ノ´▽`)ノオオオオッ♪
見事にツツジが咲き誇っていますね。

ここだけ日当たりが良いからかな。

不動院

後3キロのところまで来ました。
雲居寺前です。

「雲居寺」
創建は15世紀と伝えられ、織田信長の馬回り役の一人で信長が今川義元を桶狭間で襲撃した時、
義元に一番槍を付けた服部小平太の菩提寺として知られる。

本堂内。
厳かな雰囲気です。

お隣の羅漢堂の方へ行ってみます。

w川・o・川w オォーーー!!
凄い。
けど、ちょっと恐いw

境内の様子。
本堂と羅漢堂

可愛らしい御地蔵さん。

しばらく真っ直ぐ歩いて行きます。

道を曲がると、朱色の大きな鳥居が見えてきました。
もう参道ですね、この通りは。

参道の途中で巨大なイチョウの木に遭遇。

ご神木ですね。

立派なイチョウの木です。
長くなりそうなので、今回はこの辺りで。。。