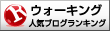近鉄ハイキングを終えて、ゴールの白子駅から一駅の鼓ヶ浦駅へ。
鼓ヶ浦駅から歩いて3分ほどのところに、子安観音寺があります。

仁王門の説明がありました。


大きな仁王様

境内の三重塔

水屋

本堂です。

本堂内へは自由に入れるのですが、撮影は出来ませんでした。

当寺は高野山真言宗の名刹で安産の霊験あらたかな霊場として全国に知られ、参詣祈願の人々の深い信仰を集めている。
人皇第四十五代聖武天皇の天平勝宝年間の勅を奉じた藤原不比等が建立したと伝えられ、道證上人の開山による二千百余年の歴史を秘めた由緒深い寺である。
寺伝によると、
「この浦に時々鼓の音あり怪しきまま網を下しけるに鼓に乗り観世音の尊像上がらせ給ふこのよしを帝きこしめし伽藍建立ありて勅願寺となりぬ。
この浦をいまに鼓ヶ浦といふ。ご本尊は殊に大悲深い難産のうれいを救い子孫長久を守らせ給ふゆえに子安観音とあがむ」
とある。


ご本尊様は、白衣観音様。


こうやくんがいました。

智慧の塔

お隣にいっぱい実が生っていました。

クチナシの実でした。
いっぱい生ってる

本堂の左手前側にお目当ての桜がありました。

2本ありますね。

天然記念物
白子不断桜です。

石柱に史蹟名勝天然記念物保存法に依り
大正十二年三月七日
内務大臣指定になっています。

この桜は、里桜の一種で四季を通じて葉が絶えず、開花期も春秋冬に及ぶのが特徴です。
永禄十年、連歌師紹巴が、東国に下ったときの紀行冨士見道記に「白子山観音寺に不断桜とて名木あり」と記され、
また観世流の貞享三年版にある「不断桜」もこの桜をうたったもので古来より全国で有名です。
また当山の縁起によれば、天平宝字年中雷火のため焼失した伽藍跡の芽生えた桜と伝えられ本尊白衣観世音の霊験のよって咲くとして尊ばれています。
なお不断桜の虫喰葉の巧妙な自然の紋様の着目して伊勢型紙が創られたという由来があります。

今の時期でも、葉は残っていました。

葉の穴ぼこが伊勢型紙の原点だそうです。

塀で仕切られた向こう側に、鳥居が見えました。
お隣に神社があるようです。
これからそちらの方へ行ってみることにします。
長くなりましたので、続きはまたにします。