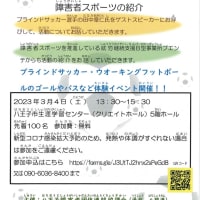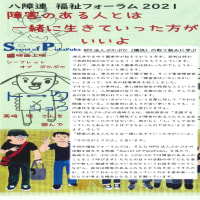八障連通信373号です。
音声版はこちら
【砂永美んさんお便り】
ここからは通信本文です。
【砂永美んさんお便り】
ありがとうショップ 代表 砂長美んです^_^ 暑中見舞い夏のお便りです。
大きなニュース 3 個のお知らせと、お仕事募集 2 件です。!!
栃木県鹿沼市のみんなのミカタグループの代表室相談係に就任しました。https://minnanomikata.com 障害者の新しい働き方を沢山の場面で作れるよう
にコツコツと頑張ります。
先週は、私の渋谷区の家の廊下に、「ハクビシン」発見。死んだふり、されました!2時間もウロウロ。警察官呼んだら、7人もきてしまった。オリンピック競技場近いのに、申し訳なかったです(^_^;)保護動物だから、上手に逃がしてくれました!(写真はFacebook にアップしました!)
◎中小企業家同友会一都三県の合同企画/「同友会が目指す障害者雇用とは?」オンラインセミナーを 8/17(火)18:00~ オンライン(Zoom)で開催します!
すでに 350 名の申し込みがあります。是非ご参加ください。※参加費無料
各県の障害者が活躍している企業の社長によるパネルディスカッションもあります!東京からは私が尊敬する経営者の一人、モンテカンポの山野 雅史社長が登壇されます。
◎基調講演 厚生労働省 障害者雇用対策課課長 小野寺 徳子氏
◎パネリスト 東京代表 株式会社モンテカンポ 山野 雅史氏、神奈川代表 株式会社ロジナス 山本 啓一氏、千葉代表 株式会社共同工芸社 箕輪 晃氏、埼玉代表 有限会社ノア 谷田 正樹氏半分のパネリストは、実際のお子様が、障害を持っている生活を共にしている経営者です。
お申し込みはコチラ → https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdytsE-lHFXD55jyDFrNzNCAexpLF.../edit
◎障害者施設の商品 5 万円買います キャンペーン スタートします。
買い物一回につき 3000 円前後。YouTube のインタビューに、答えてくれる人、又は施設の担当者又は、ファンの人。食品、非食品でも、どっちでも大丈夫です。今、コロナ禍で、働く障害者施設の商品も、売る場所の役所、駅前、等々外販売は全て中止です。何とか、少しでも、知ってもらいたい!と思って企画しました。是非一緒に YouTube に参加してくれる人も募集しています。
◎あつぎごちゃまぜフェス今年は障害のある方のアート作品を市内飲食店に掲示するまちなかアートを開催中。オンラインのライブや講演会もありま
す。私はオンラインマルシェに出店します。詳細はリンク先から検索してね。厚木市・実行委員会主催のイベントです!
https://linktr.ee/gochamaze 私の大好きな雨野千晴ちゃんは元学校の教員で、発達障害当事者、経営者です。
☆お仕事募集の案件【保険金支払担当のスタッフを募集しています!】
ぜんち共済株式会社 障害を持つ人の保険会社です。保険金支払担当のスタッフを募集しています。保険業界の経験はなくて大丈夫です。仕事を覚えてもらうようしっかりサポートします!!もし、お知り合いで転職などを検討されている方がいましたらお声掛けいただけますととても嬉しいです!どうぞよろしくお願いします(^^♪ 勤務地 東京都千代田区
大きなニュース 3 個のお知らせと、お仕事募集 2 件です。!!
栃木県鹿沼市のみんなのミカタグループの代表室相談係に就任しました。https://minnanomikata.com 障害者の新しい働き方を沢山の場面で作れるよう
にコツコツと頑張ります。
先週は、私の渋谷区の家の廊下に、「ハクビシン」発見。死んだふり、されました!2時間もウロウロ。警察官呼んだら、7人もきてしまった。オリンピック競技場近いのに、申し訳なかったです(^_^;)保護動物だから、上手に逃がしてくれました!(写真はFacebook にアップしました!)
◎中小企業家同友会一都三県の合同企画/「同友会が目指す障害者雇用とは?」オンラインセミナーを 8/17(火)18:00~ オンライン(Zoom)で開催します!
すでに 350 名の申し込みがあります。是非ご参加ください。※参加費無料
各県の障害者が活躍している企業の社長によるパネルディスカッションもあります!東京からは私が尊敬する経営者の一人、モンテカンポの山野 雅史社長が登壇されます。
◎基調講演 厚生労働省 障害者雇用対策課課長 小野寺 徳子氏
◎パネリスト 東京代表 株式会社モンテカンポ 山野 雅史氏、神奈川代表 株式会社ロジナス 山本 啓一氏、千葉代表 株式会社共同工芸社 箕輪 晃氏、埼玉代表 有限会社ノア 谷田 正樹氏半分のパネリストは、実際のお子様が、障害を持っている生活を共にしている経営者です。
お申し込みはコチラ → https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdytsE-lHFXD55jyDFrNzNCAexpLF.../edit
◎障害者施設の商品 5 万円買います キャンペーン スタートします。
買い物一回につき 3000 円前後。YouTube のインタビューに、答えてくれる人、又は施設の担当者又は、ファンの人。食品、非食品でも、どっちでも大丈夫です。今、コロナ禍で、働く障害者施設の商品も、売る場所の役所、駅前、等々外販売は全て中止です。何とか、少しでも、知ってもらいたい!と思って企画しました。是非一緒に YouTube に参加してくれる人も募集しています。
◎あつぎごちゃまぜフェス今年は障害のある方のアート作品を市内飲食店に掲示するまちなかアートを開催中。オンラインのライブや講演会もありま
す。私はオンラインマルシェに出店します。詳細はリンク先から検索してね。厚木市・実行委員会主催のイベントです!
https://linktr.ee/gochamaze 私の大好きな雨野千晴ちゃんは元学校の教員で、発達障害当事者、経営者です。
☆お仕事募集の案件【保険金支払担当のスタッフを募集しています!】
ぜんち共済株式会社 障害を持つ人の保険会社です。保険金支払担当のスタッフを募集しています。保険業界の経験はなくて大丈夫です。仕事を覚えてもらうようしっかりサポートします!!もし、お知り合いで転職などを検討されている方がいましたらお声掛けいただけますととても嬉しいです!どうぞよろしくお願いします(^^♪ 勤務地 東京都千代田区
【胡蝶蘭栽培、ホテルスイーツ製造】
障害者手帳又は 、障害をお持ちの人。千葉県富津市周辺 お給料は、最低時給は保証される可能性高いですーyoutube アロンアロンで、施設内容ご覧ください。障害が、重度でも通えれば大丈夫。問い合わせください。NPO 法人 アロンアロンまだまだ、ステイホームが、続きますがお体ご自愛ください。私の youtube 「美んチャンネル」(←検索してね)も登録者が増えて来ました!是非チャンネル登録お待ちしています。ココナラありがとうショップ、初めました!一般社団法人 ありがとうショップも 4 年目です。もっともっと、障害を持つ人達のお仕事や生活が向上する為に頑張ります。ではまた。次のお便りでお目にかかりましょうネ。
一般社団法人 ありがとうショップ 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3-1-16 グリーンハイツ201 www.arigatoshop.jp 砂長美ん 090-8454-2409 Binsunanaga@gmail.com
障害者手帳又は 、障害をお持ちの人。千葉県富津市周辺 お給料は、最低時給は保証される可能性高いですーyoutube アロンアロンで、施設内容ご覧ください。障害が、重度でも通えれば大丈夫。問い合わせください。NPO 法人 アロンアロンまだまだ、ステイホームが、続きますがお体ご自愛ください。私の youtube 「美んチャンネル」(←検索してね)も登録者が増えて来ました!是非チャンネル登録お待ちしています。ココナラありがとうショップ、初めました!一般社団法人 ありがとうショップも 4 年目です。もっともっと、障害を持つ人達のお仕事や生活が向上する為に頑張ります。ではまた。次のお便りでお目にかかりましょうネ。
一般社団法人 ありがとうショップ 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3-1-16 グリーンハイツ201 www.arigatoshop.jp 砂長美ん 090-8454-2409 Binsunanaga@gmail.com
【連載コラム Vol.58 『良いも悪いも人の縁』 八障連代表 杉浦 貢】
私自身の身体に生まれつきの障害があり、普通校と支援学校の両方に通った経験があるからでしょうか。かつての私の親と同じように、今現在...障害のあるお子さんを育てておられる親御さん、それも...小学校入学前の、まだ小さなお子さんをお持ちのご両親から...『将来ウチの子は、どっちの学校に通わせたらいいですか?』という御相談を受けたことが、過去に何回かありました。
私は特に、相談支援を仕事にしている訳じゃありませんし、その仕事をするための公的な資格があるわけでも、独自の専門性を備えている訳でもありません。ただの...いち障害当事者に過ぎません。なので...あくまでも、雑談の延長...個人的な見解のひとつとして、こんなふうにお返事させていただきました。
●大事なのは『どっちの学校に入れるか』ではない●
私が学生であった頃は、もう随分昔のことですし、世相も環境も異なります。何よりも...お子さんそれぞれ...一人ひとりの障害が異なれば、ふさわしい対応も異なります。万事に対応する答え...絶対の正解は無いのですが...とりあえず私のお答えとしては...『どちらに通おうと、足りないものはある』と思っています。
普通校では、障害のない子と同じように、同じことができるように...と要求されてしまいます。支援学校では、どれだけ障害のない子に近いことができるか...どれだけ、先生を煩わせないか...で評価されがちになります。結果、障害の重い子、手厚いケアが必要な子ほど...『気の毒な子』、『かわいそうな子』として見てしまう親御さんや先生は多いと思います。
障害があるからこそ、より良い支援が得られるように...ということで、支援学校に通っているのに...どんな障害があるかは、その子の選択や決定とは関係がないのに...結局は...『その子がどれだけ健常者に近いか』ということで優劣の評価を決める空気が作られます。
また普通校に通っていても、『みんなと同じように過ごしましょう』ということが要求されます。これはつまり...違いがあっても同じ場所にいる...という『機会の平等』ではなくて、一定のパフォーマンスに達せないものは切り捨てる、という『結果の平等』に他なりません。
普通校にせよ、支援学校にせよ...この...『結果の平等』という意識が優勢であるならば...どっちの学校に通わせるにしても、わざわざ選ぶ意味はない...と私は考えます。
お子さんを学校に通わせる際、一番大事になるのは...『普通校』なのか『支援学校』なのか...という入れ物を選ぶことではないと思います。それより大事なのは『入れ物の中身』...つまり、どんな出会いがあるか、なのであります。
普通校に通った場合でも、いい先生、いい友だちに出会えたならば...困難があり不便があっても、幸せで意義ある学校生活が送れることでしょう。手厚いケアがあるという支援学校でも、お子さんとウマの合う友だちがいなかったり、障害理解に対して知識も意欲もない、ロクデナシの先生に当たることはあります。どんな先生、どんな友だちに出会えるか、という重要なことが...入学後にやっとわかる...ほとんどバクチであることを考えるなら...『ウチの子をどっちの学校に入れようか』と悩む親御さんの姿は、私から見たら滑稽...と言ってしまうと失礼ですが...。
正直な感覚として、そこで悩んでも仕方のないことのように感じてしまうのです。しかし私自身の、そうした内心の感想とは別に...今、目の前の親御さんお悩みに対する答え...一応の結論としては...普通校に入れてあげてくださいとお伝えしました。それも、できれば...普通校の中の特別支援学級ではなく、障害のない子と同じ教室に。
この社会は、障害のない人たちが多勢で優位であり、障害者はどうしても、少数で苦戦を強いられます。全員が全員、理解者や支援者というではありません。理解されて受け入れられる体験よりも...無知、無理解から来る無配慮に晒される機会の方が、まだまだ多いのです。
『どっちの学校に入れたらいいか』という選択に関わらず、将来その子が出ていく社会は結局...『周りは健常者だらけ』という社会なのです。支援者の人たちや理解者の人たちも...やはり...ほぼだいたいが、みんな障害のない健常者です。
私は特に、相談支援を仕事にしている訳じゃありませんし、その仕事をするための公的な資格があるわけでも、独自の専門性を備えている訳でもありません。ただの...いち障害当事者に過ぎません。なので...あくまでも、雑談の延長...個人的な見解のひとつとして、こんなふうにお返事させていただきました。
●大事なのは『どっちの学校に入れるか』ではない●
私が学生であった頃は、もう随分昔のことですし、世相も環境も異なります。何よりも...お子さんそれぞれ...一人ひとりの障害が異なれば、ふさわしい対応も異なります。万事に対応する答え...絶対の正解は無いのですが...とりあえず私のお答えとしては...『どちらに通おうと、足りないものはある』と思っています。
普通校では、障害のない子と同じように、同じことができるように...と要求されてしまいます。支援学校では、どれだけ障害のない子に近いことができるか...どれだけ、先生を煩わせないか...で評価されがちになります。結果、障害の重い子、手厚いケアが必要な子ほど...『気の毒な子』、『かわいそうな子』として見てしまう親御さんや先生は多いと思います。
障害があるからこそ、より良い支援が得られるように...ということで、支援学校に通っているのに...どんな障害があるかは、その子の選択や決定とは関係がないのに...結局は...『その子がどれだけ健常者に近いか』ということで優劣の評価を決める空気が作られます。
また普通校に通っていても、『みんなと同じように過ごしましょう』ということが要求されます。これはつまり...違いがあっても同じ場所にいる...という『機会の平等』ではなくて、一定のパフォーマンスに達せないものは切り捨てる、という『結果の平等』に他なりません。
普通校にせよ、支援学校にせよ...この...『結果の平等』という意識が優勢であるならば...どっちの学校に通わせるにしても、わざわざ選ぶ意味はない...と私は考えます。
お子さんを学校に通わせる際、一番大事になるのは...『普通校』なのか『支援学校』なのか...という入れ物を選ぶことではないと思います。それより大事なのは『入れ物の中身』...つまり、どんな出会いがあるか、なのであります。
普通校に通った場合でも、いい先生、いい友だちに出会えたならば...困難があり不便があっても、幸せで意義ある学校生活が送れることでしょう。手厚いケアがあるという支援学校でも、お子さんとウマの合う友だちがいなかったり、障害理解に対して知識も意欲もない、ロクデナシの先生に当たることはあります。どんな先生、どんな友だちに出会えるか、という重要なことが...入学後にやっとわかる...ほとんどバクチであることを考えるなら...『ウチの子をどっちの学校に入れようか』と悩む親御さんの姿は、私から見たら滑稽...と言ってしまうと失礼ですが...。
正直な感覚として、そこで悩んでも仕方のないことのように感じてしまうのです。しかし私自身の、そうした内心の感想とは別に...今、目の前の親御さんお悩みに対する答え...一応の結論としては...普通校に入れてあげてくださいとお伝えしました。それも、できれば...普通校の中の特別支援学級ではなく、障害のない子と同じ教室に。
この社会は、障害のない人たちが多勢で優位であり、障害者はどうしても、少数で苦戦を強いられます。全員が全員、理解者や支援者というではありません。理解されて受け入れられる体験よりも...無知、無理解から来る無配慮に晒される機会の方が、まだまだ多いのです。
『どっちの学校に入れたらいいか』という選択に関わらず、将来その子が出ていく社会は結局...『周りは健常者だらけ』という社会なのです。支援者の人たちや理解者の人たちも...やはり...ほぼだいたいが、みんな障害のない健常者です。
だからこそ障害のある私たちは、小さいころから厳しい条件で、困難が多い環境に慣れておく必要があるわけです。また、障害のない人たち...先生や同級生にとっても、身近に障害のあるお子さんがいることで『どんな配慮が必要なのか』『どんな生活をしているのか』と...障害のある人のことを学び知るきっかけになると思うのです。
もちろん、トラブルも起きるでしょう。障害のない人からすれば『障害者は自分の権利ばかり主張する』と見えるでしょうし障害のある人からすれば、『周りから要求される基準が高い』と思われるかも知れません。
人間同士のトラブルは、どこにいたって、誰といたって起こるものです。であるならばいっその事...、『トラブルが起きないように』と考えるより、『起きたトラブルをどうするか』ということを考える方が意義が大きいと考えます。
健常者同士、障害者同士で分けられた環境でいても、そこにトラブルは起きます。トラブルが起きないことが通常なのではなく、トラブルが起きることが当たり前なのです。障害者だけ、健常者だけの環境では、『その場所の基準に外れた、異なる人』は...その場にいないものとして扱われてしまいます。
多様な人が雑多に過ごすのが社会の本質である、とするのなら...障害のある
お子さんだからといって、見せかけだけは、さも居心地が良さそうに見えるような...分け隔てられた場所で、静かにじっとしていてはいけないと思います。社会の中では、悪しき出会いが日常であり、不本意な扱いが当たり前である...つまり...『いい人に会うより、嫌な人にあってしまうことの方が多いのが当たり前』だからこそ...自分にとってより良い隣人は誰か、より良い友人は誰なのか...ということを、決して...近い位置にいたというだけで、たまたまあてがわれるのでなく、自らの意思と判断で、能動的に探して選んでいかなければなりません。
大事なのは...『どこに居るか』ではなく『誰と出会うか』という事だと思うのです。
もちろん、トラブルも起きるでしょう。障害のない人からすれば『障害者は自分の権利ばかり主張する』と見えるでしょうし障害のある人からすれば、『周りから要求される基準が高い』と思われるかも知れません。
人間同士のトラブルは、どこにいたって、誰といたって起こるものです。であるならばいっその事...、『トラブルが起きないように』と考えるより、『起きたトラブルをどうするか』ということを考える方が意義が大きいと考えます。
健常者同士、障害者同士で分けられた環境でいても、そこにトラブルは起きます。トラブルが起きないことが通常なのではなく、トラブルが起きることが当たり前なのです。障害者だけ、健常者だけの環境では、『その場所の基準に外れた、異なる人』は...その場にいないものとして扱われてしまいます。
多様な人が雑多に過ごすのが社会の本質である、とするのなら...障害のある
お子さんだからといって、見せかけだけは、さも居心地が良さそうに見えるような...分け隔てられた場所で、静かにじっとしていてはいけないと思います。社会の中では、悪しき出会いが日常であり、不本意な扱いが当たり前である...つまり...『いい人に会うより、嫌な人にあってしまうことの方が多いのが当たり前』だからこそ...自分にとってより良い隣人は誰か、より良い友人は誰なのか...ということを、決して...近い位置にいたというだけで、たまたまあてがわれるのでなく、自らの意思と判断で、能動的に探して選んでいかなければなりません。
大事なのは...『どこに居るか』ではなく『誰と出会うか』という事だと思うのです。
【編集後記】
通信 373 号をお届けいたします。今号では、コロナ過でも負けずに情報発信しておられる砂長美んさんから「夏のお便り」が届きましたので、巻頭にて掲載いたしました。砂長様、いつもながらの情報満載の寄稿、誠にありがとうございます。さて、東京を中心に「感染爆発」ともいえる状況が全国に拡大し続けています。30 代、40 代を中心に重症化のケースも報道されておりますので、さらに感染防止策を徹底してこのコロナ過を乗り切っていきましょう。
皆様からの投稿をお待ちしております。コロナ過での近況報告などお寄せください。(編集部)
皆様からの投稿をお待ちしております。コロナ過での近況報告などお寄せください。(編集部)
【連載コラム B 型肝炎闘病記 パオ 小濵 義久 闘病史 その 56】
そうして七転八倒している最中の 4 月 26 日、虎の門病院分院のエコー検査で見過ごせぬものを発見され、怪しいから早急な精密検査が必要ということで入院の申し込みをして帰った。ゴールデンウイーク明けの 5 月 8 日に入院し、19 日までの 12 日間のヘビーな検査入院となった。ヘビーというのはあのきついアンギオ(血管造影検査)が含まれていたからだ。生検の結果は悪性とも良性ともはっきりしないものの、悪性に近いグレーということで「怪しきものは罰する」の原則に則って治療しようということになった。
非常勤の仕事を 4 つも抱えていたので、グレーなればこそ夏まで待ってもらい、8 月 14 日月曜日からの入院となった。14 日にエコー検査、15 日に CT 検査をして、もう一度確認した後、18 日にラジオ波焼灼療法(以下 RFA)という治療を行った。手術でなければ何でも来いと大手を振って構えていたが、中には術後発熱し寝込んでしまう人もいると看護師さんからの情報が入る。
RFA というのは、電子レンジと同じ原理で、癌部位近くまで穿刺した針先(電極針と言い、先端が円錐形になっている)からラジオ波を発生させ、その熱で癌が発生している部位を直径 3 cm位の球形型に焼いてしまい、癌を死滅させる療法なのだ。1993 年にイタリアの医師が開発し、日本では2004 年から保険適用になっているという新しい治療法である。上記のように発熱や痛みなど副作用の出る人もいるが、何ともない人の方が多いようだ。
私の場合は何事もなく、癌治療という言葉が持つ重みは全く感じられなかった。「またか、やれやれ」と言った面持ちで入院したのに、ちょっと拍子抜けした感じもした。検査入院に近いくらいのイメージだった。術後安静が解除されたのでナースステーションまで痒みを抑えるためのアイスノンを借り
に行ったら、「小濱さん、歩いて良いのは病室内だけです。まだトイレに行く時だけにして下さい。」と少し強い口調でベテランナースに怒られてしまった。忙しく動き回っているナースに負担を掛けまいとしたのが裏目に出た。
癌切除術は身体に大きな負担をかける侵襲的な治療であるのに対して、この RFA は身体への負担が極めて少ない。それだけ入院期間も短くなり、極めて楽な治療法であり、また前日の夜まで普通に食事ができ、絶対安静は 7時間ほどで解除されるので、治療当日の夕飯が食べられるというのも嬉しい。それもお粥とかじゃないのも良い。
治療自体は楽に終わったのだが、前年の秋口から続いている不具合のため、体調は良好とは言えなかった。真夏の入院だというのに、冷房が効いているとは言え、寒くて仕方なかった。だからと言って、庭に逃げ出す気力も出て来ず、12 日間のほとんどをベッドでゴロゴロしながら過ごした。寒く感じるので、ナースエイドの人に頼んで毛布を 3 枚もらってかけていたが、それでも寒さから逃れられず、猫のように丸くなって寝ている時もあった。途中からは早く退院して夏の暑さを感じたいとさえ思った。
退院して寒さからは逃れられたものの、調子の悪さは相変わらずで、9 月 2 日には運転している車を壁ぎりぎりに止めようとして擦っている。親が金持ちならカーレーサーを目指していたかもと思うくらい、車の運転が好きだったし、上手だといろんな人から褒められてきたし、自信もあったのに、何たる
ザマだろう。プライドも 1 枚ずつ剥がされて行く。いつも靄がかかったような頭脳と締まりのない体の動きはいろんな処で歯車がきしみ、心と体のバランス、身体全体のバランスもギクシャクしたまま時だけが過ぎて行った。
私の大好きな「ジャコメッティ」の展覧会が神奈川県立近代美術館で開かれるというので、友達を誘って 7 月 16 日には逗子まで出掛けた。あの彫刻に会えれば、元気をもらえるかもしれないと期待して行ったのだが、がっかりして帰って来た。27 歳の時にスイスの美術館で私を鷲掴みにして離さなかった 2m 長の彫刻はなく、小品ばかりだった。心が躍らなかったのは、小品の所為ではなく、疲弊して延びきった心の襞にジャコメッティを味わうだけのゆとりがなかったのかもしれない。(次号に続く)
非常勤の仕事を 4 つも抱えていたので、グレーなればこそ夏まで待ってもらい、8 月 14 日月曜日からの入院となった。14 日にエコー検査、15 日に CT 検査をして、もう一度確認した後、18 日にラジオ波焼灼療法(以下 RFA)という治療を行った。手術でなければ何でも来いと大手を振って構えていたが、中には術後発熱し寝込んでしまう人もいると看護師さんからの情報が入る。
RFA というのは、電子レンジと同じ原理で、癌部位近くまで穿刺した針先(電極針と言い、先端が円錐形になっている)からラジオ波を発生させ、その熱で癌が発生している部位を直径 3 cm位の球形型に焼いてしまい、癌を死滅させる療法なのだ。1993 年にイタリアの医師が開発し、日本では2004 年から保険適用になっているという新しい治療法である。上記のように発熱や痛みなど副作用の出る人もいるが、何ともない人の方が多いようだ。
私の場合は何事もなく、癌治療という言葉が持つ重みは全く感じられなかった。「またか、やれやれ」と言った面持ちで入院したのに、ちょっと拍子抜けした感じもした。検査入院に近いくらいのイメージだった。術後安静が解除されたのでナースステーションまで痒みを抑えるためのアイスノンを借り
に行ったら、「小濱さん、歩いて良いのは病室内だけです。まだトイレに行く時だけにして下さい。」と少し強い口調でベテランナースに怒られてしまった。忙しく動き回っているナースに負担を掛けまいとしたのが裏目に出た。
癌切除術は身体に大きな負担をかける侵襲的な治療であるのに対して、この RFA は身体への負担が極めて少ない。それだけ入院期間も短くなり、極めて楽な治療法であり、また前日の夜まで普通に食事ができ、絶対安静は 7時間ほどで解除されるので、治療当日の夕飯が食べられるというのも嬉しい。それもお粥とかじゃないのも良い。
治療自体は楽に終わったのだが、前年の秋口から続いている不具合のため、体調は良好とは言えなかった。真夏の入院だというのに、冷房が効いているとは言え、寒くて仕方なかった。だからと言って、庭に逃げ出す気力も出て来ず、12 日間のほとんどをベッドでゴロゴロしながら過ごした。寒く感じるので、ナースエイドの人に頼んで毛布を 3 枚もらってかけていたが、それでも寒さから逃れられず、猫のように丸くなって寝ている時もあった。途中からは早く退院して夏の暑さを感じたいとさえ思った。
退院して寒さからは逃れられたものの、調子の悪さは相変わらずで、9 月 2 日には運転している車を壁ぎりぎりに止めようとして擦っている。親が金持ちならカーレーサーを目指していたかもと思うくらい、車の運転が好きだったし、上手だといろんな人から褒められてきたし、自信もあったのに、何たる
ザマだろう。プライドも 1 枚ずつ剥がされて行く。いつも靄がかかったような頭脳と締まりのない体の動きはいろんな処で歯車がきしみ、心と体のバランス、身体全体のバランスもギクシャクしたまま時だけが過ぎて行った。
私の大好きな「ジャコメッティ」の展覧会が神奈川県立近代美術館で開かれるというので、友達を誘って 7 月 16 日には逗子まで出掛けた。あの彫刻に会えれば、元気をもらえるかもしれないと期待して行ったのだが、がっかりして帰って来た。27 歳の時にスイスの美術館で私を鷲掴みにして離さなかった 2m 長の彫刻はなく、小品ばかりだった。心が躍らなかったのは、小品の所為ではなく、疲弊して延びきった心の襞にジャコメッティを味わうだけのゆとりがなかったのかもしれない。(次号に続く)