
フェルマーの最終定理
ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで
サイモン・シン著 青木 薫訳
新潮社 2000年
今日ではコンピューターを使って完全数の探索が続けられており、2( 216090) ×(2( 216091)ー 1)という、なんと十三万桁を越える巨大な数がエウクレイデスの規則に従うことがわかっている(訳注:1999年には419万7919桁の完全数が発見された)。
ピュタゴラスは、完全数がもつパターンや性質の豊かさに魅了され、その精妙さに心服した。完全数という概念は、一見するとやさしそうにみえるかもしれないが、そこには古代ギリシャ人には解決できなかった根本的な問題が潜んでいる。たとえば、約数の和がその数自身よりも1だけ小さい数はたくさんある(それを「わずかに不足する数」と呼ぼう)。ところが、約数の和がその数自身よりも1だけ大きい数(「わずかに過剰な数」)は一つも存在しないようなのだ。ギリシャ人たちは「わずかに過剰な数」を一つも見つけられず、なぜ見つけなれないのかを説明することもできなかった。「わずかに過剰な数」が見つからないというのに、そんな数は存在しないと証明することもできない―これは実に苛立たしい状況である。「わずかに過剰な数」は存在しないことを証明したところで何の役にも立ちはしないだろうが、それは数の本質に迫る可能性をはらんだ、研究に値する問題なのだ。ピュタゴラス教団が頭を悩ませていたのはこうした問題だった。そして二千五百年の時を経た今日でも、数学者たちは「わずかに過剰な数」が存在しないことを証明できずにいるのである。
ある理論が正しいかどうかは、人の意見には左右されないのである。それに代わって、数学の論理的構造が真理の審判者になった。これこそはピュタゴラスが文明になした最大の貢献だった―われわれは誤りをまぬがれない人間存在の判断を超えて、真理を見出す方法を手に入れたのである。
フェルマーの最終定理は次のように書かれている。
X(n) + Y( n) = Z( n)
この方程式はnが2より大きい場合には整数解をもたない。
フェルマーがメルセンヌ以外の人間に自分のアィディアを明かしたのは、このパスカルとの文通のときだけだった。そしてこのときの議論から、まったく新しい数学の一分野、確率論が生まれたのである。
紀元前第三千年紀のバビロニア人でさえ、この区別をつけるにはゼロが役立つことを知っていたし、彼らのアィディアを取り入れたギリシャ人は、今日の0に似た丸い記号を使っていた。しかしゼロは単に位置を示すだけでなく、それ自身として深い意味をもつのである。そのことを完全に理解したのは、ギリシャ人よりも数世紀後のインド人だった。インドの数学者たちは、ゼロが“無”を意味していることに気づいたのである。こうして“無”という抽象的概念にはじめて具体的な記号が与えられることになった。
ゲーデルが証明したのは、完全で無矛盾な数学体系を作るのは不可能だということだった。彼のアイディアは簡潔な二つの命題として表すことができる。
第一不完全性定理
公理的集合論が無矛盾ならば、証明することも反証することもできない定理が存在する。
第二不完全性定理
公理的集合論の無矛盾性を証明する構成的手続きは存在しない。
ゲーデルの第一不完全性定理が述べているのは、要するに、公理の集合としてどんなものを使おうとも、数学には答えることのできない問題が存在するということだ。完全性は決して達成できないものである。これに追い打ちをかけるように、第二不完全性定理はこう述べる。公理の集合として選んだものが矛盾をもたらさないと確信することは決してできない。つまり、無矛盾性は決して証明されないということだ。
ゲーデルの発見は、そのころ量子物理学の分野でなされた発見と似たところがある。不完全性定理の発表よりも四年前のこと、ドイツの物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクが不確定性原理を発見していた。ハイゼンベルクは、数学者が証明できる定理には根本的な限界があるように、物理学者が計測できる特質にも根源的な限界があることを示したのだった。
谷山(豊)は数学者としての短い経歴(31歳で自殺)で、多くの根本的なアイディアを出して数学に貢献した。シンポジウムで谷山が提出した問題には、彼のアイディアのなかでもっとも大きなものが含まれていた。しかしそれはあまりにも時代に先駆けていたため、谷山は自分のアイディアが数論に莫大な影響を与えるのを目にすることなく世を去った。谷山の知的想像力は悲しい形で失われ、それとともに日本の若手数学者たちは一人のリーダーを失ったのである。
谷山の死後、志村〔五郎〕はもてる力のすべてを注いで、楕円方程式とモジュラー形式の関係を厳密に理解しようとした。それから数年・・・・・・・。そうして志村は少しずつ、すべての楕円方程式が、どれかのモジュラー形式と関連しているに違いないと確信するようになった。だが、ほかの数学者たちは半信半疑だった。志村は、ある高名な数学者とのこんなやりとりを覚えている。その教授はこう問いただした。「きみの意見では、いくつかの楕円方程式はモジュラー形式に関連付けられるというんだね」
「いえ、そうではありません」志村は答えた。「いくつかの楕円方程式ではなく、すべての楕円方程式です」
「私は、良さ(goodness)の哲学というものをもっています。それは、数学はその内に良さをそなえていなければならないということです。」
志村 五郎
1986年、アンドリュー・ワイルズは、谷山=志村予想という道を通ってフェルマーの最終定理を証明できる可能性があることを知った。
問題解決のエキスパートは、相矛盾する二つの資質をそなえていなければならないー
たえまなく湧きあがる想像力と、じっくり考えるしぶとさである。
ハワード・E・イーヴズ
大事なのは、どれだけ考え抜けるかです。考えをはっきりさせようと紙に書く人もいますが、それは必ずしも必要ではありません。とくに、袋小路に入り込んでしまったり、未解決の問題にぶつかったりしたときには、定石になったような考え方は何の役にも立たないのです。新しいアイディアにたどりつくためには、長時間とてつもない集中力で問題に向かわなければならない。その問題以外のことを考えてはいけない。ただそれだけを考えるのです。それから集中を解く。すると、ふっとリラックスした瞬間が訪れます。そのとき潜在意識が働いて、新しい洞察が得られるのです。
アンドリュー・ワイルズ
しかし1988年3月8日、ワイルズは新聞の第一面を見て衝撃を受けた。その見出しは、フェルマーの最終定理が解決されたことを告げていたのである。『ワシントン・ポスト』と『ニューヨーク・タイムズ』の記事によれば、38歳になる東京都立大学の数学者、宮岡洋一が、世界一の難問に解法を見出したということだった。宮岡は、その時点ではまだ証明を論文として発表したわけではなく、ボンのマックス・プランク数学研究所で開かれた会議であらましを説明しただけであった。聴衆のなかにいた同研究所教授ドン・ザギエルの次の言葉は、参加者の楽観を伝えている。「宮岡の証明にはまったくわくわくさせられるし、何人かの者はその証明でうまくいきそうだとみているようだ。まだ決定的ではないが、今までのところ問題はない。
そのころ彼は岩澤理論と呼ばれる方法を調べ始めていた。岩澤理論は楕円方程式を分析するための手段で、ワイルズはこれをケンブリッジ大学のジョン・コーツのもとで学んでいた。
「五月も末のある朝のことでした。ナーダと子供たちは外に出かけ、私は机に向かって残った楕円方程式の族について考えていました。そして、ふとハリー・メーザの論文を眺めると、短い一文に目が止まったのです。そこには19世紀に作られた構成法のことが書いてありました。そのとき突然、コリヴァギン=フラッハ法を最後の楕円方程式の族に適用するために、その構成法が使えることに気づいたのです。私は午後までそのことを考え続け、昼食をとりに下に降りるのも忘れていました。3時か4時ごろになって、最後の問題はその方法で解決できるという確信が得られました。そろそろお茶の時間だったので、私は下に降りていきました。ナーダは私がこんなに遅く降りてきたことに驚いていたようです。私は彼女に言いましたーフェルマーの最終定理を解いたよ、と」
アンドリュー・ワイルズ
(ニュートン研究所でカール・ルービンが同僚に宛てたEメール)
日付:1993年6月21日、月曜、13:33:06
題 :ワイルズ
こんにちは。今日アンドリューが第一回目の講演をした。谷山=志村の証明の発表はなかったが、その方向に向かっており、講演はあと二回分残っている。最終的な結論は依然として明かそうとしない。
私の想像では、もしもEがQ上の楕円曲線で、E上の位数3の点についてのガロア表現が何らかの仮定を満足するなら、Eはモジュラーだという証明をしようとしているのだと思う。
これまでに彼が言ったことから考えるに、谷山=志村予想のすべてを証明しようというのではなさそうだ。これがフライ曲線に適用され、ひいてはフェルマーに言及するのかどうかはまだわからない。また報せる。
カール・ルービン
オハイオ州立大学
志村教授が自分の予想が証明されたことをはじめて知ったのは、『ニューヨーク・タイムズ』の第一面を見たときだったー「数学界長年の謎に、ついに『解けた!』の声」。友人の谷山豊の自殺から35年目のことだった。谷山=志村予想が証明されたことは、フェルマーーの最終定理が証明されたことよりもずっと大きな快挙だとみる専門家は多い。というのも、谷山=志村予想が証明されることは、ほかの多くの定理にとってとてつもなく大きな意義があるからだ。ところがジャーナリストたちはフェルマーにばかり焦点を合わせ、谷山=志村には軽く触れるだけ-あるいはまったく触れない-ことになりがちだった。
そして1993年、証明はケンブリッジで発表され、彼は英雄になった。ところが2ヶ月としないうちに、コリヴァギン=フラッハ法に欠陥のあることがわかり、それからというもの状況は悪くなる一方だった。コリヴァギン=フラッハ法を修正すべくあらゆる試みが行われたが、すべては失敗に終わった。
「ある月曜日の朝、そう、9月の19日のことです。私は机に向かってコリヴァギン=フラッハ法を吟味していました。この方法を生かせると思っていたわけではありませんが、少なくとも、なぜだめなのか説明できるだろうと。溺れる者は藁をもつかむといった心境でしたが、私は自信を取り戻したかった。すると突然、まったく不意に、信じられないような閃きがありました。コリヴァギン=フラッハ法は完全ではないけれども、これさえあれば、最初考えていた岩澤理論が使えることに気づいたのです。コリヴァギン=フラッハ法があれば、3年前に考えていたアプローチが使える。それはまるで、コリヴァギン=フラッハの灰の中から真の答えが立ち上がったようでした。」
岩澤理論は、それだけでは不十分だった。コリヴァギン=フラッハ法もそれだけでは不十分である。それぞれが相手を補い合ってはじめて完全になるのだ。その閃きの瞬間を、ワイルズは決して忘れないだろう。その瞬間について語るとき、あまりにも鮮烈な記憶にワイルズは涙ぐんだ。
「言葉にしようのない、美しい瞬間でした。とてもシンプルで、とてもエレガントで
・ ・・・・・・。どうして見落としていたのか自分でも分からなくて、信じられない思いで20分間もじっと見つめていました。それから、日中は数学科の中を歩き回り、何度も机に戻っては、それがまだそこにあることを確かめました。ええ、ちゃんとありましたよ。私は自分の気持ちを抑えられなくて、とても興奮していました。あれは私の研究人生で最も重要な瞬間です。あれほどのことはもう二度となしえないでしょう」
それにしてもフェルマーの最終定理の証明に大きな役割を果たした日本人がこれほど多いのはどうしたわけだろう。故谷山豊さん、プリンストン大学教授の志村五郎先生、岩澤理論の故岩澤健吉先生(プリンストン大学名誉教授、1998年10月死去)。また、本書では取り上げられていないが、現在UCLAの教授である肥田春三先生の仕事は、ワイルズの証明に本質的なところで寄与しているという。ひょっとすると、日本人の頭は数論向きなのか(個人的にはそうは思えないが)? 人文系の学問にくらべて言葉の壁がそれほど問題にならない数学や自然科学は、日本人の活躍しやすい分野なのか? あるいは、どの分野でも日本人が大勢活躍していて、私が知らないだけなのか? それとも単なる偶然なのか? みなさんはどう思われるだろうか。
訳者あとがき
ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで
サイモン・シン著 青木 薫訳
新潮社 2000年
今日ではコンピューターを使って完全数の探索が続けられており、2( 216090) ×(2( 216091)ー 1)という、なんと十三万桁を越える巨大な数がエウクレイデスの規則に従うことがわかっている(訳注:1999年には419万7919桁の完全数が発見された)。
ピュタゴラスは、完全数がもつパターンや性質の豊かさに魅了され、その精妙さに心服した。完全数という概念は、一見するとやさしそうにみえるかもしれないが、そこには古代ギリシャ人には解決できなかった根本的な問題が潜んでいる。たとえば、約数の和がその数自身よりも1だけ小さい数はたくさんある(それを「わずかに不足する数」と呼ぼう)。ところが、約数の和がその数自身よりも1だけ大きい数(「わずかに過剰な数」)は一つも存在しないようなのだ。ギリシャ人たちは「わずかに過剰な数」を一つも見つけられず、なぜ見つけなれないのかを説明することもできなかった。「わずかに過剰な数」が見つからないというのに、そんな数は存在しないと証明することもできない―これは実に苛立たしい状況である。「わずかに過剰な数」は存在しないことを証明したところで何の役にも立ちはしないだろうが、それは数の本質に迫る可能性をはらんだ、研究に値する問題なのだ。ピュタゴラス教団が頭を悩ませていたのはこうした問題だった。そして二千五百年の時を経た今日でも、数学者たちは「わずかに過剰な数」が存在しないことを証明できずにいるのである。
ある理論が正しいかどうかは、人の意見には左右されないのである。それに代わって、数学の論理的構造が真理の審判者になった。これこそはピュタゴラスが文明になした最大の貢献だった―われわれは誤りをまぬがれない人間存在の判断を超えて、真理を見出す方法を手に入れたのである。
フェルマーの最終定理は次のように書かれている。
X(n) + Y( n) = Z( n)
この方程式はnが2より大きい場合には整数解をもたない。
フェルマーがメルセンヌ以外の人間に自分のアィディアを明かしたのは、このパスカルとの文通のときだけだった。そしてこのときの議論から、まったく新しい数学の一分野、確率論が生まれたのである。
紀元前第三千年紀のバビロニア人でさえ、この区別をつけるにはゼロが役立つことを知っていたし、彼らのアィディアを取り入れたギリシャ人は、今日の0に似た丸い記号を使っていた。しかしゼロは単に位置を示すだけでなく、それ自身として深い意味をもつのである。そのことを完全に理解したのは、ギリシャ人よりも数世紀後のインド人だった。インドの数学者たちは、ゼロが“無”を意味していることに気づいたのである。こうして“無”という抽象的概念にはじめて具体的な記号が与えられることになった。
ゲーデルが証明したのは、完全で無矛盾な数学体系を作るのは不可能だということだった。彼のアイディアは簡潔な二つの命題として表すことができる。
第一不完全性定理
公理的集合論が無矛盾ならば、証明することも反証することもできない定理が存在する。
第二不完全性定理
公理的集合論の無矛盾性を証明する構成的手続きは存在しない。
ゲーデルの第一不完全性定理が述べているのは、要するに、公理の集合としてどんなものを使おうとも、数学には答えることのできない問題が存在するということだ。完全性は決して達成できないものである。これに追い打ちをかけるように、第二不完全性定理はこう述べる。公理の集合として選んだものが矛盾をもたらさないと確信することは決してできない。つまり、無矛盾性は決して証明されないということだ。
ゲーデルの発見は、そのころ量子物理学の分野でなされた発見と似たところがある。不完全性定理の発表よりも四年前のこと、ドイツの物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクが不確定性原理を発見していた。ハイゼンベルクは、数学者が証明できる定理には根本的な限界があるように、物理学者が計測できる特質にも根源的な限界があることを示したのだった。
谷山(豊)は数学者としての短い経歴(31歳で自殺)で、多くの根本的なアイディアを出して数学に貢献した。シンポジウムで谷山が提出した問題には、彼のアイディアのなかでもっとも大きなものが含まれていた。しかしそれはあまりにも時代に先駆けていたため、谷山は自分のアイディアが数論に莫大な影響を与えるのを目にすることなく世を去った。谷山の知的想像力は悲しい形で失われ、それとともに日本の若手数学者たちは一人のリーダーを失ったのである。
谷山の死後、志村〔五郎〕はもてる力のすべてを注いで、楕円方程式とモジュラー形式の関係を厳密に理解しようとした。それから数年・・・・・・・。そうして志村は少しずつ、すべての楕円方程式が、どれかのモジュラー形式と関連しているに違いないと確信するようになった。だが、ほかの数学者たちは半信半疑だった。志村は、ある高名な数学者とのこんなやりとりを覚えている。その教授はこう問いただした。「きみの意見では、いくつかの楕円方程式はモジュラー形式に関連付けられるというんだね」
「いえ、そうではありません」志村は答えた。「いくつかの楕円方程式ではなく、すべての楕円方程式です」
「私は、良さ(goodness)の哲学というものをもっています。それは、数学はその内に良さをそなえていなければならないということです。」
志村 五郎
1986年、アンドリュー・ワイルズは、谷山=志村予想という道を通ってフェルマーの最終定理を証明できる可能性があることを知った。
問題解決のエキスパートは、相矛盾する二つの資質をそなえていなければならないー
たえまなく湧きあがる想像力と、じっくり考えるしぶとさである。
ハワード・E・イーヴズ
大事なのは、どれだけ考え抜けるかです。考えをはっきりさせようと紙に書く人もいますが、それは必ずしも必要ではありません。とくに、袋小路に入り込んでしまったり、未解決の問題にぶつかったりしたときには、定石になったような考え方は何の役にも立たないのです。新しいアイディアにたどりつくためには、長時間とてつもない集中力で問題に向かわなければならない。その問題以外のことを考えてはいけない。ただそれだけを考えるのです。それから集中を解く。すると、ふっとリラックスした瞬間が訪れます。そのとき潜在意識が働いて、新しい洞察が得られるのです。
アンドリュー・ワイルズ
しかし1988年3月8日、ワイルズは新聞の第一面を見て衝撃を受けた。その見出しは、フェルマーの最終定理が解決されたことを告げていたのである。『ワシントン・ポスト』と『ニューヨーク・タイムズ』の記事によれば、38歳になる東京都立大学の数学者、宮岡洋一が、世界一の難問に解法を見出したということだった。宮岡は、その時点ではまだ証明を論文として発表したわけではなく、ボンのマックス・プランク数学研究所で開かれた会議であらましを説明しただけであった。聴衆のなかにいた同研究所教授ドン・ザギエルの次の言葉は、参加者の楽観を伝えている。「宮岡の証明にはまったくわくわくさせられるし、何人かの者はその証明でうまくいきそうだとみているようだ。まだ決定的ではないが、今までのところ問題はない。
そのころ彼は岩澤理論と呼ばれる方法を調べ始めていた。岩澤理論は楕円方程式を分析するための手段で、ワイルズはこれをケンブリッジ大学のジョン・コーツのもとで学んでいた。
「五月も末のある朝のことでした。ナーダと子供たちは外に出かけ、私は机に向かって残った楕円方程式の族について考えていました。そして、ふとハリー・メーザの論文を眺めると、短い一文に目が止まったのです。そこには19世紀に作られた構成法のことが書いてありました。そのとき突然、コリヴァギン=フラッハ法を最後の楕円方程式の族に適用するために、その構成法が使えることに気づいたのです。私は午後までそのことを考え続け、昼食をとりに下に降りるのも忘れていました。3時か4時ごろになって、最後の問題はその方法で解決できるという確信が得られました。そろそろお茶の時間だったので、私は下に降りていきました。ナーダは私がこんなに遅く降りてきたことに驚いていたようです。私は彼女に言いましたーフェルマーの最終定理を解いたよ、と」
アンドリュー・ワイルズ
(ニュートン研究所でカール・ルービンが同僚に宛てたEメール)
日付:1993年6月21日、月曜、13:33:06
題 :ワイルズ
こんにちは。今日アンドリューが第一回目の講演をした。谷山=志村の証明の発表はなかったが、その方向に向かっており、講演はあと二回分残っている。最終的な結論は依然として明かそうとしない。
私の想像では、もしもEがQ上の楕円曲線で、E上の位数3の点についてのガロア表現が何らかの仮定を満足するなら、Eはモジュラーだという証明をしようとしているのだと思う。
これまでに彼が言ったことから考えるに、谷山=志村予想のすべてを証明しようというのではなさそうだ。これがフライ曲線に適用され、ひいてはフェルマーに言及するのかどうかはまだわからない。また報せる。
カール・ルービン
オハイオ州立大学
志村教授が自分の予想が証明されたことをはじめて知ったのは、『ニューヨーク・タイムズ』の第一面を見たときだったー「数学界長年の謎に、ついに『解けた!』の声」。友人の谷山豊の自殺から35年目のことだった。谷山=志村予想が証明されたことは、フェルマーーの最終定理が証明されたことよりもずっと大きな快挙だとみる専門家は多い。というのも、谷山=志村予想が証明されることは、ほかの多くの定理にとってとてつもなく大きな意義があるからだ。ところがジャーナリストたちはフェルマーにばかり焦点を合わせ、谷山=志村には軽く触れるだけ-あるいはまったく触れない-ことになりがちだった。
そして1993年、証明はケンブリッジで発表され、彼は英雄になった。ところが2ヶ月としないうちに、コリヴァギン=フラッハ法に欠陥のあることがわかり、それからというもの状況は悪くなる一方だった。コリヴァギン=フラッハ法を修正すべくあらゆる試みが行われたが、すべては失敗に終わった。
「ある月曜日の朝、そう、9月の19日のことです。私は机に向かってコリヴァギン=フラッハ法を吟味していました。この方法を生かせると思っていたわけではありませんが、少なくとも、なぜだめなのか説明できるだろうと。溺れる者は藁をもつかむといった心境でしたが、私は自信を取り戻したかった。すると突然、まったく不意に、信じられないような閃きがありました。コリヴァギン=フラッハ法は完全ではないけれども、これさえあれば、最初考えていた岩澤理論が使えることに気づいたのです。コリヴァギン=フラッハ法があれば、3年前に考えていたアプローチが使える。それはまるで、コリヴァギン=フラッハの灰の中から真の答えが立ち上がったようでした。」
岩澤理論は、それだけでは不十分だった。コリヴァギン=フラッハ法もそれだけでは不十分である。それぞれが相手を補い合ってはじめて完全になるのだ。その閃きの瞬間を、ワイルズは決して忘れないだろう。その瞬間について語るとき、あまりにも鮮烈な記憶にワイルズは涙ぐんだ。
「言葉にしようのない、美しい瞬間でした。とてもシンプルで、とてもエレガントで
・ ・・・・・・。どうして見落としていたのか自分でも分からなくて、信じられない思いで20分間もじっと見つめていました。それから、日中は数学科の中を歩き回り、何度も机に戻っては、それがまだそこにあることを確かめました。ええ、ちゃんとありましたよ。私は自分の気持ちを抑えられなくて、とても興奮していました。あれは私の研究人生で最も重要な瞬間です。あれほどのことはもう二度となしえないでしょう」
それにしてもフェルマーの最終定理の証明に大きな役割を果たした日本人がこれほど多いのはどうしたわけだろう。故谷山豊さん、プリンストン大学教授の志村五郎先生、岩澤理論の故岩澤健吉先生(プリンストン大学名誉教授、1998年10月死去)。また、本書では取り上げられていないが、現在UCLAの教授である肥田春三先生の仕事は、ワイルズの証明に本質的なところで寄与しているという。ひょっとすると、日本人の頭は数論向きなのか(個人的にはそうは思えないが)? 人文系の学問にくらべて言葉の壁がそれほど問題にならない数学や自然科学は、日本人の活躍しやすい分野なのか? あるいは、どの分野でも日本人が大勢活躍していて、私が知らないだけなのか? それとも単なる偶然なのか? みなさんはどう思われるだろうか。
訳者あとがき










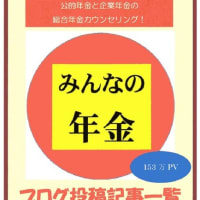






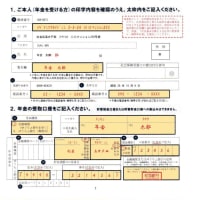

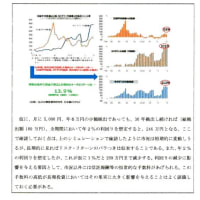
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます