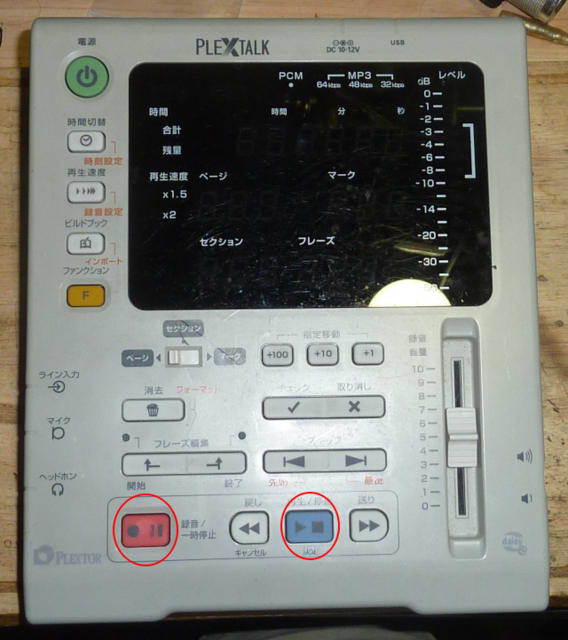BT-168Dという乾電池チェッカー。アマゾンでは200円ちょっとで売られていたこともあったようです。秋月で420円で買ったのですが、使い便利が悪く全く使わなかったので、いつ買ったかも覚えていません。

乾電池のチェックは、単3と単4の電池ケースに放電抵抗をつないだものをテスターで測っていました。電池ケースは接触抵抗を少なくするために、リン青銅板を使ったバネ接点にしているため、電池を抜き差しするのに力が必要で次第に使わなくなり、テスターで直接チェックするだけになっていました。
BT-168Dという乾電池チェッカーは電池を挟むだけでデジタル表示してくれるので便利なのですが、電池を挟む部分を下に向けないと表示が天地逆になります。
ゆるく挟んでいると電池が抜け落ちてあらぬ方向に転がっていきます。
電池を挟む部分を上にすると、オレンジの部分の抑えの方を左手で右に押すようになり、力の入れ方が不自然で、なおかつ表示が天地逆になるので、なんとも使い勝手が今ひとつでした。
写真のように横に置いて電池を挟めば安定するのですが、接点が電池に届きません。


プラスとマイナスの接点にリン青銅板をはんだ付けして接点を延長しました。電池を挟む長さが単一電池ギリギなので、あまり厚い板をはんだ付けすると、電池が挟めなくなります。0.3mm厚のリン青銅板をはんだ付けするとギリギリ大丈夫でした。


チェッカーを台の上に置いて横にして電池を挟んでも単4できちんと測定できます。

次に測定負荷が殆ど無いようなので、押しボタンを押したときだけ負荷かけた状態を図れるようにします。13Ωを並列にして6.5Ωにしました。実測6.4Ωでした。1.5Vの電池で約230mA、1.2Vで190mAの負荷になります。



無負荷で図って1.57Vの単3乾電池で、負荷ボタンを押すと1.4Vまで下がります。ちなみでテスターで無負荷の状態で測って1.54Vでした。テスターとチェッカーの無負荷の状態の誤差は0.03Vでした。