古代エジプトで地球の大きさを初めて計測した「エラトステネス」を紹介したブログのなかで、実際の地球一周を約40,000kmと書きましたが、なぜ40,000kmなのか?というお話です。
長さの基本単位について、古代のメソポタミアやエジプト、ローマなどでは、腕のひじ部分から指先までを1キュビットという単位で表していました。もっとも、その長さは地域によってまちまちでした。この時代、長さの基本としたのは、国王などの権力者の身体といわれています。今でも、ヤードやフィート、インチは、人体の長さを起源に持つ長さの単位として用いられています。
しかし、長さがまちまちでは精密な製品を製造するには不都合です。そのため、18世紀のフランスにおいて、「1キロメートルの基準が、赤道から北極までの長さの1万分の1」 として決められました。つまり、地球一周は4倍の約40,000 km、半径は円周率の2倍で割って約6,400 kmというのは計算で出せますよね。正確な数値としては、赤道周長が40,075 km、極周長が39,941 km、半径が6,357 kmとなります。このずれは当時の測量技術による誤差や、実際には赤道から北極までを測量できないので、ほぼフランス国内で測量が行われたことが理由のようです。この時の測量はダンケルクからバルセロナの距離を経線に沿って三角測量で測定し、その値を元にして計算が行われたそうです。
1799年にフランスでメートル法が公布されました。「全ての時代に、全ての人々に」というスローガンが掲げられたといいます。長さの基本単位は、時代や国を問わず使えるようになっていきました。
長さの基本単位について、古代のメソポタミアやエジプト、ローマなどでは、腕のひじ部分から指先までを1キュビットという単位で表していました。もっとも、その長さは地域によってまちまちでした。この時代、長さの基本としたのは、国王などの権力者の身体といわれています。今でも、ヤードやフィート、インチは、人体の長さを起源に持つ長さの単位として用いられています。
しかし、長さがまちまちでは精密な製品を製造するには不都合です。そのため、18世紀のフランスにおいて、「1キロメートルの基準が、赤道から北極までの長さの1万分の1」 として決められました。つまり、地球一周は4倍の約40,000 km、半径は円周率の2倍で割って約6,400 kmというのは計算で出せますよね。正確な数値としては、赤道周長が40,075 km、極周長が39,941 km、半径が6,357 kmとなります。このずれは当時の測量技術による誤差や、実際には赤道から北極までを測量できないので、ほぼフランス国内で測量が行われたことが理由のようです。この時の測量はダンケルクからバルセロナの距離を経線に沿って三角測量で測定し、その値を元にして計算が行われたそうです。
1799年にフランスでメートル法が公布されました。「全ての時代に、全ての人々に」というスローガンが掲げられたといいます。長さの基本単位は、時代や国を問わず使えるようになっていきました。














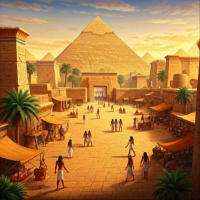
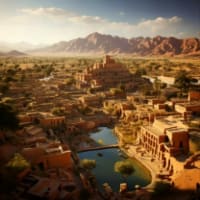



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます