長さや重さの歴史についてお話させていただいておりますが、その基準を定める制度を度量衡(どりょうこう)といいます。度は長さ、量は体積、衡は質量を表します。
古代中国の黄河流域では、紀元前1700年頃には度量衡制度があったようです。その基準は地域や時代によって異なっていましたが、紀元前221年に秦の始皇帝が統一したことで、全国的な基準が確立されました。例えば、長さの単位として「尺」が使われ、重さの単位として「斤」、体積の単位として「升」がありました。
日本の度量衡の歴史も、中国からの影響を大きく受けています。701年の大宝律令で初めて度量衡の制度が定められ、中国の制度を参考にして尺貫法が導入されました。1590年の豊臣秀吉の太閤検地では、各地で異なっていた計量単位を統一し、農地の面積や収穫量を正確に把握するための基準が整えられました。1669年には江戸の枡を京枡に統一し、計量の基準をさらに明確にしたそうです。
昔の度量衡は、その時代の権力者が徴税の基準を定めたり、大規模な建築を行ったり、天文や気象の知識に基づく権威保持のために用いられてきたようです。














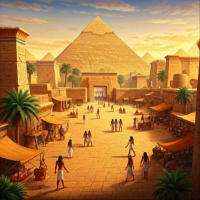
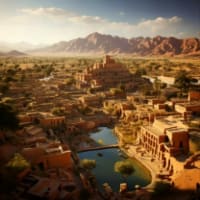



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます