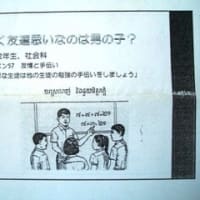みなさんこんにちは、平野です。前回は人々が子どもの権利を理解し、苦しい状況にあっても子どもの権利を守ることの大切さについて書きました。そしてその中で「人々」はおとなたちだけではないこと、そして国際子ども権利センターは子どもの権利の実現における子どもの主体的な関わりを推進してきたことにも触れました。今回はこの「おとなと子どもの両方で実現する子どもの権利」について、ライツベースアプローチ(RBA=Rights-Based Approaches)の観点も交えて紹介したいと思います。
【地域ぐるみで子どもを守る】
2005年度のプロジェクト「プレイベン州コムチャイミア郡における、児童労働および子どもの性的搾取、人身売買を防止するため学校ベースの防止ネットワークづくりとハイリスクの生徒のいる家庭の収入向上プログラム」については、SBPN(School Based Prevention Network=学校ベースの人身売買防止ネットワーク)の活躍を中心にこれまで度々ご報告してきました。国際子ども権利センターは2004年には同郡において「児童労働および子どもの性的搾取、人身売買を防止するため地域ベースの防止ネットワークづくりプログラム」を実施しました。ここでの意識啓発活動の担い手はCBPN(=Community Based Prevention Network=地域ベースの人身売買防止ネットワーク)でした。
CBPNのメンバーは、村長、警察官、教師、女性と子どもの代表などの地域の主だった人たちです。子どもの権利、人身売買問題、人身売買関連法、及びジェンダーの役割などについて研修を受けたCBPNメンバーが、地域の人々に意識啓発活動を実施しました。のべ17,189人が参加した大規模なキャンペーンのほか、メンバーは仕事や日常の場で人々に働きかけ、またレイプやDVなどの問題にも積極的に介入しました。
【子ども自身の主体的関わりを促進するSBPN】
105名のCBPNメンバーには9名の子ども代表が含まれ、また意識啓発キャンペーンに参加した17,198人のうち9,242人は子どもでした。国際子ども権利センターは、CBPNの活動に手ごたえを感じるとともに、子どもたち自身のより主体的な関わりが欠かせないと考えました。このCBPNからSBPNへの移行は、RBAの考え方に基づいています。RBAは人権の視点から開発や開発協力を行おうとするアプローチで、権利を保有する者(rights holder) の権利実現を要求する能力、およびrights holderの権利実現のため努力する責務を負う者(duty bearer)の義務を履行する能力の両方を強化するものです。子どもたちの人身売買防止においては、子どもたちがrights holderで周囲のおとなたちがduty bearerということになります。責務を負うおとなとともに、権利を保有する子どものエンパワーメントが重要だと考え、2005年度はSBPNの活動へと進んだのです。
※ RBAの概念は、ここで触れた内容だけで説明されるような単純なものではもちろんありません。興味のある方は、開発と人権の研究で知られる川村暁雄さんの論文などを参考にされることをおすすめします。
※ 写真は子どもたちと子どもたちに出稼ぎについて話を聞く郡の役人です
遠く離れていても、カンボジアの子どもたちのエンパワーメントに協力できます↓
http://jicrc.org/pc/member/index.html