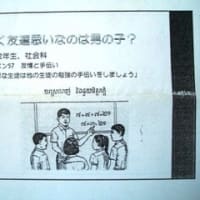みなさんこんにちは、平野です。これまで4回に渡り人身売買の実態についての記事を投稿してきました。今回は私が国際子ども権利センターカンボジア事務所での1年間で学んだそれらのことに基づいて、今後の人身売買撲滅への取り組みのあり方について、3回に分けて私なりに意見を述べさせていただきたいと思います。
【よそ者に気をつけろ、で充分か】
これまでの意識啓発活動においては「よそ者に気をつけろ」(stranger, danger)という言葉に象徴されるように、甘い話を持って村にやってくるよそ者を信用してはいけない、ということが意識啓発の基本に据えられていることが多々ありました。しかし、これまでご説明の通り、このような「まだ見ぬ異邦人」を警戒するだけでは不充分です。実際には、人身売買業者は自らは姿を現さずに村人を利用するケースが多く、親戚や友人知人隣人による就職斡旋を信用した結果、人身売買の被害に遭う人が多いからです。
それについては、もちろん意識して戦術を変えてきている団体もあり、国際子ども権利センターのパートナー団体であるHCCのスタッフも、実際にそういった身近な人々を信用した結果被害に遭っている人がいることをワークショップなどで説明しています。
【それでも出稼ぎに行く人は行く】
意識啓発活動はこれまで一定の成果を挙げてきたと思います。しかし意識啓発を受けた人々は、みな出稼ぎを止めるでしょうか。貧困と一口に言っても家族によって差がありますので、そのようなリスクをおかすくらいなら行かない、という家族も当然いるでしょうが、一方でそれでも出稼ぎに行く、あるいは子どもを行かせる、という家族も多いと思います。それだけの意識啓発を受けたのになぜ?と思われる方もいるかもしれませんが、それは以下の理由からではないかと私は考えています。
・身近で出稼ぎの成功例を見ており、具体的な被害体験を聞く機会は少ない
・たとえ人の被害体験を聞いても、自分は大丈夫だろうと思う
第一の理由ですが、人身売買による性的搾取の被害に遭うのは、出稼ぎ者の中でごく限られた人々です。その性質上許しがたい犯罪である一方、数の面で言うと(重労働低賃金だったり、辛い思いをすることも多いとしても)縫製工場なりで職を得る人が圧倒的に多いのです。また、被害に遭った人がなかなか表立って体験を話そうとはしないのも当然です。
第二の理由ですが、例えば日本で免許更新のときに飲酒運転による人身事故の映画を見せられてゾッとした人たちは、みな生涯飲酒運転を控えるでしょうか?あるいは、身近な人に騙された人の話を聞いた人は、即座に自分の身近を疑うでしょうか?誰にでも「自分は大丈夫」という考えがある上に、過酷な貧困状態にあるのですから、(確率の面で言えば)必ずしも高くない危険性に目をつぶってしまうことは非難できることではありません。
次回は、こられの現状を踏まえた上で、今後の人身売買撲滅のあり方について書かせていただきたいと思います。
※写真は前回に続き国境の風景です。古着を売りに行く人々の後のリヤカーを引く少年が見えます。
人身売買の撲滅にあなたの力を貸してください↓
http://jicrc.org/pc/member/index.html