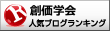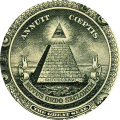以前にとある本で「法華経は単なる物語でしかない」という事を読んだことがある。確かに法華経は壮大な物語ではあるが、そこに示された内容はとても興味深いもので、それこそ日蓮が「文底秘沈」と言った事なのだろう。
法華経の如来寿量品で明かされた久遠実成の前と後で、「仏」の位置づけが大きく変化している。そもそも釈迦(ここでいう釈迦とはインド応誕の仏教の始祖)が説いた「仏」というのはどういった存在なのか。そこは原始仏教を見ていけば判ると思うが、恐らく修行の先に行きつく境涯としての仏だったのではないだろうか。それは煩悩を克服し、この世界のあらましを知悉して人々を救い導く存在と言えるかもしれない。
しかし久遠実成の釈尊というのはそういった存在ではない。この事は前にも書いているが、改めてここで書いていく。
久遠実成以前、仏とは長き渡る修行の結果として得られる境涯と言われていた。仏教では娑婆世界は苦悩が渦巻く世界で、そこから解脱し悟りを得ることでそれら苦悩から解放されると説く。だから仏教徒は出家し悟りを得る為に修行に励む。また解脱する事で輪廻転生から抜け出し二度と娑婆世界には生まれて来ないとも言われていたりする。
しかし久遠実成では、その仏とは私達の心の中の本質的な処に存在していると説かれた。文上で釈迦は五百塵点劫という人智も及ばない過去に「すでに成仏」をしていたと説き、その釈迦はこの娑婆世界に常にあって菩薩行を常に行じるなかで、時として様々な仏と出現もすれば、苦悩の中で悩み足掻く人々としても現れるという事が説かれたのである。
ではこれは具体的にどの様な事を指し示しているのか、そこについて日蓮は開目抄で「九界も無始の仏界に具し仏界も無始の九界に備りて真の十界互具百界千如一念三千なるべし」と述べているが、これはどう言った事なのだろうか。そこについて九識論の観点から考えてみたい。
仏界を説いた十界論や、そこから派生した百界千如とは境涯論であり、私達の一念(心)が生活の中でどの様に現れるのかと言う、謂わば諸法実相の「諸法」について説かれている。そこでは仏界も境涯の一つとして説かれていたが、久遠実成により仏界とは境涯ではなく「実相(全ての物事を起こす根源)」として説かれたと言っても良い。だから日蓮も開目抄において仏界と九界の具備の関係として、それこそが「真の十界互具百界千如一念三千なるべし」と述べたのだろう。法華経如来寿量品で説かれた仏界とは単なる境涯論の範疇では無かったのである。
九識論とは心の構造を重層的に現している論であり、その構造を具体的に示している。これは天台大師智顗が述べたものでり、日蓮によれば天台宗以外の法相宗などでは九識ではなく阿頼耶識を心の中核と捉える八識論であった様である。過去の記事にも書いているが、ここで九識論についておさらいをしてみようと思う。少し入り組んだ話にもなるが、少しの間お付き合い願いたい。
私達はこの世界を五感で認識している。五感とは眼・耳・鼻・舌・肌の事を指すが、九識論では単にこれら五感を受容器官とは捉えておらず、それぞれの受容器官を「識」と捉え、それぞれに受け取った情報をそのまま伝達するのではなく、選択し識別する働きがあると言う。そしてこれら五識から受け取った情報を元に、今いる状況を認識し、主体的に働いている識を「意識」と呼び、これが六識と呼ばれている。私達が「自分自身の心だ」と認識しているのはこの意識の事になる。
西欧諸国ではこの意識を永らくの間、自我の本質だと考えていた。具体的には17世紀に居た哲学者、ルネ・デカルトの方法序説に書き記されているが、全ての事象を疑っても最後に残るのは思惟する自分自身であり、この存在は疑うことは出来ないと述べた。それが「我思う故に我在り」だった。しかし19世紀に入り、西欧に於いても深層心理という事が注目され始めた。この走りとして有名な心理学者としてジームクント・フロイトやカール・グスタフ・ユングであった。この深層心理では私達が意識しているその心の奥底に、日常では認識も出来ない精神活動があり、実はそれこそが私達を突き動かしている心の本質だというものだった。
大乗仏教においては唯識派と呼ばれる中では、この無意識領域については既に5世紀頃から議論をされており、そこでは意識の奥に心の本質があると考えられていた。その結晶とも言うものがこの九識論となっている。少し横道に逸れたが話を続けていく。
九識論では先の述べたこの六識(意識)の奥には末那識というのがあると説かれている。そしてそれこそが「自我(エゴ)」の本体だと言う。私達が日常意識する、しないにかかわらず他者と分離して、独立した自分自身を感じるのはこの末那識の働きの一分である。そしてこの末那識の更に奥底にあるのが阿頼耶識(蔵識)だと言われている。阿頼耶識とは過去から自分自身の行いや記憶など、全て記録されている識と言われている。蓄積されているから「蔵の識」とも呼ばれているが、実は末那識を生み出しているのはこの阿頼耶識による「錯誤」だと言うのだ。これは一体どういう事なのだろうか。
私は以前にふと考えた事がある。それは幼稚園の頃の私と、今の私、この両者は果たして同一の存在なのだろうかという事だった。成る程、今の私は幼稚園で起きた事、体験した事で未だに鮮明に思い出す事が出来るし、その時々に心のなかで感じた事や考えた事も鮮明に思い出す事が出来る。しかしそれらは全て記憶を元にした事であって、それが完全に一貫した「私(自我)」であると言う保障は無い。いや、記憶以外に自我の一貫性を保障出来るものが一切無いという事に気が付いたのだ。しかしその記憶によって「私(自我)」として認識する存在は何なのか。そこにこそ「九識(阿摩羅識)」というものが関与しているのではないかと思ったのである。
私は過去に池田大作氏の「法華経の智慧」や「仏法と宇宙を語る」というものを貪り読んだことがあった。そこで池田氏は「自我」については大海原に発生する波の様なものであるという話をしていた。しかし法華経や日蓮の御書を読んでみる限り、実はそういった概念は存在しない。
強いて例えるのであれば、中央にハロゲンランプを置き、その周囲に様々な色のガラスを配置する。するとハロゲンライトの光はガラスに着色された色ごとに、周囲の壁には様々な色の光を投影する。ある部分はシアン系の色が見えたり、場所によっては赤や黄色などの色も投影されるだろう。場所によっては隣り合ったガラスの色が干渉しあいガラスで示された色以外の光が投影されるかもしれない。この場合、この色のついたガラスは八識の様なもので、そこから壁に投影された色の光は自我(末那識)かもしれない。個々の色はそれぞれに異なり、互いに関係しながら壁を彩っている。しかし壁に色ガラスを通して光を投影するのは、ハロゲンランプそのものが発している光であり、色のガラスでもない。ましては壁に投影されている様々な色の光は、けして独自に壁に投影されているのではなく、ハロゲンランプの光と色ガラスの合わせもった効果によってなのである。
人や生物の持つ自我もこの様な関係性の上で出現しているのではなかろうか。ここでいう色ガラスとは阿頼耶識の事であり、阿頼耶識には過去遠々劫からの行いが蓄積されている。この阿頼耶識の更に奥深くにある九識(阿摩羅識)の働きが、この阿頼耶識を通してこの娑婆世界に出現する時、その阿頼耶識に刻まれた様々な記憶により個別の違いを出すが、これが自我となる。そしてその自我の先に思惟する意識も備われば様々な受容識(五識)も生まれ、それが私達の心となりこの娑婆世界で活動しているという構造だ。
なかなか小難しく、また迂遠な話にも聞こえるだろうが、私達の自我や心を生じさせる「根源識」ともいうべきものが、法華経の如来寿量品では「久遠実成の釈尊」として示され、それが百界千如としてこの世界に様々な境涯として出現し、そこから社会(衆生世間)や環境(国土世間)も作り出されていくものだというのが一念三千。そしてこの「根源識(九識)」こそが法華経で「久遠実情の釈迦」という存在で示された仏の実の姿であって、それは十界論の様な横並びにある境涯というものではない。だから日蓮は九界即仏界、仏界即九界として御書の中でも述べていたのでり、天台大師も「九識心王真如の都」と呼んだのかもしれない。