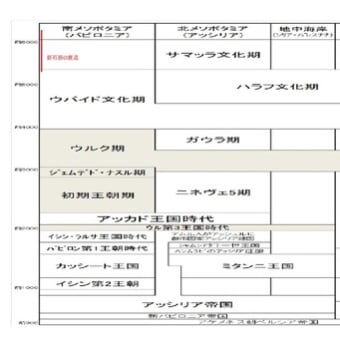補足追加しています
暦は天体の支配するものであり、支配は数として現れる、神秘数また聖なる数として認識されていた。
関東地方の縄文海進地域の太陰暦は半年一年暦 神秘数6 から始まり12までになっていた。
6波状突起口縁の土器と12波状突起の土器

一方北陸地域では半年一年暦 神秘数6 から神秘数3 になっていた。
6波状突起口縁土器と 3突起口縁土器

関東地域では二至 183日から半年一年暦 6回の月の満ち欠けをベースにして上弦と下弦の12弦にしたものと推察している。
二至二分、四立八節の太陽暦との出会いは、12弦の暦が完成してからだったものと思う。
6,12突起の土器が出来てかなり後から 3突起の土器は作られたようだから。
また12突起の土器のそれぞれの突起は、先が2山に作られていて、上弦と下弦に対応していたものと考える。
北陸地域では 6突起の土器に 3突起が加わる形で土器の口縁に突起が、作られている。
双方の土器には 4突起の土器は共通して存在しており、そこに神秘数 3が分ったことで二十四節気の暦が作られ、それから太陽暦と太陰暦のシンクロすることが理解されたものと考えている。
それにしても縄文中期には何れの地域でも太陽暦と太陰暦が並列使用できる状態になっていたと考えることが出来ると言うことは、大変なことで有ると思う。現在の暦は基本的に太陽暦であり、太陰暦はそれとは独立に存在している。
縄文時代のこの暦の状態は現代と殆ど何も変らないと云うことである。それは4500年前からと言うことになるのです。
写真はお借りしました