経済のからくり見抜く金銭教育を
金融の規制緩和が進み、今は多くの
金融機関から、様々な商品が販売されることになると、
消費者は一層公正な情報を入手し、賢明な選択をしなければならない。
そのための消費者教育や情報は公的機関だけでなく、
各種団体からも提供されているが、トラブルは一向に減らない。
特に不正に取引されて利用されている金融機関がらみ
の被害は増加する一方である。
この被害を防止するために、弁護士会などを中心に
消費者保護法が検討されているが、合せて、
小学生からの金銭教育の根本的見直しが重要ではなかろうか
消費者教育は、既に学校教育に導入され
社会人教育も盛んである。しかし、その効果がなく
苦情や被害者が増えるのはなぜだろうか。
被害者は10代から20代の若者に多い。安易に契約する
若者には消費者教育、つまり金銭教育の徹底が必要である。
日本の金銭教育は、江戸時代の身分社会に確立した
相矛盾する概念に立脚している。
つまり、武士の「灰吹きと金持ちはたまるほど汚い」
「仁者は富まず」と、商人の「人間万事金の世の中」
「地獄のさたも金次第」との隔たりである。
学校教育に採用されたのは、寺子屋以来教育を掌握してきた
武士の考え方であり、教育の場には金の威力を無視し、
卑しみ、蔑視せざるを得なかった武士階級の
思いが強く残っている。
一方、経済社会で重視されるのは
商人的発想の利益と競争である。
したがって金銭教育では、お金を稼ぐ人間と金銭との
かかわりを教えなければならない。
(朝日新聞 1998年8月28日 論壇 宮本一子 一部抜粋)
10年たった今もなお、オレオレ詐欺など
消費者を狙った悪徳商法が続いている。
マスメディアなど報道が過熱する頃には、
多くの人が被害者になっていたり、
事件が一旦収まったかと思えば、別の場所では
新たな消費者犯罪が起こる。
いたちごっこの繰り返しである。
被害を未然に防ぐには、消費者1人1人、金銭感覚に
気をつけることが必要になってくる。
ノリの場合、小学生の頃、毎月のおこづかい制ではなく
欲しいものを買うときに欲しい費用分をもらう形だった。
小学校、中学校と基本的に学校にお金は持っていく必要はなかった。
自ずと、両親のお金の使い方が自分にとっての金銭教育になった。
よく小学生3,4年の頃は、母親と中古品のゲームソフトを下見と
いって見ただけで回った思い出がある。
物は手に入らないのだけど、それでも自分の中であれもこれもいいけど
次はこれを買いたいから、お金を貯めようという風など思った。
今でも、この経験?のためか、じっくりと物を買う習慣が身についてる。
小学生に比べて、使うことの出来るお金の裁量は
大きくなったけれど、大学生になった今でも
昔のことを思い出しながら、お金を大切に扱わなければ
いけないと感じる。
金融の規制緩和が進み、今は多くの
金融機関から、様々な商品が販売されることになると、
消費者は一層公正な情報を入手し、賢明な選択をしなければならない。
そのための消費者教育や情報は公的機関だけでなく、
各種団体からも提供されているが、トラブルは一向に減らない。
特に不正に取引されて利用されている金融機関がらみ
の被害は増加する一方である。
この被害を防止するために、弁護士会などを中心に
消費者保護法が検討されているが、合せて、
小学生からの金銭教育の根本的見直しが重要ではなかろうか
消費者教育は、既に学校教育に導入され
社会人教育も盛んである。しかし、その効果がなく
苦情や被害者が増えるのはなぜだろうか。
被害者は10代から20代の若者に多い。安易に契約する
若者には消費者教育、つまり金銭教育の徹底が必要である。
日本の金銭教育は、江戸時代の身分社会に確立した
相矛盾する概念に立脚している。
つまり、武士の「灰吹きと金持ちはたまるほど汚い」
「仁者は富まず」と、商人の「人間万事金の世の中」
「地獄のさたも金次第」との隔たりである。
学校教育に採用されたのは、寺子屋以来教育を掌握してきた
武士の考え方であり、教育の場には金の威力を無視し、
卑しみ、蔑視せざるを得なかった武士階級の
思いが強く残っている。
一方、経済社会で重視されるのは
商人的発想の利益と競争である。
したがって金銭教育では、お金を稼ぐ人間と金銭との
かかわりを教えなければならない。
(朝日新聞 1998年8月28日 論壇 宮本一子 一部抜粋)
10年たった今もなお、オレオレ詐欺など
消費者を狙った悪徳商法が続いている。
マスメディアなど報道が過熱する頃には、
多くの人が被害者になっていたり、
事件が一旦収まったかと思えば、別の場所では
新たな消費者犯罪が起こる。
いたちごっこの繰り返しである。
被害を未然に防ぐには、消費者1人1人、金銭感覚に
気をつけることが必要になってくる。
ノリの場合、小学生の頃、毎月のおこづかい制ではなく
欲しいものを買うときに欲しい費用分をもらう形だった。
小学校、中学校と基本的に学校にお金は持っていく必要はなかった。
自ずと、両親のお金の使い方が自分にとっての金銭教育になった。
よく小学生3,4年の頃は、母親と中古品のゲームソフトを下見と
いって見ただけで回った思い出がある。
物は手に入らないのだけど、それでも自分の中であれもこれもいいけど
次はこれを買いたいから、お金を貯めようという風など思った。
今でも、この経験?のためか、じっくりと物を買う習慣が身についてる。
小学生に比べて、使うことの出来るお金の裁量は
大きくなったけれど、大学生になった今でも
昔のことを思い出しながら、お金を大切に扱わなければ
いけないと感じる。










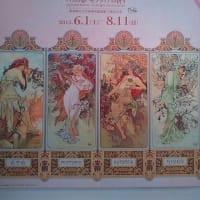









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます