図書館・語り・紙芝居・集団相手の絵本よみ・ボランティアなどについて書きます。
絵解きボランティア
紙芝居が学校から排除になった理由
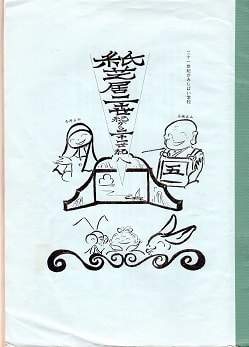
図書館で、どうして絵本の読み聞かせと紙芝居が厳密に区別される場合があるのか、その原因の一つについて書きます。
私の手元に「21世紀かみしばい学校」記録『紙芝居ー20世紀から21世紀へ』編集・発行:紙芝居文化推進協議会、発行:平成14年11月20日 があります。神奈川県立図書館OPCで検索してみましたが、見つかりませんでした。昔、私が箕面に行った時に、売られていたのか配布だったのか覚えていないのですが、その時に手に入れた記憶があります。
この冊子は、平成14年に神奈川県立図書館であった講演会の記録ですが、資料もたくさんついていて、私にとっては魅力的な冊子でしたので、本だなの隅に突っ込んでありました。講師は 加藤武郎氏(当時は童心社顧問)、橋口英二郎氏(当時は教育画劇の編集長)です。
その中で、加藤氏の講演、2ページ目の部分を要約します。
<1967年(昭和42年)に、文部省は「教材整備十カ年計画」を発表するが、この計画によってそれまで小学校の教材に入っていた紙芝居が削除されることになりました。その頃までは、小学校の教材として指定されていたのですね。舞台だけは、6学級に1台ですかね、残ったのですが、紙芝居の予算が全くなくなってしまったのです。
その後、教育画劇や童心社といった版元はもちろんのこと、たくさんの文化人などが文部省に陳情をし、紙芝居は文化としても大事、教材としてもすぐれていると訴えたのです。その結果、消耗品で買ってよいという通達が文部省から出るのですが、すでに遅きに失しました。この消耗品というのは先生たちにとっては、大変使いづらい予算なのですね。このことは、紙芝居にとって大きな打撃になったのです。(この項、橋口氏の講演記録参照) こういう通達が出ますと、小学校向けの紙芝居を出しても売れないわけで、いきおい、幼稚園・保育園向けの作品が多くなるのです。>
私がもう少し突っ込んで知りたいことは、昭和42年に削除になった理由ですが、冊子をくまなく読んで、「文部省としては、紙芝居もういいんじゃないのという姿勢だった」「担当者の単純なミス」という二つのポイントを見つけました。前者は橋口氏の推察、後者は教育画劇社長の升川氏の直言文中、豪快な校長先生が察したこと、として書かれています。
前者は、「小学生にはもう少し高レベル」の判断ですし、後者はほんとうにつまらないミスです。紙芝居業界がこれを踏まえてどうやって前に進んできたかというと、出版社は園児向けのリストを作ってPRしたし、神奈川県立図書館は手作り紙芝居コンクールを始めたし、ということですよね。
今では、小学校の教科書に、おはなしから紙芝居を作るという項目もあるくらいですから、先輩方の苦労も徐々に報われているという風に思っています。
結局、その担当者がどうして削除したかは、今となっては闇の中です。巷間言われる「紙芝居は戦争協力したから」という理由は、「その時代のメディアはみんな協力した」のですから、削除の理由にならないでしょう。それどころか戦後、ほとんどのメディアが自分の戦争責任をあいまいにしてやり過ごした中、紙芝居だけが当時の責任者の佐木秋夫が自分達の責任を語ったそうですが、
(この部分は「占領期における戦争責任論」吉田裕ー一橋大学機関リポジトリ 1991-02-01 より)
逆に見ればとても正直で誠実な行動だと思います。それを「紙芝居だけが責任がある」と のけ者にする勢力さえあったそうで、割り切れない気分になったこともありました。
昔のことゆえ、情報開示を迫るということもしなかったのでしょう。戦後20年以上経っていますが、紙芝居を何となく学校から遠ざけたいという気分が大きいように思います。当時は「子どもの権利」についてもあまり知られていませんでしたから、ミニ演劇としての特徴をやっと見つけて、その延長線上に視聴覚資料として扱った図書館の基準もなんとなくわかります。
今は、DVDも子どもの本も横並びの感覚がありますが、依然として「本だけ一段上」にしたい人の影もちらついています。「一段上」の気分・・・それは、私が図書館ボランティアを始めた昔はもっとすごかったです。今も「メディアを超える」なんて、別の市ですが図書館の講演会でやるんだものね、あんまり変わっていないのかも。
そんな時代を過ごしながら、私はこんな小さな楽しみをずっと持ち続けたような気がします。それは「昔、不運が重なって学校から排除になった子ども(紙芝居)を見つけたので、肩をたたいてその個性が伸びるようお手伝いをしたい」という楽しみ。私のような人間が、何か世の中のお役に立てるならば、そういう道を選ぶのもまた自由な選択でしょう。
もちろん、特定のものに肩入れするのでなく、絵本もおはなしも、本来の個性が光って見えてくるスタイルであれば、誰にでも受け入れられやすく、そのものが持っている本質が立ち上がってくるような気がします。
| « 「カメのえん... | 脚本 『雪の... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |
| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |




