浪江・小高原発を断念!!地元反発で、東北電が表明【女川、東通の再稼働方針は変えず】
☆同社の原発計画撤回は、
☆2003年に地元の反対などから
☆断念した巻原発(新潟県)に次いで2例目。
☆停止中の女川原発1~3号 機(宮城県女川町、石巻市)と
☆東通原発1号機(青森県東通村)の
☆再稼働を目指す方針は変えなかった。
☆運転開始後29年となる女川原発1号を含む既存の全4基で、
☆住民が納得できる形での安全対策実現のハードルは決して低くない。
☆安全対策の実施には巨額の投資が必要となる。
☆新設計画を残したままの
☆東通原発2号機建設の行方にも大きく影響する。
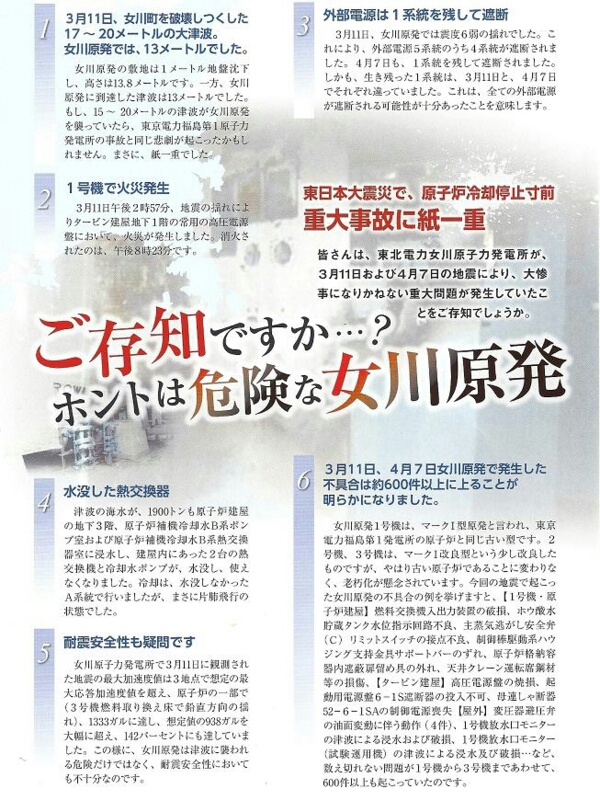 女川原発 柏崎刈羽原発 危機一髪|happyluckyのブログ
http://s.ameblo.jp/kimito39/entry-11325854884.html?
女川原発、原発再稼働認めない!!防災計画【宮城県美里町】
女川原発 柏崎刈羽原発 危機一髪|happyluckyのブログ
http://s.ameblo.jp/kimito39/entry-11325854884.html?
女川原発、原発再稼働認めない!!防災計画【宮城県美里町】
河北新報 2013年03月29日より
…………………………………………………
■福島事故、地元反発で浪江・小高原発を断念 東北電が表明
東北電力は28日、浪江・小高原発
(福島県浪江町、南相馬市)の新設計画の撤回を表 明した。
予定地が東京電力福島第1原発事故後に警戒区域となったのに加え、
原発事故で 被災した地元自治体や住民らが計画中止を求めており、
実現は不可能と判断した。原発事 故後、
大手電力事業者が原発の新設計画を取りやめるのは初めて。
東北電の海輪誠社長は同日、仙台市青葉区の本店で記者会見し
「地元の心情を踏まえる と、計画を進めるのは極めて困難。
経営として適切ではないと判断した」と述べた。
予定 地の活用は「地元と相談する」とした。
浪江・小高原発は出力82万5000キロワット。
浪江町と南相馬市小高区にまたがる 予定地
(約150ヘクタール)は原発事故後、全域が警戒区域となった。
小高区側は昨年 4月に避難指示解除準備区域になり、
浪江町側も4月1日に同区域に変わる。
地元では原発事故を受け11年12月、
浪江町議会が誘致の白紙撤回を、南相馬市議会が
計画中止要請をそれぞれ決議した。
馬場有浪江町長、桜井勝延南相馬市長も建設反対の 考えを示していた。
東北電は1968年に建設計画を発表。
用地買収は一部地権者の強い反対で完了してい なかった。
昨年3月には原発事故を踏まえ「16年度着工、21年度運転開始」
としてい た計画をいずれも「未定」とした。
同社の原発計画撤回は、2003年に地元の反対など から
断念した巻原発(新潟県)に次いで2例目。
海輪社長は運転停止中の
女川原発1~3号機(宮城県女川町、石巻市)と
東通原発1号 機(青森県東通村)について
「重要な電源で安全対策に取り組む」と述べ、
再稼働を目指す姿勢を示した。
東北電は浪江・小高原発の計画断念に伴い、
2013年3月期の連結純損益を下方修正 した。
用地取得費費をはじめ関連の特別損失
180億円を計上するなどした結果、赤字幅 は
昨年10月の公表時より50億円拡大し、
純損失は1050億円になると見込む。
◎福島の現実 当然の判断/東北電原発の存廃、さらなる「選択」も
東北電力は28日、浪江・小高原発(福島県浪江町、南相馬市)の新設計画を断念した 。
東京電力福島第1原発事故の影響を受ける地元では、計画中止を求める声が拡大してい た。
撤回は当然の判断と言えるが、結果的に電力事業者として事故後初めて、
福島県が目指す「脱原発」に協力する形となった意味は重い。
東北電の海輪誠社長は撤回の理由を
「今も(原発事故の)避難者がいる福島県の厳しい 現実を踏まえた」と説明。
創業以来の電力供給地・福島への配慮をにじませた。
一方で計画撤回はあくまで「福島固有の理由」と強調した。
停止中の女川原発1~3号 機(宮城県女川町、石巻市)と
東通原発1号機(青森県東通村)の再稼働を目指す方針は 変えなかった。
それでも東北電は浪江・小高の計画撤回に続き、
原発事業の「選択」を迫られる可能性 がある。
原発事故を教訓に原子力規制委員会が
7月に導入する原発の新安全基準は、
過酷事故に 備えた大規模な安全対策を求める方向。
運転開始後29年となる女川原発1号を含む既存 の全4基で、
住民が納得できる形での安全対策実現のハードルは決して低くない。
安全対策の実施には巨額の投資が必要となる。
新設計画を残したままの東通原発2号機建設の行方にも大きく影響する。
東北電は原発停止に伴う火力燃料費の増大で財務が悪化。
7月からの電気料金引き上げ (家庭向け平均11.41%)を政府に申請している。
原発の安全対策費を含め、料金原価となる費用には厳しい目が向けられている。
東北電には原発事業に対する丁寧な説明が求められている。 (解説=報道部・小沢邦嘉)
河北新報 2013年03月29日より
http://www.kahoku.co.jp/news/2013/03/20130329t63026.htm
河北新報 2013-03-29
浪江・小高原発断念/「現実」に即した妥当な判断
河北新報 2013-03-29
東北電力がきのう、計画していた浪江・小高原発
(福島県浪江町、南相馬市)の建設断念を正式に表明した。
同社にとっては、巻(新潟県)に次ぐ原発新設計画の断念となる。
浪江・小高の実現可能性は以前から相当に低かった。
用地取得に手間取ったのに加え、福島第1原発事故が決定的な影響を及ぼした。
地元了解を得るのがほぼ不可能になっていたことを考えれば、
いたずらに計画だけを残すのは意味がない。
思い切って軌道修正を図ったことは、適切な判断だと言える。
取得済みの広大な用地をどうするかが課題になるが、
原発事故からの地域再生を念頭に活用していくべきだ。
原子力以外の新たな電源なども検討する価値があるだろう。
地元雇用への貢献につながる。
浪江・小高の建設計画が明らかになったのは1968年だった。
東北電力の女川(宮城県女川町、石巻市)、
東京電力の福島第2(福島県楢葉町、富岡町)と
同じ60年代後半の高度成長期に当たる。
東北電力は70年から本格的な用地取得に乗り出したが、
地元地権者の反対も根強く、40年以上たっても終わっていない。
東日本大震災と原発事故は、建設をさらに遠のかせる結果になった。
重大な放射能汚染を被った福島県内で、脱原子力の動きが強まるのは当然だ。
原発事故後、浪江町と南相馬市の議会が
白紙撤回などを決議して、反対姿勢を鮮明にしていた。
さらに「県内にある全原発10基の廃炉は県民の総意」
(佐藤雄平知事)という状況であり、
新規原発が受け入れられる余地はなかった。
運転開始時期を先送りしながら計画を存続させる方法もあり得るが、
原発事故の犠牲になった福島県でやるべきことではない。
東京電力はいまだに、福島第2原発の廃炉方針を示していないが、
それは福島県民の思いを逆なでする振る舞いだ。
原発事故後の県内世論を意識してか、東北電力は昨年3月、
それまで明示していた着工と運転開始の時期を初めて「未定」という表現に変えた。
客観情勢からはもっと早く決断できたとも思えるが、
原発事故後の「地元の心情」(海輪誠社長)も
理由に断念を決めたのは正しい選択だ。
東北電力は大幅な電気料金引き上げを申請し、国の審査を受けている。
新たな負担を求める一方で、
実現可能性のない原発計画に固執することは東北の人たちにとって理解し難い。
福島第1原発から20キロ圏内にある
浪江・小高原発の予定地は来月、避難指示解除準備区域に再編される。
取得済みの土地の今後の活用方法について、
東北電力は「地元の発展に役立つ方向で自治体などと協議していく」という。
周辺の地域では、いまだに住民が戻れないでいる。
地元電力としてぜひ、被災地の生活再建に貢献できるような活用策を実現すべきだ。
河北新報 社説より2013-03-29
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2013/03/20130329s01.htm














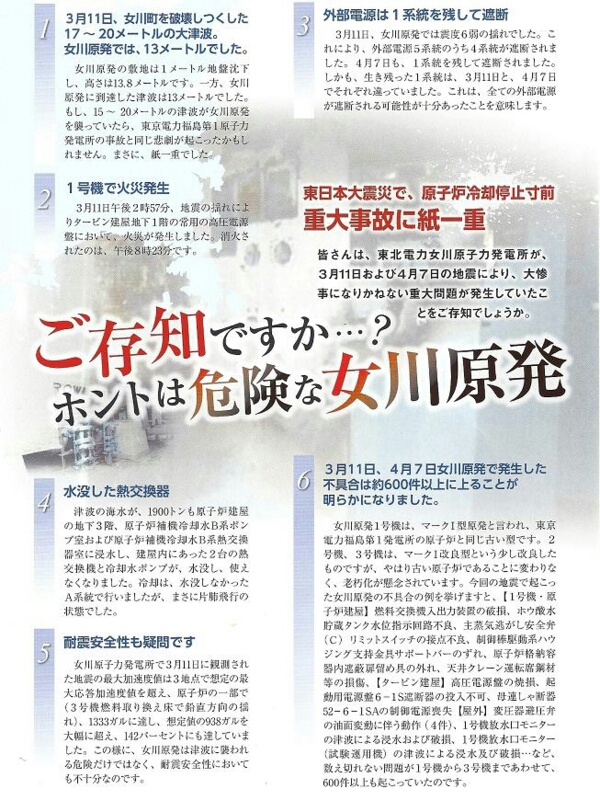
 復活 @sohnandae
復活 @sohnandae



