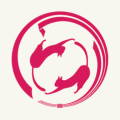ユジンはサンヒョクがソウルに帰ったあと、何度も何度も電話をかけた。しかし、サンヒョクは電話をとってくれなかった。ユジンは仕方なく
「サンヒョク、本当にごめんなさい」と留守電メッセージを残すしかなかった。

サンヒョクはユジンのメッセージを聞いて、1人暗い部屋で物思いに沈んでいた。ユジンが泣いて謝り、自分が許したとしても、問題は何も変わらない。ユジンはあの男と、週五日もドラゴンバレーで働いている。そして彼はユジンを愛していると宣言していて、ユジンは彼に惹かれている。自分は婚約者なのに、遠いソウルで指を加えて見ているしかないのだ。この10年、いやユジンに恋してからずっと、どれほど自分のものにしたくて、この腕に抱くのを待っていたのか?そしてまだ待たなければならないのか?サンヒョクは絶望感で、ユジンと話す気になれなかった。

ユジンは頭を冷やすために、夜のスキー場を散歩した。すると、ミニョンがぼんやりと座っているのが見えた。ミニョンとユジンは作りかけのカフェに腰を下ろし、目の前の薪の明かりを見つめていた。昨夜の暖炉前での出来事が自然に思い出されて、2人の口はますます重くなった。
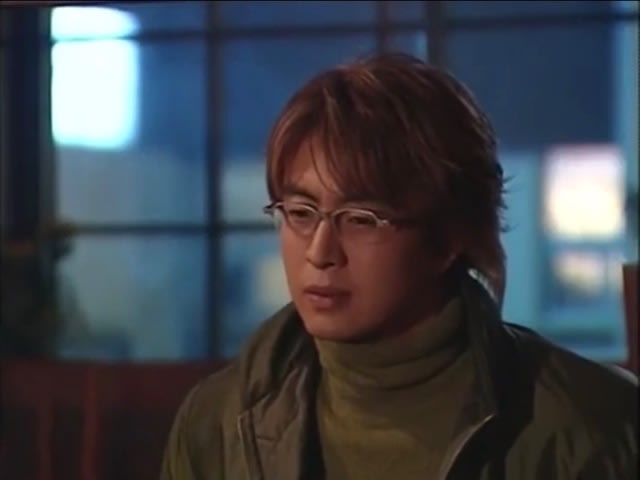
ミニョンがぽつりと話しはじめた。とても優しい慈しむような笑みを浮かべながら。
「チェリンに別れを告げました。彼女のために、傷が浅いうちに告げたほうが良いと思ったんです。でも、本当は彼女のためではなく、自分のためだったのかもしれません。僕が楽になりたかったんです。」
ユジンは黙ったまま前を見据えていた。
「サンヒョクさんの前であなたに愛してるって言ったことは謝ります。傷つける気持ちはありませんでした。僕の気持ちに変わりはありませんが、もう答えを求めることはありません。だから僕に安心して接してください。」

すると、ユジンはなんとも言えない切ない顔でミニョンを見つめた。それが何を意味するのか、ミニョンには分からなかったが、胸の奥がズキンと疼いた。

ユジンはすっと目を逸らすと、静かに立ち上がり、カフェを出て行った。そして、外からカフェを振り返り、ミニョンの寂しげな後ろ姿にまた一つ切なげなため息をついた。求めないと言われるともどかしくなり、安心しろと言われると切なくなる。ユジンの心はミニョンへの申し訳なさで張り裂けそうだった。
次の日の夕方、ミニョンがキム次長とロビーで別れると、ユジンとチョンアが話しているのが見えた。
「オンニ、忙しいときに抜けちゃってごめんね。今日の夜か、明日の朝一でもどるから。」
「ユジン、ちゃんとサンヒョクと話し合ってくるのよ。」
ユジンはサンヒョクに会いにソウルに行くつもりらしかった。ミニョンは切ない気持ちになりながらも、密かに車で駅まで送ろうと思った。
ミニョンが車に乗り込むと、ユジンがタッチの差でシャトルバスを逃したところだった。
ミニョンは車のウインドウを下げて、ターミナルまで送るとつげた。ユジンは素直にお礼を言って車に乗りこんだ。
車内は静まりかえっていた。
「ソウルまででなくて、ターミナルまで送るから怒ってるんですか?」
ミニョンが笑って言うと、ユジンも微笑んで
「いいえ」
と答えた。
「婚約者に会いに行くんですか?」
「はい」
「連絡せずに急に行くと、きっとびっくりして喜びますよ。」
ユジンはまたニッコリ微笑んだ。
正直、ユジンは自分が何をしたいのか分からなかった。サンヒョクは大切で、確かに仲直りしたかったけれど、ミニョンに惹かれている自分もいて、どうしたら良いか分からない。サンヒョクは昔から大好きで、一緒にいると安心するけれど、それはチンスクと一緒にいると安心するのと同じ種類の安らぎな気もした。わたしはサンヒョクを愛しているのだろうか?最近この疑問が頭をよぎる。でも、とにかくサンヒョクの顔を見て、仲直りしなければ、と思った。

ミニョンは親切にもソウルまでのバスチケットを買ってくれた。しかも、別れ際に優しく話した。
「ユジンさん、約束してくださいね。戻ってくるときは笑顔で帰って来ると」
ユジンは走りだしたバスの中から、小さくなっていくミニョンを見ながら、ミニョンの優しさに心が温まるのを感じた。
ミニョンは次第に小さくなっていくバスをぼんやりと見つめてため息をついた。好きな人を他の男の元に送るなんてどうかしている。気持ちとは裏腹に、そんなことしか出来ない自分がもどかしかった。本当は行くなと言いたいのに。
サンヒョクは番組の収録を終えてもぼんやりと塞ぎこんでいた。ユジンのことを考えると気が滅入って仕方ない。それなのに先輩DJのユヨルは
「おまえ、早く婚約者に会わせろよ。美人なんだろ?」などと満面の笑みで話しかけてくる。サンヒョクは黙って下を向くだけだった。
サンヒョクがコーヒーを飲もうと廊下を曲がると、そこに思わぬ人がいた。ユジンだった。かなり緊張した顔に無理矢理笑みを浮かべていた。本当は胸がトクンと高鳴って、とても嬉しかったのに、許せない気持ちが勝り、わざと冷たい顔をした。

2人は無言のまま、廊下の長椅子に座っていた。サンヒョクは黙ったまま真っ直ぐに前を見据えていた。
ユジンは顔を覗きこむようにして言った。
「ねぇ、サンヒョク。嬉しくないの?ソウルに来て真っ先にここに来たのよ。」
わざと明るい声でおどけたように話すユジン。しかし、サンヒョクの眼差しは冷たかった。
「大事な仕事はどうしたんだよ?抜けて良かったのか?」
ユジンは少し傷ついた顔をした。
「あいつに今日ここに来ることを話したのか?」
「ええ」
「僕に会うことも?」
「、、、ええ」
「あいつには何でも話す仲なんだな」
サンヒョクは鼻で笑うように話した。嫉妬と苛立ちが滲んだ顔つきだった。

ユジンは本当に申し訳なさそうに伝えた。
「サンヒョク、この前のことはごめんなさい。わたしが悪かったわ。あなたをあんな風に帰してしまうなんて。わたし、あなたに会いたくて来たのよ。ねっ。」
サンヒョクはユジンを真っ直ぐに見て、冷たい目つきで言った。
「こんなふうに突然来て、謝れば僕が許すと思ったのか?」
「サンヒョク、、、」
「なんだよ。僕らしくないと思ってるのか。僕が君に傷つけられたように、僕だって君を傷つけることが出来るんだよ。」
ユジンはどうして良いか分からなかった。でもミニョンと約束したように、笑顔だけは絶やさないように、歯を食いしばって話した。
「わたし、少し時間があるから、一緒に夕食を食べましょう?」
サンヒョクは、その媚びるような顔色をうかがうようなユジンの態度にイライラしていた。メチャクチャに傷つけてやりたかった。自分がされたように。
「仕事があるからやめておく。」
「そう、分かったわ。本当は明日帰ろうと思ったけど、今日帰れば早くつきそうだわ。」
「じゃあな、気をつけて帰れよ」
サンヒョクはユジンの顔もろくに見ずに行ってしまった。
残されたユジンはメタメタに傷つけられて、泣きたくなったがぐっと我慢してため息をついた。もとは自分が蒔いた種だ。あんなに優しいサンヒョクを怒らせるなんて、まだ時間が必要なのだ。

ユジンは帰りのバスの中で物思いにふけった。サンヒョクと自分はこんなにこじれたからもうダメだろうか。サンヒョクは許してくれないのだろうか。考えると悲しくてたまらなかった。そして、ドラゴンバレーに近づくと、化粧を直して笑顔を作った。ミニョンと約束したように。外は凍てつくような寒さでまるでユジンの心のようだった。

一方でサンヒョクはバーでひとりウイスキーを片手に、煙草をくゆらせていた。さっきのユジンへの態度に後悔ばかりが押し寄せた。ぎゅっと抱きしめて「わざわざ来てくれてありがとう。嬉しいよ。」と言えば良かったのに、踏み躙られたプライドがそうさせなかった。ウイスキーは不味くて、杯だけがどんどん進んで、やがて悪酔いしてきた。
サンヒョクはバーを出て、ふらつきながらいつかユジンと一緒に話したときのように、一人で花壇に登って、両手でバランスをとって歩いた。しかし、あの日のように、バランスを崩しても、横で手をとって微笑むユジンの姿はなかった。
サンヒョクはユジンの留守電に向かってメッセージを入れた。
「ユジン、、、さっきはごめん。本当は会いに来てくれてすごく嬉しかったのに、酷いこと言っちゃって。ほんと、ごめん、、、。僕が悪かった」

しかし、少し考えてメッセージを消去した。そんな留守電を残しても虚しいだけだった。サンヒョクはいつまでもグレーの空を眺めていた。涙がいつまでも頬をつたっていた。