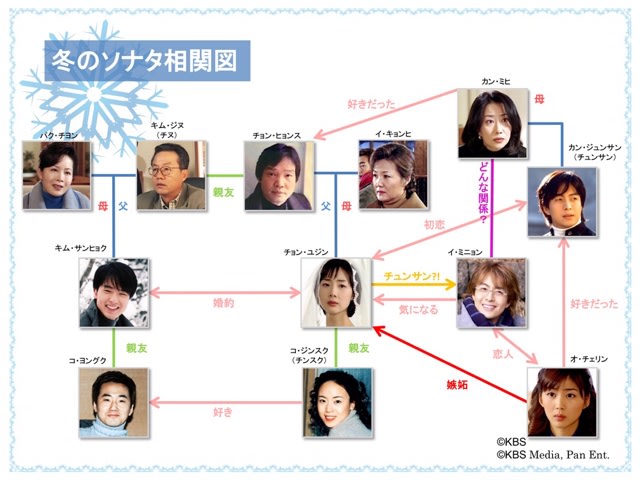

ユジンは久しぶりに、父親の墓を訪れていた。父ヒョンスの墓は春川を望む川のほとりの山の上に会った。ユジンはこんもりとした土葬の墓を前にしゃがみこんでいた。どうしても亡き父親と話がしたくて、実家から足を運んだのだった。この日は空が曇っており、遠くの景色は霞がかかったようにくすんで見えた。

「アッパ(お父さん)私ね、夢を見たの。チュンサンと二人でここにきてね、お父さんにあいさつするの。二人で仲良くお酒を1配ずつ飲んで、仲睦まじい姿を見せつけるの。そしてずっと一緒にずっと一緒に、、、。私が彼を好きになったのは、初めから私たち、ひとつだったからなんだね。そうでしょう?お父さん。だから、わたし、もう夢を見ちゃいけないんだよね。いけないでしょう?お父さん。」

ユジンは父親の前でひとしきり涙を流すと、山道をとぼとぼと歩いて降りて行った。ぼんやりと目の前を歩いてくるカップルを見ていると、ふいにそれが自分とチュンサンに見えた。



「チュンサン、さようなら」
ユジンは春川の山並みに別れを告げた。

ユジンはバスでソウルに戻ると、その足でサンヒョクの会社を訪ねた。昼休みのサンヒョクを捕まえると、サンヒョクは嬉しそうに目を細めて「久しぶり」と言った。二人は近くの定食屋に向かい、温かいチゲ鍋を食べながら話をした。
「会社を辞める?」
サンヒョクはびっくりした顔でユジンを見つめた。
「うん、最近は全然仕事がはかどらなくて。こんな調子だとみんなに迷惑をかけちゃうわ。」
ユジンは正直、チュンサンとの思い出がたくさんある会社で、これ以上仕事をすることができなかったのだ。しかも、ソウルの建築業界は狭いので、図らずともまた出会う機会もあるだろう。それに耐える自信はなかった。いっそのこと、誰も知らないうんと遠くに行ってしまいたかった。すると、サンヒョクは優しく笑って言った。
「疲れただろうから、しばらくゆっくりしなよ。今まで頑張って働いてきたんだから。」
しかし、ユジンがサンヒョクを誘った理由はそれだけではなかったのだった。

「サンヒョク、お願いがあるの。チュンサンに会わせてほしいの。私が連絡しても出てくれないし。あなたから連絡してもらえないかしら?」
やっぱり、という表情でサンヒョクはため息をついた。「いやだよ。それは断る。だって、君がこれ以上傷つくのを見たくないから。僕がそばについててやるから、あいつのことは忘れてくれ。」
しかしユジンはかたくなだった。
「迷惑はかけないわ。ただ、チュンサンに伝えたいことがあるだけなの。あなたにはいつも頼み事ばかりで悪いけど、チュンサンに伝えてほしいの。最後に伝えたいことがあると。ねっ、お願い。」

サンヒョクは今まで一度もユジンの頼みごとを断ったことがなかった。いや、断れなかった。またしても今回だけ、と言うユジンを前にサンヒョクは渋々とうなずくのだった。おいしそうなチゲ鍋はすっかり不味くなってしまったのだった。

その頃、チュンサンは会社のマルシアンでキム次長と話をしていた。チュンサンはアメリカに帰国するために、スキー場のリノベーションを他社に引き継ぐか否かで迷っている。すると、次長は自分が全て引き継ぐから、と話し始めた。チュンサンは無責任なのは分かっていたが、これ以上ユジンのいる韓国にはいたくなかった。ユジンと彼女との思い出を忘れてしまいたかった。チュンサンが知らず知らずのうちに顔を曇らせていると、キム次長が口を開いた。

「お前とユジンさん、いつまで苦しむのかな?時々見てると辛くなるぞ。」

次長はぼそりとつぶやいて去って行った。すると突然、チュンサンの携帯が鳴った。それはサンヒョクからの着信だった。






















