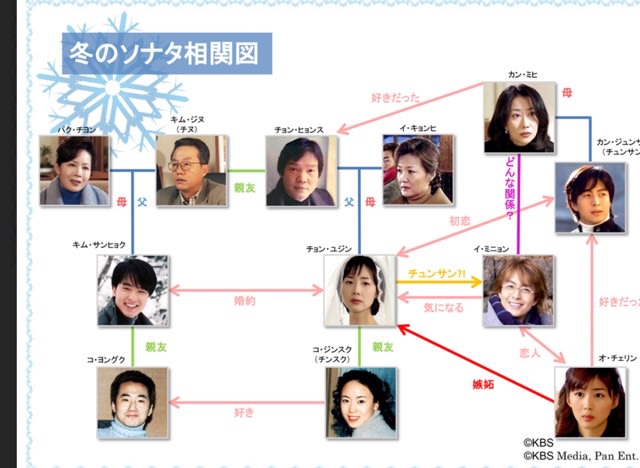
チュンサンが電話をとると、相手はサンヒョクだった。サンヒョクはユジンが自分に会いに来たことを話した。
「そうか、彼女、会いに行ったんだな。ユジンは大丈夫だったか?」
サンヒョクはユジンがチュンサンに会いたいといったことを告げた。
「会いたいって?話したいことがある?、、、、わかったよ。」
チュンサンは短い電話を終えると、フッとため息をつくのだった。

その数日後、ユジンはポラリスで自分の荷物をまとめていた。会社の同僚に別れの挨拶をするために、珍しく黒いスーツを着ている。先輩のチョンアが慌てて駆け込んできた。
「ちょっとユジン、どういうつもり?まさかほんとに?」
チョンアは困った顔で天を仰いだ。
ユジンは箱に荷物を入れながら話し始めた。
「クビになる前に自分で荷物をまとめているのよ。」
「ちょっとユジン!」
「オンニ、本当にごめんなさい。自分一人でじっくり考えなおしたいの。これからどうしたいか」
そういうと、一つの建物の模型を目の前に出してきた。
「オンニ、この模型覚えてる?これは私が初めて設計した家なよ。でも、結局は費用が掛かりすぎて、不可能だって言われた。」
「覚えてるよ。それがどうしたの?」
「私ね、不可能なことはやめようと思って。もうどうにもならないことはあきらめるわ」

さすがのチョンアも、ユジンが模型のことを言っているのではなくて、チュンサンのことをあきらめるのだということはわかった。チョンアはユジンの気持ちを考えると、一度会社を辞めてゆっくり休むのもよいかもしれないと思った。知り合ってからユジンが誰かを一身に愛して傷つくのを見たことがなかったから。そして、傷つきながらもこんなに幸せそうな彼女を見たこともなかったから。今、ユジンはまた以前の物憂げな女性に戻ってしまった。そんな彼女が再び幸せになるには、もう一度情熱を注げるものを見つけるのがよい気がしたのだった。
ユジンは家の模型をきれいにラッピングして大事そうに抱えて事務所を出て行った。そんな彼女をじっと見つめる男性がいた。それはチュンサンだった。久しぶりに見るユジンはだいぶやせてしまって、もともと色白だった肌が、透き通るように白くなり、今にも消えてしまいそうなほど儚げだった。それを見るだけで、心は暗く沈んでしまう。チュンサンは近くに車を止めると、ユジンの跡をそっとつけて待ち合わせの公園に向うのだった。

ユジンは冬の公園でベンチに座っていた。子供たちがピカピカの遊具で無邪気に遊んでいるのを、ぼんやりと眺めていた。すると、一人の少年が、ユジンの模型に興味をもって触り始めた。
「僕、それほしい?」
「いいの?」少年は無垢な目でユジンを見つめている。
「うん、森の中にある家なの。いいから持ってって。」
「おばさんはいいの?」
「おばさん?!お姉さんて言ってよ。わたしはね、この家は心の中に建てたからもういいの。」
しかし少年はユジンの顔と模型を交互に眺めた後
「やっぱりいらないや」
と言って駆け出して行った。

残されたユジンはため息をつきながらまたとぼとぼと歩きだしたが、チュンサンの姿を見て足を止めた。久しぶりに会うチュンサンは疲れた表情だったけれど、前と変わらず優しい笑みをたたえていた。明るいブラウンに染められた髪が昼の光に照らされて、きらきらと輝いていた。初めてバスの中で出会ったときに、制服姿のチュンサンを見て『キレイだ』と思ったことを思い出して、心がドクンと波打って震えた。
ふたりは無言のまま近くの備え付けのテーブルに向かい合って座った。先に口を開いたのはユジンだった。
「元気だった?」

チュンサンは何も言わずにまぶしそうにユジンを眺めてうなづくと、目の前に置かれた模型に手を伸ばした。
「これ、面白いでしょ?持ってく?」
チュンサンはそれには答えずにうつむきながら話し始めた。
「ユジン、ごめんな。君にはどうしても知られたくなかったのに、やっぱり隠し切れなかった。」

しかし、ユジンはチュンサンをまっすぐに見て言った。
「ほんとね。隠し通してほしかったわ。いっそのこと知らないまま別れたかったのに。」

するとチュンサンは愛おしそうな目でユジン見つめた。
「君は大丈夫?」
しかしユジンは答えずに言った。
「あなたは?」
今度もまたチュンサンは何も答えずにつらそうな顔で目を伏せてしまう。二人の間に微妙な空気が漂っていた。

それでも、ユジンはチュンサンをまっすぐ見ることをやめなかった。今日、絶対に伝えたいことがあったのだから。18歳の時に言えなかった言葉を贈りたい。ミニョンには伝えたことがあったけれど、チュンサンに対して口にするのは初めてだった。
「チュンサン、愛してる」
チュンサンはハッと顔を上げてユジンをじっと見つめた。ユジンはどこまでもまっすぐで無垢な目でチュンサンを見ていた。
「今までもずっと愛してたし、これからもずっと愛してる。でもこれっていけないことなのかな?だめなことなのかな?」

はじめは悲しい目でユジンを見つめていたチュンサンも、フッと優しい顔になって言った。
「そんなことないよ」
「そうだよね。全然悪くないよね。わたし、悪くないと思うことにする。私たちの愛は見苦しくもないし恥ずかしくもないわ。胸を張って言える。どれだけときめいて胸が苦しくなったか。どれだけ辛くて切なかったか。わたしにとって、どれも大切な記憶なの。私はあなたを本当に愛してたのよ。それは絶対に覚えておいてね。約束よ。わたしは一つ残らず全部覚えておくから。記憶だけは私のもの。だから、あなとも私のことを忘れないでね。一つ残らず覚えておいて。わたしは、一生あなたとの記憶と生きていくから。ね?」

そういうと、ユジンはハラハラと声も上げずに泣きだした。そしてチュンサンもまた、悲しそうな目つきでユジンをしっかりと見つめて言った。
「そうだね。絶対に覚えておくよ。何があっても君を忘れないから。絶対に」

そういうと、チュンサンもまた声を上げずにはらはらと涙をこぼすのだった。チュンサンは、二人の最後の誓いだから、これだけは何があっても破るまい、それだけがいまユジンのためにできるたった一つの約束だと思っていた。
ユジンもチュンサンも泣き笑いの顔で言った。
「ありがとう、本当にありがとう、チュンサン」
「僕もだよ。ありがとう、ユジン」

二人にはもう何も言うことはなった。チュンサンはユジンが作った模型をそっと大事に抱えると、ゆっくりと立ち上がった。二人は一歩一歩をかみしめるように公園の外まで歩いてきた。
ユジンは言った。

「チュンサン、一つだけ約束して。私たち、振り返らずに別れましょう。最後の記憶が後姿なんて絶対に嫌なの」
「わかったよ」
「本当よ?絶対に振り返っちゃだめだからね。」


そういうと、ユジンはゆっくりと背を向けて歩き始めた。チュンサンも同時に後ろを向いて歩き始めた。二人はそれぞれの道を真っ直ぐに見つめて、泣きながら心の中で別れをつげた。暖かな風が二人の間を吹き抜けていった。春はもうそこまできていた。























