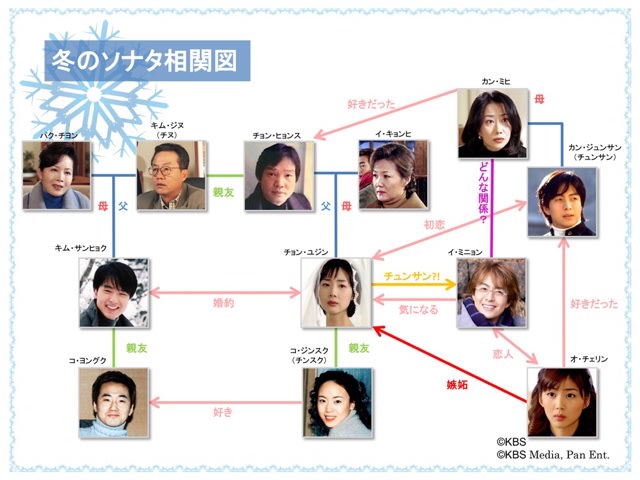
春川を一人で訪れたミニョンは、チュンサンが数か月の間だけ通った春川高校に足を延ばしてみることにした。高校に行けば、記憶が戻るかもしれない、少しでもチュンサンの心を理解したい、と願っていた。

一方でユジンも、チュンサンの生徒記録を見るために春川高校を訪れていた。久しぶりの高校を目の前に、ユジンは憂鬱そうな顔をした。自分はパンドラの箱を開けるのかもしれない、と漠然とした不安を感じていた。そしてゆっくりと校門をくぐると、校舎に続く坂道を登り始めた。ユジンは、カガメルことパク先生が放送室にいると聞き、そちらに向かった。放送室に入るのは、前回サンヒョクとの婚約式をやった時に、チェリンの彼氏としてミニョンに会った時以来だった。

一方でミニョンは物珍しそうに校舎を眺めた。前回チェリンに連れられてきたときには感じなかった懐かしさを感じる。赤煉瓦の校舎、誰もいない教室、そして焼却炉。チュンサンの家で大切にしまわれていた手紙に書いてあった。『焼却炉であなたが降らせてくれた雪、とっても面白かった。落ち葉が雪なんて素敵なアイデアね。ありがとう。』二人の甘い思い出に、思い出せなくても、思わず顔がほころんだ。

ユジンはそっと放送室に入った。すると妹のヒジンがゴムまりのように飛びついてきた。「オンニ!(お姉ちゃん)」硬い表情だったユジンも、思わず顔がほころんだ。ヒジンは屈託のない笑顔で、放送部員たちに姉を紹介した。
「みんな、うちのお姉ちゃんよ。うちの学校出身で、しかも放送部なの!よろしくね。今日は結婚式の招待状を先生に届けに来たんだって。」
生徒たちは無邪気にユジンを取り囲んで話し始めた。皆口々にユジンがきれいだとか、カガメルは昔から意地悪かとか、放送部の顧問だったのかと聞いてきた。そしてヒジンが言った。
「お姉ちゃん、あいつ厳しくて困るんだけど。ねえ、あの先生を感動させる方法を教えてよ。」
するとユジンは生き生きとした表情で話し始めた。
「カガメルはああ見えても繊細なの。詩が大好きで、特に愛の詩が大好きだから、なんでも詩みたいに朗読すると喜ぶのよ。ただのニュースでも、心を込めて詩みたいに読むと、感動して泣いちゃうんだから。」
みんなは大喜びで盛り上がった。そして、一人の女子生徒が、試しにマイクをオンにして、今から愛の詩を読んでみると言い出した。ユジンは一緒に聞いていくことになった。それはサラ・ディズデールという詩人の『初恋』という詩だった。

愛しい眼差しで振り返って 後ろを付いていく私を確かめて下さい
あなたの愛で 私を奮い立たせて下さい
たとえ陽が照り雨風が吹き付けても そよ風が燕を 舞い上がらせるように 私たちが遠くへ飛んでいけるようにして下さい ・・・・・
けれど 初恋がまた私を呼んだら どうしたらいいの
りりしい海が波を包むように 私をしっかり抱き締めて下さい
丘にひっそりと建つあなたの家まで 私を遠く連れていって下さい
安らぎで屋根を繋ぎ 愛でドアを閉めて下さい ・・・・・
けれど 初恋がまた私を呼んだら どうしたらいいの?

ユジンはその詩を感慨深い面持ちで聞いていた。焼却炉でチュンサンと二人で落ち葉を燃やしたこと、雪に見立てて降らせてくれたこと、ピアノ講堂で『初めて』を弾いてくれたこと、一つ一つの思い出を鮮明に思い出していた。そして、そっと部屋を出ると思い出の場所へと歩き始めた。

そのころ、ミニョンもひとり、ピアノ講堂でピアノを弾いていた。一度もピアノを弾いた記憶のないミニョンだったが、いざピアノに触ると、さっきテープでチュンサンが弾いていた『初めて』を、すらすら弾くことができた。記憶の中からメロディだけが沸きあがってくるような不思議な感覚だった。そしてさっき読んだユジンの手紙を思い出した。『チュンサン、さっき講堂で引いてくれた曲、”初めて”だったよね。ほんとに上手だった。ちょっとだけかっこよく見えたわ。見とれそうになっちゃった。』そんなミニョンの耳にも『初恋』の詩が聞こえてきた。ミニョンもまたその詩を知らなかったが、心を打たれた表情でじっと耳を澄ませるのだった。

ミニョンは講堂を出た後、ゆっくりと高校を後にした。やはり記憶は戻らなかったが、それでも頭の奥底で、何かがうごめくのを感じていた。今のミニョンにはそれで十分だった。そしてユジンもまたピアノを見に講堂を訪れた。真っ暗な部屋の中で、一つだけ空いたカーテンの日の光を浴びて、あの日のようにピアノが置かれていた。ピアノは黒く美しく輝いていた。ユジンは導かれるようにピアノの前に座った。そして鍵盤に触ろうとしてふと前を見た。ピカピカのピアノの表面に映るのは、あの日の二人ではなく、悲しそうな顔をした10年後の自分の姿だった。ユジンは先ほどの詩を思い出していた。

「けれど 初恋がまた私を呼んだら どうしたらいいの?」
ひとりでにハラハラと涙をこぼれてしまう。そして、ピアノを弾くのをあきらめて、ふたを静かに閉めて立ち上がった。心が乱れてしまい、カガメルに招待状を渡すこともなく、静かに高校を去っていくのだった。
こうして二人は同じ場所にいながら、一度も顔を合わせることなく高校を後にした。
























