こんにちは。新型コロナウイルスになったことで、久しぶりに時間があり、冬のソナタを7回分書けました。外部からのアクセスが多いようで、一から読んでいただいている方もおり、光栄です。高校生のときが一番楽しく書けたのですが、時系列がぐちゃぐちゃになってるので、修正して番号をつけてアップし直しました。創作バージョンは別にして、アップしてあります。それではよろしくお願いします。
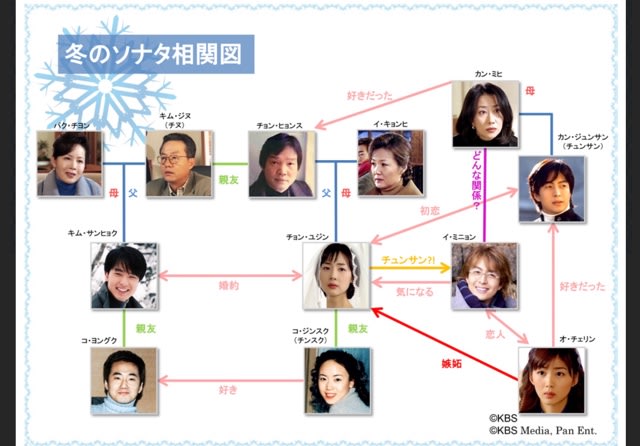
チェリンは猛スピードで春川高校に車を飛ばた。そしてさっそくカガメル(ゴリラ)先生を捕まえて、ユジンと既に話したのか、と聞いた。もっともカガメルときたら、まんまるな目でチェリンを見つめた挙句、「お前誰だっけ?」という始末だったが。チェリンはよくも美貌と知性と家系では右に出るものがいない自分を忘れるなんて、と内心ムッとしたが、ぐっと気持ちを抑えて笑みを浮かべていた。するとそこに、ふらりとユジンが現れた。ユジンは疲れた様子だったが、チェリンを見るとにっこりと笑った。カガメルも、ユジンを見てご満悦の様子だった。何しろ、彼女はカガメルお気に入りの優等生のキムサンヒョクともうすぐ結婚するのだから。チェリンは目を細めて厳しい顔でユジンを見たが、気を取り直してニッコリと微笑んだ。

「先生、今日は結婚のご報告と調べ物があって来たんです。」
チェリンの顔色が変わった。
「おもしろいな、久しぶりなのに。この前サンヒョクもここに来たぞ。」
今度はユジンが驚いてカガメルを見つめる。カガメルがなぜサンヒョクが訪ねてきたかを話し始めようとすると、チェリンが遮って、いかにカガメルが昔と変わらずにステキか、と延々と誉めそやした。ユジンは訳もわからずにポカンとしているし、カガメルはますますご機嫌な顔になった。やがてカガメルはちょっと用事があるから、待っていてほしい、結婚式は行くからな、と言い始めた。ユジンは先生も忙しいのだ、と遠慮して今日はいったん帰ることにした。カガメルは歩き始めたがくるりと後ろを向いて笑った。
「チョンユジン!自分の結婚式に遅刻するなよ。お前は遅刻の女王だからなぁ。」
これには暗い顔をしていたユジンも笑ってしまった。カガメルと学校だけは今も昔も変わらない。何となくほっとしてしまったのだ。
ユジンとチェリンが歩いていると、チェリンは調べ物の中身について、根掘り葉掘り聞き始めた。しかし、ユジンははぐらかして教えようとしない。チェリンは確かにユジンがソウルに帰るまで見届けないと安心できなかった。ソウルまで乗せて行くと言っても、いや、まずは実家に寄るというユジンに、無理矢理実家まで送ると言い張って、二人はユジンの実家に向かった。
ユジンの実家の前にはサンヒョクの車が止まっていた。チェリンはそれを見るとほっとした。これでサンヒョクにバトンタッチできる。チェリンはそそくさと帰って行った。

突然のサンヒョクの登場に、またまた驚いているユジンだったが、母に挨拶を済ませると、サンヒョクの車でソウルに向かった。ユジンは何もかもが負に落ちなくて、サンヒョクに聞いた。
「サンヒョクは最近高校にきたんでしょう?どうして?」
しかし、サンヒョクはカガメルに招待状を渡したのだ、と笑って言うばかりだった。
「この前、中学の友達に会いに行ったとき?わたしがカンミヒさんの話をしたら、あなた慌てて行っちゃったじゃない?あの時?」
しかし、サンヒョクはそんなことあった?と言って、あとはモゴモゴと適当な事を言うばかりで、話にならなかった。ユジンはどうにも納得出来なくて、そんなサンヒョクを不審な目で見つめていた。二人の道中は非常に気まずいものになってしまった。
やがて日もとっぷりと暮れた頃、車はソウルのアパートに着いた。ユジンは心ここに在らず、と言う表情でさよならを言うとアパートに入って行った。それを見届けたサンヒョクはほっとした表情で車をスタートさせるのだった。

しかし、ユジンはサンヒョクが去ったのを確認して、アパートを飛び出すと、大通りまで走った。そして、さっきとは打って変わって厳しい表情でタクシーを捕まえた。ユジンはミニョンが定泊しているホテルに向かっていた。やはり、もう一度だけミニョンに会って確かめたかった。ミニョンはチュンサンなのかと。サンヒョクは何かを隠しているようだし、今日のチェリンの様子もおかしかった。カガメルにも聞くチャンスがなかったし、もはや本人に確かめるしかないと思っていた。ユジンはミニョンの部屋の前に立つと、長い時間インターフォンを押そうかと悩んでいた。しかし、あと数センチ先のボタンを押す勇気が持てなかった。ここまで来て自分は何をしているのか?必死の思いで振り解いたミニョンの腕を取り戻したいと言うのか?それはあまりにも無責任な気がした。

ユジンはすんでのところで指を引っ込めて、踵を返した。そして、エレベーターの中で崩れ落ちて、涙を流していた。やはり、自分にはサンヒョクを捨ててミニョンのもとに行く覚悟は出来なかったのだ。そんな自分が不甲斐なくて、行き先のロビー階のボタンも押さずに、いつまでも泣いているのだった。

その頃ミニョンもまた、ユジンから返されたポラリスのネックレスを見つめていた。今日が韓国最後の夜だった。ユジンへの想いは全てスーツケースに入れて、この国に置いて行こう、明後日の今頃はアメリカで新しい仕事と生活が待っている、何よりミヒが向こうで待っている、そう思い込もうとしても、寂しくて悲しくて、お酒が手放せなかった。
こうして二人の眠れない長い夜は少しずつ更けていくのだった。


























