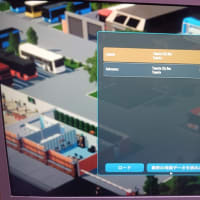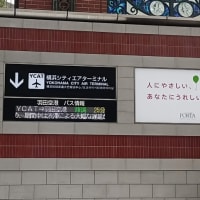<前回から続く>
さて資料展示コーナーを見学した後は、いよいよお待ちかね?の地下の採掘坑道に入ります。

資料館の建物の中に坑道の入口ができています。

地下採掘場跡のうち実際に入って見学できるのは一部分だけ。この地図で見ると大半は立ち入り禁止区域で物足りなく感じてしまいますが・・・。
まずは下り階段をずんずん降りていきます。

階段の途中から目の前に巨大な地下空間が広がります。当然ながら地下は携帯電話は圏外。
地下の温度は12度程度ですが30度越えの暑い中にいたからか持参のカーディガンを着ない状態でも寒さ感じないです。冷房が強くかかってる室内ぐらいなイメージ
地下での撮影は立ち止まることでの混雑や危険防止のため、狭い通路では不可。広い場所でOKだそう。
私の前の組が歩くのが遅い人だったので余裕を見ながらゆっくり進めました。

ところどころ横方向に大きな空間が現れます

さらに奥に向かい進みます。通路は順路が作ってあって行きと帰りで仕切られています。右側の壁に柵が見えますが、この場所も後で回ります。
地下空間内の湿度はかなり高め。手すりが湿っているばしょがあったり、たまに雨漏りのようにポタッポタッと雫が落ちてくる場所もあります

以前に假屋崎省吾氏の展覧会を開催した時の名残だそうで一部の作品が坑内に残されて展示されています。

上を見ると明り取り?の竪穴が掘られている場所も。

壁に見える横方向のシマシマは手掘りの後だそう。

奥が明るい場所も・・出口に通じる空間??

見学できる部分だけでも地下空間はとにかく広くて圧倒されます。
これはもう百聞は一見に如かずとしか言いようがないですね

壁に縦線が掘られている場所も。昭和35年に採掘が完全機械化されて、この縦線は機械化初期のものだそう。
これはこれでこの模様も幾何学的で古代遺跡かなにかのような雰囲気があります。溝に指を入れてみたものの、かなり深そう。
奥のエリアにはスタッフがいて写真撮影サービスのようなものをやってましたね・・。

壁に掘られた採掘当時使われていた階段も発見!
残念ながらこの階段は通れません。

教会のようになっている場所も発見。遺跡のようにみえますね

先ほど通ってきた場所が見えます。上から見るとさらにこの空間の広さに圧倒されますね。

展示スペースのようになっていてパネルなどが展示されている場所も。
映画やドラマの撮影にもいろいろ使われていて、その際の光景なども紹介されています。他にワインや米の貯蔵場所としても使われていたこともあるそう

採掘していた当時の機器や規格で切り出された石が展示されている一角も。
最初は「一部分しか見学出来たいのか~」と少々残念に思ったものの、見学可能エリアを一回りしただけでも、巨大な地下空間に圧倒されますね。まさに百聞は一見に如かず、映像や写真では凄さが伝わらないと思うので機会があれば一度は訪問をお勧めしたいですね。
解説によれば地下空間の温度は夏場は12度程度、冬は5度程度までさがるようです。この日は30度超えの猛暑の日でしたが天然の冷房?冷蔵庫を味われるので、こういう夏の暑い日に訪れるのもいいかも??
ただ冬場だと石の華という石に含まれるゼオライトが乾燥して結晶となって現れる現象がみれるそうで冬の楽しみもあるよう。
<次回に続く>
【PR】楽天市場で「大谷石」を検索
2021/9/10 11:12(JST)