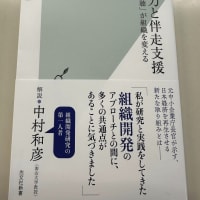kurogenkokuです。
465冊目は・・・。
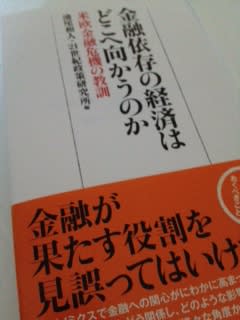
金融依存の経済はどこへ向かうのか
池尾和人+21世紀政策研究所 編 日経プレミアシリーズ
金融依存というテーマについては、リフレ派の書籍も、本書のような金融依存に否定的な書籍もいろいろ読んできたのですが、そのどっちがいいとか悪いとかいう議論は抜きにして。
本書を読んで勉強になったと思うのは「第2章」と「第4章」。
「第2章」では、グリーンスパンの回顧録から中央銀行の金融政策に対してややもすると懐疑的な一面が読み取れます。
***********************
多くのエコノミストは、過去十年にわたって、世界的にインフレが抑制されてきた主要な要因が、中央銀行の金融政策にあると認めている。そうであればいいと私も思う。(中略)だが、政策発動や、インフレと戦う中央銀行という信認が過去十年から二十年の長期金利の低下に主導的な役割を果たしたという見方は大いに疑問である。長期金利の低下(そして謎)は金融政策以外の要因で説明できる。(中略)実質長期金利の低下圧力は世界に広がっていったが、われわれがそれに対抗する資源をもっていたのか疑問に思う。日本は明らかに対抗できなかった。
***********************
また「第4章」では米国発の金融危機や米国バブルを引き起こした原因は何だったのか、①モノを中心とする実物取引の収支尻、経常収支の世界的不均衡(グローバル・インバランス)、②世界規模での活発な金融取引を反映した過剰流動性仮説、の2つの仮説について考察しています。
インバランス仮説に立てば中国などの過剰な貯蓄が原因となりグローバル・インバランスを生じ、それによるネット資本フローが米国に流れ込んで金利低下圧力や過剰流動性などを招き住宅バブルに繋がったということですが、著者が言うように、米国自身をはじめとする国々の過剰な金融緩和が金利低下や過剰流動性を促し、それが住宅バブルを生んで、結果的にグローバル・インバランスを引き起こしたという過剰流動性仮説のほうがやはりしっくりくるんでしょうね。
他にもいろいろ書きたいところはあるのですが、コストパフォーマンスの高い良書なので是非お読みいただきたいと思います。
【目次】
第1章 金融拡大の30年間を振り返る
第2章 グリーンスパンの金融政策―リスクテイクへの働きかけは経済成長を促進するか
第3章 世界的バランスシート調整がもたらす「日本化現象」―アベノミクスで脱「日本化」は可能か
第4章 グローバル・インバランス―金融危機と日本の企業部門
第5章 アベノミクスと日本財政を巡る課題―現実の直視から、財政再建は始まる
<iframe src="http://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?t=kurogenkoku-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4532262046&ref=tf_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>